【2年生版・文例集】通知表の所見はこれで完璧!小学校2年生の成長が伝わる言葉が必ず見つかる
小学校の先生方、日々の業務、本当にお疲れ様です。1年生のあどけなさが抜け、心も体も大きく成長する小学校2年生。学期末に作成する通知表は、その確かな成長を保護者の方々に伝えるための大切な架け橋です。しかし、頭を悩ませている先生も多いのではないでしょうか。一人ひとりの個性を的確に表現し、次への意欲につながる言葉を見つけるのは、簡単なことではありません。
この記事では、
小学校2年生に特化した通知表の所見文例を網羅的にご紹介します。2年生の所見で使える、国語や算数といった教科別の具体的な文例はもちろん、生活面や学習面での成長を伝えるための豊富なフレーズを、すぐに使える形でまとめました。
この記事で分かること
- 小学校2年生の通知表所見を書く際に押さえるべき、1年生との違い
- 国語、算数、生活、音楽、図画工作、体育といった全教科の具体的な所見文例
- 「基本的生活習慣」や「学習態度」「思いやり・協力」など、行動の記録に関する20項目の豊富な所見文例
- 特別な支援が必要な児童向けの自立活動に関する所見文例
- 子どもと保護者の心に響く所見を作成するためのヒント
おすすめの書籍はこちら💁
通知表 所見 文例 小学校2年 を書く上で大切なポイント
2年生の所見を書く際には、1年生からの成長を意識することが重要です。基本的なポイントに加え、2年生ならではの視点も押さえておきましょう。
1. 「自分」から「仲間」への意識の広がりを捉える
2年生になると、自分のことだけでなく、友達やグループ、クラスといった「集団」を意識した言動が増えてきます。「〇〇さんと協力して~」「クラスのために~」といった、仲間との関わりの中で見られた成長や貢献を具体的に記述すると、2年生らしさが伝わります。
2. 抽象的な思考の芽生えを記述する
学習面では、かけ算九九や漢字など、抽象的な概念の理解が進みます。「なぜそうなるのか」という理由やきまりを見つけようとする姿、筋道を立てて考えようとする姿など、思考力の成長を捉えて言葉にすることが大切です。
3. 具体的なエピソードで成長を物語る
これは全学年に共通しますが、特に重要です。「頑張りました」という評価だけでなく、「かけ算九九の練習で、休み時間も友達と問題を出し合い、最後まで諦めずに覚えました」のように、具体的な行動やエピソードを添えることで、所見が生き生きとし、保護者の心に深く響きます。

【教科別】2年生の通知表所見文例
2年生 国語の所見文例

- 物語の登場人物の気持ちの変化を、本文の言葉を根拠にして読み取ることができます。「最初は~と思っていたけれど、〇〇の言葉で~という気持ちに変わった」と、筋道を立てて説明できる力がついてきました。
- 新しく習う漢字に大変意欲的で、形や意味、音訓を関連付けながら熱心に覚えています。自分で熟語を見つけてノートに書きためるなど、語彙を増やそうとする努力は素晴らしいです。
- 説明文を読む際には、段落ごとの要点を見つけるのが上手です。「はじめ」「中」「おわり」といった文章の構成を意識して読むことができ、内容の理解が深まっています。
- 自分の体験したことや考えたことを、順序よく文章に書くことができます。特に、会話文を効果的に使うことで、その場の様子が生き生きと伝わる作文を書きました。
- 音読では、場面の様子を想像し、声の大きさや速さを工夫して読んでいます。グループでの発表では、友達と声を合わせる楽しさを感じながら、生き生きと役割を読むことができました。
- 主語と述語の関係を正しく理解し、文の組み立てがしっかりとしてきました。「何がどうする」を意識することで、より分かりやすい文章が書けるようになっています。
- 人の発表を聞く態度が立派です。最後まで体を向けて聞き、感想を言うときには「〇〇さんの~というところがすごいと思いました」と、具体的な言葉で良い点を伝えることができます。
- 言葉遊びの学習では、言葉の響きやリズムを楽しみながら、たくさんの言葉を見つけることができました。言葉に対する豊かな感性が育っています。
- 話し合い活動では、友達の意見に付け加えたり、質問したりしながら、自分の考えを深めることができます。対話を通して学ぶ楽しさを知っています。
- 読書が好きで、様々なジャンルの本に親しんでいます。本から得た知識や言葉を、会話や作文の中で自然に活用しており、読書が力になっていることが分かります。
2年生 算数の所見文例
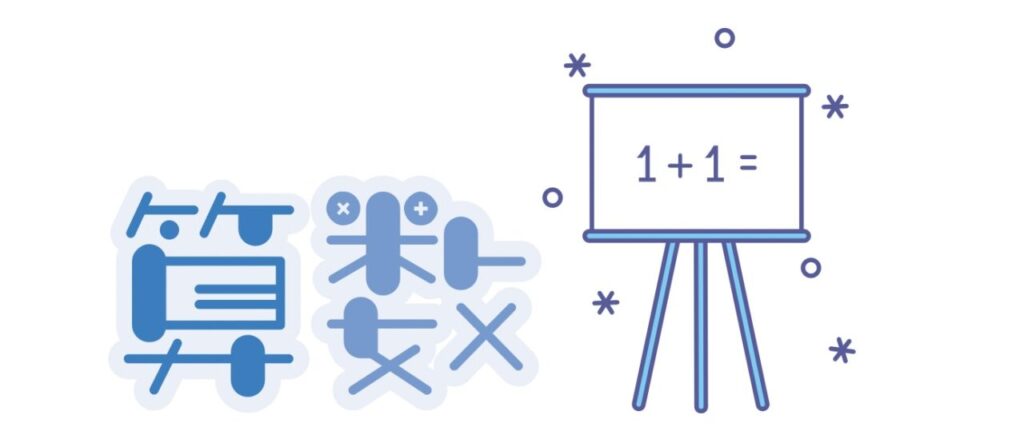
- かけ算九九の学習に粘り強く取り組み、全ての段を暗唱できるようになりました。カードを使ったり、友達と問題を出し合ったりと、自分なりに工夫して努力した成果です。
- たし算とひき算の筆算の仕組みをよく理解しています。位をそろえて書くこと、繰り上がり・繰り下がりに気をつけることを意識し、正確に計算することができます。
- 図形の学習では、三角形や四角形の特徴に興味を持ち、身の回りから様々な形を見つけようとしました。辺や頂点の数に着目し、仲間分けをする活動では、鋭い観察力を発揮しました。
- かさや長さの単位について、量感を伴って理解しています。「1Lは牛乳パックくらい」など、具体的なものと結びつけて考えることで、生活の中で算数を活用する力が育っています。
- 文章問題を解くとき、問題場面を図や絵に表して考えることができます。式だけでなく、「どうしてその式になるのか」を自分の言葉で説明しようとする論理的な思考力が伸びています。
- 時計の学習では、時刻と時間の違いを理解し、何時何分から何分後の時刻を求める問題にも意欲的に取り組みました。生活の中で時間を意識する姿が見られます。
- 計算のきまりを見つけるのが得意です。交換法則や結合法則などを、ブロック操作を通して感覚的に理解し、計算を工夫しようとする態度が素晴らしいです。
- ノートの使い方がとても丁寧です。日付やページ、問題番号をきちんと書き、式と答えを分かりやすく整理しています。学習の積み重ねが一目で分かるノートです。
- 自分の考えを友達に説明するのが上手です。難しい問題も、順を追って分かりやすく話すことができるため、周りの友達の理解を助けてくれています。
- 答えが合っているか確かめる「見直し」の習慣がついてきました。自分の間違いに気づき、自力で訂正できるようになったことは、大きな成長です。
2年生 生活の所見文例

- 野菜の栽培活動では、毎日欠かさず水やりをし、愛情を込めて育てました。小さな変化にもよく気づき、観察カードに絵や言葉で詳しく記録することができました。命を育てる責任感を学びました。
- 町探検の活動では、グループの友達と協力し、安全に気をつけて探検することができました。お店の人に、事前に考えた質問をはきはきとすることができ、地域の素晴らしさを発見できました。
- 自分の生まれた頃から今までの成長を振り返る学習では、ご家族にインタビューしたことを嬉しそうに話してくれました。自分の成長を支えてくれた人々への感謝の気持ちが育っています。
- 生き物の飼育活動では、生き物の気持ちになって、住みやすい環境を工夫していました。命あるものを大切にする優しい心が素晴らしいです。
- 動くおもちゃ作りでは、材料の特性を生かし、どうすればもっと面白く動くかを友達と試行錯誤しました。創意工夫する楽しさを味わうことができました。
- 公共施設の利用の仕方を学ぶ学習では、図書館や公民館でのマナーを守って行動することができました。みんなで使う場所を大切にしようとする公徳心が育っています。
- 1年生を学校案内する活動では、お兄さん・お姉さんとして、優しく分かりやすく説明しようと努力していました。下級生を思いやる気持ちが芽生えています。
- 季節の変化に関心を持ち、春夏秋冬の自然の様子や遊びの違いを見つけるのが上手です。豊かな感性で自然と関わっています。
- 話し合い活動では、司会や記録などの役割を責任をもって果たし、みんなで一つのことを成し遂げる喜びを感じています。
- 探検で見つけたことや調べたことを、聞いている人に分かりやすく伝えるために、絵や実物を見せるなど、発表の仕方を工夫することができました。
2年生 音楽の所見文例

- 歌うことが大好きで、歌詞に込められた情景や気持ちを想像しながら、表情豊かに歌います。〇〇さんの伸びやかな歌声は、クラスの歌声を一層美しいものにしています。
- 拍の流れに乗って、体を動かしたり、楽器を演奏したりすることができます。リズムを組み合わせて、簡単な音楽を作る活動では、独創的なアイデアを出していました。
- 鍵盤ハーモニカの指使いがとても上手になりました。両手を使って演奏することにも挑戦し、友達と音を合わせて合奏する楽しさを味わっています。
- 楽譜に書かれている記号(強弱記号など)の意味を理解し、表現を工夫しながら演奏しようとしています。音楽への探求心が素晴らしいです。
- 日本のわらべうたや世界の様々な音楽に親しみ、それぞれの曲の面白さや雰囲気の違いを感じ取っています。多様な音楽文化への関心が広がっています。
- 鑑賞の学習では、音楽から感じ取ったことや想像したことを、言葉や絵で自由に表現することができます。豊かな感受性が光ります。
- グループでの音楽づくりでは、リーダーシップを発揮し、友達の意見をまとめながら、みんなで一つの音楽を創り上げる中心的な役割を果たしました。
- 楽器の準備や後片付けを率先して行い、周りの友達にも優しく声をかけています。みんなが気持ちよく学習できる雰囲気を作ってくれる存在です。
- 音楽に合わせて体を動かす表現活動では、恥ずかしがらずに、全身を使ってのびのびと自分を表現することを楽しんでいます。
- 練習すればするほど上手になることを実感し、難しい曲にも諦めずに取り組んでいます。努力することの大切さを音楽を通して学んでいます。
2年生 図画工作の所見文例

- カッターナイフを安全な使い方で、上手に扱えるようになりました。窓を作って光を取り入れるなど、カッターナイフの特性を生かした作品作りに挑戦しました。
- 絵の具の混色に関心を持ち、様々な色を試しながら、自分のイメージに合った色を作り出すことを楽しんでいます。色彩感覚が豊かです。
- 身近な材料の特徴から想像を広げ、ユニークな作品を生み出す発想力が素晴らしいです。空き箱やペットボトルが、〇〇さんの手にかかると素敵な宝物に生まれ変わります。
- 表したいことのイメージを明確に持ち、細かいところまでこだわって丁寧に作品を仕上げようとします。粘り強さと集中力があります。
- 友達の作品の良いところをたくさん見つけ、「そのアイデア、面白いね」「色の使い方がきれいだね」と、温かい言葉で認め合うことができます。
- 粘土の造形活動では、ひも状にしたり、平たくのばしたりと、様々な技法を試しながら、生き生きとした動物を作ることができました。観察力が優れています。
- 共同制作では、友達とイメージを共有し、協力しながら一つの大きな作品を作り上げる楽しさを味わいました。自分の役割を責任をもって果たしていました。
- 鑑賞の活動では、作品の面白いところや素敵なところを見つけ、自分なりの言葉で感想を述べることができます。
- 後片付けまでが作品作りと捉え、使った道具を丁寧に洗い、次の人が気持ちよく使えるように整頓することができます。
- 自分の作品に自信と愛着を持ち、作品に込めた思いや工夫した点を、生き生きとした表情で語ってくれます。自己表現の喜びを感じています。
2年生 体育の所見文例

- ボールゲームでは、チームの友達と声をかけ合い、パスをつなぐなど、協力してゴールを目指すことができるようになりました。ルールを理解し、作戦を考えて動こうとしています。
- マット運動では、前転や後転などの基本的な技がスムーズにできるようになりました。技のポイントを意識し、より美しい回転を目指して練習に励んでいます。
- 用具の準備や片付けを、仲間と協力して素早く行うことができます。安全に気をつけて活動しようとする意識が高いです。
- 跳び箱運動では、恐怖心に打ち勝ち、開脚跳びに挑戦しました。踏み切りや着手の位置を考えながら、何度も練習する粘り強さが見られました。
- 表現運動では、様々な動きを組み合わせて、物語の登場人物になりきって踊ることを楽しんでいます。想像力豊かで、表現力が伸びています。
- 運動会では、応援団として、大きな声で仲間を応援し、チームを盛り上げました。勝敗だけでなく、仲間と協力する大切さを学びました。
- なわとびでは、あや跳びや交差跳びなど、新しい技に意欲的に挑戦し、できる技がどんどん増えています。目標に向かって努力する姿が輝いています。
- 友達が技に挑戦している時には、自然に「がんばれ!」と応援したり、できたら一緒に喜んだりできる、温かい心を持っています。
- 自分の体力や技能に合わせて、運動の強度や目標を調整しようとするなど、自分の体と向き合う力が育ってきました。
- ルールを自分たちで工夫し、みんなが楽しめるように改善しようと提案することができます。遊びを創造する力がついてきました。
【行動の記録】小学校2年生の通知表所見文例
基本的生活習慣

- 1年生のお手本となるべく、自ら正しい言葉遣いや時間を守る行動を心がけています。上級生としての自覚が芽生えています。
- 学習の準備や後片付けが、言われなくても自分で見通しをもってできるようになりました。自己管理能力が向上しています。
- 朝の会が始まる前に着席し、静かに読書をして待つなど、落ち着いて一日を始める習慣が完全に身についています。
- 持ち物の管理がしっかりできており、忘れ物がありません。ご家庭での声かけに感謝いたします。
- 自分の机やロッカーの整理整頓を常に心がけており、学習環境を自分で整える意識が高いです。
- 丁寧な言葉遣いができ、相手や場面に応じた話し方をしようと努力しています。
- 授業と休み時間の切り替えが素早く、チャイムと共に学習への意識を高めることができます。
- 服装の乱れなどに自分で気づき、さっと直すなど、身だしなみへの意識が向上しました。
- ハンカチやティッシュを常に身につけ、衛生的な生活を心がけることができています。
- 規則正しい生活リズムの大切さを理解し、毎日元気に登校しています。健康管理への意識が高いです。
学習態度

- 学習内容への理解が深まり、自信をもって手を挙げて発表する回数が格段に増えました。
- 分からない言葉や事柄があると、すぐに質問したり、図書室で調べたりと、知的好奇心を行動に移すことができます。
- 友達の発表を、自分の考えと比べながら聞くことができます。「〇〇さんと同じです。理由は~」など、根拠を明確にして発言できます。
- 授業の最後まで集中力を保ち、真剣な態度で学習に取り組んでいます。その姿は周りの生徒の模範となっています。
- 学習計画を立て、家庭での学習に見通しをもって取り組もうとしています。自律的な学習習慣が育ちつつあります。
- ノートの書き方が上達し、要点をまとめたり、色を使って分かりやすく工夫したりしています。
- 一度間違えた問題も、諦めずに、なぜ間違えたのかを考えて自力で解き直そうとします。粘り強い学習態度です。
- グループ学習では、自分の役割を理解し、積極的に意見を出しながら課題解決に貢献しています。
- 学習用具を大切に扱い、常に整理整頓されています。物を大切にする心が学習態度にも表れています。
- 新しいことを学ぶことへの喜びを全身で表現し、常に前向きな姿勢で授業に参加しています。
挨拶
- 相手の目を見て、にこやかに挨拶をすることができます。心のこもった挨拶は、周りの人を明るい気持ちにさせます。
- 校内で会う先生方だけでなく、地域の方々にも自分から進んで挨拶ができます。社会の一員としての自覚が感じられます。
- 「おはようございます」「さようなら」だけでなく、「ありがとうございます」「失礼します」など、場面に応じた挨拶が使い分けられます。
- 友達同士でも気持ちの良い挨拶を交わしており、クラスの温かい雰囲気作りに貢献しています。
- 少し恥ずかしそうにしていた1年生に、「おはよう」と優しく声をかける姿が見られ、上級生としての成長を感じました。
- 元気な挨拶をクラスに広めようと、挨拶係としてポスターを作るなど、自主的な活動をしています。
- 呼ばれた時の「はい」という返事が、いつもはきはきとしており、気持ちが良いです。
- 挨拶の声が、以前にも増して大きくなりました。自信の表れだと感じています。
- 職員室などに入退室する際の挨拶が、丁寧に行えます。礼儀正しい態度が身についています。
- 挨拶はコミュニケーションの第一歩であることを理解し、大切にしようとする姿勢が見られます。
健康・体力の向上
- 一年間、大きな病気や怪我もなく、元気に学校生活を送ることができました。丈夫な体は日々の生活習慣の賜物です。
- 外で元気に遊ぶことで、基礎体力が向上し、持久走では最後まで粘り強く走ることができるようになりました。
- 自分の体調をよく理解しており、「少し疲れ気味です」など、自分から申し出ることができます。自己管理能力が育っています。
- 手洗いやうがいを励行し、感染症予防への意識が高いです。自分の健康を自分で守ろうとしています。
- 好き嫌いが減り、栄養のバランスを考えて給食を食べようと努力しています。
- 体育の学習に意欲的に参加し、体を動かすことの楽しさを全身で表現しています。
- 運動を通して、自分の体力の限界に挑戦したり、目標を達成したりする喜びを味わっています。
- 良い姿勢を保つことの重要性を理解し、学習中も背筋を伸ばすよう心がけています。
- 休み時間には、友達を誘ってドッジボールをするなど、体を動かす遊びを企画しています。
- 健康な生活を送るためには、運動・食事・睡眠が大切であることを理解し、実践しようとしています。
外で元気に遊ぶ
- 休み時間には、学年や男女の垣根を越えて、大勢の友達と楽しそうに遊んでいます。優れたコミュニケーション能力の持ち主です。
- 鬼ごっこやドッジボールなどの集団遊びでは、ルールを工夫してみんながもっと楽しめるように提案することができます。
- 鉄棒やうんていなど、少し難しい遊具にも挑戦し、できることがどんどん増えています。チャレンジ精神が旺盛です。
- 遊びの中で友達と意見がぶつかっても、話し合って解決しようとする社会性が育っています。
- 校庭の自然に親しみ、季節の変化を感じながら、伸び伸びと過ごしています。豊かな感性の表れです。
- 一人でいる子がいると、「一緒に遊ぼう」と自分から優しく声をかけることができます。
- 遊びのリーダーとして、みんなをまとめ、安全に気をつけて遊ぶよう呼びかけています。
- 体を動かすことが大好きで、そのエネルギーは学習への意欲にもつながっています。
- 遊びの中で順番を守ったり、道具を譲り合ったりすることが自然にできています。
- 自分たちで新しい遊びを考え出すなど、創造力を働かせて遊びを豊かにしています。
給食で好き嫌いなく食べる
- 苦手な食材にも、一口は挑戦しようと努力する姿に、大きな精神的成長を感じます。
- 「この野菜は体に良いんだよ」と、栄養に関する知識を友達に教えながら、楽しく給食を食べています。
- 食べ物を作ってくれた人への感謝の気持ちを忘れず、いつも「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶を丁寧にしています。
- 食事のマナーが身につき、正しい箸の持ち方で、姿勢良く食べることができます。
- 給食を残さず食べられた日は、達成感に満ちた表情を見せてくれます。成功体験が自信になっています。
- アレルギーのある友達に配慮し、給食当番の際には細心の注意を払って配膳しています。
- 食べるスピードが速くなり、時間内に余裕をもって食べ終えることができるようになりました。
- 様々な国の料理にも興味を持ち、食文化の多様性を楽しんでいます。
- 友達と今日の給食のメニューについて話すなど、食事が楽しいコミュニケーションの場になっています。
- 食材がどのように育てられ、給食になるのかという過程に関心を持ち、食べ物を大切にしようとしています。
自主・自立
- 朝の会が始まる前に、その日の学習予定を確認し、自主的に準備を進めることができます。
- 先生の指示を待つのではなく、クラスのために今すべきことを見つけ、自分から進んで行動できます。
- グループ学習では、リーダーを決めなくても、それぞれが自分の役割を理解し、主体的に活動を進めようとします。
- 自分の意見をしっかりと持ち、友達の意見に安易に流されず、堂々と発表することができます。
- 忘れ物をした際には、人のせいにせず、自分の問題として捉え、次はどうすればよいかを考えています。
- 自分の興味・関心に基づいて、図書室で本を選んだり、調べ学習をしたりと、学びを広げようとしています。
- 係活動では、自分たちで活動内容を企画・運営し、クラスをより良くしようと努力しています。
- 自分のことは自分でするという意識が高く、身の回りのことをきちんと管理できています。
- 休み時間の過ごし方や学習の進め方など、自分で考えて決める力がついてきました。
- 1年生のお手本になろうという気持ちが、より自立した行動へとつながっています。
自分の力で考え、行動する
- 問題にぶつかった時、「どうしてだろう」「どうすればいいかな」と、原因や解決策を自分なりに考え抜こうとします。
- 生活科の探検活動では、自分なりの課題を見つけ、それを解決するために主体的に情報を集めていました。
- 友達とのトラブルの際も、感情的になる前に、まず相手の言い分を聞こうとする冷静さがあります。
- ただ教えられたことを覚えるだけでなく、その背景にある「きまり」や「仕組み」を発見しようとします。
- より良いクラスにするために、「〇〇というルールを作りませんか」と、自分の考えを根拠とともに提案できました。
- 掃除の時間には、どうすれば効率よく時間内にきれいにできるかを考え、友達と協力して実践しています。
- 周りの状況をよく見て、困っている人がいれば、指示される前にさっと手を差し伸べることができます。
- 人の意見を鵜呑みにせず、「自分はこう思う」という視点を大切にしています。
- 計画を立て、見通しをもって物事に取り組むことができるようになってきました。
- 失敗を恐れず、まずはやってみようというチャレンジ精神があり、その経験から多くを学んでいます。
粘り強く取り組む
- 難しい計算問題や長文読解にも、すぐに諦めることなく、最後まで集中して取り組むことができます。
- 一度や二度の失敗でくじけず、できるようになるまで何度も挑戦する強い心を持っています。
- 漢字の練習や計算ドリルなど、地道な努力を毎日こつこつと続けることができる真面目さがあります。
- 体育の跳び箱では、目標の高さを跳べるようになるまで、繰り返し練習する粘り強さを見せてくれました。
- 時間がかかる作品作りでも、最後まで丁寧に仕上げようとする根気強さは素晴らしいです。
- 友達が諦めかけている時に、「一緒に頑張ろう」と励まし、周りの意欲を引き出すことができます。
- 「もう少しでできそう」という感覚を大切にし、目標達成に向けて努力を惜しみません。
- 困難な課題ほど意欲を燃やすタイプで、乗り越えた時の達成感を力に変えています。
- 自分の考えがまとまらない時も、粘り強く言葉を探し、何とか伝えようと努力します。
- 途中で投げ出さずに最後までやり遂げることが、大きな自信につながっていることを理解しています。
目標に向かって取り組む
- 「漢字テストで満点をとる」「なわとびで二重跳びを10回跳ぶ」など、具体的で少し高い目標を自分で立てることができます。
- 目標達成のために、今週は何をするか、今日は何をするか、と計画を立てて努力することができます。
- 自分の目標をクラスで発表し、友達と励まし合いながら取り組むことで、意欲を持続させています。
- 目標達成の過程で、うまくいかないことがあっても、やり方を変えるなど工夫することができます。
- 学習発表会では、自分の役を完璧に演じるという目標を掲げ、堂々とした姿を見せてくれました。
- 目標を達成した時の喜びを素直に表現し、その成功体験を次の活動へのエネルギーにしています。
- 個人の目標だけでなく、クラス全体の目標(あいさつ運動など)にも、積極的に貢献しようとします。
- たとえ目標に届かなくても、それまでの努力の価値を認め、潔く結果を受け止めることができます。
- 友達が目標に向かって頑張っている姿を、心から応援することができる素敵な心を持っています。
- 常に向上心を持ち、一つの目標をクリアすると、すぐに次の新たな目標を見つけて挑戦しようとします。
責任感
- 係や当番の仕事を、クラスのみんなのために、最後まで責任をもってやり遂げます。その真摯な態度は皆の信頼を得ています。
- 自分がやるべきことは、言われなくてもきちんと把握し、計画的に進めることができます。
- グループで決めた役割は、たとえ地味な仕事であっても、決して手を抜くことなく誠実に取り組みます。
- 自分の失敗を素直に認め、人のせいにしない潔さがあります。その上で、次はどうするかを前向きに考えています。
- 生き物係として、休日も生き物のことを気にかけ、命を預かることの重みを理解して行動しています。
- 日直の仕事では、クラスの前に立って、はきはきとした態度で会を進めることができ、責任感の成長を感じました。
- 友達との約束は、どんな小さなことでも大切にし、必ず守ろうとします。
- クラスの一員としての自覚が高まり、自分の行動がクラス全体に与える影響を考えて行動できるようになりました。
- 任された仕事は、最後までやり遂げるだけでなく、より良くするためにどうすればよいかまで考えています。
- 忘れ物を届けたり、落ちているゴミを拾ったりと、自分の責任範囲を超えて、クラスのために行動できます。
創意工夫
- 図画工作では、ありきたりな表現にとどまらず、材料の使い方を工夫して自分だけの世界を表現します。
- 生活科のおもちゃ作りでは、どうすればもっと遠くまで飛ぶか、速く走るかを試行錯誤し、素晴らしい発明をしました。
- 話し合いが行き詰った時に、誰もが思いつかないようなユニークな視点から意見を出し、場を和ませ、活性化させます。
- ノートのまとめ方では、イラストや関連図を用いるなど、学習内容が楽しく、分かりやすくなるような工夫を凝らしています。
- 係活動で、みんなが楽しめるような新しい企画を考え、クラスを盛り上げてくれました。
- 普段の生活の中でも、「もっとこうしたら便利なのに」と考え、改善しようとする姿勢が見られます。
- 友達のアイデアに感心すると、それをヒントに、さらに発展させた自分のアイデアを生み出します。
- 発表の仕方で、クイズ形式を取り入れるなど、聞いている人を楽しませるための工夫ができます。
- 掃除の仕方でも、どうすれば効率が上がるかを考え、友達と協力して新しいやり方を試しています。
- きまりきったやり方にとらわれず、自分らしい方法を見つけようとする探求心が素晴らしいです。
思いやり・協力
- 困っている友達にいち早く気づき、ためらうことなく「大丈夫?」と声をかけることができる、温かい心の持ち主です。
- グループ活動では、自分の意見を言うだけでなく、まだ発言していない子に「〇〇さんはどう思う?」と話を振るなど、周りへの配慮ができます。
- 勉強で分からないところがある友達に、上から教えるのではなく、一緒に考えようとする優しい姿勢があります。
- 荷物が多くて困っている友達がいると、自然に「持つよ」と手を差し伸べることができます。
- 誰かが失敗してしまっても、責めるのではなく、「ドンマイ!」「次頑張ろう」と励ますことができます。
- 友達の良いところを見つけるのが上手で、それを素直に言葉にして伝えられるため、周りの自己肯定感を高めています。
- 大変な作業や難しい役割も、友達と協力すれば乗り越えられることを知っており、積極的に協働しようとします。
- 自分と違う意見を持つ友達のことも尊重し、違いを認め合った上で、解決策を探ろうとします。
- クラスが一つにまとまるためにはどうすればよいかを考え、みんなが楽しく過ごせるような雰囲気づくりに貢献しています。
- 自分のことだけでなく、常に周りの人の気持ちを想像して行動しようとする姿に、大きな成長を感じます。
生命尊重・自然愛護
- 生活科で育てた野菜を収穫する際には、命をいただくことへの感謝の気持ちを言葉にしていました。
- 校庭で見つけた虫やカエルを、大切そうに観察し、最後は「元気でね」と声をかけて自然に返すことができる優しい心を持っています。
- 植物も生きていることを理解し、校庭の木や花を傷つけないように大切に扱っています。
- 命をテーマにした読み聞かせでは、真剣な眼差しで聞き入り、命の尊さについて深く考えている様子でした。
- 給食の牛乳パックをきれいに洗ってリサイクルに出すなど、環境を守るための具体的な行動ができています。
- 道端に咲く小さな花にも目を向け、その美しさに感動できる豊かな感性を持っています。
- 友達が生き物を乱暴に扱おうとした時に、「生き物も痛いと思うよ」と、勇気をもって伝えることができました。
- 使わない教室の電気を消して回るなど、資源を大切にしようとする意識が高いです。
- 自然の美しさや不思議さに感動し、それを絵や作文で表現するのが上手です。
- 生きとし生けるものすべてに、かけがえのない命があることを、日々の生活の中で感じ取っています。
勤労・奉仕
- 自分の役割が終わっても、他に手伝えることはないかと探し、進んでクラスのために働こうとします。
- 誰かが気づく前に、教室の汚れや乱れを見つけ、さっと片付けたり拭いたりすることができます。
- 「ありがとう」と言われることに喜びを感じ、人の役に立つことの素晴らしさを知っています。
- みんなが嫌がるような仕事でも、文句一つ言わず、笑顔で引き受けることができます。
- 黒板をきれいにしたり、配付物を配ったりと、先生の仕事も進んで手伝ってくれ、大変助かっています。
- クラスのために働くことを「やらされている」のではなく、「自分たちのクラスを良くするため」と前向きに捉えています。
- 働くことの楽しさや大切さを、自分の行動を通して周りの友達に伝えています。
- 運動会の準備では、重い用具も友達と協力して運び、進んで活動していました。
- 大掃除では、普段は手の届かないような場所まできれいにしようと、一生懸命働いていました。
- 奉仕の心を持っており、見返りを求めず、純粋な気持ちで人のために行動できる立派な態度が身についています。
係活動
- 係活動を「自分たちのクラスを楽しくする活動」と捉え、責任と誇りをもって取り組んでいます。
- どうすれば活動がもっと盛り上がるか、メンバーと知恵を出し合い、ユニークな企画を立てて実行しました。
- 係のメンバーとよく連携し、報告・連絡・相談をしながら、計画的に活動を進めることができています。
- 活動の様子を新聞にまとめたり、みんなの前で堂々と発表したりと、活動の成果を伝える力も素晴らしいです。
- 自分の係だけでなく、他の係の活動にも関心を持ち、協力したり、良い点を認め合ったりしています。
- 活動を通して、自分の得意なことを発見し、それをクラスのために役立てる喜びを感じています。
- 休み時間も使いながら、熱心に活動の準備をする姿は、周りの生徒の意欲を高めています。
- 係の仕事で意見が分かれた時も、感情的にならず、話し合いで解決しようと努力できます。
- クラスの一員として、自分に与えられた役割を果たすことの重要性を学んでいます。
- 活動の反省を次につなげ、常により良い活動を目指そうとする向上心があります。
掃除
- 掃除の時間になると、気持ちを切り替え、時間いっぱい無言で自分の持ち場をきれいにしています。
- 机や椅子を丁寧に運び、教室の隅々までほうきが届くようにするなど、工夫して掃除に取り組んでいます。
- 友達と協力し、ほうき役とちりとり役の連携がスムーズにできています。
- 雑巾の絞り方が上手になり、拭き残しがないように丁寧に床を拭くことができます。
- 自分の担当場所が終わると、まだ終わっていない友達を手伝いに行くなど、周りを見て行動できます。
- 「みんなが使う場所だから」という意識を持ち、責任感をもって取り組んでいます。
- 掃除道具を大切に扱い、後片付けもきちんと行い、ロッカーを整頓しています。
- 汚れている場所を自分で見つけ、どうすればきれいになるかを考えながら掃除しています。
- 掃除をすることで、自分の心もすがすがしくなることを感じているようです。
- 1年生の掃除の様子を見て、優しくやり方を教えてあげる姿は、頼もしいお兄さん・お姉さんでした。
給食当番
- 衛生面に気をつけ、手洗い、消毒、白衣の着用を徹底し、責任感をもって配膳しています。
- 友達と協力し、声を掛け合いながら、効率よく準備を進めることができます。チームワークが素晴らしいです。
- クラスのみんなが公平になるように、量を考えながら丁寧につぎ分けることができます。
- 「いただきます」の時間に間に合うように、見通しをもって手際よく仕事を進めることができます。
- アレルギーを持つ友達への配慮を忘れず、先生と確認しながら慎重に配膳を行っています。
- 当番の仕事を通して、みんなのために働くことのやりがいと喜びを感じています。
- 後片付けでは、率先して牛乳パックを片付けたり、ワゴンをきれいに拭いたりしています。
- 当番ではない日でも、準備が遅れていると、自分から進んで手伝うことができます。
- 「今日の給食、楽しみだね」など、ポジティブな声かけで、給食の時間を楽しい雰囲気にしています。
- 仕事の段取りが上達し、1年生の頃と比べて、落ち着いて行動できるようになりました。
公正・公平
- 誰に対しても同じ態度で優しく接することができ、クラスの中に安心感が生まれています。
- 遊びの仲間決めなどでは、仲間はずれが出ないように、自分から声をかけるなど配慮しています。
- 物事を決めるときには、一部の人の意見だけでなく、クラスみんなの意見を聞こうとする姿勢があります。
- ゲームなどの勝敗に対しても、ルールを守って正々堂々と取り組み、相手の結果を素直に称えることができます。
- 役割分担の際には、好き嫌いで決めるのではなく、みんなが納得できる公平な方法を提案できます。
- 自分と違う考えや意見も、まずは一度受け止めて聞こうとする、広い心を持っています。
- 自分に間違いがあった場合は、正直にそれを認め、謝ることができる誠実さがあります。
- 仲の良い友達であっても、間違っていることには「それは違うと思う」と、きちんと伝える勇気があります。
- 「みんなが楽しいのが一番」という考えを持っており、そのためのルール作りにも積極的に参加します。
- えこひいきや偏見がなく、誰のことも同じ一人の人間として尊重しようとする態度が育っています。
公共心・公徳心
- 自分が使った後の水道の蛇口をきちんと閉めるなど、公共の資源を大切にしようとする意識が高いです。
- 廊下に落ちているゴミを、誰に言われるでもなく拾ってゴミ箱に捨てることができます。
- 図書室や体育館など、みんなで使う場所では、ルールを守って静かに、安全に利用できます。
- トイレのスリッパが乱れていると、次の人が使いやすいように、さっと並べ直すことができます。
- 学校の物を自分の物のように大切に扱い、壊したり汚したりしないように気をつけています。
- 廊下は静かに右側を歩くなど、他の人の迷惑にならないように考えて行動できています。
- 地域の一員としての自覚を持ち、登下校の際も広がって歩かず、交通ルールを守っています。
- 節電や節水を意識し、環境問題にも少しずつ関心を持ち始めています。
- 落し物を見つけた際には、持ち主のことを考えて、すぐに先生に届けることができます。
- 社会のルールやマナーを守ることは、みんなが気持ちよく生活するために大切であることを理解しています。
【自立活動】小学校2年生の通知表所見文例
個別の支援計画に基づき、一人ひとりの児童が自分の課題を乗り越え、成長していく姿を具体的に記述するための文例です。
- 気持ちが昂った時に、以前より早く落ち着けるようになりました。深呼吸をする、クールダウンの場所へ行くなど、自分で気持ちを切り替える方法が身についてきました。
- 授業中、集中が切れそうになると、自分で決めた「お助けグッズ」を使って、再び学習に意識を戻せるようになってきました。集中できる時間が着実に伸びています。
- 「次は〇〇をします」と活動の見通しを言葉で伝えることで、安心して次の行動に移れるようになりました。先のことを予測する力が育っています。
- 友達との関わりの中で、自分の気持ちを伝えるだけでなく、「今、貸してほしい」「後でならいいよ」など、相手の状況に応じた言葉のやり取りができる場面が増えました。
- 板書をノートに写すのが苦手でしたが、タブレットで撮影したり、重要なキーワードだけを書き出したりと、自分に合った学習方法を見つけ、意欲的に取り組んでいます。
- 大きな音や人混みが苦手でしたが、少しずつ慣れる練習を重ね、今では体育館での集会にも落ち着いて参加できるようになりました。大きな自信につながっています。
- 曖昧な指示の理解が難しい場面で、「つまり、どういうことですか」と、自分から質問して確認できるようになりました。
- グループ活動では、聞く役に徹することが多かったですが、最近は自分の意見を書いたカードを見せながら、少しずつ発言できるようになってきました。
- 急な予定変更にも、以前ほど混乱することが少なくなりました。気持ちの切り替えが上手になってきた証拠です。
- 手先の器用さが増し、ハサミやのりを使った作業がスムーズになりました。作品を完成させる喜びを味わうことで、活動への参加意欲が高まっています。
自立活動の所見文例は、詳しくこちらの記事にまとめています💁
各学年の所見文例集リンク
各学年の所見文例集はこちらから👇
まとめ
このページでは、通知表の所見文例 小学校2年版として、教科別、行動の記録、自立活動の視点から、具体的な文例を数多くご紹介しました。2年生は、仲間意識が芽生え、思考力が深まり、大きく飛躍する学年です。ここに挙げた文例をヒントに、ぜひ目の前のお子さんのきらりと光る個性や、確かな成長の足跡を、先生自身の言葉で紡いであげてください。先生からの愛情のこもったメッセージは、子どもたちと保護者の心に届き、3年生への大きな希望となるはずです。
参考外部リンク
各教科の目標や内容については、学習指導要領で確認することが、より的確な所見を作成する上で不可欠です。以下の文部科学省のページで、改めてご確認いただくことをお勧めします。





コメント