「納得がいかないことがあると、教室を飛び出して壁を叩いたり蹴ったりする…」
「急に癇癪を起こして、授業が止まってしまう…」
毎日、目の前で起きる子どもの衝動的な行動に、どう寄り添えば良いのか——。
多くの先生方が、現場でこうした悩みに直面されているのではないでしょうか。行動の背景にある「本当の気持ち」を理解しようにも、どう糸口を見つければ良いのか分からないことも多いはずです。
この記事では、
私自身の経験を通して見えてきた、子どもの「感情」と「行動」を理解し、より良い関わりにつなげるためのヒントを、具体的なステップである「感情支援サイクル」とともにお伝えします。
おすすめの自立活動『アンガーマネージメント』についてはこちらから👇
気持ちのコントロールにはこちらの教材がおすすめです。無料ダウンロードできます👇
はじめに:目の前の子どもの「怒り」、どう受け止める?
廊下を怒って歩き回り、壁を叩いたり蹴ったりする子ども。その姿に「困ったな」「危ないな」と、思わず身構えてしまうのは当然のことかもしれません。
実際、私のクラスでも、物が壊れるほどの強い怒りを表現する子がいました。棚を拳で殴って凹ませたり、バケツを蹴り飛ばし破壊したり…。今も教室に残る傷を見るたびに、当時の対応への反省や、子どもの怒りを受け止めきれなかった悔しさが胸に残ります。物が壊れることへの焦り、そして保護者対応への不安…先生ならきっと共感してくださるのではないでしょうか。

でも、その“怒り”の奥には、
- 「わかってもらえない悔しさ」
- 「頑張ったのに、うまくいかなかった不安」
- 「誰かに自分のつらさを気づいてほしい」
といった、子ども自身も気づけていない「本当の気持ち」が隠れていることが本当に多いのです。

まず大切なのは、衝動的な行動そのものを「問題行動」とだけ捉えるのではなく、その背景にある子どもの感情に目を向ける視点を持つことです。
支援の方法
子どもが「なんでこんなにイライラするんだろう?」「どうして泣きたくなるんだろう?」と、自分の気持ちをうまく理解できていないとき、その感情を言葉で説明することは非常に難しいものです。感情が言葉にならないからこそ、行動で表現するしかない、という状況も少なくありません。
だからこそ、私たち大人が子どもの気持ちを「言葉にしてあげる」ことが、驚くほど大きな意味を持ちます。
子どもの行動を見て、その奥にある気持ちを正確に言葉にしてみる。
「◯○されたんだね。本当は◯◯したかったんだね。それで、今、すごく悔しいんだね」
「期待していたのに、思い通りにいかなくて、不安になったんだね」
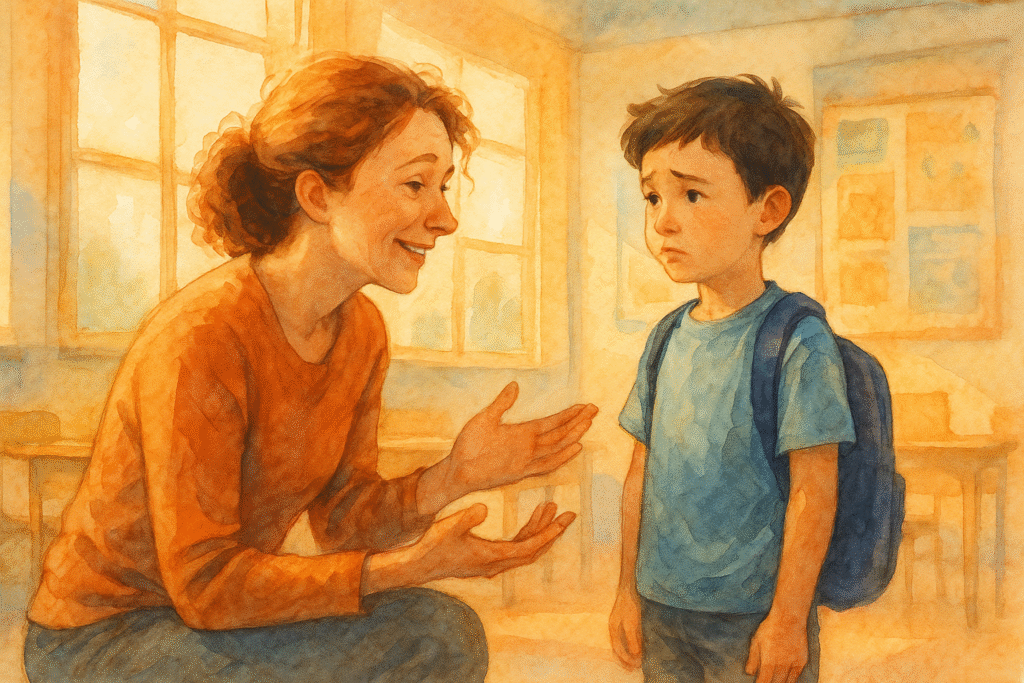
このように、子どもの「感情」と「言葉」を繋いであげる支援によって、子どもは「あ、そうか、自分はこう感じていたのか」と自分の気持ちに気づき始めます。そして、「この先生は、私の気持ちを分かってくれようとしている」という安心感が芽生えます。
何よりも、「相手が、自分自身も気づいていなかったり、うまく言葉にできなかったりする自分の気持ちを、自分以上に正確に、あるいは共感的に言語化してくれたとき」、人は心の底から安心し、その場で抱えている怒りや不安といった強い感情を少しずつ手放すことができるのです。
この「分かってもらえた」という実感が、子どもと先生との間に確かな信頼関係を築く出発点となります。
具体的なスキルの記事はこちら↓
スキル練習のその前に…「土台」は何が必要か
「アンガーマネジメント」「適切な自己表現の方法」などを学ぶSST(ソーシャルスキルトレーニング)は、子どもたちが感情とどう向き合い、表現するかを学ぶ上で非常に有効な手段です。
しかし、どんなに優れたSSTのプログラムがあったとしても、その「土台」となる子ども自身の感情理解や、先生との間の信頼関係が築けていない状態では、その効果は半減してしまいます。
考えてみてください。
- 自分の感情がよく分からない
- 先生に話してもどうせ分かってもらえないだろうと思っている
そんな子どもにとって、SSTは「正しいとされる行動を一方的に教えられているだけ」のように感じられ、「やらされ感」につながってしまう可能性があります。
どれだけSSTを行っても、その前に「この先生は自分の気持ちを理解しようとしてくれた」「つらい時に寄り添ってくれた」という共感された経験がなければ、学んだスキルを「自分のために使おう」という意欲につながりにくいのです。
土台ができた時のおすすめのSST↓
実践!先生と子どもを繋ぐ「感情支援サイクル」
では、具体的にどのように関われば、子どもが自分の「気持ち」と「ことば」を繋ぎ、少しずつ感情をコントロールできるようになるのでしょうか。
ここで役立つのが、私自身が大切にしている「感情支援サイクル」という段階的な関わりのプロセスです。
このサイクルを意識した、各段階での先生の関わり方のポイントをご紹介します。
| 段階 | 内容 | 先生の関わり方のポイント(例) |
|---|---|---|
| ① 感情体験 | 怒り・悲しみ・困惑などの強い感情が発生 | 子どもの行動や表情をよく観察し、「今、何か強い感情を感じているな」とまずは子どもの状態をそのまま受け止めます。 |
| ② 共感・言語化 | 先生が子どもの気持ちを代弁し、受け止める(感情と言葉を繋ぐ) | 子どもの感情に寄り添い、「〜だったんだね」「〜って感じたのかな?」と優しく言葉にして伝えます。子どもの気持ちを「言い当てる」のではなく「寄り添う」イメージで。 |
| ③ 自己肯定感の芽生え | 「それは当然だよ」「よくがんばったね」と、感情や状況を肯定的に価値づける | 「そういう状況なら、そう感じるのも無理ないよね」「そこまでよく我慢したね」など、子どもの感情や、そこに至るまでの努力や葛藤を肯定的に伝えます。 |
| ④ 行動の選択肢づくり | 「次どうしたい?」「こんな方法もあるよ」と、落ち着くための具体的な方法や代替行動を共有 | 子どもが落ち着き始めたら、「この後、どうしたい?」「他にどんなことができるかな?」と一緒に考えます。先生からいくつかの選択肢を提示することも有効です。 |
| ⑤ 実践と振り返り | 実際に選んだ行動を試し、結果や気持ちの変化を共に振り返ることで気づきを深める | 選んだ行動を子どもが実践できるようサポートします。その後、「どうだった?」「やってみて気持ちは変わった?」など、具体的な行動と感情の変化を振り返ります。 |
| ⑥ 再体験 | このサイクルを繰り返し体験することで、感情理解と行動選択のスキルが身につく | 一度の成功だけでなく、繰り返しこのサイクルを経験することが大切です。失敗から学び、次につなげる機会と捉えます。 |
先生の「言葉」が、子どもを変える力になる
子どもが、強い怒りの感情から少しずつクールダウンできた——そのこと自体が、素晴らしい一歩です。
しかし、もしそこに先生からの「あなたの気持ち、こうだったんだね」という言葉による理解が加わったとしたら、子どもの内面にはさらに大きな変化が生まれます。
先生に自分の気持ちを言語化され、受け止めてもらったと感じた子どもは、次のような肯定的な変化を見せるようになることが多いのです。
- 「次も、落ち着いてみよう」と、自分で感情を調整しようという意欲が生まれる
- 「自分は先生に気持ちを分かってもらえる人間なんだ」と、自己肯定感が芽生える
- 「この先生には、つらい気持ちも話しても大丈夫だ」と、先生への信頼感が高まり、SOSを出しやすくなる
つまり、衝動的な行動が落ち着くだけでなく、自分自身を肯定的に捉える力(自己認知力)や、他者とのより良い関係性を築く力(対人関係能力)といった、子どもたちがこれからを生き抜く上で不可欠な力も育っていくのです。
最後に
子どもへの「支援」とは、「問題となる行動をなくすこと」「正しい行動を一方的に教え込むこと」ではありません。
むしろ、「その子が、自分の感情や考えに気づき、自分で自分を理解できるようになること」、そして「自分にとってより良い選択肢を選べるようになること」を、先生が温かくお手伝いすることだと私は考えています。
そのためには、
- 目の前の子どもの感情に、まずは寄り添ってみること。
- 子どもが言葉にできない気持ちを、先生が代わりに言葉にしてあげること(感情と言葉を繋ぐこと)。
- その感情や、それまでの子どもの頑張りを価値づけてあげること。
- そして、その上で、より良い行動を試してみる「練習」の機会を一緒に作ること。
この感情支援サイクルを、焦らず、丁寧に、そして繰り返し行っていくことが、結果として子ども自身が「落ち着いた行動」を選択できるようになることにつながっていきます。
「どうしてこの子は、こんなことをするんだろう?」と、子どもの行動に頭を悩ませてしまう時こそ、ほんの一瞬立ち止まって、
「この子は今、本当はどんな気持ちでいるんだろう?」
と、子どもの心の声に耳を澄ませてみてください。
「相手が自分の気持ちを自分以上にうまく言語化してくれたとき、人は安心し、怒りを手放せる」——この力は、私たち大人にとっても、そして子どもたちにとっても、生きていく上でかけがえのないものです。
先生の「どんな気持ち?」という温かい問いかけと、「感情と言葉を繋ぐ支援」こそが、子どもの自己理解と自己コントロール、そして未来への希望を育む、何よりの鍵となるはずです。
※特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。






コメント