お子さんへの、やさしい教え方・遊び方

私は、特別支援学級教員。小学校で18年間勤務し、そのうち8年間は特別支援学級を担任。知的障害、自閉スペクトラム症、ADHDなど多様な子どもたちと関わりながら、個々に合わせた支援方法を実践してきました。
保護者としても、日々家庭でのSSTや子育てに取り組んでいます。
「うちの子、お友達とうまく関われないみたい…」
「気持ちの切り替えが苦手で、どう声をかけたらいいか分からない」
「学校での集団行動についていけるか心配…」
そんなふうに悩み、不安になることはありませんか?
私自身、担任として、また親として、たくさん悩みながら子どもたちと関わってきました。だからこそ、今、伝えたいことがあります。
特別支援教育や療育の現場で注目されている「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」は、実は特別な場だけでなく、家庭の中でも、無理なく楽しく取り組むことができます。
高価な教材は必要ありません。日々の生活の中に、小さな「工夫」と「声かけ」を取り入れるだけで、お子さんの「社会で生きる力」は着実に育っていきます。
この記事では、
- なぜ家庭でのSSTが大切なのか
- 家庭で取り組むSSTの基本的な考え方
- 今日からできる、具体的な教え方・遊び方
を、発達障害・グレーゾーンのお子さんの特性を踏まえながら、実際の現場や家庭での体験談を交えて、分かりやすくお伝えします。
実践的な内容を、ささっと知りたい方は、目次から「3.今日からできる!家庭での具体的な教え方・遊び方」へどうぞ。
※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。
関連記事はこちら💁
1.なぜ「家庭」でのSSTが大切なの?
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、学校や療育施設で行われるイメージがあるかもしれません。
もちろん、専門的な支援の場も大切ですが、子どもたちが最もリラックスできる「家庭」こそ、SSTのスタートラインです。
家庭には、
- 失敗しても受け止めてもらえる安心感
- 繰り返し練習できる時間
- 子ども一人ひとりに合わせたサポート
があります。
私自身、クラスで行ったSSTではうまくできなかった子が、
家庭で少しずつ練習を積み重ねたことで、
ある日、「せんせい、こんなことできたよ!」と嬉しそうに報告してくれたことがありました。
家庭での積み重ねは、子どもの「できた!」という自信につながります。
そしてその小さな自信が、学校や社会でも新しい一歩を踏み出す力になります。

2.家庭で取り組むSSTの基本的な考え方
家庭でのSSTを成功させるコツは、次の3つです。
(1)完璧を目指さない
最初から正解を求める必要はありません。
「少しできた!」を一緒に喜ぶことが大切です。
例えば、
- 「あいさつ」を練習する場合でも
→ 目が合わなくても、声が小さくても、「おはよう」が言えたらOK!
(2)子どもに合わせた「小さなステップ」で進める
いきなり難しい課題に挑戦すると、子どもは不安になってしまいます。
その子にとって「ちょっと頑張ればできること」を目標にしましょう。
たとえば、
「友だちに『貸して』と言う練習」をしたいときは、
- まずは家族に「貸して」と言う
- ぬいぐるみに「貸して」と話しかける
といったステップから始めるのも効果的です。
(3)失敗もOK!を伝える
うまくいかなかったときも、
「チャレンジできたこと自体が素晴らしい」と伝えましょう。
「今はまだうまくいかないだけだよ」
「何回も練習して、少しずつできるようになろうね」
という声かけが、子どもの心を支えます。
3.今日からできる!家庭での具体的な教え方・遊び方
ここからは、私自身が教室や家庭で実践してきた「家庭SST」の例を紹介します!
【例1】絵カードで「表情」や「気持ち」を伝える練習
表情や気持ちを読み取るのが苦手なお子さんには、絵カードを使った遊びがおすすめです。
- 「この顔、どんな気持ちかな?」
- 「この顔だったら、どうする?」
といったクイズ形式にすると、楽しみながら練習できます。
無料教材はこちら💁
ポイント
→ 正解を求めすぎず、「そう思ったんだね!」と受け止めることを大切にしましょう。
「絵カード」はアイデアだけでなく、実際のツールや教材と組み合わせることで、よりスムーズに定着します。
特に支援学級では、視覚的にわかりやすいアイテムがあると、子どもたちの反応が大きく変わります。
ここでは、私が実際に使用して「これは良かった!」と思える教材を紹介します👇
このカードは、45種類もの多様な表情が分かりやすいイラストで描かれており、言葉での説明だけでは伝わりにくい感情を視覚的に伝えることができます。カードを見ながら「今どんな気持ちかな?」「〇〇な気持ちだね」と一緒に確認することで、自分の内面と向き合いやすいようです。
裏面には表情の意味が記載されているため、支援者側も共通理解を持って 個別の支援を行いやすいのが便利です。
カード自体も丈夫で扱いやすく安心です。

【例2】ごっこ遊びで「やりとり」を練習
- お店屋さんごっこ
- 病院ごっこ
- バスごっこ
など、役割を決めて会話する遊びは、社会的なやりとりの練習にぴったりです。

たとえばお店屋さんごっこでは、
「いらっしゃいませ」「これください」「ありがとうございました」などの自然な流れを、遊びながら体験できます。
ポイント
→ はじめは大人がサポートして、「こんなふうに言ってみよう!」と優しくモデルを見せてあげると◎
【例3】成功体験を「見える形」で残す
小さな成功を、カレンダーやシール台帳に記録していく方法も効果的です。
- 「今日は『ありがとう』が言えたね!シール貼ろう」
- 「お友達に『どうぞ』ができたね!カレンダーにハナマル!」
子ども自身が成長を実感できることで、次への意欲が湧いてきます。
家庭でSSTを取り入れるとき、「できた!」という達成感を形に残してあげると、子どものやる気がグッと高まります。
我が家や学級でもよく活用しているのが、ごほうびシールです。
たとえば、ちいかわのごほうびシール や、にこにこマークの感情シール など、子どもが「かわいい!」と感じて自然と続けたくなるようなデザインを選ぶと効果的です。
「できたね」「がんばったね」という小さな成功体験を、視覚的に見える形で残していくことで、SSTの効果も継続しやすくなります。
【参考記事】
【SSTを成功に導く!日常支援と温かい学級づくりで子どもの成長をサポートする方法】
まとめ:家庭でのSSTは、子どもと親の「安心」を育てる時間
家庭でのSSTは、特別なものではありません。
毎日の中に、ほんの少しだけ意識して取り入れるだけで十分です。
- できたことを一緒に喜ぶ
- 少しずつチャレンジを広げる
- 失敗しても大丈夫と伝える
この積み重ねが、
子どもたちの「生きる力」を育みます。
そして何より、親子の信頼関係もぐっと深まっていきます。
完璧を目指す必要はありません。
できることから、ひとつずつ。
あなたとお子さんのペースで、ゆっくり進んでいきましょうね。
【あわせて読みたい】
- 【先生だって不安になる。でもだからこそ伝えられるソーシャルスキルのこと】
- 【子どもが“使いたくなる”ソーシャルスキルとは?】
- 【SSTを成功に導く!日常支援と温かい学級づくりで子どもの成長をサポートする方法】
※この記事にはアフィリエイトリンクを含みますが、収益化設定をしていません。
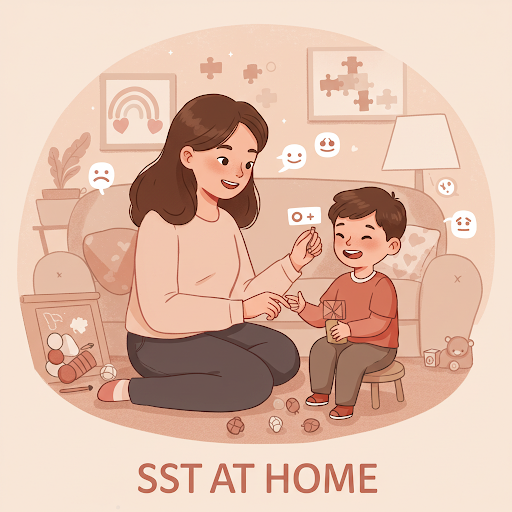




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47d6c840.8bfad8e4.47d6c841.74205f0b/?me_id=1359086&item_id=10002491&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmanabi-mono%2Fcabinet%2F2kaime_l_2%2F86175025_l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント