準備いらずで楽しめる!特別支援学級のコミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア
特別支援学級の運営において、子どもたち一人ひとりの発達段階や特性に合わせた自立活動は欠かせません。中でも「コミュニケーション力」は、友達と仲良くしたり、自分の気持ちを伝えたり、集団生活に楽しく参加したりするための大切な土台となります。
「クラスで孤立しがちな子がいる…」
「自分の気持ちをうまく言葉にできず、トラブルになってしまう…」
「どうすれば、子どもたちの自然な関わり合いを生み出せるだろう…?」
このような悩みを抱えている先生も、いらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、
私が実際に特別支援学級で実践してきた活動の中から、特に準備が少なく、子どもたちが夢中になって楽しめる「コミュニケーション力を高める自立活動」を5つ厳選してご紹介します。
どの活動も、楽しみながら自然と会話が生まれ、子どもたちの「話す」「聴く」「気づく」力が育まれるものばかりです。ぜひ、明日からのクラス運営のヒントにしてください。
※「本記事にはアフィリエイトリンクを含みます」
おすすめの自立活動はこちら👇
自立活動の引き出しを増やしたいときは、こちらの書籍もおすすめです。

自立活動の計画はこちらから💁
コミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア① 「自己紹介ビンゴゲーム」
新学期やクラス替えの時期にぴったりの、アイスブレイクの定番アクティビティです。「話しかける」という最初のハードルを、ゲームの力で楽しく乗り越えられます。
こんな子におすすめ
• 新学期や新しい環境に緊張し、自分から話しかけるのが苦手な子
• クラスメイトに興味を持つきっかけが欲しい子
• 場面緘黙の傾向があり、まずは書いたり指さしたりして参加したい子
詳しくはこちらをご覧ください💁
ねらい
- 友だちに話しかけるきっかけを作る
- 自分のことを相手に伝える練習
- クラスの仲間への関心を育てる
準備物
- 自己紹介ビンゴカード(「好きなアニメ」「夏休みの思い出」などのお題を9~16マス程度書いたもの。手書きでも、PCで作成したものでもOK)
- 筆記用具
進め方の手順
- 子どもたちにカードと筆記用具を配ります。
- 「友だちに質問して、同じ答えだったらサインをもらおう!」など、ルールを分かりやすく説明します。
- 活動スタート!子どもたちは自由に教室を歩き回り、友だちにインタビューします。
- ビンゴになった子から、見つけた友だちの紹介をみんなの前で発表してもらいます。

配慮のポイント&うまくいかない時のヒント
誰に話しかけたら良いか分からず立ちすくんでしまう子には、先生が「〇〇さんはアニメが好きみたいだよ。聞いてみようか?」と具体的に橋渡しをします。「断られても大丈夫。次の人を探しに行こうね!」と事前に伝えることで、断られることへの心の準備もできます。なかなかビンゴにならずに困っている子がいれば、「〇〇さんのマス、あと一つだね!誰か同じ答えの人はいないかな?」と全体に声をかけ、自然に助け合える雰囲気を作りましょう。
コミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア②「わたしの〇〇ベスト3」
「好きな食べ物」「最近うれしかったこと」など、自分の考えを整理して発表するシンプルなスピーチ活動です。自己理解と他者理解を深める第一歩になります。
こんな子におすすめ
• 自分の考えや気持ちを整理して話すのが苦手な子
• 人前で話す経験を積みたいが、長い作文やスピーチはハードルが高い子
• ADHDの傾向があり、思考が発散しやすい子(「ベスト3」という枠組みが思考を助けます)
詳しくはこちらをご覧ください👇
ねらい
- 自己理解を深め、自分の考えを整理する
- 自分の意見を言葉で表現する力を養う
- 友だちの話を静かに聞く「傾聴」の姿勢を育てる
準備物
- ホワイトボード(発表内容を書くため)
- テーマカード(「好きな給食」「行ってみたい場所」など。あると子どもが選びやすいです)
進め方の手順
- 「今日のテーマは『好きな〇〇ベスト3』です」とテーマを発表します。(子どもに選ばせるのも良い)
- それぞれ自分のベスト3を考え、発表する順番を決めます。
- 発表者は前に出て、自分のベスト3を発表します。聞いている子は静かに聞くルールを徹底します。
- 発表後、「〇〇さんの1位は~だったね!」と内容を振り返ったり、質問タイムを設けたりします。
配慮のポイント&うまくいかない時のヒント
話す内容が思いつかない子には、「これとこれなら、どっちが好き?」と具体的な選択肢を提示して考えをサポートします。人前で話すのが苦手な子は、先生と一緒に発表したり、座ったまま発表したり、紙に書いたものを見せながら話したりと、本人が安心できる方法を選べるようにしましょう。他の子の発表中に集中が途切れてしまう場合は、「発表が終わったら質問タイムがあるよ」と予告したり、「感想を言う係」などの役割を与えたりするのも効果的です。

コミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア③「人間知恵の輪」
言葉だけでなく、体を使った協力が必要なグループワークです。自然と「どうしようか?」という相談が生まれ、問題解決能力も育まれます。
こんな子におすすめ
• 言葉でのコミュニケーションは苦手だが、体を動かすのは好きな子
• 集団での問題解決を通して、協調性を学びたい子
• つい自分の意見を押し通そうとしてしまう子
詳しくはこちらをご覧ください👇
ねらい
- チームで協力する楽しさを体験する
- 言葉と非言語(身振り手振り)でコミュニケーションをとる
- 相手の立場を考え、配慮する力を育む
準備物
- 特になし(動きやすいように、少し広いスペースを確保してください)
進め方の手順
- 数人のグループを作り、全員で輪になって内側を向きます。
- 全員が両手を前に出し、向かい側や隣の人の手をランダムに握ります。(右手はAさん、左手はBさん、のように)
- 手をつないだまま、絡まった状態から元のきれいな一つの輪に戻れるように、グループで協力します。
- 「ここをくぐってみよう」「順番に動こう」など、声をかけ合いながら挑戦します。
配慮のポイント&うまくいかない時のヒント
体に触れられるのが苦手な子や、感覚過敏の子には無理強いは禁物です。「どうやったら解けるか指示を出す司令塔役」や「タイムを計る係」など、他の役割で参加できるように配慮しましょう。すぐに諦めてしまいそうなグループには、「どこか一つでも解けそうなところはないかな?」とヒントを与え、小さな成功体験を積ませることが大切です。活動中は転倒などに十分注意し、「ゆっくり動こうね」と声をかけ、安全を第一に進めましょう。
コミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア④「こころカルタ」
「最近ドキドキしたことは?」「今、話したいことは?」といった“こころ”に関する質問が書かれたカードを使って、おしゃべりを楽しむゲームです。感情の言語化を優しくサポートします。
こんな子におすすめ
• 自分の感情を言葉にするのが苦手な子(感情語彙が少ない子)
• 気持ちを内に溜め込んでしまい、うまく表現できない子
• 友だちの気持ちを想像するのが苦手な子
詳しくはこちらにまとめています👇
ねらい
- 自分の感情に気づき、言葉にする練習(感情の言語化)
- 安心して自己開示できる体験を積む
- 友だちの気持ちに耳を傾ける雰囲気づくり
準備物
- こころカルタ
進め方の手順
- 机の上に質問カードを裏返して並べます。
- 順番にカードを1枚めくり、書かれている質問に答えます。
- 答えは自由です。話したくないときは「パス」もできるルールを最初に伝えます。
- 一人の話が終わったら、「そうなんだね」「教えてくれてありがとう」と受け止める言葉をかけます。
配慮のポイント&うまくいかない時のヒント
最も大切なのは「話したくないときはパスしてもいい」というルールです。この選択肢があることで、子どもたちは安心して活動に参加できます。先生自身が「これはちょっと恥ずかしいからパス!」と手本を見せるのも効果的です。誰かの話を茶化すような言動があった場合はすぐに止め、「ここでは、どんな話も『そうなんだね』って聞くのがお約束だよ」と、場の安全性を丁寧に再確認しましょう。
コミュニケーションを育む自立活動5つのアイデア⑤「すきなのどっち?」ゲーム
「カレーとラーメン、どっちが好き?」など、究極の(?)二択を出し合って答えるだけの超シンプルゲーム。朝の会や帰りの会、ちょっとしたスキマ時間に最適です。
こんな子におすすめ
• 会話のきっかけを掴むのが苦手な子
• 発話に困難さがある子(選択式で答えやすい)
• 自信がなく、自分の意見を言うことに抵抗がある子
詳しくはこちらにまとめています👇
ねらい
- 会話のきっかけ(導入)を簡単にする
- 選んで答えるだけの簡単な自己表現
- 相手の好みや意外な一面を知る
準備物
- 特になし(お題を書いたカードがあるとバリエーションが広がります)
進め方の手順
- 先生が「犬と猫、すきなのどっち?」とお題を出します。
- 子どもたちは一斉に、あるいは順番に指名されて答えます。
- 慣れてきたら、子どもたち自身にお題を出してもらいます。
- 「どうしてそっちが好きなの?」と理由を付け加えるルールにすると、より会話が深まります。
配慮のポイント&うまくいかない時のヒント
言葉での表現が難しい子には、お題のイラストや写真カードを用意し、指差しで答えられるようにする視覚支援が有効です。「選んで答えるだけ」という手軽さが、会話が苦手な子の「話してみよう」という気持ちを引き出します。ゲームが単調になってきたら、「どうしてそっちが好きなの?」と理由を付け加えるルールにしたり、子どもたち自身にお題を出してもらったりすると、より会話が深まります。どんな答えも「面白いね!」「なるほど!」と肯定的に受け止めましょう。
まとめ:大切なのは「正解」よりも「対話のプロセス」
今回紹介した5つの活動は、いずれも「話すことが楽しい」「自分のことを知ってもらえてうれしい」「友だちのことをもっと知りたい」というポジティブな感情を育むことを目的としています。
大切なのは、活動を通して子どもたちが安心して自分を表現し、お互いを受け入れ合う経験をすることです。活動が盛り上がること以上に、一人ひとりの小さな声に耳を傾け、「話してくれてありがとう」と伝える先生の姿勢が、何よりのコミュニケーションのお手本となります。
自立活動は“正解を出す学習”ではなく、“自分を知り、他者と関わる中で、安心して居られる場所を育てる学び”です。
まずは朝の会の5分間、できそうな活動から試してみませんか? この記事が、先生と子どもたちの豊かなコミュニケーションの一助となれば幸いです。








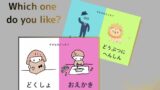



コメント