通知表の所見を書く時期になると、「毎年同じような表現になってしまう」「この子の個性や成長をどう言葉にすればいいのか…」と頭を抱えることはありませんか?
特に特別支援学級では、一人ひとりの子どもが持つユニークな個性と、それぞれのペースで進む成長のプロセスに深く寄り添う必要があります。だからこそ、通知表の所見には、その子らしさがきらりと光る、温かい言葉を届けたいですよね。
この記事では、
特別支援学級における通知表所見の書き方に焦点を当て、6つの観点ごとにすぐに使える文例を30個ご紹介します。明日からそのまま使えるフレーズばかりなので、あなたの所見作成がグッと楽になるはずです。
📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!
「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。
登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。
PDFの受け取りは、たったの30秒!
以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。
所見の作成がぐっと楽になると思います。
▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼
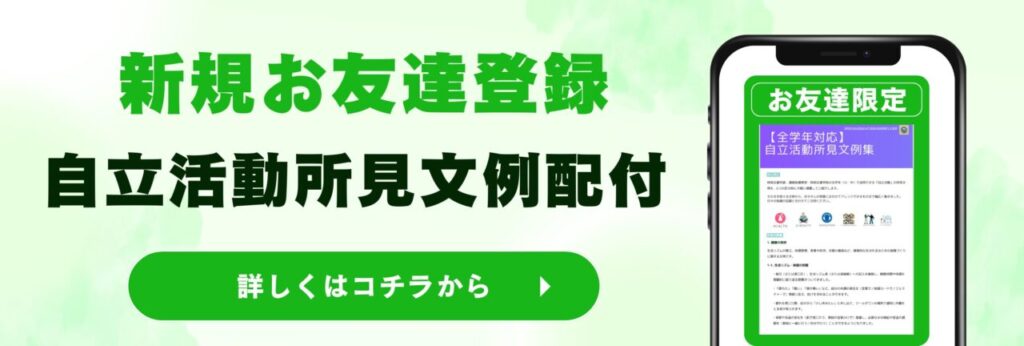
書籍のご案内
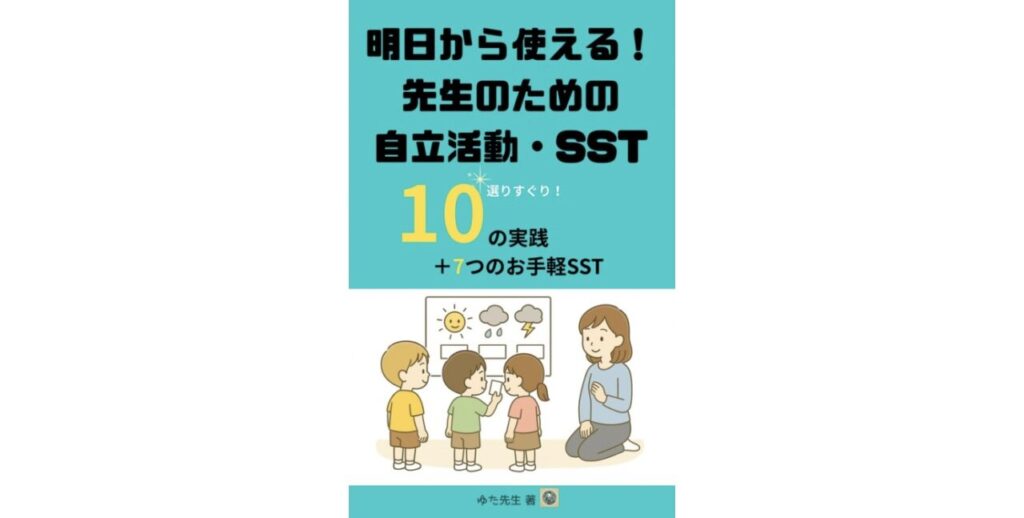
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
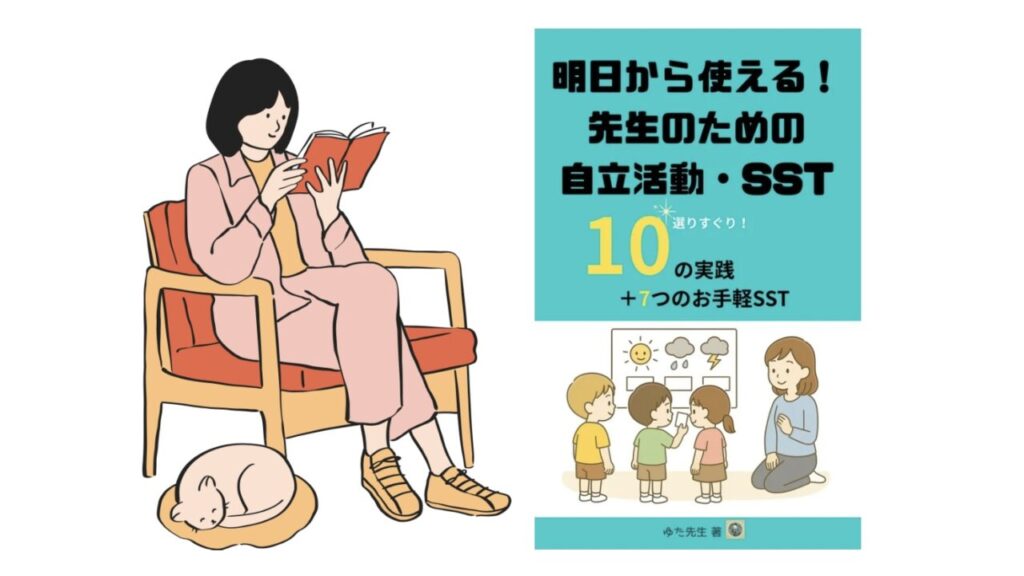
特別支援学級だけでなく、通級指導教室や通常学級での配慮にも活用できる内容です。「活動例がマンネリ化してきた…」「子どもに合う新しいネタが欲しい」そんなときに、きっと役立つ“実践のヒント集”になるはずです。
通知表所見を書くときに大切にしたい3つの視点
所見は単なる「評価」ではありません。子どもの成長を保護者と分かち合うための、大切な「メッセージ」です。以下の3つの視点を意識して書き進めましょう。
① 評価ではなく「成長の物語」を伝える
「できた」「できなかった」という結果だけでなく、子どもがどのような努力をし、どんな工夫を重ねて成長したのかを“物語”として紡ぎましょう。小さな一歩でも、その背景にある努力に光を当てることで、所見が温かいメッセージに変わります。
② 配慮が必要な点は「プロセス」で表現する
苦手なことや課題がある場合でも、「~ができない」「~が苦手」と直接的に書くのは避けましょう。代わりに、「~に難しさがあるが、〇〇しようと努力する姿が見られた」「~に取り組むことで、少しずつ力がつき始めている」といった、プロセスや前向きな姿勢を伝える表現を心がけます。
③ 保護者・本人にも伝わる言葉で
教育や医療の専門用語は避け、保護者が読んで子どもの成長が目に浮かぶような、分かりやすい言葉を選びましょう。例えば、「視覚的な支援」を使うことで集中できた場合は、「イラストや写真を見て理解することで、集中して取り組めました」のように具体的に伝えるのがポイントです。
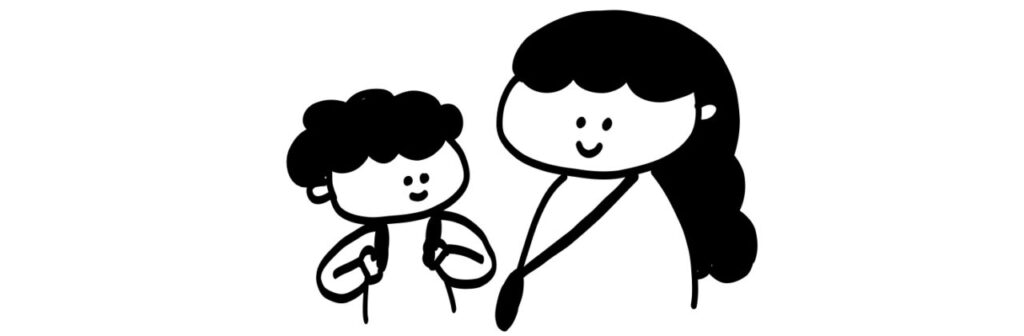
6つの観点別・通知表所見の文例30選【特別支援学級向け】
ここでは、特別支援学級の子どもたちの多様な成長に合わせた所見の文例を、6つの観点に分けてご紹介します。ぜひ、あなたのお子さんにぴったりの言葉を見つけてください。
① 学習面(学習の理解・取り組み方)
- 興味のある単元では目を輝かせ、意欲的に取り組み、粘り強く考える姿が見られました。
- 先生や支援員の声かけを受けながら課題の見通しを立て、落ち着いて学習に取り組むことができました。
- 書くことに難しさがありますが、自分の考えを言葉やイラストで表す練習に前向きに取り組みました。
- 計算や読み書きの基礎的な力を安定して発揮し、着実にステップアップしています。
- 視覚的な教材(例:絵カード、図)を活用することで、内容の理解がぐんと深まりました。
② 社会性(人との関わり、集団活動)
- 友達との関わりの中で、自分の気持ちを「~してほしい」と具体的に言葉で伝えようとする姿が増えました。
- 集団活動では、周囲の動きを意識して行動できる場面が増え、協力する喜びを感じているようです。
- 先生からの誘導や声かけを素直に受け入れ、活動への参加意欲が一段と高まりました。
- ルールのある遊びに繰り返し取り組む中で、相手の気持ちを意識して関わる力が育ってきました。
- 友達とのトラブルが起きた際には、教師と一緒に気持ちを整理し、解決しようと努める姿が見られました。
③ 感情面(情緒の安定・自己理解)
- 気持ちが高ぶった際に、自分で「深呼吸をしよう」と思い出し、落ち着いて行動に移せる場面がありました。
- 自分の感情に気づき、「いまモヤモヤする気持ち」「嬉しい気持ち」などと言葉で表現する力が育ってきました。
- 予想外の出来事に戸惑うこともありますが、安心できる関わりの中で落ち着きを取り戻し、気持ちを切り替えることができました。
- 「できたことノート」に日々の小さな成功を記録することで、自分に自信を持つようになり、表情も明るくなりました。
- 気持ちを落ち着けるために、自らクールダウンできる場所(例:読書コーナー)を選ぶなど、自分の気持ちを調整する工夫が見られます。

④ 自立活動(生活・見通し・調整力)
- 朝の準備や帰りの支度を、持ち物を確認しながら自分のタイミングで見通しを持って進められるようになりました。
- 支援カードやタイマーなどのツールを上手に活用し、自分の行動を計画的にコントロールする力が育っています。
- 学習や活動が始まる前に、気持ちや身体を落ち着ける準備をする習慣が定着し、スムーズに移行できるようになりました。
- 苦手な活動や新しい課題にも、「まずは少しだけやってみよう」と前向きに取り組もうとする気持ちが芽生えています。
- スケジュール表を確認しながら、一日の流れを意識して過ごすことで、見通しを持って行動できる場面が増えました。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
⑤ コミュニケーション面(やりとり・表現)
- 自分の思いを言葉や身振り、表情を使って積極的に伝えようとする場面が増えています。
- 先生の問いかけに対して、アイコンタクトや頷きで応じる姿が安定し、スムーズなやりとりができるようになりました。
- 絵や写真、筆談などの代替手段を使って、自分の気持ちや考えを伝える力が豊かに育ってきました。
- 「おはよう」「ありがとう」「ごめんなさい」など、日常のあいさつやお願いのやりとりが、気持ちを込めてスムーズに行えるようになってきました。
- 友達や先生の話を最後まで聞こうとする姿勢が育っており、会話のキャッチボールができる場面が増えています。
⑥ 身体面・健康(運動・感覚・健康管理)
- 体育や体を使った活動に、無理なく自分のペースで楽しんで取り組む姿が見られました。
- 自分の体調の変化に気づき、「疲れた」「お腹が痛い」「休みたい」などと具体的に伝えられるようになってきました。
- 音や光、特定の感触に対する感覚の偏りに配慮した環境設定(例:個別スペース、イヤーマフ)により、落ち着いて学習に向かうことができています。
- 毎朝の健康観察で、自分の体調に関心を持つようになり、健康チェックにも意欲的に取り組んでいます。
- 大きな音や特定のにおいに敏感な場面でも、教師に「ちょっと苦手」と伝えたり、対処の方法を相談したりできるようになりました。
通知表所見を書くときのコツ3選
これらのコツを意識することで、より心に響く所見が書けますよ。
- その子の“成長の物語”を思い出す
どんなに小さな変化でも、「できたこと」の背景にある努力や工夫、乗り越えた経験を思い出して具体的に書きましょう。具体的なエピソードを一つ添えるだけで、所見に深みが増します。 - マイナス表現は“プロセス表現”に
「できなかった」や「苦手」という直接的な表現は避け、「今は難しさがあるが、〇〇しようと努力している」「~の課題はあるが、〇〇に取り組むことで少しずつ改善している」のように、現在の状況と今後のプロセスを示す言葉を選びましょう。 - 「次のステップ」で締めくくる
子どもの現在の成長を称賛するだけでなく、今後のさらなる成長への期待を込めて締めくくりましょう。例えば、「~ができるようになりました。今後は、この力を生かして〇〇に挑戦していくことを期待しています」のように、次の目標や展望を示すと、前向きな印象を与えられます。
まとめ|通知表所見は、保護者と分かち合う“成長の記録”
特別支援学級の通知表所見は、教師から保護者・本人へ届ける“ことばのプレゼント”です。日々の関わりの中で見つけた子どもの小さな努力や、きらりと光る個性、そして着実な成長を丁寧に見つめ、前向きな言葉で記録していきましょう。
この記事でご紹介した文例やコツが、あなたの所見作成の一助となれば幸いです。あなたらしい温かい言葉で、子どもたちの成長を伝えてくださいね。
関連記事
こちらに自立活動の所見をまとめています👇







コメント