小学校1年生の通知表の所見は、一人ひとりの成長を的確に捉え、保護者に伝えるための大切なメッセージです。何を書けば良いのか、どのような表現が適切なのか、悩まれる先生も多いことでしょう。
この記事では、
通知表の所見文例を網羅的にご紹介します。国語や算数といった教科別の文例から、生活態度や学習態度といった行動の記録に関する文例まで、すぐに使える具体的なフレーズを豊富に集めました。
この記事を読むと分かること
- 小学校1年生の通知表所見を書く際の基本的なポイント
- 国語、算数、生活、音楽、図画工作、体育といった全教科の具体的な所見文例
- 「基本的生活習慣」や「学習態度」など、行動の記録に関する20項目の豊富な所見文例
- 個別の配慮が必要な児童向けの自立活動に関する所見文例
- 所見作成にかかる時間を大幅に短縮するためのヒント
【通知表所見文例小学校1年】を書く上での大切なポイント
文例を紹介する前に、小学校1年生の所見を書く上で大切にしたい3つのポイントを確認しておきましょう。
1. ポジティブな表現を心がける
所見は、児童の成長を認め、励ますためのものです。できていない点や課題を指摘する際も、「〇〇が苦手です」と断定するのではなく、「〇〇に挑戦しています」「〇〇ができるようになると、さらに伸びるでしょう」といった、今後の成長を期待させるポジティブな表現を使いましょう。
2. 具体的なエピソードを盛り込む
「頑張っています」だけでは、どのような姿なのか伝わりません。「休み時間に、苦手だった計算カードの練習を友達と繰り返し、今ではすらすら言えるようになりました」のように、具体的なエピソードを交えることで、所見に説得力が生まれ、保護者にも学校での様子が鮮明に伝わります。
3. 一人ひとりの成長を捉える
他の子と比較するのではなく、その子自身の以前の姿と比べて、どのような成長があったかを記述することが重要です。「入学当初は発言することが少なかったですが、今では自分の考えを自信をもって言えるようになりました」など、個人の成長の軌跡を捉えた言葉は、児童と保護者の大きな喜びとなります。
【教科別】1年生の通知表所見文例
1年生 国語の所見文例

- いつも丁寧な字で、とめ、はね、はらいに気をつけて書こうとする意識が素晴らしいです。特に漢字の練習では、書き順を確かめながら一画一画、心を込めて書いています。
- 音読が大変上手です。登場人物の気持ちを考え、声の大きさを変えたり、間を取ったりと工夫して読んでいます。クラスの友達も〇〇さんの音読をいつも楽しみにしています。
- 話す・聞くの学習では、友達の発表を最後まで静かに聞き、良いところを見つけて感想を伝えることができます。〇〇さんの温かい言葉に、発表した子も嬉しそうな表情をしています。
- 作文では、自分が体験したことや感じたことを、生き生きとした言葉で表現することができます。「〇〇が楽しかったです」だけでなく、「まるで〇〇のようでした」といった表現も使え、感性の豊かさが光ります。
- ひらがなの形を正しく覚え、整った字が書けるようになりました。入学当初から毎日こつこつと練習を続けた努力の成果です。今では、お手本のような美しい字を書きます。
- 授業中の発言が大変活発です。物語を読んで「主人公はどうして〇〇したんだろう」と自分なりの問いを見つけ、クラス全体の学びを深めてくれる存在です。
- 語彙が豊富で、自分の気持ちや考えを的確な言葉で伝えることができます。友達との会話でも、難しい言葉を自然に使い、周りを驚かせています。
- 人の話を集中して聞く姿勢が身についています。先生や友達が話している時は、体を向けて、目を見てうなずきながら聞いており、話している人も安心して話すことができます。
- 書くことへの意欲が非常に高いです。日記やお手紙など、授業以外でも進んで文章を書いており、表現することの楽しさを感じているようです。
- 物語の世界に入り込むのが得意です。読み聞かせの時間には、いつも目を輝かせながら聞き入っており、その豊かな想像力は今後の学習の大きな力となるでしょう。
1年生 算数の所見文例
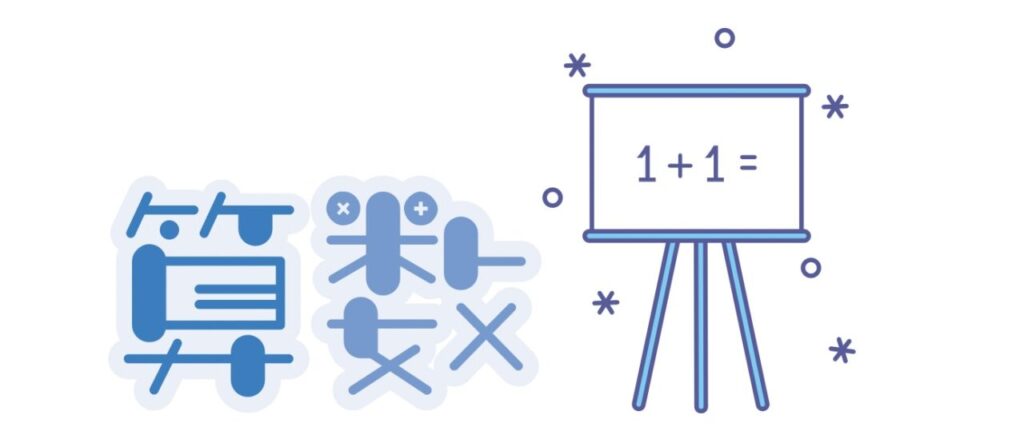
- 計算練習に意欲的に取り組んでいます。初めは時間がかかっていたたし算・ひき算も、繰り返し練習することで、速く正確にできるようになりました。粘り強さの成果です。
- ブロック操作が大変上手です。数の合成・分解の学習では、ブロックを巧みに使いながら数の仕組みを理解し、友達にも分かりやすく説明してあげていました。
- 図形感覚に優れています。かたちづくりの学習では、色板を組み合わせて独創的な形を作り出したり、身の回りから様々な形を見つけたりと、楽しみながら学習を深めています。
- 文章問題を読むと、問題の場面を絵や図に表して考えることができます。式を立てるだけでなく、なぜその式になるのかを筋道立てて説明できる論理的な思考力が育っています。
- 時計の学習に大変興味を持ちました。長い針と短い針の役割をすぐに理解し、休み時間には「先生、今〇時〇分だよ」と元気に教えてくれました。
- 数える活動が得意です。たくさんのものを数える時も、一つひとつ指で押さえたり、印をつけたりと、正確に数えるための工夫を自分で見つけることができます。
- 自分の考えをノートに分かりやすくまとめる力があります。計算の筆算だけでなく、考え方の過程を言葉で書き加えるなど、後で見返しても分かるように工夫しています。
- 問題が解けると「やったー!」と声を上げて喜び、算数そのものを楽しんでいる様子が伝わってきます。その前向きな姿勢が、クラス全体の学習意欲を高めています。
- 難しい問題にも諦めずに挑戦します。すぐに答えが出なくても、様々な角度から考えたり、教科書を読み返したりと、粘り強く取り組むことができます。
- 学習したことを生活の中で見つけるのが上手です。お店の値段を見て計算したり、おやつの数を数えたりと、算数が身近なものであることを実感しているようです。
1年生 生活の所見文例

- 学校探検では、探検バックを手に、興味津々で校長室や職員室を回りました。出会った先生方に元気な挨拶としっかりとした質問ができて、大変立派でした。
- アサガオの世話を毎日欠かさず行いました。水やりをしながら「葉っぱが増えたよ」「つるが伸びてきた」と小さな変化にも気づき、愛情を込めて育てている様子が伝わってきました。
- 生き物への関心が非常に高いです。虫かごを持って校庭の虫を探したり、飼育している生き物の様子を熱心に観察したりと、命を大切にする優しい心が育っています。
- 秋見つけの活動では、どんぐりや落ち葉など、たくさんの秋を夢中になって集めました。集めたもので素敵なお面を作り、その発想力の豊かさに感心させられました。
- 友達と協力して活動する場面で、リーダーシップを発揮することができます。グループでの話し合いでは、みんなの意見を上手にまとめ、活動を引っ張ってくれました。
- 地域の「まちたんけん」では、お店の人に大きな声で挨拶をし、はきはきとインタビューすることができました。地域の人と関わることの楽しさを実感できたようです。
- 昔の遊びの学習では、こま回しやお手玉に熱心に挑戦しました。なかなかうまくできなくても、何度も繰り返し練習する粘り強さが見られました。
- 自分の役割をきちんと理解し、責任をもって果たすことができます。生き物係として、当番の日でなくても「えさは足りているかな」と気にかける姿は素晴らしいです。
- 季節の変化に敏感で、豊かな感性を持っています。「雲の形が面白いね」「風が気持ちいいね」と、自然の美しさや面白さを感じ取り、言葉で表現することができます。
- 身の回りの仕事に意欲的です。教室で汚れている場所を見つけると、さっと雑巾で拭いたり、友達がこぼした牛乳を一緒に片付けてあげたりと、よく気がつく優しい心を持っています。
1年生 音楽の所見文例

- いつも元気いっぱいの明るい歌声で、クラスの歌声をリードしてくれています。歌詞の意味を考え、気持ちを込めて歌おうとする姿勢が素晴らしいです。
- リズム感が良く、手拍子や楽器でリズムを打つのがとても上手です。音楽に合わせて体を動かす活動では、いつも楽しそうに全身で表現しています。
- 鍵盤ハーモニカの練習に熱心に取り組みました。指使いを一つひとつ確認しながら、こつこつと練習を重ね、今では「きらきら星」をすらすらと弾けるようになりました。
- 様々な音楽を聴いて、その曲の雰囲気や情景を想像することが得意です。「この曲は、小鳥が話しているみたい」など、豊かな感性で音楽を味わっています。
- グループでの音楽づくりでは、友達と意見を出し合いながら、協力して一つの音楽を作り上げることができました。自分の担当する楽器に責任をもって取り組んでいました。
- 歌うことが大好きで、音楽の時間だけでなく、休み時間にも友達と楽しそうに歌っています。音楽が〇〇さんの生活の一部になっていることが伝わってきます。
- 楽器の準備や後片付けを素早く行うことができます。自分のものだけでなく、周りを見て手伝うこともでき、みんなが気持ちよく学習できる雰囲気を作ってくれています。
- 指揮をよく見て、それに合わせて歌ったり演奏したりすることができます。音楽全体の流れを感じ取ろうとする集中力があります。
- 日本のわらべうたや遊び歌に興味を持ち、喜んで参加しています。昔から伝わる音楽の面白さや心地よさを感じ取っているようです。
- 発表会では、大勢の前でも堂々と、練習の成果を発揮することができました。やり遂げた後の満足そうな表情が、大きな成長を感じさせました。
1年生 図画工作の所見文例

- 絵を描くことが大好きで、画用紙いっぱいに自分の世界をのびのびと表現します。特に、〇〇さんの描く人物の表情はいつも豊かで、見ているこちらも楽しくなります。
- 色彩感覚が豊かです。空の色を数種類の色を混ぜて表現するなど、自分なりの工夫を凝らして、深みのある作品に仕上げています。
- 粘土を使った造形活動では、指先を器用に使って、細かい部分まで丁寧に作り込むことができます。完成までの見通しをもって、根気強く作業を進める集中力は素晴らしいです。
- 廃材を使った工作では、材料の形や色からイメージを広げ、ユニークな作品を生み出します。その発想力の豊かさにはいつも驚かされます。
- 友達の作品の良いところを見つけて、「その色、きれいだね」「面白い形だね」と具体的に褒めることができます。温かい雰囲気の中で創作活動ができています。
- 道具の使い方が丁寧で、後片付けもきちんとできます。絵の具のパレットや筆をきれいに洗う姿から、物を大切にする心が育っていることが分かります。
- 観察力に優れており、対象をよく見て描くことができます。花の絵を描いた際には、花びらの枚数や葉の筋まで、細かく観察して表現していました。
- 自分の作品に愛着を持ち、作品が完成すると、その時の気持ちや頑張ったところを嬉しそうに話してくれます。創作活動を通して、自己表現の楽しさを感じています。
- はさみやカッターを安全に正しく使うことができます。難しい形を切る時も、慎重に、そして根気強く取り組むことができます。
- 共同制作では、友達と協力しながら一つの作品を作り上げる楽しさを味わうことができました。自分の役割を果たしつつ、全体のバランスを考えて作業を進めていました。
1年生 体育の所見文例

- 運動することが大好きで、いつも意欲的に体育の学習に参加しています。特に、かけっこでは、腕を大きく振って、ゴールまで力いっぱい走り抜ける姿が輝いています。
- ボール運動では、投げる・捕るの基本技能が着実に上達しています。友達と声をかけ合いながら、パス練習を繰り返し行った成果です。
- 鉄棒運動では、逆上がりに挑戦し、何度も失敗しながらも諦めずに練習を続けました。できるようになった時の満面の笑みは、努力が実った素晴らしい瞬間でした。
- ルールを守って、友達と仲良く運動することができます。鬼ごっこやゲームでは、勝敗にこだわるだけでなく、みんなで楽しもうという気持ちが伝わってきます。
- 準備運動や整理運動にも真剣に取り組みます。体の仕組みや怪我の防止に関心を持ち、自分の体を大切にしようとする意識が高いです。
- ダンスの表現活動では、音楽のリズムに乗って、全身を使ってのびのびと表現することを楽しんでいます。恥ずかしがらずに自分を表現できるのは素晴らしいことです。
- なわとびの練習にこつこつと取り組み、前回し跳びが連続で跳べるようになりました。目標をもって努力する大切さを学んだようです。
- 体育係として、号令をかけたり、用具の準備をしたりと、責任をもって活動し、授業がスムーズに進むように貢献してくれました。
- 友達が技に挑戦している時には、「がんばれ!」「おしい!」と自然に声援を送ることができる優しい心を持っています。クラスの温かい雰囲気を作ってくれる存在です。
- 水泳学習では、水に顔をつけるのが苦手でしたが、少しずつ挑戦し、最後には潜れるようになりました。自分のペースで目標を乗り越えた経験は、大きな自信になったことでしょう。
【行動の記録】小学校1年生の通知表所見文例
基本的生活習慣

- 毎朝、教室に入るとすぐにランドセルをしまい、その日の学習の準備を手際よく整えることができます。落ち着いて一日をスタートする良い習慣が身についています。
- ハンカチやティッシュなど、自分の持ち物を毎日忘れずに持ってくることができます。持ち物への意識が高く、自己管理能力が育っています。
- 授業の始まりと終わりの挨拶が、いつもはきはきと気持ちよくできます。けじめのある学校生活を送ろうとする姿勢が素晴らしいです。
- 休み時間と学習時間の切り替えがきちんとできます。チャイムが鳴ると、遊びを止めて速やかに自分の席に着くことができます。
- 自分の使ったものや場所を、次に使う人のことを考えてきれいに片付けることができます。ロッカーの中もいつも整理整頓されています。
- 「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムが整っており、毎日元気に登校しています。ご家庭でのご協力に感謝いたします。
- 丁寧な言葉遣いを心がけており、先生や友達に対して「~です」「~ます」と話すことができます。
- 服装の乱れに自分で気づき、直すことができます。シャツを入れたり、名札をつけたりと、身だしなみを整える意識があります。
- 下校の際には、忘れ物がないか自分の机の中や周りをきちんと確認してから帰ります。責任感の表れです。
- 規則正しい生活を送ろうとする意識があり、健康観察カードなども自分で記入しようと努力しています。
学習態度

- 常に学習意欲が高く、新しいことを学ぶのを楽しんでいます。「なぜだろう」「どうしてだろう」と知的好奇心にあふれた質問をよくします。
- 最後まで話を集中して聞く姿勢が素晴らしいです。先生や友達の話に静かに耳を傾け、大切なことを聞き逃さないようにしています。
- 授業中は正しい姿勢を保ち、学習に取り組むことができます。その真剣な態度は、周りの友達にも良い影響を与えています。
- ノートを丁寧に書くことができます。マス目いっぱいに整った字で書き、学習の足跡をきちんと残そうとしています。
- 発表する際には、自信をもって、みんなに聞こえる大きな声で話すことができます。自分の考えを伝えようとする意欲を感じます。
- 分からないことがあると、すぐに「分かりません」と助けを求めるのではなく、まずは自分で考えようと努力する姿が見られます。
- 学習用具を大切に扱い、準備や片付けをきちんと行うことができます。鉛筆もいつもきちんと削られています。
- 友達の意見もしっかりと聞き、自分の考えと比べながら学習を深めることができます。多様な考え方に触れる楽しさを感じています。
- 一度学習したことも、繰り返し復習しようとする真面目さがあります。漢字練習など、こつこつと努力を積み重ねています。
- 学習活動に前向きで、どんなことにも「やってみたい」と積極的に挑戦します。そのチャレンジ精神をこれからも大切にしてほしいです。
挨拶
- いつでも、どこでも、誰にでも、気持ちの良い挨拶ができます。〇〇さんの元気な「おはようございます!」の声で、一日が明るく始まります。
- 相手の目を見て、にこやかに挨拶をすることができます。心が通い合う、温かい挨拶です。
- 廊下で来客の方とすれ違う際にも、自分から立ち止まって「こんにちは」と挨拶ができます。礼儀正しい態度が身についています。
- 「ありがとう」「ごめんなさい」を、適切な場面で素直に言うことができます。感謝と反省の気持ちを言葉で表現できるのは素晴らしいことです。
- 朝、教室に入ってくる友達一人ひとりに「〇〇さん、おはよう」と声をかけており、クラスの和やかな雰囲気を作っています。
- 職員室など、教室以外の場所に入る時も、「失礼します」と声をかけてから入ることができます。TPOに応じた挨拶ができます。
- 挨拶の声が小さい友達がいると、「もっと大きい声で言おうよ」と優しく促す姿も見られ、クラス全体で挨拶を良くしていこうという気持ちが感じられます。
- 登下校の際には、見守り隊の方々にも、感謝の気持ちを込めて「ありがとうございます」と挨拶ができています。
- 返事の「はい」がとてもはきはきとしており、聞いている方も気持ちが良いです。呼ばれたらすぐに反応できる素直さがあります。
- 入学当初に比べて、格段に挨拶の声が大きくなりました。自信をもって声を出せるようになった成長の証です。
健康・体力の向上
- 毎日元気に登校し、ほとんど休むことなく学校生活を送ることができました。健康な体づくりへの意識が高いです。
- 体育の時間をはじめ、体を動かすことが大好きで、いつも生き生きと活動しています。体力の向上が見られます。
- 手洗いやうがいを丁寧に行い、感染症の予防に努めています。自分の健康は自分で守るという意識が育っています。
- 自分の体調の変化に気づき、「少し頭が痛いです」などと先生に伝えることができます。
- 好き嫌いなく、給食をバランスよく食べようと努力しています。食べ物と健康のつながりを理解し始めています。
- 運動会のかけっこでは、ゴールを目指して最後まで力いっぱい走りました。体力だけでなく、精神的な強さも感じられました。
- 休み時間には、外で元気に体を動かしており、体力の向上につながっています。
- 健康観察カードへの記入を通して、自分の生活リズムを振り返る習慣がつきつつあります。
- 姿勢に気をつけて学習に取り組んでおり、良い姿勢を保つための筋力がついてきました。
- 「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さを理解し、規則正しい生活を心がけています。ご家庭でのご協力に感謝いたします。
外で元気に遊ぶ
- 休み時間になると、真っ先に校庭へ飛び出していき、友達と元気いっぱい遊んでいます。心身ともに健康な証拠です。
- 鬼ごっこやドッジボールなど、ルールのある遊びを友達と楽しむことができます。体を動かす爽快さを感じているようです。
- 鉄棒やジャングルジムなど、様々な遊具を使って工夫して遊んでいます。バランス感覚や筋力が育っています。
- 男女分け隔てなく、大勢の友達の輪の中に入って遊ぶことができます。コミュニケーション能力の高さがうかがえます。
- 友達と遊ぶ中で、順番を守ったり、遊具を譲り合ったりと、社会的なルールを学んでいます。
- 雨の日で外に出られない時も、教室で工夫して体を動かす遊びを考えるなど、いつでも活動的です。
- 外で遊んだ後は、きちんと手洗いをし、汗を拭うなど、衛生面にも気をつけることができています。
- 遊びの中で友達と意見がぶつかった時も、自分の気持ちを伝え、相手の言い分を聞こうとする姿が見られます。
- 新しい遊びを考えたり、遊びのルールを工夫したりと、創造力を働かせて遊びを豊かにしています。
- 自然と触れ合うのが好きで、虫を探したり、草花で遊んだりと、校庭の自然の中で伸び伸びと過ごしています。
給食で好き嫌いなく食べる
- いつも美味しそうに給食を食べています。「今日の給食、おいしいね」と友達と話しながら、楽しい雰囲気で食事をしています。
- 苦手な食べ物が出てきても、一口は挑戦してみようと努力する姿が見られます。素晴らしいチャレンジ精神です。
- 給食を残さず食べられた日には、とても嬉しそうな表情をしています。達成感が次への意欲につながっています。
- 様々な食材に興味を持ち、「このお野菜は何?」と質問するなど、食への関心が高いです。
- 配膳された給食は、感謝の気持ちを込めて、最後まで食べようと頑張っています。食べ物を大切にする心が育っています。
- 友達が苦手なものを残していると、「少し頑張ってみようよ」と励ましの声をかけている姿は、とても立派です。
- アレルギーに配慮し、自分の食べられるものをきちんと理解して食事をしています。自己管理能力があります。
- 入学当初は食べるのが遅かったですが、今では時間内に食べ終えることができるようになりました。大きな成長です。
- 食事のマナーを守り、正しい姿勢で、お箸を上手に使って食べることができます。
- 栄養士の先生の話にもよく耳を傾け、食べ物と体の関係について学ぼうとしています。
自主・自立
- 先生の指示を待つだけでなく、次に何をすべきかを自分で考えて行動することができます。
- 朝の準備や帰りの支度など、自分の身の回りのことを自分一人の力で最後までやり遂げようとします。
- 分からないことがあった時、まずは自分で教科書や資料を見て調べようとする探求心があります。
- グループ活動では、リーダーでなくても、自分の意見をしっかりと述べ、主体的に参加しようとします。
- 自分の持ち物の管理がきちんとできています。忘れ物をしても、人のせいにせず、自分の責任として受け止めることができます。
- 学習計画を立て、それにしたがって家庭学習を進めようと努力しています。自律的な学習態度が育ちつつあります。
- 休み時間の過ごし方を自分で決め、有意義に時間を使おうとしています。
- 自分の考えや気持ちを、人の意見に流されずに、はっきりと表現することができます。
- 失敗を恐れずに、新しいことにも進んで挑戦しようとする意欲があります。
- 係の仕事など、自分の役割を言われなくても責任をもって果たそうとする姿に、自立心の芽生えを感じます。
自分の力で考え、行動する
- 問題解決の場面で、すぐに答えを求めるのではなく、自分なりの解決策を粘り強く考えようとします。
- 「どうしてこうなるのかな」と常に問いを持ち、物事の仕組みや理由を知ろうとする知的な探求心があります。
- 友達との間でトラブルが起きた時も、感情的にならず、どうすれば解決できるかを冷静に考えようとします。
- グループでの話し合いでは、人の意見を聞いた上で、それに対する自分の考えを述べることができます。
- 生活科の観察活動では、自分なりの視点で気づいたことを発見し、それを皆に伝えようとします。
- 掃除の時間、汚れている場所を自分で見つけ、どうすればきれいになるかを考えて工夫して取り組んでいます。
- 「先生、〇〇してもいいですか」ではなく、「〇〇しようと思いますが、いいですか」と、自分の考えをもって提案することができます。
- 学習の中で、より良い方法はないか、もっと簡単なやり方はないかと、常に考えながら取り組んでいます。
- 人の真似をするだけでなく、自分らしさを表現しようと、作品作りや発表で工夫を凝らしています。
- 自分の行動に責任を持ち、周りの状況をよく見て、今何をすべきかを判断して動けるようになってきました。
粘り強く取り組む
- 一度始めたことは、最後まで諦めずにやり遂げようとする強い意志を持っています。
- 計算練習や漢字練習など、地道な努力をこつこつと続けることができます。その真面目さが学力の基礎を支えています。
- 難しい課題に直面しても、「難しいからやらない」ではなく、「どうすればできるかな」と考え、粘り強く挑戦します。
- 体育の鉄棒運動では、何度も失敗しながらも練習を続け、ついに逆上がりができるようになりました。素晴らしい根性です。
- 時間のかかる作業でも、集中力を切らさずに黙々と取り組むことができます。
- 自分の立てた目標に向かって、根気強く努力を続けることができます。
- 思うようにいかなくても、すぐに投げ出さず、気分を切り替えてもう一度挑戦しようとします。
- 友達が諦めかけている時に、「もう少し頑張ろうよ」と励ますことができる頼もしい存在です。
- 細かい作業も、最後まで丁寧に、気を抜かずに仕上げることができます。
- 困難なことでも、やり遂げた時の達成感を知っており、それが次の挑戦への意欲となっています。
目標に向かって取り組む
- 「なわとびで二重跳びができるようになる」など、自分で具体的な目標を立て、それに向かって計画的に練習することができます。
- 目標を達成するために、今何をすべきかを考え、日々の努力を積み重ねることができます。
- 学習発表会では、自分のセリフを完璧に覚え、堂々と発表するという目標を立て、見事に達成しました。
- 目標達成までの過程を楽しみ、試行錯誤すること自体に価値を見出しているようです。
- 一つの目標を達成すると、すぐに次の新しい目標を見つけて挑戦しようとする向上心があります。
- 友達と励まし合いながら、クラス全体の目標に向かって一丸となって取り組むことができます。
- 自分の目標を周りに宣言することで、自分を励まし、意欲を高めることができています。
- 目標が達成できた時の喜びを素直に表現し、その経験が大きな自信につながっています。
- たとえ目標が達成できなくても、そこまでの努力の過程を振り返り、次への糧とすることができます。
- 高い目標にも臆することなく、「やってみたい」と前向きに挑戦する姿は、周りの友達にも良い刺激を与えています。
責任感
- 係や当番の仕事を、言われなくても最後まで責任をもってやり遂げます。クラスのみんなが安心して頼りにしています。
- 自分がやるべきことをきちんと把握し、忘れることなく実行できます。
- グループ活動では、自分の役割を自覚し、チームに貢献しようと一生懸命取り組みます。
- 自分が使った場所や物は、必ず元の状態よりもきれいにして片付けようとします。
- 友達との約束を大切にし、必ず守ろうとします。信頼できる存在です。
- 自分の過ちを素直に認め、「ごめんなさい」と謝ることができる誠実さがあります。
- 生き物係として、毎日欠かさず世話をし、命を預かることの責任を理解しています。
- 日直の仕事では、朝の会や帰りの会の司会を、責任感をもって立派に務めあげました。
- クラスのために自分にできることはないかと常に考え、進んで仕事を見つけて行動します。
- 任された仕事は、途中で投げ出すことなく、最後までやり抜く強い責任感を持っています。
創意工夫
- 図画工作の作品作りでは、自分なりのアイデアを加え、独創性あふれる作品を生み出します。
- 問題解決の場面で、既存の方法にとらわれず、新しいやり方を考えて試してみようとします。
- 生活科の遊びの工夫では、身近な材料を使って、面白いおもちゃを発明しました。発想力が豊かです。
- 話し合い活動で行き詰った時、誰も思いつかなかったような視点から意見を出し、議論を活性化させます。
- ノートのまとめ方を自分なりに工夫し、絵や図を使って分かりやすく整理しています。
- より良くするためにはどうすれば良いかを常に考え、改善しようとする姿勢があります。
- 友達の意見の良いところを取り入れ、さらに自分のアイデアを加えて発展させることができます。
- 遊びのルールを、みんながもっと楽しめるように工夫して提案することができます。
- 表現活動において、自分らしさを出すための工夫を凝らしており、見る人を楽しませてくれます。
- 掃除の時間に、どうすれば効率よくきれいにできるかを考え、新しいやり方を試しています。
思いやり・協力
- 困っている友達がいると、さっと駆け寄り、「どうしたの?」「手伝おうか?」と優しく声をかけることができます。
- グループ活動では、自分の意見を主張するだけでなく、友達の考えにも真剣に耳を傾け、協力して課題を解決しようとします。
- 重い荷物を持っている友達がいると、進んで「半分持つよ」と言って手伝ってあげる優しい心を持っています。
- 自分のことだけでなく、クラス全体のことを考え、みんなが気持ちよく過ごせるように行動できます。
- 体調が悪そうな友達に気づき、そっと先生に知らせてくれるなど、周りをよく見ています。
- 転んでしまった友達に、優しく手を差し伸べ、保健室まで付き添ってあげていました。
- 自分のものさしなどを、忘れた友達に快く貸してあげることができます。
- 友達が良いことをしたり、頑張ったりした時に、「すごいね!」「上手だね!」と心から褒めることができます。
- 班で協力して作業する場面では、率先して大変な役割を引き受け、貢献しようとします。
- みんなで使うものを大切に扱い、次に使う人のことを考えた行動がとれます。
生命尊重・自然愛護
- 生き物係として、毎日愛情を込めて世話をし、命の尊さを実感しています。
- 校庭で見つけた小さな虫も、決してむやみに殺したりせず、優しく観察し、元の場所に戻してあげることができます。
- 生活科で育てているアサガオに毎日水をやり、「大きくなってね」と声をかけています。植物にも命があることを感じています。
- 道端に咲いている花を大切にし、折ったり摘んだりすることなく、その美しさを味わうことができます。
- 給食を残さず食べることで、命をいただいていることへの感謝の気持ちを表しています。
- 動物や植物が登場する物語を読むと、登場人物に深く共感し、命の大切さについて考えています。
- 校庭の木々や草花の変化によく気づき、季節の移ろいを感じ取る豊かな感性を持っています。
- ゴミが落ちていると、進んで拾ってゴミ箱に捨て、学校をきれいにしようとします。自然環境を大切にする心の表れです。
- 友達が生き物を乱暴に扱っていると、「優しくしてあげて」と注意することができる勇気を持っています。
- 命に関する授業では、真剣な表情で話を聞き、自分なりに命の重さについて考えている様子がうかがえました。
勤労・奉仕
- 自分の当番活動だけでなく、みんなのために進んで仕事を見つけて働こうとします。
- 「誰かがやるだろう」ではなく、「自分がやろう」という気持ちで、クラスのために行動できます。
- 重いものを運んだり、汚れる仕事だったり、人が嫌がるような仕事も、率先して引き受けます。
- 働くことの尊さや、人の役に立つことの喜びを感じているようです。
- 掃除の時間、時間いっぱい黙々と働き、任された場所をピカピカにしています。
- 先生や友達が困っていると、すぐに「何かお手伝いすることはありますか」と声をかけることができます。
- クラスで使う用具の準備や片付けなど、みんなが気持ちよく学習できるように、陰で支えてくれています。
- ボランティア活動にも関心があり、募金活動などに積極的に協力していました。
- 自分の役割を最後までやり遂げるだけでなく、周りを見て、手伝いが必要な友達をサポートできます。
- 感謝の言葉をかけられると、はにかみながらも、とても嬉しそうな表情をします。奉仕の心が育っています。
係活動
- 自分の係の仕事に誇りを持ち、責任をもって活動しています。
- どうすればもっと係活動が楽しくなるか、クラスの役に立てるかを考え、新しい企画を提案してくれました。
- 係のメンバーと協力し、声をかけ合いながら、和やかな雰囲気で活動を進めることができています。
- 活動に必要なものを事前に準備するなど、見通しをもって取り組んでいます。
- 活動の記録を丁寧に書いたり、皆への報告を分かりやすくしたりと、最後まで責任をもって務めています。
- 自分の係だけでなく、他の係の活動にも関心を持ち、良いところを認め合うことができます。
- 活動中に問題が起きても、メンバーと話し合い、解決しようと努力します。
- みんなの前で活動内容を発表する際、堂々とした態度で、分かりやすく説明することができました。
- 休み時間も使って、熱心に係の仕事に取り組む姿は、他の児童の模範となっています。
- 係活動を通して、自分の役割を果たすことの重要性と、友達と協力することの楽しさを学んでいます。
掃除
- 掃除の時間になると、すぐに自分の持ち場へ行き、黙々と作業を始めます。「黙働」が身についています。
- 隅々まで目を配り、小さなゴミやほこりも見逃さずにきれいにしようとします。
- ほうきの使い方、雑巾の絞り方など、正しい掃除の仕方を理解し、実践しています。
- 自分の担当場所が終わると、「どこか手伝うところはありますか」と、他の場所も手伝おうとします。
- 机や椅子を丁寧に運び、教室を広く使って掃き掃除や拭き掃除ができるように工夫しています。
- 友達と協力して、重い教卓などを運び、見えない場所まできれいにしようとします。
- 掃除道具を大切に扱い、使った後はきちんと片付けることができます。
- 時間いっぱい、最後まで手を抜かずに掃除に取り組む真面目さがあります。
- 汚れている場所を自分で見つけ、担当場所でなくてもきれいにしようとする姿が見られます。
- 掃除を通して、自分たちが使う場所をきれいにすることの気持ちよさを感じているようです。
給食当番
- 給食当番の仕事に責任をもち、白衣をきちんと着て、衛生面に気をつけて配膳しています。
- 食器や食缶を運ぶ際には、周りに気を配り、安全に運ぶことができます。
- 友達と協力し、手際よく準備を進めることができます。おかずを均等につぎ分けるのが上手です。
- 「いただきます」の前に、みんなの準備が終わっているかを確認するなど、周りを見る力があります。
- アレルギーのある友達への配慮を忘れず、間違えがないように慎重に配膳することができます。
- 後片付けでは、残った牛乳を片付けたり、食器を種類ごとにまとめたりと、率先して動いています。
- 当番の仕事を通して、みんなのために働くことの喜びを感じているようです。
- 「ごちそうさま」の後の片付けも、他の人より早く始め、スムーズに終わるように貢献しています。
- 当番ではない日も、準備が遅れていると、さっと手伝いに行く優しさがあります。
- 衛生管理の意識が高く、配膳台をきれいに拭いたり、身支度を整えたりする姿は立派です。
公正・公平
- 誰に対しても分け隔てなく、同じ態度で接することができます。
- 遊びの仲間はずれなどを決してせず、自分から声をかけて輪に入れようとします。
- 物事を決めるときには、自分の意見だけでなく、みんなの意見を聞いて、公平に判断しようとします。
- ゲームや勝負事で、ルールをきちんと守り、正々堂々と取り組むことができます。
- 当番活動などを、特定の人に偏ることなく、みんなで分担しようと提案します。
- 仲の良い友達だけでなく、いろいろな友達と関わろうとする広い心を持っています。
- 自分に不利なことでも、正直に話すことができる誠実さがあります。
- 話し合いで意見が分かれた時、多数決だけでなく、少数意見も尊重しようとします。
- 係や役割を決める際、自分勝手な理由でなく、適材適所を考えて推薦することができます。
- えこひいきすることなく、誰の意見でも良いものは良いと認めることができる素直さを持っています。
公共心・公徳心
- みんなが使う教室や廊下、水道などをきれいに使おうとする意識が高いです。
- スリッパが乱れていると、自分が使っていなくても、さっと並べ直すことができます。
- 廊下や階段は静かに右側を歩くなど、学校のルールをしっかりと守って生活しています。
- 節水や節電を心がけ、使わない電気を消したり、水を出しっぱなしにしないように気をつけたりしています。
- 図書館では、静かに本を読み、他の人の迷惑にならないように行動できます。
- 自分が使った後の手洗い場が濡れていたら、次の人が気持ちよく使えるように拭いています。
- ゴミの分別をきちんと行い、リサイクル活動にも積極的に協力しています。
- 地域の一員としての自覚を持ち、登下校の際も、道に広がらず安全に歩くことができます。
- 落し物を見つけると、すぐに先生に届けます。正直で立派な行動です。
- 公共のものを自分だけのもののように扱わず、みんなで大切に使おうという気持ちが育っています。
【自立活動】小学校1年生の通知表所見文例
個別の配慮や支援が必要な児童向けの所見です。一人ひとりの課題や目標に合わせて、スモールステップでの成長を具体的に記述することが大切です。
- クールダウンの場所や方法を自分で選べるようになり、気持ちが乱れた時に、落ち着いて自分の気持ちを立て直すことができるようになってきました。
- 「手伝ってください」「分かりません」など、困った時に自分からSOSのサインを言葉やカードで伝えられる場面が増えました。
- 視覚的な支援(絵カードやスケジュール表)を手がかりに、次に行うことを自分で確認し、見通しをもって活動に参加できるようになりました。
- 友達との関わりの中で、自分の気持ちを一方的に伝えるだけでなく、「〇〇さんはどう思う?」と相手の気持ちを尋ねようとする姿が見られるようになりました。
- 苦手な音や光に対して、イヤーマフを使うなど、自分でできる対処法を身につけ、落ち着いて学習に取り組める時間が増えています。
- 手先の細かな動きがよりスムーズになり、ハサミを線に沿って切ったり、紐を結んだりと、できることが増え、自信につながっています。
- 集中が途切れそうになった時、決められた休憩を取ることで、気持ちを切り替え、再び学習に取り組むことができるようになりました。
- 自分の考えを言葉で表現するのが難しい時、絵やジェスチャーを使って伝えようと工夫する姿が見られます。表現方法が豊かになりました。
- ルールのある遊びに参加し、順番を待ったり、勝ち負けを受け入れたりすることができるようになってきました。友達と遊ぶことの楽しさを感じています。
- 感覚の過敏さに配慮しながら、粘土や絵の具などの感触遊びに少しずつ挑戦し、楽しめるようになってきました。活動の幅が広がっています。
特別支援学級の通知表「所見」に特化した文例集はこちら💁
書籍のご案内
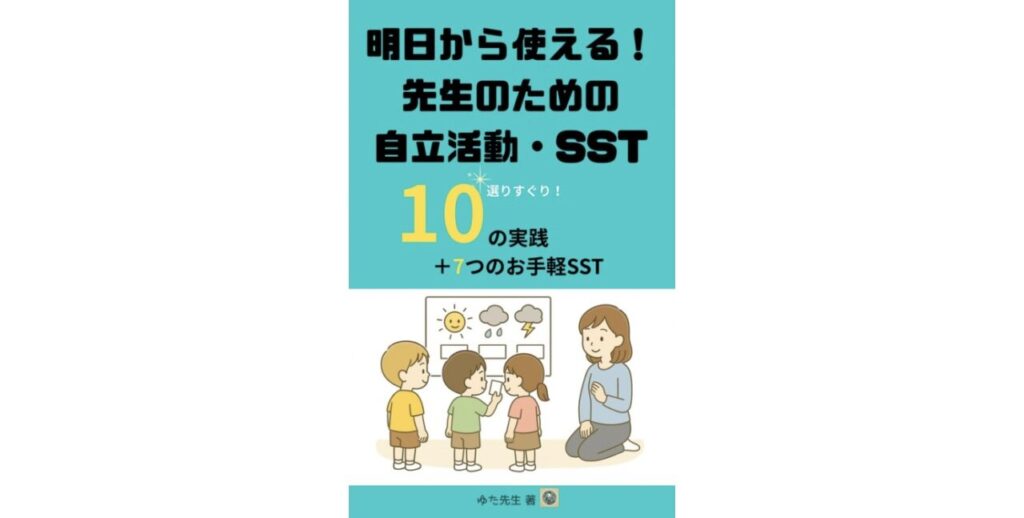
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle、書籍版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。→note 教材セットはこちら
各学年の所見文例集リンク
各学年の所見文例集はこちらから読むことができます👇
まとめ
今回は、小学校1年生の通知表の所見文例を、教科別、行動の記録、自立活動に分けてご紹介しました。1年生は、入学してから心も体も大きく成長する大切な時期です。ここに挙げた文例はあくまで一例です。ぜひ、日々の教育活動の中で見つけた、その子ならではの輝く瞬間や具体的なエピソードを盛り込み、世界に一つだけの所見を作成してください。先生からの温かいメッセージは、子どもたちと保護者にとって、何よりの励みとなるはずです。
参考外部リンク
所見作成の際には、学習指導要領の趣旨を理解しておくことも重要です。以下の文部科学省のページもぜひご参照ください。
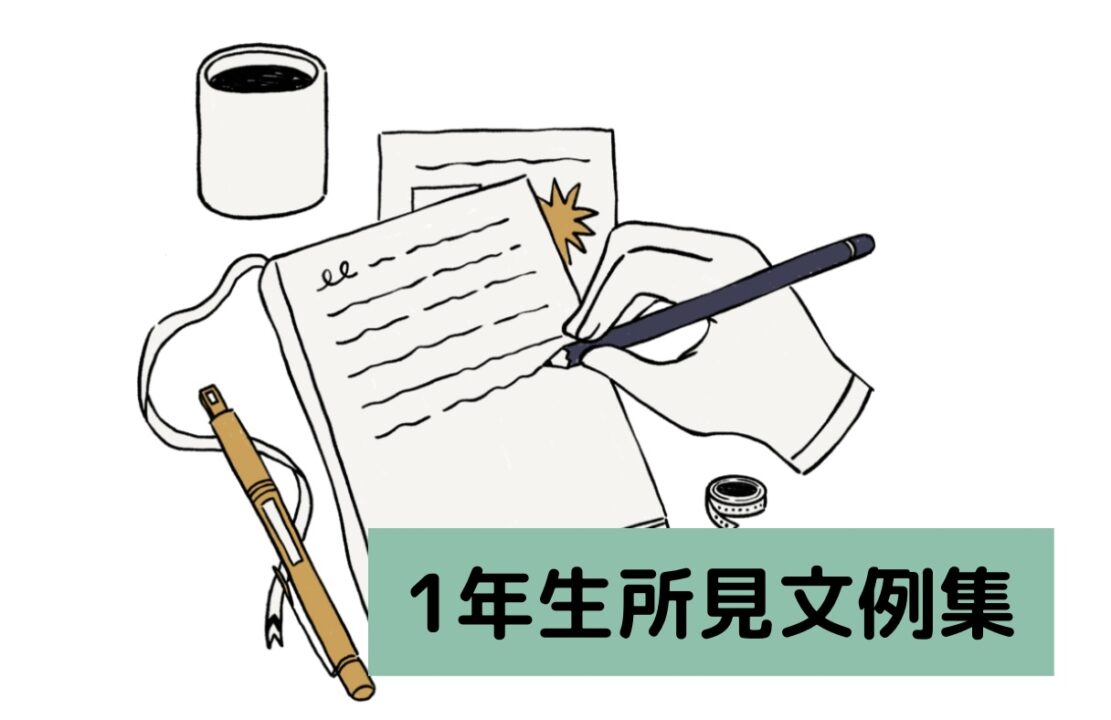



コメント