【永久保存版】通知表 所見 文例 小学校3年|教科別・行動面で使える文例200選以上!
この記事では、通知表所見文例 小学校3年をテーマに、豊富な文例を教科別・行動面別にご紹介します。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
- すぐに使える小学校3年生の通知表所見の具体的な文例
- 国語や算数など、主要教科ごとの成長を伝える表現方法
- 「基本的生活習慣」や「思いやり・協力」など、行動の記録に関する詳細な文例
- 子供一人ひとりの個性を尊重し、次の学びに繋げるための所見の書き方のヒント
膨大な文例を掲載していますので、ぜひお子さんの姿と照らし合わせながら、最適な表現を見つけるための参考にしてください。
通知表所見文例 小学校3年 を書く上での大切な視点
小学校3年生は、具体的な物事を考える段階から、少しずつ抽象的な事柄についても考えられるようになる、思考力が大きく伸びる時期です。また、集団の中での自分の役割を意識し始め、友達との関わりも深まります。いわゆる「ギャングエイジ」の入り口に立ち、仲間意識が芽生える大切な時期でもあります。所見を書く際は、こうした3年生特有の発達段階を踏まえ、一人ひとりの成長の様子を具体的に捉え、保護者に分かりやすく伝えることが重要です。
- 具体的なエピソードを盛り込む:「頑張った」だけでなく、「○○の場面で、△△という工夫をして最後までやり遂げた」のように、具体的な行動や事実を記述しましょう。
- 成長した点を明確にする:学期の初めと比べて、どのような点が、どのように伸びたのかを記述することで、成長の過程が伝わります。
- ポジティブな言葉で未来へ繋げる:課題点を指摘する場合も、「〇〇が苦手です」ではなく、「〇〇の力を伸ばすために、△△に挑戦していくことを期待しています」のように、前向きな表現を心がけましょう。

3年生 所見 国語

3年生の国語では、物語の登場人物の気持ちの変化を読み取ったり、自分の考えを文章にまとめたりする力が求められます。辞書を引く習慣や、ローマ字の学習も始まります。
国語の所見文例
- 物語文「三年とうげ」の学習では、登場人物の気持ちが大きく変わる場面に線を C引き、その理由を自分の言葉で的確に説明することができました。読解力が着実に育っています。
- 「自分の考えを伝えよう」の単元では、説得力のある文章を書くために、理由や具体例を複数挙げる工夫が見られました。論理的に考える力が伸びています。
- 分からない言葉が出てくると、すぐに国語辞典を引いて意味を調べる習慣が身についています。語彙が豊富で、日々の会話や作文にも活かされています。
- 毎日の漢字練習に熱心に取り組み、一画一画とても丁寧に書いています。小テストでは常に満点を取るなど、努力が着実に実を結んでいます。
- ローマ字の学習に意欲的に取り組み、休み時間にも友達と問題を出し合うなど、楽しみながら覚えることができました。タイピングの基礎となる大切な力です。
- グループでの話し合い活動では、友達の意見に静かに耳を傾け、賛成する点や違う考えをはっきりと述べながら、話し合いを深めることができます。
- 音読がとても上手です。場面の様子や登場人物の気持ちが伝わるように、声の大きさや速さを工夫して読むことができ、聞いている人を引き込みます。
- 観察記録を書く際には、「まるで〜のようだ」といった比喩表現を使い、生き生きと様子が伝わる文章を書くことができました。表現力が豊かです。
- 詩の学習では、言葉のリズムや響きの面白さを感じ取り、自分でもオリジナルの詩を作成して楽しむ様子が見られました。言葉への感性が育っています。
- 作文を書く際に、段落のつながりを意識し、「はじめ」「中」「おわり」の構成で分かりやすくまとめる力がついてきました。文章構成力が向上しています。
3年生 所見 算数
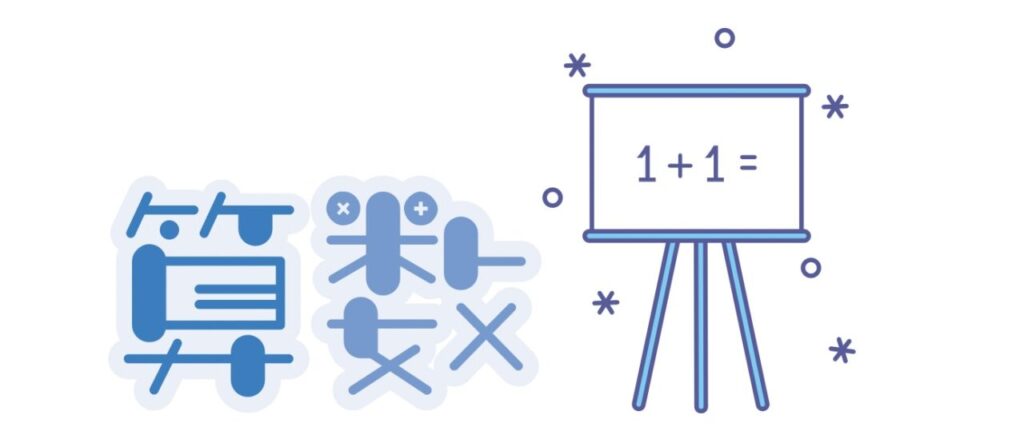
3年生の算数では、わり算、円と球、分数、小数など、新しい概念が数多く登場します。具体的な操作活動を通して、数の仕組みを理解することが大切になります。
算数の所見文例
- わり算の学習では、おはじきを使った操作活動を通して、「等分除」と「包含除」の二つの意味を正しく理解することができました。文章問題も正確に立式できます。
- コンパスを使った作図がとても得意です。円の中心を見つけ、丁寧かつ正確に美しい模様を描くことができ、作品は教室に掲示しました。
- 難しい計算問題にも、答えが出るまで粘り強く挑戦します。途中で間違いに気づくと、どこで間違えたのかを自分で見つけ、やり直す真面目さがあります。
- 小数や分数の学習では、数直線や図を使って数の大きさを視覚的に捉えることで、大小関係を正しく理解することができました。
- 図形の問題では、箱の形(直方体・立方体)の辺や頂点の数を、実際に箱を触りながら正確に数えることができました。立体を捉える感覚が優れています。
- グループで問題解決に取り組む際には、自分の考えを図や式で友達に分かりやすく説明し、みんなの考えをまとめるリーダーシップを発揮しました。
- 「重さ」の学習では、身の回りにある様々な物の重さを予想し、実際に測って比べる活動に興味津々で取り組んでいました。量感への関心が高いです。
- 計算ドリルに毎日こつこつと取り組み、計算のスピードと正確さが飛躍的に向上しました。努力の成果がはっきりと表れています。
- 授業中に「どうしてそうなるの?」と根本的な問いを投げかけることが多く、物事の本質を理解しようとする探究心を持っています。
- 学習したそろばんの知識を活かし、日常の簡単な計算を暗算で素早く解くことができます。数の感覚が非常に鋭いです。
3年生 所見 理科

3年生から始まる理科。身近な自然事象への興味・関心を高め、観察や実験を通して問題解決能力の基礎を養うことが目標です。
理科の所見文例
- 昆虫の観察では、ルーペを上手に使って体のつくりを細かく観察し、足の数や体のしま模様などを詳しくスケッチすることができました。観察力が鋭いです。
- 「風やゴムの力」の実験では、どうすれば車が遠くまで進むのか、ゴムの伸ばし方や風の当て方を工夫しながら、友達と協力して試行錯誤する姿が見られました。
- 太陽の動きを調べる活動では、一日中、時間ごとに影の向きや長さを根気強く記録し、太陽と影の関係性を見事に発見することができました。探究心と忍耐力があります。
- 植物の成長の観察では、毎日欠かさず水やりをし、葉の数や茎の長さを熱心に記録していました。生き物に対する愛情と責任感が感じられます。
- 実験の結果を予想する際に、「たぶん〇〇になると思う。なぜなら~」と、自分の経験に基づいた根拠を明確にして発言することができます。
- 豆電球と乾電池を使った実験では、回路の仕組みに強い関心を持ち、どうすれば明かりがつくのかを夢中になって調べていました。科学的な思考力の芽生えを感じます。
- 実験器具の準備や後片付けを、率先して丁寧に行うことができます。安全に気を配り、グループの仲間と協力して活動を進められる頼もしい存在です。
- 「音のふしぎ」の学習では、糸電話で音が伝わる仕組みに感動し、休み時間にも様々な素材で糸電話を作って試すなど、知的好奇心が旺盛です。
- 観察や実験の結果をまとめる際には、図や表を効果的に使い、誰にでも分かりやすい記録を残すことができます。整理・分析する力があります。
- 磁石の性質を調べる実験では、N極とS極の関係を発見したときの驚きと喜びが表情にあふれていました。発見の楽しさを全身で味わえる素直な心を持っています。
3年生 所見 社会

3年生の社会科では、自分たちの住む市区町村の様子や、スーパーマーケットなど地域の仕事について学びます。地図記号の学習も始まります。
社会の所見文例
- 校外学習で行ったスーパーマーケットの見学では、お店の人の話を熱心に聞き、商品の陳列の工夫やバックヤードの様子について多くの質問をしていました。学習意欲が非常に高いです。
- 自分たちが住む町の地図作りでは、実際に町を探検して見つけた建物や公園を、方位や地図記号を正しく使って表現することができました。
- 地域の安全を守る仕組みについて調べる学習では、消防署や警察署の役割について、図書室の本やインターネットを使って自主的に調べ、分かりやすく新聞にまとめることができました。
- 昔のくらしを調べる学習で、おじいさんやおばあさんにインタビューを行い、洗濯板や七輪などの道具について生き生きと発表することができました。コミュニケーション能力が高いです。
- 「店で働く人」の学習を通して、多くの人々の努力によって自分たちの生活が支えられていることに気づき、感謝の気持ちを持つことができるようになりました。
- 交通安全マップの作成では、危険な場所はどこか、どうすれば安全に過ごせるかをグループで真剣に話し合い、自分たちの手で安全な町を作ろうとする意識が見られました。
- 市の農家の仕事について学んだ際には、野菜がどのように作られ、店に並ぶのかという流通の仕組みに強い関心を示していました。社会の仕組みへの理解が深まっています。
- 地図記号を覚えるのが得意で、カルタ遊びでは誰よりも早く札を取ることができます。楽しみながら知識を身につける力があります。
- 発表の際には、資料を指し示しながら、聞いている人が分かりやすいように、はっきりとした声で話すことができます。プレゼンテーション能力が育っています。
- 学習を通して、自分たちの町への愛着が深まった様子で、「この町の〇〇なところが好きだ」と誇らしげに語る姿が印象的でした。
3年生 所見 音楽

音楽の所見文例
- リコーダーの学習に熱心に取り組み、「シ」と「ラ」の指使いをすぐにマスターし、美しい音色で演奏することができます。練習の成果が表れています。
- 歌を歌うことが大好きで、いつも明るく伸びやかな歌声を響かせています。歌詞に込められた気持ちを考え、表情豊かに歌うことができます。
- 「いろんなリズム」の学習では、手拍子や足踏みで楽しそうにリズムを打ち、自分たちで創作したリズムパターンを友達と合わせて楽しむ姿が見られました。
- 鑑賞の授業では、曲の雰囲気や情景を想像し、「キラキラした感じ」「悲しい気持ちがする」など、自分なりの言葉で感想を述べることができます。感受性が豊かです。
- 合奏の練習では、鉄琴の担当として、周りの楽器の音をよく聞き、全体の響きを考えながら自分のパートを責任もって演奏することができました。
- 音楽に合わせて体を動かす活動では、恥ずかしがらずに、リズムに乗ってのびのびと表現することを楽しんでいます。音楽を全身で味わっています。
- 世界の様々な音楽に興味を持ち、特にサンバのリズムがお気に入りのようです。音楽を通して多様な文化に触れる楽しさを感じています。
- 楽譜を読む力がついてきました。ト音記号や四分音符などの基本的な記号を理解し、簡単なメロディーなら楽譜を見て演奏することができます。
- 音楽会に向けて、鍵盤ハーモニカの練習に一生懸命取り組みました。難しい指使いの部分も、諦めずに何度も練習する粘り強さがあります。
- 音楽係として、授業の始まりと終わりの挨拶を元気よく行い、クラスの音楽学習を明るい雰囲気でリードしてくれています。
3年生 所見 図画工作

図画工作の所見文例
- 絵の具の混色を楽しみながら、自分だけのオリジナルの色をたくさん作り出していました。色彩感覚が豊かで、作品はいつも鮮やかで独創的です。
- 「光と影から生まれる形」の題材では、光を通す材料を上手に組み合わせ、幻想的で美しい作品を創り上げました。発想力が素晴らしいです。
- 粘土を使った作品作りでは、指先を器用に使い、動物の毛並みや表情など、細部にまでこだわって丁寧に表現することができます。集中力が高いです。
- カッターナイフの安全な使い方をすぐに覚え、曲線を滑らかに切り抜くなど、正確な作業が得意です。道具を大切に扱うことができます。
- 作品の鑑賞の時間には、友達の作品の良いところを具体的に見つけて、「この色の使い方がきれいだね」と積極的に伝えることができます。
- 空き箱やペットボトルなどの材料の形から想像を膨らませ、ユニークなロボットを作り上げました。身の回りの物から新たな価値を見出す力があります。
- 版画の制作では、彫刻刀で彫る部分と残す部分をよく考えて、力強い線が印象的な作品を完成させました。計画的に作業を進める力があります。
- 後片付けが非常に丁寧です。絵の具のパレットや筆をきれいに洗い、次の人が気持ちよく使えるように整頓することができます。
- 一度描き始めたら、最後まで諦めずに自分のイメージを形にしようとします。作品作りに対する情熱と粘り強さには感心させられます。
- 共同制作では、全体のバランスを考えながら、自分の役割を果たし、友達と協力して一つの大きな作品を創り上げる喜びを味わうことができました。
3年生 所見 体育

体育の所見文例
- 鉄棒運動では、逆上がりの練習に意欲的に取り組みました。何度も失敗しながらも、友達のアドバイスを聞き入れ、見事に成功させた時の笑顔は輝いていました。
- ボール運動がとても得意で、特にドッジボールでは、状況をよく見て正確なパスを出し、チームの勝利に大きく貢献しました。
- 短距離走では、力強い腕の振りと地面をしっかり蹴るフォームが身につき、記録が大幅に向上しました。目標に向かって努力できる素晴らしい力を持っています。
- マット運動では、前転や後転などの基本的な技を、手をつく位置や体の丸め方を意識して、滑らかに行うことができます。
- ゲームや試合では、ルールをしっかりと守り、勝っても負けても相手チームを尊重するスポーツマンシップあふれる態度で臨むことができます。
- 準備運動や整理運動にも真剣に取り組み、安全に運動することの大切さを理解しています。体育係として、号令をかけ皆をまとめる姿も立派です。
- リズムダンスの表現では、音楽に合わせて体を動かすことを心から楽しんでおり、その楽しそうな様子が周りの友達にも伝わっています。
- 縄跳びが大変上手で、二重跳びやあや跳びなど、難しい技にも次々と挑戦し、成功させています。不断の努力の賜物です。
- チームで戦うゲームでは、作戦を立てる際に積極的にアイデアを出し、仲間を励ます声かけを忘れません。リーダーシップを発揮できる存在です。
- 水泳学習では、水への恐怖心を克服し、顔をつけて泳げるようになりました。自分の目標に向かって一歩一歩進むことができる強い心を持っています。
3年生 所見 外国語活動

外国語活動の所見文例
- ALTの先生の英語の質問にも、物おじせずに、知っている単語を使って積極的に答えようとする意欲があります。コミュニケーションを楽しんでいます。
- 英語の歌やチャンツを覚えるのが早く、いつも元気な声で楽しそうに歌っています。リズムに乗って英語に親しむことができています。
- 「好きなものなあに?」の活動では、 “I like blue.” のように、自分の好きな色や果物を、ジェスチャーを交えながら上手に伝えることができました。
- 友達とのカードゲームを通して、動物や文房具などの英単語をたくさん覚えました。楽しみながら語彙を増やすことができています。
- 外国の文化に強い興味を示し、あいさつや食べ物の違いについて、進んで質問する姿が見られました。国際理解への関心が高いです。
- 電子黒板の英語の絵本に興味津々で、イラストと音声を頼りに、物語の内容を理解しようと集中して聞き入っていました。
- ペア活動では、相手の目を見て笑顔で “Hello.” と挨拶し、簡単なやり取りを続けることができます。英語でのコミュニケーションの素地が育っています。
- アルファベットの大文字と小文字の形をよく理解しており、カルタ遊びでは素早く正しいカードを見つけることができます。
- 間違いを恐れずに、まずは英語で話してみようという前向きな姿勢が素晴らしいです。この積極性をこれからも大切にしてほしいと願っています。
- 授業で習った “Thank you.” や “You’re welcome.” などの表現を、給食の配膳の時など、日常生活の中でも自然に使うことができています。
3年生 所見 道徳

道徳の所見文例
- 「正直、誠実」をテーマにした授業で、登場人物の揺れ動く気持ちに深く共感し、「自分だったらどうするか」を真剣に考え、自分の言葉で意見を述べることができました。
- グループでの話し合いでは、自分とは異なる意見にもしっかりと耳を傾け、「〇〇さんと同じで、私も△△だと思います」と、友達の考えを尊重しながら発言できます。
- 「親切、思いやり」の学習を通して、相手の立場に立って考えることの大切さに気づき、困っている友達にさっと手を差し伸べる姿が以前にも増して見られるようになりました。
- 生命の尊さについて考える授業では、生き物を大切にしようとする気持ちを一層強くしたようです。自分の考えを道徳ノートに丁寧に書き記していました。
- 教材文を読んで、心を動かされた部分に線を C引き、なぜそう感じたのかを的確に発表することができます。豊かな感受性を持っています。
- 「感謝」の気持ちについて学んだ後、給食の調理員さんや家族への感謝の気持ちを手紙に表すなど、学習したことを実生活に結びつけて考えることができます。
- 「きまり」はなぜ大切なのかを、自分たちの生活と関連付けながら深く考えることができました。集団生活におけるルールの重要性を理解しています。
- 授業の最後に書く振り返りでは、その時間に学んだことや自分の心の変化を、素直な言葉で綴ることができます。内省する力が育っています。
- 友達の素晴らしい発表に対して、自然に拍手を送ることができます。互いを認め合い、高め合おうとする温かい雰囲気作りに貢献しています。
- 「あきらめない心」について考えた授業は特に心に残ったようで、その後の体育の授業で苦手な逆上がりに粘り強く挑戦する姿が見られました。道徳的価値の自覚が芽生えています。
3年生 所見 総合的な学習の時間
総合的な学習の時間の所見文例
- 「わたしたちの町じまん」の探究活動では、自分で「町の歴史」というテーマを設定し、図書館で熱心に資料を集め、模造紙に見やすくまとめて発表できました。
- 福祉体験学習では、車いすに乗っている方の話を真剣に聞き、自分たちにできることは何かをグループで話し合い、具体的な行動目標を立てることができました。
- 地域の伝統文化を調べる活動で、和紙作りの職人さんにインタビューを行いました。事前に質問をしっかり準備し、聞き取った内容を丁寧にメモする姿は大変立派でした。
- 環境問題についての学習では、インターネットを使ってごみの分別やリサイクルについて調べ、分かったことをもとに、家庭でできるエコ活動を提案することができました。
- 発表会では、パワーポイントを上手に使い、調べた内容を聞き手に分かりやすく伝えようと工夫する姿が見られました。情報活用能力が育っています。
- 活動の中で疑問に思ったことをそのままにせず、先生や友達に質問したり、図書室で調べたりして、自分で解決しようとする探究心があります。
- グループでの活動では、タイムキーパーや書記などの役割を責任をもって果たし、計画的に学習を進める上で中心的な役割を担いました。
- 活動の記録をこまめに取り、学習の過程で分かったことや感じたことを学習ポートフォリオに丁寧にまとめることができています。学びを振り返る力があります。
- 異年齢交流活動では、下級生に優しく活動内容を教えたり、困っている子を助けたりするなど、上級生としての自覚と優しさにあふれた行動ができました。
- 学習の成果を地域の方々の前で発表した際には、少し緊張しながらも、堂々とした態度で自分たちの学びの成果を伝えることができました。大きな自信につながったことでしょう。
【行動の記録】通知表 所見 文例 小学校3年
ここからは、「行動の記録」に関する所見文例を項目別にご紹介します。
基本的生活習慣
- 毎朝、教室に入るとすぐにランドセルをしまい、提出物を出し、朝の準備を自主的に手際よく行うことができます。
- 学習用具の管理が大変丁寧です。机の中はいつも整頓されており、忘れ物をすることもほとんどありません。
- 休み時間の後も、チャイムが鳴るとすぐに遊びを切り上げ、気持ちを切り替えて席に着くことができます。
- ハンカチやティッシュなど、身の回りのものを常にきちんと持ち歩いており、清潔を心がける意識が高いです。
- 授業と休み時間の区別がしっかりついており、時間を守って行動できるため、周りの友達の良い手本となっています。
- 自分の持ち物には丁寧に名前を書き、大切に扱うことができます。物を長く使おうとする気持ちが育っています。
- 下校の際には、明日の時間割を自分で確認し、必要なものをきちんと揃えてから帰ることができます。
- 廊下を静かに歩く、スリッパをそろえるなど、学校での生活のきまりを意識して、落ち着いて行動できます。
- 規則正しい生活リズムが身についているようで、授業中に眠そうな様子を見せることなく、元気に活動しています。
- 使ったものを元の場所に戻す習慣がついています。教室の共用の道具も、いつもきれいに整頓してくれます。
学習態度

- 授業中は常に正しい姿勢を保ち、先生の話を目と心で聞こうとする真剣な態度が見られます。
- 分からないことがあると、積極的に手を挙げて質問し、理解しようとする意欲にあふれています。
- ノートの字が大変丁寧で見やすいです。大事なところは色分けするなど、後から見返しやすいように工夫しています。
- 友達の発表を、体を向けて真剣に聞いています。発表が終わると、温かい拍手を送る優しさも持っています。
- 一度始めた課題は、チャイムが鳴るまで集中して粘り強く取り組むことができます。
- グループ学習では、自分の意見を言うだけでなく、友達の考えも引き出しながら、話し合いを活発に進めることができます。
- 新しいことを学ぶのが大好きで、授業中はいつも目を輝かせています。その知的好奇心は大変素晴らしいです。
- 課題が早く終わると、静かに読書をするなど、自分で時間を見つけて有意義に過ごすことができます。
- 授業のめあてを意識して学習に取り組むことができます。毎時間、自分の学びを振り返り、着実に力をつけています。
- ペアワークでは、相手に分かりやすく説明しようと、図を描いたり身振りを加えたりする工夫が見られます。
挨拶
- 毎朝、誰よりも先に「おはようございます」と、明るく気持ちの良い挨拶をしてくれます。
- 先生だけでなく、地域の方や他の学年の友達にも、自分から進んで挨拶することができます。
- 相手の目を見て、はっきりと聞き取りやすい声で挨拶できるため、とても清々しい気持ちになります。
- 「ありがとう」「ごめんなさい」が、その場の状況に応じて素直に言える優しい心を持っています。
- 挨拶をすると、にこやかな笑顔で挨拶を返してくれるので、周りの雰囲気を明るくしてくれます。
- 挨拶運動の当番になった際には、校門に立ち、大きな声で登校してくる皆に声をかけ、手本を示してくれました。
- 授業の始めと終わりの挨拶では、いつも背筋を伸ばし、心を込めてお辞儀をすることができます。
- 廊下で来客の方とすれ違う際にも、立ち止まって「こんにちは」と挨拶ができる礼儀正しさがあります。
- 友達同士でも「おはよう」「また明日」と自然に声を掛け合っており、良好な人間関係を築いています。
- 挨拶は人と人との心をつなぐ大切なものだと理解しており、率先して行動で示してくれています。
健康・体力の向上
- 体育の授業や休み時間に、進んで体を動かし、いつも元気に活動しています。
- マラソン大会に向けて、業間休みもこつこつと練習を重ね、自分の記録を大幅に更新することができました。
- 手洗いうがいを丁寧に行うなど、病気を予防しようとする意識が高く、一年間元気に過ごすことができました。
- 自分の体調の変化に気づき、調子が悪い時には無理をせず、先生にきちんと伝えることができます。
- 早寝早起きが習慣になっているようで、毎日生き生きとした表情で登校してきます。
- 体育の授業では、最後まで諦めずに走り抜くなど、自分の体力の限界に挑戦しようとする強い気持ちが見られます。
- 運動会では、リレーの選手として力強い走りを見せ、チームに大きく貢献しました。
- 体力テストの各種目で、昨年度の自分の記録を上回ろうと、一生懸命取り組む姿が立派でした。
- 健康な体はバランスの良い食事から作られることを理解し、給食を残さず食べようと努力しています。
- 運動を通して、体力がついただけでなく、困難に立ち向かう精神的な強さも育っているように感じます。
外で元気に遊ぶ
- 休み時間になると、真っ先に校庭に飛び出し、友達とドッジボールや鬼ごっこを楽しんでいます。
- 男女問わず多くの友達と関わり、いつも笑顔で体を動かして遊んでいます。クラスの元気印です。
- 鉄棒やジャングルジムなど、様々な遊具を使って、工夫しながら遊ぶことが得意です。
- 遊びの中で友達と意見がぶつかった時も、自分たちで話し合って解決しようとする社会性が育っています。
- 体を動かすことの楽しさを全身で表現しており、その姿は周りの友達にも良い影響を与えています。
- 一人でいる子がいると、「一緒に遊ぼう」と優しく声をかけることができる思いやりの心を持っています。
- 季節ごとの自然を遊びに取り入れるのが上手で、秋には落ち葉を集めて見せに来てくれました。
- 遊びのルールを自分たちで決め、みんなが楽しめるように配慮することができます。
- 雨の日でも、室内で体を動かす遊びを考え出すなど、いつでも元気に過ごしています。
- 外で思い切り遊ぶことで、心も体もリフレッシュできているようで、午後の授業にも意欲的に取り組めます。
給食で好き嫌いなく食べる
- 毎日、出された給食は感謝の気持ちを込めて、ほとんど残すことなくきれいに食べています。
- 苦手な野菜が出た時も、一口は挑戦してみようと努力する前向きな姿勢が見られます。
- 「このお魚は骨まで食べられるんだよ」と、食べ物に関する知識を友達に教える姿が見られます。
- 食わず嫌いをせず、まずは食べてみようという気持ちがあり、食べられるものが少しずつ増えてきました。
- 食べ物の栄養について関心があり、「これを食べると元気が出るんだ」と言いながら食べています。
- 友達と楽しそうに会話をしながら、和やかな雰囲気で食事をすることができています。
- 食器の片付け方がとても丁寧で、配膳員さんに「ありがとう」とお礼を言うことも忘れません。
- アレルギーに配慮し、友達と献立を確認し合うなど、安全に給食を食べようとする意識が高いです。
- おかわりも積極的にしており、丈夫な体を作ろうという気持ちが伝わってきます。
- 食事のマナーをよく守り、正しい箸の持ち方で、姿勢良く食べることができています。
自主・自立
- 朝の会が始まる前に、自分でその日の学習の準備を整えることができます。
- 先生の指示を待つのではなく、次に何をすべきかを自分で考えて行動に移せます。
- 係の仕事に責任感を持ち、誰に言われるでもなく、毎日こつこつと役割を果たしています。
- 分からない問題があっても、まずは自分で教科書や資料集を調べて解決しようとします。
- 自分の意見をしっかりと持ち、周りに流されることなく、堂々と発表することができます。
- グループ活動では、リーダーシップを発揮し、話し合いをまとめ、皆を引っ張っていくことができます。
- 自分の持ち物の管理がしっかりできており、自己管理能力が育ってきています。
- 学級会で、クラスをより良くするためのアイデアを自主的に提案することができました。
- 休み時間に、次の授業の準備をさっと済ませてから遊びに行くなど、見通しを持って行動できます。
- 自分の間違いに気づいた時、素直に認め、自らやり直そうとする誠実さがあります。
自分の力で考え、行動する
- 問題解決学習において、既習の知識を活用し、自分なりの方法で答えを導き出そうとします。
- 調べ学習では、与えられたテーマについて、何を知りたいのかを明確にし、計画的に調べることができます。
- 友達と意見が異なった時も、感情的にならず、なぜそう考えたのか理由を筋道立てて説明できます。
- クラスで問題が起きた時、「どうすれば解決できるか」を自分事として捉え、建設的な意見を述べることができます。
- 実験では、結果をただ待つのではなく、「こうしたらどうなるだろう」と新たな仮説を立てて試そうとします。
- 生活科の町探検では、地図を頼りに自分たちの力で目的地までたどり着くことができました。
- 作文では、ありきたりの表現ではなく、自分の体験に基づいた瑞々しい言葉で思いを綴ることができます。
- 周りの状況をよく見て、今自分が何をすべきかを判断し、主体的に行動できる場面が増えました。
- 答えが一つではない問いに対しても、多角的な視点から物事を考え、自分なりの答えを見つけようとします。
- 人の真似をするのではなく、自分らしい工夫を加えようとする独創性を持っています。
粘り強く取り組む
- 算数の難しい文章問題にも、すぐに諦めずに図を描いたりして、解けるまでじっくりと考えることができます。
- 体育の逆上がりの練習では、毎日休み時間も練習を続け、ついに成功させました。その達成感は格別だったことでしょう。
- 根気のいる版画の彫る作業も、集中力を切らさず、最後まで丁寧に仕上げることができました。
- 漢字の書き取り練習では、自分が納得できるまで、何度も書き直す真面目さがあります。
- 一度やると決めたことは、途中で投げ出さずに最後までやり遂げようとする強い意志を持っています。
- 長縄跳びの練習では、なかなかうまく跳べない友達に対しても、「大丈夫だよ」と励ましながら、何度も一緒に練習していました。
- 調べ学習で必要な情報がすぐに見つからなくても、本の種類を変えるなど、方法を工夫して探し出すことができます。
- 困難なことにも「まずはやってみよう」と挑戦する気持ちがあり、失敗を恐れない強さがあります。
- 合奏の練習で、難しいフレーズも指使いを何度も確認しながら、自主的に練習する姿が見られました。
- こつこつと努力を積み重ねることの大切さを理解しており、その真摯な態度は周りの模範となっています。
目標に向かって取り組む
- 漢字テストで満点を取るという目標を立て、毎日計画的に学習を進めることができました。
- マラソン大会では、自分の目標タイムを設定し、それに向かって真剣に練習する姿が見られました。
- 「二重跳びを30回跳ぶ」という目標を掲げ、日々練習に励み、見事に達成しました。
- 夏休みの自由研究では、自分で決めたテーマを、最後まで責任をもって調べ上げることができました。
- 係活動で「みんなが楽しめるイベントを企画する」という目標を立て、友達と協力して見事に成功させました。
- 学習発表会では、自分のセリフを完璧に覚え、堂々と発表するという目標を達成し、大きな自信をつけました。
- 目標を達成するために、今何をすべきかを考え、計画的に努力することができるようになってきました。
- 目標が達成できた時の喜びを知っており、それが次の挑戦への意欲につながっています。
- 学級目標である「友達に優しくする」を常に意識し、具体的な行動で示してくれています。
- 自分の立てた目標に向かってひたむきに努力する姿は、周りの友達にも良い刺激を与えています。
責任感
- 生き物係として、毎日欠かさず水槽の掃除やえさやりを行い、生き物の命を大切にしています。
- 学級委員として、クラスをまとめるという責任を自覚し、朝の会や帰りの会の司会を立派に務めています。
- 自分に与えられた役割は、たとえ地味な仕事であっても、最後まで手を抜かずにやり遂げます。
- グループで決めた役割分担をしっかりと守り、自分の仕事に責任をもって取り組むことができます。
- 当番活動を忘れている友達がいると、そっと声をかけて教えてあげる優しさがあります。
- 自分の失敗を素直に認め、きちんと謝ることができる誠実さを持っています。
- クラスの一員としての自覚があり、みんなのために自分ができることを探して行動しようとします。
- 日直の仕事では、その日の連絡事項を責任をもって皆に伝えようとする姿が見られます。
- 一度引き受けたことは、途中で投げ出すことなく、最後までやり遂げる真面目さがあります。
- 彼の責任感の強さは、クラスメートからの厚い信頼につながっています。
創意工夫
- 図工の作品作りでは、身の回りにある材料をうまく組み合わせ、自分だけの独創的な世界を表現しました。
- 調べ学習のまとめ方では、クイズ形式を取り入れるなど、見る人が楽しめるような工夫が見られました。
- 係活動で、皆が楽しく参加できるようなオリジナルのゲームを考案し、クラスを盛り上げてくれました。
- 理科の実験で、よりうまく結果が出るように、グループで話し合いながら道具の使い方を工夫していました。
- ただ覚えるだけでなく、語呂合わせを考え出すなど、楽しみながら学習を進める工夫をしています。
- 生活科で作ったおもちゃを、もっと面白くするために、友達とアイデアを出し合いながら改良を重ねていました。
- ノートのまとめ方が非常に上手で、図やイラストを使って、一目で内容が分かるように工夫されています。
- 決まったやり方に固執せず、もっと良い方法はないかと常に考えながら物事に取り組む姿勢があります。
- 自由研究では、誰も思いつかないようなユニークな視点でテーマを設定し、見事にまとめ上げました。
- 彼の豊かな発想力と工夫する力は、今後の学習においても大きな武器となることでしょう。
思いやり・協力
- 困っている友達がいると、誰よりも早く気づき、「大丈夫?」と優しく声をかけることができます。
- 体調の悪い友達がいると、荷物を持ってあげたり、保健室まで付き添ってあげたりする優しい心を持っています。
- グループ活動では、自分の意見ばかりを主張するのではなく、友達の意見にも熱心に耳を傾けることができます。
- 重いものを運んでいる人がいると、さっと駆け寄って「手伝うよ」と言える、素晴らしい行動力があります。
- 掃除の時間、自分の分担区が終わると、まだ終わっていない場所を手伝いに行くなど、協力する態度が身についています。
- 自分のことだけでなく、常に周りの人のことを考えて行動できる、心優しい生徒です。
- 友達の頑張りや良いところを素直に認め、「すごいね!」と褒めることができる温かい心を持っています。
- クラスの皆が楽しめるように、遊びのルールを工夫するなど、集団全体のことを考えることができます。
- 学習で分からないところを、友達に分かりやすく丁寧に教えてあげる姿がよく見られます。
- 彼の思いやりのある言動が、クラス全体を温かい雰囲気にしてくれています。
生命尊重・自然愛護
- 生き物係として、金魚やカメを我が子のように可愛がり、責任をもってお世話をしています。
- 校庭で見つけた小さな虫も、決してむやみに殺さず、そっと草むらに返してあげる優しい心を持っています。
- 理科の授業で育てている植物に毎日話しかけながら、愛情を込めて水やりをする姿が印象的でした。
- 道端に咲いている花や草木を大切にし、折ったり踏んだりしないように気を付けて歩いています。
- 「命は一つしかない大切なもの」ということをよく理解しており、友達との関わりの中でもその気持ちが表れています。
- 動物に関する本を読むのが好きで、様々な生き物の生態に深い関心を持っています。
- 遠足で訪れた公園で、ゴミが落ちているのを見つけると、率先して拾うなど、自然を愛する気持ちが行動に表れています。
- 雨上がりのカタツムリをじっと観察するなど、身近な自然の変化に気づき、感動できる豊かな感性を持っています。
- 給食を残さず食べることで、食べ物になった命に感謝するという気持ちを表現しています。
- 生きとし生けるものすべてに優しい眼差しを向けることができる、心の温かい生徒です。
勤労・奉仕
- みんなが使う教室をきれいにしようと、誰も見ていないところでも、隅々まで丁寧に掃除をします。
- 当番活動ではない日でも、黒板が汚れていたらさっときれいに拭くなど、自ら仕事を見つけて動くことができます。
- クラスのために働くことに喜びを感じており、どんな仕事にも意欲的に取り組んでくれます。
- 運動会の準備では、重いテントの脚を友達と協力して運ぶなど、力仕事も嫌がらずに引き受けてくれました。
- 落ちているゴミを見つけると、ごく自然に拾ってゴミ箱に捨てることができます。
- ボランティア活動にも関心があり、募金活動などに積極的に協力する姿が見られました。
- 働くことの尊さを理解し、給食の調理員さんや用務員さんにも感謝の気持ちをもって接することができます。
- 自分の役割を黙々とこなす真面目な姿は、周りの友達の良い刺激になっています。
- 「ありがとう」と言われることに喜びを感じ、人の役に立つことを進んで行おうとします。
- 誰かがやらなければならない仕事に気づき、進んで引き受けてくれる頼もしい存在です。
係活動
- 図書係として、みんなが本を好きになるように、おすすめの本を紹介する手作りのポスターを作成してくれました。
- 放送係として、はっきりとした聞き取りやすい声でアナウンスを行い、全校児童に情報を正確に伝えています。
- 保健係として、石鹸の補充や手洗い調べを責任をもって行い、クラスの健康維持に貢献しています。
- レク係として、クラスのみんなが楽しめるようなユニークな遊びを企画・運営し、いつもクラスを盛り上げてくれます。
- 掲示係として、季節に合わせた飾り付けを工夫し、教室を明るく楽しい雰囲気にしてくれています。
- 自分の係の仕事に誇りを持ち、どうすればもっと良くなるかを常に考え、主体的に活動しています。
- 係のメンバーと協力し、計画的に活動を進めることができます。リーダーシップを発揮する場面も増えました。
- 活動に必要なものを事前に準備したり、終わった後に片付けをしたりと、見えないところでも真面目に仕事に取り組んでいます。
- 係活動を通して、クラスの一員としての自分の役割を自覚し、責任をもって果たすことの大切さを学んでいます。
- 次の係への引き継ぎも、仕事内容を分かりやすくファイルにまとめるなど、最後まで責任をもって行いました。
掃除
- 掃除の時間になると、すぐに自分の持ち場へ行き、時間いっぱい真面目に掃除に取り組みます。
- 机や椅子を丁寧に運び、教室の隅々までほうきで掃くなど、いつも熱心に掃除をしています。
- 雑巾の絞り方がとても上手で、床や窓をピカピカに磨き上げてくれます。
- 無言清掃を心がけ、友達と協力しながら静かに、そして集中して取り組むことができます。
- 自分の担当場所が終わると、「手伝うことはありますか」と周りに声をかけることができます。
- ほうきやちりとりなどの掃除用具を、いつもきれいに洗い、大切に扱っています。
- 汚れがひどい場所にも気づき、自分から進んできれいにしようとする姿は大変立派です。
- 掃除をすることで、みんなが気持ちよく過ごせるということをよく理解しています。
- 掃除反省会では、自分たちの班の良かった点や改善点を具体的に発表することができます。
- 彼の丁寧な仕事ぶりのおかげで、教室はいつも清潔に保たれています。
給食当番
- 給食当番の仕事に責任を持ち、衛生に気を付けて、手際よく配膳の準備をすることができます。
- 身支度をきちんと整え、アルコール消毒を忘れずに行うなど、衛生管理の意識が高いです。
- おかずやご飯を、みんなに公平に行き渡るように、量を考えながら丁寧によそっています。
- 重い食缶も、友達と協力して安全に運ぶことができます。
- 配膳中は静かに行動し、周りの友達の迷惑にならないように気を配っています。
- 「いただきます」の前に、みんなの配膳が終わっているかを確認する気配りができます。
- 牛乳瓶の片付けや食器の返却も、率先して行い、当番としての役割を最後まで果たします。
- 苦手な食べ物がある子にも、「少しだけでも食べてみない?」と優しく声をかける姿が見られます。
- 当番活動を通して、クラスのみんなのために働くことの喜びを感じているようです。
- 時間内に配膳を終え、みんなが落ち着いて給食を食べられるように、常に周りを見て行動しています。
公正・公平
- 誰に対しても分け隔てなく、同じ態度で接することができる、さわやかな心を持っています。
- ゲームやスポーツの際には、ルールを厳密に守り、不正を許さない正義感があります。
- グループ分けや役割分担の際に、みんなが納得できるような公平な方法を提案することができます。
- 仲の良い友達だからといって、特別扱いすることなく、常に公正な判断をしようと努めます。
- 話し合い活動で、まだ意見を言えていない子に「〇〇さんはどう思う?」と話を振る配慮ができます。
- 自分に不利な状況でも、感情的にならず、事実に基づいて冷静に物事を判断できます。
- 当番活動の仕事量を、みんなで平等に分担しようと、常に気を配っています。
- みんなの意見を公平に取り入れ、学級会での話し合いを円滑に進めることができます。
- 自分の間違いだけでなく、友達の間違いもきちんと指摘できる勇気を持っています。
- 彼の公平な態度は、クラスメートからの信頼を集め、学級の安定に繋がっています。
公共心・公徳心
- みんなが使う水道の水を出しっぱなしにせず、こまめに止めるなど、公共のものを大切に扱えます。
- 図書館では静かに本を読むというルールを守り、他の利用者の迷惑にならないように行動できます。
- 廊下に落ちているゴミを、誰に言われるでもなく、さっと拾ってゴミ箱に捨てることができます。
- スリッパや傘立ての傘など、次に使う人が気持ちよく使えるように、いつもきれいに整頓しています。
- 教室の電気の消し忘れに気づき、自分から進んで消すなど、節電への意識が高いです。
- 校外学習の際には、公共交通機関でのマナーをよく守り、静かに過ごすことができました。
- トイレのスリッパを次の人のためにそろえるなど、小さな心がけを自然に行うことができます。
- 学校は自分たちだけのものではなく、みんなのものだという意識を持って生活しています。
- 地域のクリーン活動にも関心があり、自分たちの町をきれいにしたいという気持ちが育っています。
- 彼の公徳心の高い行動は、周りの友達にも良い影響を与え、クラス全体の意識を高めてくれています。
自立活動の所見
※特別支援学級や通級指導教室などで、個別の指導計画に基づき自立活動を行っている場合の文例です。
- (健康の保持)体のバランスを取る練習に意欲的に取り組み、平均台の上を最後まで渡りきることができるようになりました。
- (心理的な安定)気持ちが落ち着かない時に、クールダウンの場所で気持ちを切り替える方法を自分で選べるようになってきました。
- (人間関係の形成)ソーシャルスキルトレーニングを通して、友達との関わり方を学び、休み時間に「入れて」と自分から声をかけられるようになりました。
- (環境の把握)絵カードを使って一日の見通しを立てることで、安心して学習活動に取り組むことができるようになっています。
- (身体の動き)はさみやのりを使った微細運動のトレーニングを重ね、指示された線を Cまっすぐに切ることができるようになりました。
- (コミュニケーション)自分の気持ちを言葉で伝えることが難しい時、絵カードや指差しで要求を伝えられる場面が増えました。
- (心理的な安定)自分の好きなことや得意なことを見つけ、自信をもって活動に取り組むことで、自己肯定感が高まっています。
- (人間関係の形成)友達とトラブルになった際に、すぐに手が出るのではなく、一度立ち止まって先生に助けを求められるようになりました。
- (身体の動き)ボタンのかけ外しや靴ひもを結ぶ練習を根気強く続け、身の回りのことを自分でできる喜びを感じています。
- (コミュニケーション)発語の練習を毎日こつこつと続け、聞き取れる言葉の数が増え、二語文で話せるようになってきました。
自立活動の詳しい所見文例はこちら💁
各学年の所見文例集リンク
まとめ
この記事では、通知表 所見 文例 小学校3年をテーマに、様々な文例をご紹介しました。通知表の所見は、保護者にとって我が子の学校での様子を知るための大切な手がかりであり、子ども自身にとっては自分の成長を実感し、次への意欲につなげるための重要なメッセージです。ここに挙げた文例を参考にしながらも、ぜひ先生ご自身の言葉で、目の前のお子さん一人ひとりの輝きと確かな成長を伝えてあげてください。先生方の通知表作成が、少しでもスムーズに進むことを心から願っています。
さらに詳しい指導のポイントについては、下記の公式サイトも参考にしてください。




コメント