新年度が始まり、特別支援学級の担任になった皆さん。
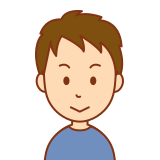
「特別支援の担任って、何をどうすればいいんだろう?」
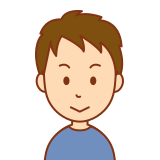
「通常学級と全然違うって聞くけど、具体的にどう違うの?」
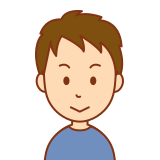
「うまくやれるのかな……?」
そんな不安を抱えている先生も多いと思います。私も、初めて特別支援学級を担当したとき、まさに同じ気持ちでした。
通常学級とは違い、クラスの子どもたちが一人ひとり異なる特性を持ち、必要な配慮も違います。全員が同じペースで学習するわけではなく、「学級経営」というより「個別支援」の要素が強い。この環境の中で「何をどこから手をつけたらいいのか?」と迷うのは、当然のことだと思います。
でも、大丈夫です。一つずつやるべきことを整理しながら進めていけば、自然と見えてくるものがあります。ここでは、4月1日にやっておくと良いことを、私自身の経験をふまえながらお伝えします。
特別支援学級では、何よりも 「この子はどんな子?」を知ること が大切です。
具体的な4月1日からの仕事のリストはこちら👇
支援学級の子について理解を深めたい方はこちらをご参考ください👇
① まずは「児童理解」から始める
通常学級なら、学級全体の流れを考えてスタートすることが多いですよね。でも、特別支援学級では「一人ひとりの特性を知ること」がスタートラインになります。
▶︎ 具体的にやること
1. 個別の指導計画を読む
• 去年の記録を見て、児童の得意・苦手や、どんな支援が効果的だったのかを知る
• どんな場面で困りやすいのか、どんな対応が安心につながるのかをチェック
2. 前担任や支援員に話を聞く
• 昨年度の関わり方や、特に気をつけた方がいいことを聞く
• 具体的な授業の進め方 を確認する(個別学習の時間の使い方、活動の流れなど)
• 支援学級での様子(どんなタイミングで落ち着かなくなるか、集中しやすい環境は?)
• 交流学級での様子(どんな教科でどのくらい参加していたか、集団の中での様子)
• 交流学級に行く教科の確認(本人の負担になっていないか、教科によって支援の工夫が必要か)
3. 可能なら保護者とも話す
• 児童の家庭での様子や、保護者がどんなことを不安に感じているかを確認
• 保護者がこの1年間で子どもにどんな力をつけさせたいと思っているのかを聞く
• 例えば、「自分で身支度をできるようになってほしい」「友達との関わりを増やしてほしい」など
• 保護者の願いを知ることで、学校と家庭が同じ方向を向いて支援しやすくなる
• 保護者との信頼関係を築くことが、その後の支援をスムーズにする
特別支援学級では、「まずは関係を作る」ことがとても大切です。授業をスムーズに進めることよりも、「先生と一緒なら安心できる」という信頼関係を築くことを優先しましょう。
② 教材の選定──何を使うか決める
子どもたちの学びのペースは一人ひとり違います。通常学級の教材をそのまま使うのか、別のものを準備するのか、慎重に検討する必要があります。
▶︎ 具体的にやること
1. 通常学級の教材を使うかどうか考える
• 自閉症・情緒のクラスなら、通常学級の教材をそのまま使えることもある
• ただし、問題の量を調整したり、補助プリントを作る必要があることも
2. 児童の特性に合わせた教材を選ぶ
• 例えば、書くことが苦手な子には、選択式の問題を増やしたり、タブレットを活用したり
• 数学が苦手な子には、視覚的に理解しやすい教材を使う
3. 早めに発注する
• 校内の教材選定のタイミングを確認し、間に合うように発注をかける
• 昨年度の教材データを参考にすると、選びやすい
③ 週の予定を決める──流れをつかむ
特別支援学級は、通常学級と違って、時間割が一人ひとり異なることが多いです。交流学級で授業を受ける子もいれば、ほとんど特別支援学級で過ごす子もいます。
だからこそ、 「この子は1週間どんな流れで過ごすのか?」を早めに整理すること が大事です。︎
▶︎ 具体的にやること
1. 交流学級の時間割を確認する
• 児童がどの授業に参加するのか、交流学級の先生に確認
• できるだけ早く1週間の予定をもらう
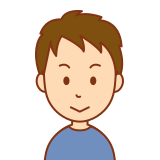
どの先生も忙しい様子です。声をかけるのは後にしようと思いがち。ただ、これがわからなければ,私たちは先に進めません。出来れば、職員会や打ち合わせで職員全員と必要性について共有したいところです。
2. 特別支援学級の時間割を作る
• 児童が無理なく学習を進められるように、バランスを考える
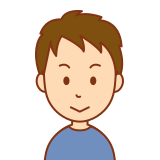
年度はじめは学年集会が計画されます。優先して参加できるよう、時間割を作りましょう。
• 他の特別支援学級と一緒に活動できる時間があるかを確認
④ そのほか4月1日にやっておくと良いこと
1. クラスの環境を整える
• 安心できる空間づくり
• 自分のスペースが決まっていると安心する子が多いので、机の配置を工夫する
• 必要に応じて、視覚的な支援(スケジュール表や手順カード)を準備
• 刺激が強すぎないように調整
• 余計な装飾を減らし、集中しやすい環境を整える
2. 支援員や他の先生と連携する
• 支援員との情報共有
• 支援員がどこまでサポートしてくれるのかを確認
• 役割分担を明確にする
• 通常学級の先生と連携
• 交流授業のサポート方法を相談する
• 児童が困ったときの対応について共有する
最後に──不安なのは当たり前
特別支援学級の担任になりたての頃は、「本当にこれでいいのか?」と悩むことも多いと思います。でも、大丈夫。 最初から完璧にできなくていいんです。
特別支援学級は、 「子どもと一緒に成長する場所」 です。子どもたちと一緒に試行錯誤しながら、一歩ずつ進んでいけばいいです。
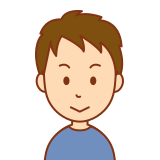
「なんとかなる!」くらいの気持ちで、まずは 子どもたちのことを知ること から始めてみてください。応援しています
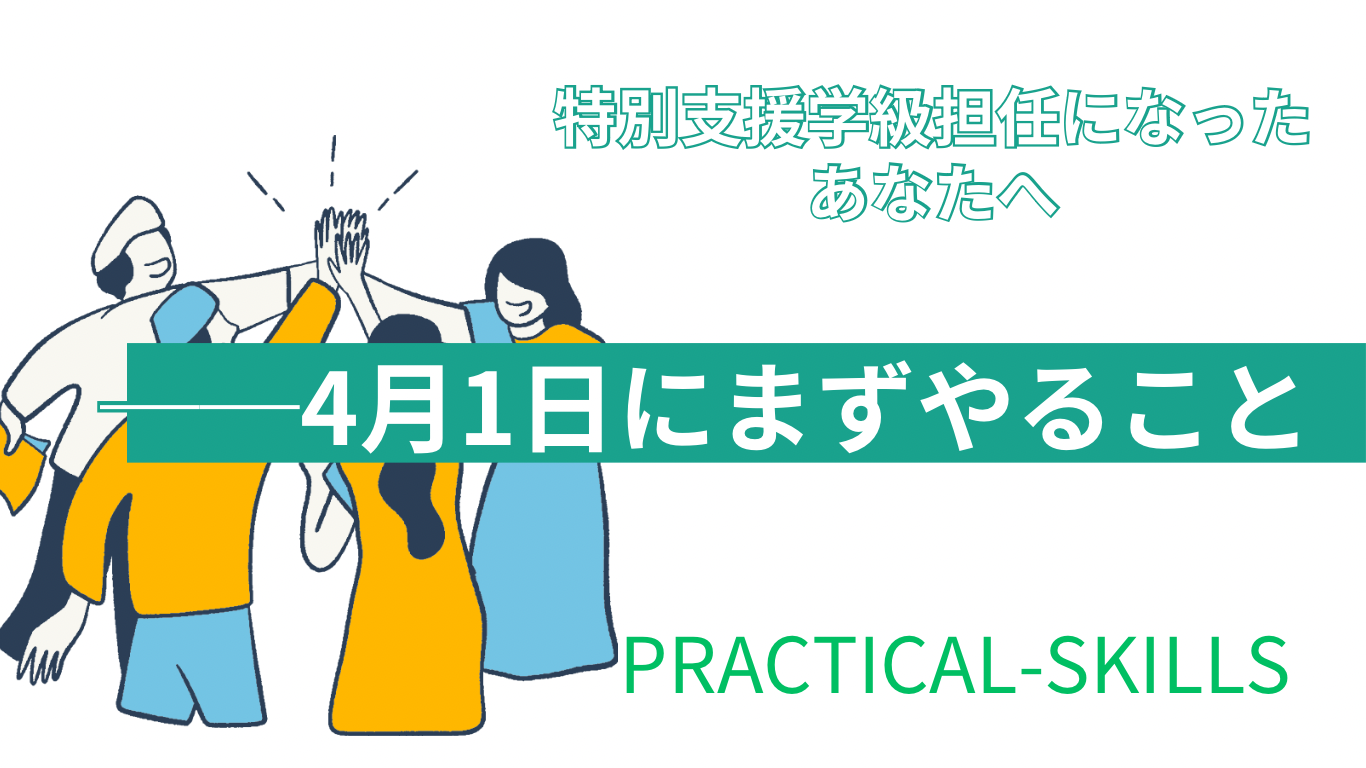
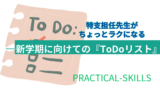


コメント