お子さんの
「○○のせいで!」という言葉に、「また人のせいにして…」と、がっかりしたり、時には苛立ちを感じたりすることはありませんか?
発達障害のあるお子さんを育てる保護者の方や、指導にあたる先生方の中には、トラブルが起きた際に他人のせいにする(=他責思考)傾向が見られる子どもの言動に、何度も言い聞かせても改善しないように見えて、「このままで大丈夫なのだろうか」と不安を感じている方もいるかもしれません。
しかし、そうした言動の背景には、本人の“困り感”や認知特性が深く関係しています。決して、反省していないわけでも、わざと責任転嫁しているわけでもないのです。
この記事では、
「発達障害 × 他責思考」というテーマで、子どもたちの言動の背景に迫りながら、叱るだけでは変わらない場面での関わり方のヒントを5つ紹介します。子どもの自己肯定感を育み、自律的な成長を促すための具体的なアプローチを一緒に考えていきましょう。
他責思考の子には、こちらの活動がおすすめです👇
協力型ゲームを通して学べるこちらのSSTがおすすめです👇
1.「他責思考」とは?発達障害の子どもに見られる特徴
他責思考とは、物事がうまくいかない時に、自分以外の人や環境に責任を求める傾向のことです。これは誰にでも見られる傾向ですが、発達障害のある子どもたちの中には、特に強く、頻繁に現れるケースがあります。
その背景には、自分の行動を客観的に振り返る力(メタ認知)や、他者の視点を想像する力(心の理論)が育ちにくいといった特性が関係していることが多いです。
たとえば、発達障害の特性別に見てみると…
- ASD(自閉スペクトラム症)の子は、自分の考えやルールに強く固執しやすく、「自分は正しい」と思い込む傾向があるため、他人の意見や視点に立つのが難しい場合があります。
- ADHD(注意欠如・多動症)の子は、衝動性から咄嗟に「言い訳」をしてしまい、自分の責任を冷静に振り返ることが難しい場合があります。また、失敗体験を積み重ねることで自己肯定感が低下し、「自分にはできない」という気持ちから責任を回避しようとすることもあります。
このように、他責的な言動は、子ども自身の性格というよりも、「できない」ことの表れ、つまりは「困り感のサイン」であることが多いのです。
2.なぜ「叱る」だけでは逆効果になるのか?言葉が届かない理由
教師や保護者が「自分の責任を考えなさい!」「言い訳しないで!」と叱っても、なかなか子どもの行動が変わらないのは、叱る=理解するではないからです。
特に発達障害のある子どもは…
- 言葉での抽象的な指導が伝わりにくい 状況や感情を言葉で説明されても、具体的にイメージするのが難しい場合があります。
- 失敗体験を繰り返すことで自己肯定感が下がっている 何度も叱られることで「自分はダメな子だ」と感じ、さらに自信を失い、問題解決への意欲が低下することがあります。
- 注意されたこと自体に感情が揺さぶられてしまい、内容が届かない 叱られたことへの恐怖や不安が先行し、指導の内容そのものを受け止める余裕がなくなってしまいます。
そのため、「叱って理解させる」という一方的な関わりは、かえって子どもの心を閉ざし、逆効果になることも少なくありません。

3.もう悩まない!「叱る」から「伝わる」へ変える、具体的な関わり方ヒント5選
では、叱るだけでは伝わらない発達障害のある子どもの他責思考に対し、どのように関われば良いのでしょうか? 子どもが自ら考え、行動を選べるようになるための具体的なヒントを5つご紹介します。
- 「そう思ったんだね」と気持ちを受け止める。否定から入ると、子どもは心を閉ざし、話を聞こうとしなくなってしまいます。まずは、「○○くんはそう思ったんだね」「そう感じたんだね」と、子どもの言動や感情を一旦すべて受け止める姿勢を示しましょう。子どもが「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じることで、安心して次のステップに進めます。
- 場面を一緒に振り返るシートやカードを使う。 抽象的な言葉だけでなく、視覚的なツールを活用することで、子どもは冷静に状況を整理しやすくなります。SST(ソーシャルスキルトレーニング)カードや状況再現イラスト、または自分で作れる振り返りシートなどを使い、客観的に「事実」と「自分の気持ち」、そして「相手の気持ち」を分けて考えられるように支援
- 「誰が悪いか」より「次にどうするか」を重視 責任追及は、子どもを萎縮させるだけです。「誰が悪いか」という犯人探しではなく、「この後、どうしたら解決できるかな?」「次からはどうすればもっと良くなると思う?」と、具体的な未来の行動に焦点を当てて問いかけましょう。子ども自身に次の行動の選択肢を一緒に考えさせることで、自分の言動に前向きな意識を持たせることができます。
- 「立場を変える」ロールプレイを取り入れる 他者の視点に立つ練習は、社会性を育む上で非常に重要です。 劇遊びや役割交換活動、例えば「こころカルタ」のような感情理解を促すツールや、ペアでの寸劇などを通して、自分以外の人の気持ちや状況を想像する経験を積ませましょう。実際に相手の立場になってみることで、共感性が育まれます。
- 「できたこと」を丁寧に言葉でフィードバック 良い行動ができた時には、決して見逃さず、具体的に褒めましょう。些細なことでも「今、自分の気持ちを落ち着いて言えたね」「○○くんのいい聞き方だったよ」と具体的に伝えることで、子どもは「自分はできる」という自己理解と自己肯定感を育てていきます。成功体験の積み重ねが、次への意欲に繋がります。
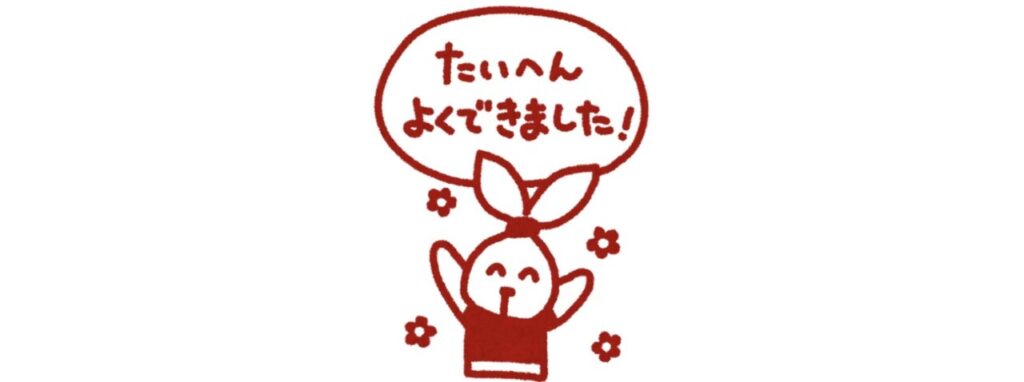
4.実際の場面から|“責任転嫁”が減った子の変化
ある高学年の児童は、トラブルが起きるとすぐに「○○のせいだ!」と周囲を責める傾向がありました。
担任として最初は注意や叱責を重ねていましたが、なかなか状況は改善しません。そこで、半年にわたり、振り返りシートを使いながら、ゆっくりと事実と気持ちを整理する時間を確保するようにしました。すぐに効果は出ませんでしたが、根気強く続けることで、ある日その子が「本当は、自分が先に手を出してしまった」と、自ら語れるようになったのです。
変化は急には起きませんが、子どもの認知の特性を理解し、本人が「言葉にして整理する」「客観的に振り返る」といった経験を積むことで、少しずつ自分の行動に対する責任意識が芽生えてくることを実感しました。
5.支援者・保護者へのメッセージ|「他責=悪」ではない
私たちはつい、「他人のせいにするのは良くない」「自分の行動には責任を持つべき」と考えがちです。もちろんそれは大切な価値観ですが、発達障害のある子にとっては、そのステップに至るまでに“支援”が必要です。
叱って変わらないのは、本人が反省していないからではなく、「反省する力」や「状況を客観視する力」がまだ十分に育っていないから、と捉えることが大切です。まずはそこを理解したうえで、長い目で、具体的な方法で育てていくことが、特別支援教育や子育てにおいて非常に大切な役割です。
完璧を目指すのではなく、一歩ずつ子どもの成長を信じて寄り添いましょう。
さいごに|「どうしたら変わるか」を一緒に考える関係へ
「他責思考」という言葉の裏にあるのは、もしかしたら困っている子どもたちのSOSのメッセージかもしれません。
叱る前に、「なぜそう言うのか?」「何に困っているのか?」を一緒に考えてみることで、子どもとの関係は少しずつ、しかし確実に変わっていきます。子どもが安心して自分の気持ちを話せる、信頼できる関係を築くことが、問題解決への第一歩となるでしょう。
関連する実践記事はこちら👇
国立障害者リハビリテーションセンターを参考にしました。発達障害に関する基本的な情報、診断、支援方法など、網羅的かつ信頼性の高い情報が提供されています。








コメント