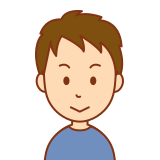
「自立活動で、子どもたちが主体的に楽しめる活動はないかな?」

「学級レクのネタが尽きてしまった…準備なしで盛り上がるゲームが知りたい!」

「アイスブレイクで、クラスの雰囲気を一気に和ませたい!」
そのお悩み、何を言ってもゲームがすべて解決します!
「何を言ってもゲーム」は、ルールが簡単で準備も不要、どんな場所でもすぐに始められる、ゲームです。単純なルールだからこそ奥が深く、子どもたちが絶対引っかかる面白い仕掛けがたくさんあります。
この記事では、
そんな子ども向けの定番ゲーム「何を言ってもゲーム」を、教育的な視点から徹底的に深掘りしていきます。
この記事を読めば分かること
- 「何を言ってもゲーム」の基本的なルールと、盛り上げるためのコツ
- 自立活動6区分27項目に基づいた、専門的な「ねらい」の解説
- 学級レクで子どもたちの心を掴む、効果的な活用方法
- すぐに使える!学年別の面白いクイズ・ひっかけ問題の例題集
- 活動を成功させるための、子どもたちへの配慮とアレンジ方法
📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!
「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。
登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。
PDFの受け取りは、たったの30秒!
以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。
所見の作成がぐっと楽になると思います。
▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼
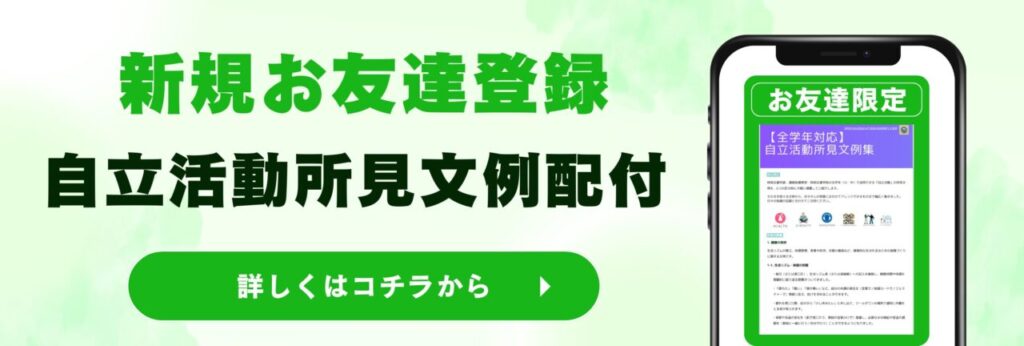
書籍のご案内
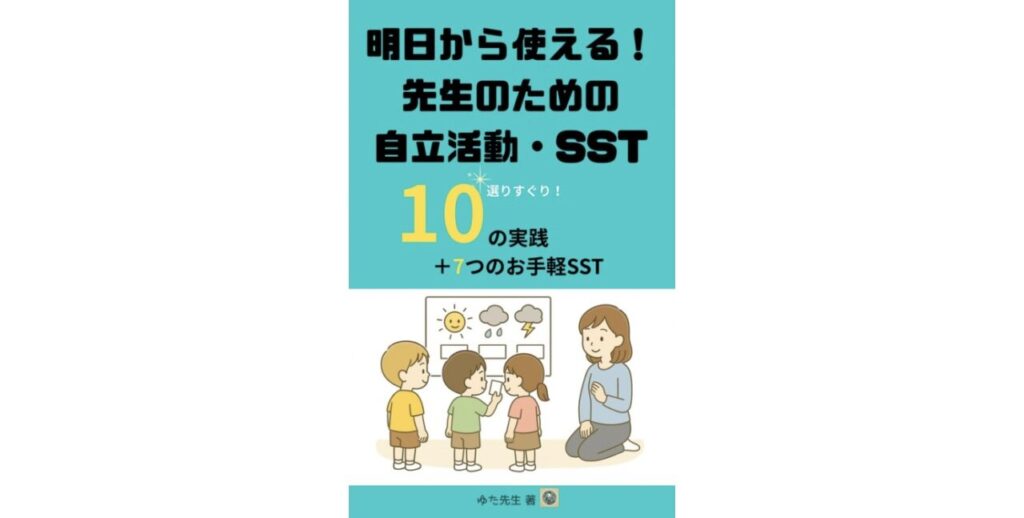
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
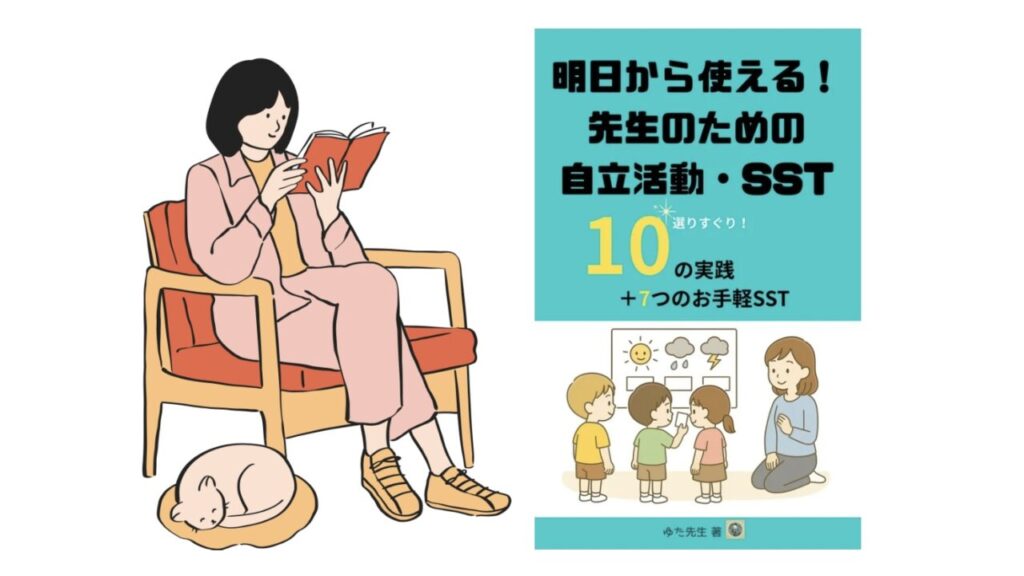
何を言ってもゲームのルールは驚くほど簡単!子ども向けに分かりやすく解説
「何を言ってもゲーム」の最大の魅力は、そのルールのシンプルさです。初めて遊ぶ子どもでも、一度説明を聞けばすぐに理解できます。まずは基本的なルールを確認しましょう。
基本的なルール
- 出題者(先生)が、参加者(子どもたち)に「〇〇と言ってください」とお題を出します。
- 参加者は、出題者が言った「〇〇」という言葉をそのまま答えます。
- しかし、出題者がお題の前に「『何を言っても』と言ったら」という前置きを付けた場合は、参加者は何も言ってはいけません(沈黙が正解)。
- もし「『何を言っても』と言ったら」という前置きがあるにもかかわらず、何か言葉を発してしまったらアウト(負け)です。
【例】

- 出題者(先生): 「『りんご』と言ってください」
- 参加者(子ども): 「りんご」(セーフ)
- 出題者(先生): 「『何を言っても』と言ったら、『ばなな』と言ってください」
- 参加者(子ども): 「……(沈黙)」(セーフ)
- 参加者(子ども): 「ばなな」(アウト!)
たったこれだけです。非常に簡単ですよね。このシンプルなルールの中に、子どもたちの「聞く力」「集中力」「判断力」を試す要素が詰まっています。
ゲームをさらに面白くするローカルルール
基本的なルールに慣れてきたら、以下のようなローカルルールを追加すると、さらにゲームが盛り上がります。
- スピードアップ: 出題のテンポを徐々に上げていくことで、スリルと集中力が高まります。
- ジェスチャー付き: 「バンザイして」など、言葉だけでなく身体の動きを指示に加えます。「『何を言っても』と言ったら、ジャンプして」と言われてジャンプしたらアウトです。
- 「逆」バージョン: 「『何を言っても』と言ったら、何かを言わなければならない」という逆のルールで遊ぶのも、頭の切り替えが必要になり面白いです。
- 出題者交代制: アウトになった人が次の出題者になるルールです。子どもたちが主体的にゲームに参加する機会が増えます。
このように、基本ルールは崩さずに少しアレンジを加えるだけで、ゲームの難易度や楽しさを自在にコントロールできます。子どもたちの実態に合わせて、最適なルールを設定してみてください。
自立活動のねらいを解説!6区分27項目と「何を言ってもゲーム」の関連性
「何を言ってもゲーム」は、ただ楽しいだけのゲームではありません。特別支援教育における「自立活動」のねらいを達成するための、非常に有効なツールとなり得ます。ここでは、文部科学省が示す学習指導要領の「自立活動における6区分27項目」と関連付けながら、このゲームが持つ教育的価値を詳しく解説します。
参考:文部科学省 特別支援教育
1. 心理的な安定
この区分は、情緒の安定や状況理解、適切な自己表現などに関わります。「何を言ってもゲーム」は、特に以下の項目と深く関連します。

- (1)情緒の安定に関すること: ゲームで失敗(アウト)した時に、悔しい気持ちをコントロールし、笑いに変えたり、次の挑戦に意欲を向けたりする経験は、感情の適切な処理能力を育みます。先生が「あー、引っかかった!面白い!」「ドンマイ、次頑張ろう!」とポジティブな雰囲気を作ることで、子どもたちは失敗を恐れずに挑戦する楽しさを学びます。
- (2)状況の理解と判断・行動に関すること: 「『何を言っても』と言ったか、言わなかったか」という特定の条件を正しく聞き取り、その状況に応じて「言う」「言わない」という適切な行動を瞬時に判断するプロセスは、まさにこの項目のねらいそのものです。繰り返し行うことで、状況に応じた行動選択の力を養います。
2. 人間関係の形成
この区分は、他者との関わり方や集団への参加の仕方を学ぶことを目的としています。

- (1)他者とのかかわりの基礎に関すること: ゲームのルールを守って参加すること、友達が成功したら一緒に喜び、失敗したら一緒に笑うことなど、共通の体験を通して他者との一体感を育みます。出題者の言葉や表情に注目し、意図を読み取ろうとすることも、他者理解の第一歩となります。
- (2)集団への参加の基礎に関すること: ゲームという明確なルールの下で、順番を守ったり、他の参加者の様子を見たりしながら活動に参加する経験は、集団参加の態度を養います。最初は見ているだけだった子どもも、楽しそうな雰囲気に誘われて「やってみたい」という気持ちが芽生えるきっかけにもなります。
3. コミュニケーション
この区分は、言語の受容・表出や、コミュニケーション手段の活用能力を育むことを目的としています。このゲームは、コミュニケーション能力の育成に直結する活動と言えます。

- (1)言語の受容・表出に関すること: このゲームの核心は「聞く力」、つまり言語の受容能力です。出題者の指示を正確に聞き取り、その意味を理解することが求められます。特に、「『何を言っても』と言ったら」という否定の条件を聞き分けることは、高度な聞き取り能力のトレーニングになります。また、正解・不正解を問わず、言葉を発する・発しないという行為自体が、言語表出の練習となります。
- (2)言語形成の基礎に関すること: ゲームの中で様々な単語(りんご、ばなな、車など)に触れることで、語彙を増やすきっかけになります。先生が意図的に子どもたちの興味関心がある言葉や、学習中の単元に関連する言葉をお題にすることで、楽しみながら語彙力を高めることができます。
- (3)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること: 言葉を発するだけでなく、「沈黙する」「ジェスチャーをする」といった非言語的なコミュニケーションもゲームの重要な要素です。状況に応じて、どのコミュニケーション手段(発話、沈黙、身体表現)を選択すべきかを判断する力を養います。
このように、「何を言ってもゲーム」は、楽しさの中に自立活動のねらいが豊富に含まれています。先生がこれらのねらいを意識して声かけやルール設定を行うことで、活動の効果をさらに高めることができるでしょう。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
学級レクで絶対盛り上がる!何を言ってもゲームが面白い理由と活用術
「何を言ってもゲーム」は、学級レクやアイスブレイクにも最適な活動です。なぜこのゲームが子どもたちの心を掴み、クラスを一体にする力を持っているのでしょうか。その理由と、効果的な活用術をご紹介します。
なぜこんなに面白い?盛り上がる理由
- 準備が一切不要: 教室、体育館、バスの中など、場所を選ばず、思い立ったその瞬間に始められます。特別な道具も必要ありません。
- ルールが超シンプル: 全員がすぐにルールを理解できるため、説明に時間を取られることなく、すぐに活動に入れます。
- 一体感が生まれる: 「あー!言っちゃった!」「セーフ!」といった反応が自然に生まれ、クラス全体が同じ気持ちを共有できます。引っかかった時の面白いリアクションが、教室を笑いの渦に巻き込みます。
- 適度な緊張感: 「次は引っかからないぞ」という集中力と、「言っちゃうかも」というドキドキ感が、子どもたちをゲームに夢中にさせます。
- 先生と子どもの距離が縮まる: 先生がユニークなお題を出したり、わざと引っかかってみせたりすることで、普段とは違う一面を見せることができ、子どもたちとの心理的な距離がぐっと縮まります。
学級レクでの効果的な活用シーン
- 新学期のアイスブレイクに: まだお互いに緊張している新学期の初めに。簡単なルールで笑いが生まれ、クラスの雰囲気を一気に和ませることができます。
- 授業の間のリフレッシュに: 集中力が切れてきた授業の合間に、5分程度の短い時間で行うことで、気分転換になり、その後の学習への集中力を高めます。
- レクリエーション大会の種目として: クラス対抗や班対抗で、最後まで残った人数を競う形式にすれば、応援にも熱が入り、クラスの団結力を高めることができます。
- バスレクの定番として: 移動中のバスの中は、できる活動が限られます。座ったままでできるこのゲームは、バスレクの鉄板ネタとして大活躍します。
盛り上げるための先生の関わり方
- 雰囲気作り: 「よーし、みんな先生の言葉によーく集中して聞いててね!絶対引っかけるぞー!」のように、最初に期待感を高める声かけをしましょう。
- テンポと間の使い方: 最初はゆっくり、慣れてきたら徐々にテンポアップ。そして、ここぞという場面で少し「間」を作ることで、子どもたちの緊張感を高めることができます。
- 表情や声のトーン: 真剣な表情で簡単な問題を出したり、優しい声でひっかけ問題を出したりと、表情や声のトーンを使い分けることで、子どもたちはより一層先生の言葉に引き込まれます。
- ポジティブなフィードバック: 引っかかってしまった子には、「おしい!」「引っかかってくれてありがとう!盛り上がったよ!」など、失敗がネガティブな経験にならないような温かい声かけを心がけましょう。

【先生必見】何を言ってもゲームで使える絶対引っかかる面白い例題集
さあ、ここからは先生がすぐに使えるクイズの例題集です!簡単なものから、子どもたちが「えー!」と思わず声を上げてしまうような、面白いひっかけ問題まで、レベル別にご紹介します。
レベル1:まずは肩慣らし!簡単編
まずは基本的な問題で、ゲームのルールを全員で確認しましょう。
- 「『おはよう』と言ってください」
- 「『こんにちは』と言ってください」
- 「『さようなら』と言ってください」
- 「『何を言っても』と言ったら、『ありがとう』と言ってください」
- 「自分の名前を言ってください」
- 「先生の名前を言ってください」
- 「『何を言っても』と言ったら、隣の人の名前を言ってください」
レベル2:ちょっと意地悪?応用・ひっかけ編
慣れてきたところで、少し頭を使うひっかけ問題に挑戦です。
【早口言葉系】
- 「『赤パジャマ』って3回言ってください」→(言わせた後で)→「『何を言っても』と言ったら、『青パジャマ』と言ってください」
- 「『カエルぴょこぴょこ』って3回言ってください」→(言わせた後で)→「じゃあ、これは?」とカエルの絵を見せる → 「カエル!」と言ったらアウト(何も指示していない)
【言い間違い誘発系】
- 「『シャンデリア』って10回言ってください」→(言わせた後で)→「毒リンゴを食べたお姫様はだーれだ?」→「シンデレラ!」と言ったらアウト(正解は白雪姫)※これは純粋なクイズですが、ゲームの流れで出すと引っかかりやすいです。
- 「『ピザ』って10回言ってください」→(言わせた後で)→(肘を指さして)「ここは?」→「ひざ!」と言ったらアウト(正解はひじ)
【ジェスチャー系】
- 「右手を上げてください」
- 「左手を上げてください」
- 「『何を言っても』と言ったら、両手を上げてください」
- (先生が頭を触りながら)「『肩』と言ってください」→(子どもは「肩」と言う)
- (先生が肩を触りながら)「『頭』と言ってください」→(子どもは「頭」と言う)
- (先生が膝を触りながら)「『何を言っても』と言ったら、『お腹』と言ってください」
【リズム系】
- (手拍子をしながら)「パン、パン」→「真似してください」→ 子ども「パン、パン」
- (手拍子をしながら)「パン、パン、パパン」→「真似してください」→ 子ども「パン、パン、パパン」
- (手拍子をしながら)「『何を言っても』と言ったら、『パン』と一回だけ叩いてください」
レベル3:これはだまされる!超難問編
高学年や、ゲームに慣れている子どもたち向けの、少し意地悪な上級問題です。
【ルールを逆手にとる系】
- 「このゲームのルールを言ってください」→(子どもがルールを説明し始める)→「アウト!先生は『〇〇と言ってください』って言ってないよ!」
- 「これから『何を言ってもゲーム』を始めます。『何を言っても』と言ったら、何も言わないでくださいね。いいですか?」→「はい!」と返事をした子がアウト。
【思い込みを利用する系】
- 「『空』と言ってください」→「空」
- 「『海』と言ってください」→「海」
- 「『川』と言ってください」→「川」
- 「『何を言っても』と言ったら、『森』と言ってください」→(沈黙が正解)
- (間髪入れずに)「じゃあ、『火』は?」→「火!」と思わず言ってしまう子が多いです。これは「『〇〇と言ってください』」という指示形式ではないため、本来は答える必要がありません。
【究極の心理戦】
- (しばらく簡単な問題を続けた後、真剣な顔で)
- 「……よし、次が最後の問題です。いいですか、よーく聞いてくださいね。」
- (少し間をあけて)
- 「『何を言っても』と言ったら、『やったー』と言ってください」
- (子どもたちが黙っているのを確認して)
- 「……はい、今黙っていた人、全員アウトー!」
- 子ども「えーなんで!?」
- 先生「先生、『何を言ってもゲーム、スタート!』って言ってないよ。まだゲームは始まってませんでした!」
これらの例題を参考に、先生自身のオリジナル問題を作ってみるのも楽しいでしょう。子どもたちの興味や、その日の出来事に関連したお題を出すと、さらに盛り上がること間違いなしです。
何を言ってもゲームを子ども向けにアレンジする際の注意点と配慮
「何を言ってもゲーム」は、非常に優れた活動ですが、すべての子どもが楽しめるようにするためには、いくつかの配慮が必要です。特に、年齢や発達段階、クラスの特性に応じたアレンジと注意点を押さえておきましょう。
低学年向けのアレンジと配慮
- ルールの丁寧な確認: 低学年の子どもたちには、一度の説明でルールを理解するのが難しい場合もあります。実際に先生がお手本を見せたり、簡単な練習問題を繰り返したりして、全員がルールを理解してから本番に進みましょう。「『何を言っても』が付いてたら、お口にチャックだよ」など、分かりやすい言葉で伝えるのがポイントです。
- ジェスチャーを多めに: 言葉だけの指示よりも、「ジャンプして」「頭をさわって」など、身体を動かす指示を多く取り入れると、子どもたちは視覚的にも楽しむことができます。
- 短い時間で区切る: 低学年の集中力は長く続きません。5分程度の短い時間で一度ゲームを区切り、「また明日やろうね!」と次への期待感を持たせるのが効果的です。
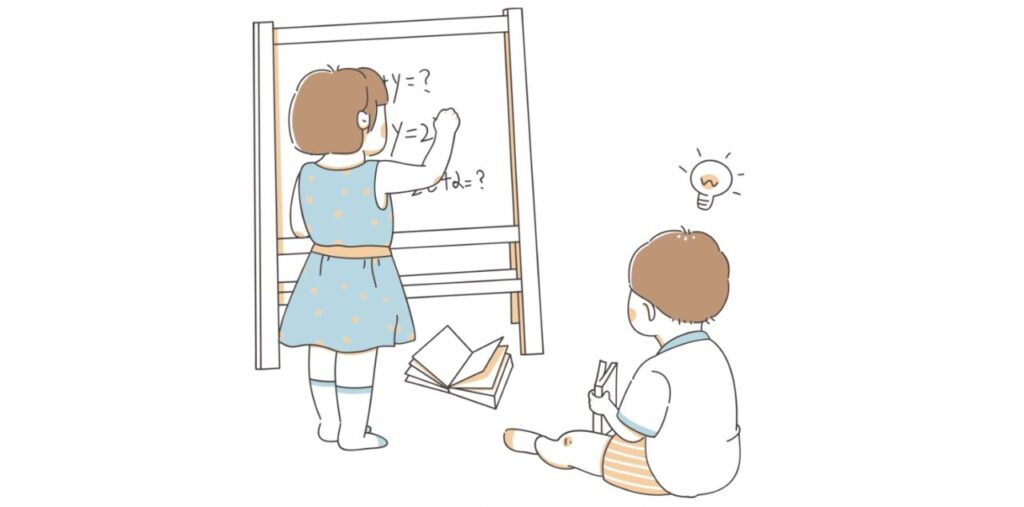
高学年向けのアレンジと配慮
- スピードと難易度を上げる: 高学年には、テンポを速くしたり、本記事で紹介したような少し意地悪なひっかけ問題を混ぜたりすることで、挑戦意欲を掻き立てることができます。
- 子どもたちに出題させる: ルールを完全に理解している高学年には、出題者の役を任せてみましょう。どうすれば友達を引っかけることができるか、論理的に考える力や、場を盛り上げる表現力を養うことができます。
- チーム戦にする: 個人戦だけでなく、班対抗のポイント制にすると、協力する楽しさや、チームとしての戦略を考えるなど、より高度な関わりが生まれます。
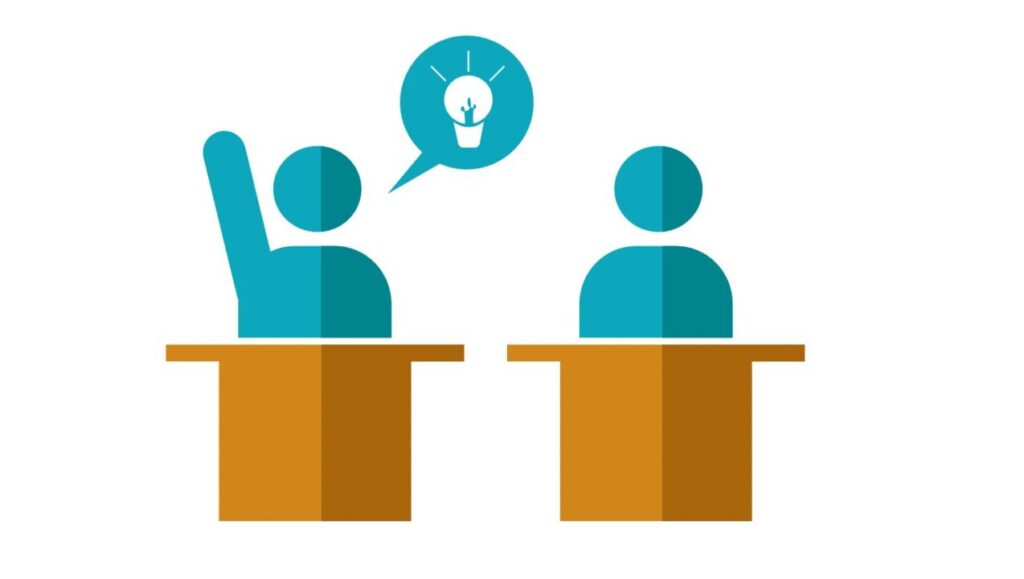
すべての子どもが楽しむためのユニバーサルな配慮
- 失敗を笑いに変える雰囲気作り: 最も大切なのは、「失敗しても大丈夫」という安心感のある雰囲気です。先生が率先して引っかかったり、「ナイスひっかかり!」と声をかけたりすることで、失敗が楽しいことであるという文化をクラスに作りましょう。
- 聴覚情報の聞き取りが苦手な子への配慮: 指示を聞き取ることが難しい子どもには、「『何を言っても』と言ったら」の合図として、特定のカードを見せる、ジェスチャーを加えるなどの視覚的な補助があると、参加しやすくなります。
- 勝ち負けにこだわりすぎない: このゲームの目的は、勝者を決めることではなく、全員で楽しむことです。負けた子を責めたりせず、最後まで残った子をみんなで称えるような、温かい終わり方を心がけましょう。
まとめ:最高のコミュニケーションツールで、子どもたちの笑顔と成長を引き出そう
今回は、「何を言ってもゲーム」について、簡単なルール解説から、自立活動における専門的なねらい、そして学級レクで盛り上がるための具体的な例題まで、詳しくご紹介しました。
このゲームは、単なる暇つぶしの遊びではありません。
- 聞く力、判断力、集中力を養う脳トレであり、
- 感情のコントロールや他者との関わりを学ぶソーシャルスキルトレーニングであり、
- そして何より、先生と子ども、子ども同士の心を繋ぐ最高のコミュニケーションツールです。
準備は何もいりません。必要なのは、先生の「みんなで楽しもう!」という気持ちだけです。
ぜひ、この記事を参考に、明日からの自立活動や学級レクで「何を言ってもゲーム」を実践してみてください。きっと、子どもたちのこれまで見えなかった素晴らしい笑顔と、確かな成長の姿に出会えるはずです。
無料教材はこちら💁♀️
※本記事はアフィリエイトを含みます。





コメント