「あと少しでチャイムが鳴るけれど、何をしよう?」「雨が降って外で遊べない…」
そんなとき、小学生の子供たちが教室で楽しく過ごせる遊びを知っていると、先生も子供たちも安心ですよね。特に、準備に時間がかかったり、特別な道具が必要だったりすると、なかなか気軽に始めることができません。
この記事では、
教室でできる簡単な遊びから、道具なしで盛り上がるゲームまで、小学校の1年生から6年生まで、学年を問わずみんなで楽しめる遊び方をたっぷりとご紹介します。
低学年から高学年まで、子供たちの発達段階に合わせた遊びを幅広く掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
※「本記事にはアフィリエイトリンクを含みます」
自立活動の案はこちらから💁
教室でできる簡単な遊びは?道具なしで盛り上がるゲームも!
小学校の教室は、ただ勉強するだけの場所ではありません。ちょっとしたスキマ時間や雨の日など、室内で過ごさなければならない時間も、遊びを通して子供たちの発想力やコミュニケーション能力を育む貴重な機会です。
特に、道具なしで盛り上がるゲームは、準備の手間がなく、いつでもどこでも始められるため、とても便利です。簡単なルールで誰でもすぐに参加できる遊びは、学級の雰囲気も明るくしてくれます。
ここからは、学年別に遊びのアイデアを見ていきましょう。
1. 教室でできる遊び【低学年向け(1・2年生)】
小学校の低学年は、ルールを理解し始め、友達との関わりを楽しむ時期です。簡単なルールで、体を動かしたり、想像力を働かせたりする遊びがおすすめです。
遊び①:震源地ゲーム
- どんな遊び?
- クラスの中から「震源地」を一人決めます。
- 震源地は、みんなに気づかれないように「ジェスチャー」をします。
- 震源地と同じジェスチャーをした子は、次の震源地になります。
- 他の子は、誰が震源地かを推理します。
- おすすめポイント
- 観察力や集中力が養われます。
- 全員で一斉に体を動かすので、一体感が生まれます。
- 道具なしでできるので、すぐに始められます。
遊び②:なんでもバスケット
- どんな遊び?
- フルーツバスケットの応用版です。
- 「朝食にパンを食べた人!」など、テーマを先生が指定します。
- 該当する子は、席を移動します。
- 鬼は、空いた席に座ります。
- おすすめポイント
- 自己紹介や共通の話題を見つけるきっかけになります。
- 身体を動かす楽しさもあります。
遊び③:お絵かき伝言ゲーム
- どんな遊び?
- 班ごとに一列に並びます。
- 先頭の人にお題を見せ、先頭の人は次の人の背中に指で絵を描きます。
- 最後の人まで絵を伝え、最後の子がお題を当てます。
- おすすめポイント
- 「背中に絵を描く」という非日常的な行為に、子供たちは夢中になります。
- お互いの表現を読み取ることで、コミュニケーション能力が育まれます。

2. 教室でできる遊び【中学年向け(3・4年生)】
中学年になると、少し複雑なルールも理解できるようになり、協力したり、頭を使ったりする遊びが楽しめるようになります。
遊び①:進化じゃんけん
- どんな遊び?
- 最初はみんな「卵」の状態からスタート。
- じゃんけんをして、勝つごとに「ひよこ」→「にわとり」→「人間」と進化していきます。
- 進化するときのポーズを工夫するとさらに盛り上がります。
- おすすめポイント
- じゃんけんという簡単なルールで、誰もがすぐに参加できます。
- 勝ち負けを繰り返す中で、悔しさや喜びを分かち合えます。
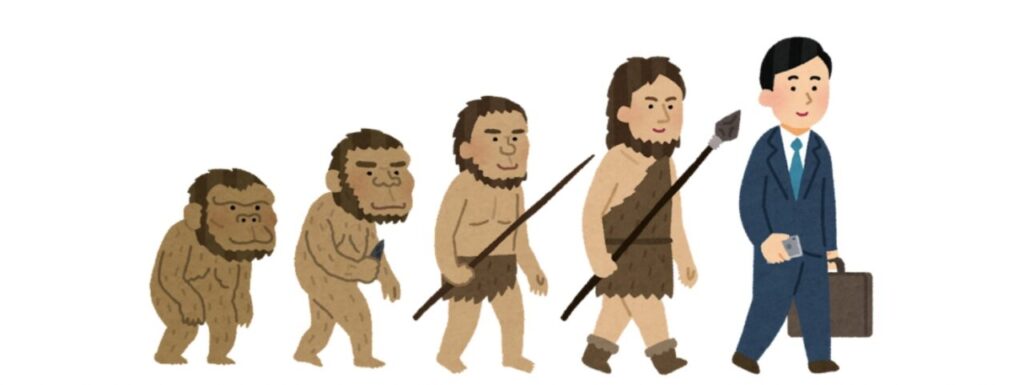
遊び②:古今東西ゲーム
- どんな遊び?
- 先生が「都道府県!」などのお題を出します。
- 円になったり、班ごとに並んだりして、順番にテーマに沿った単語を言っていきます。
- 単語が思いつかなかったり、間違えたりしたらアウトです。
- おすすめポイント
- 知識を競う楽しさがあります。
- 制限時間を設けると、スピード感が出てさらに盛り上がります。
遊び③:ワードウルフ
- どんな遊び?
- 全員に同じお題の単語が書かれたカードを配ります。ただし、一人(または数人)だけ違う単語が書かれています。
- みんなで単語について話し合い、誰が違う単語を持っている「ウルフ」かを推理します。
- ウルフは、自分がウルフだとバレないように、みんなの話にうまく合わせる必要があります。
- おすすめポイント
- 論理的な思考力や、相手の表情や言葉から真意を読み取る力が養われます。
- 心理戦の要素が強く、白熱した展開になります。
3. 教室でできる遊び【高学年向け(5・6年生)】
高学年になると、より思考力やチームワークが求められる遊びが人気です。戦略を立てたり、協力したりする中で、さらに深い学びや仲間との絆を深めることができます。
遊び①:人間間違い探し
- どんな遊び?
- クラスを2つのチームに分けます。
- 一方のチームは教室の外に出て、もう一方のチームは教室の中でポーズや配置を変えます。
- 教室の外に出ていたチームは、変化した部分を見つけ出します。
- おすすめポイント
- 観察力や記憶力が鍛えられます。
- みんなで協力して「間違い」を作る過程も楽しめます。
遊び②:ジェスチャーゲーム
- どんな遊び?
- チームに分かれ、お題のジェスチャーをします。
- 「動物」「職業」「スポーツ」など、様々なテーマでお題を出します。
- 早く当てたチームの勝ちです。
- おすすめポイント
- 言葉を使わずに表現することで、豊かな発想力や表現力が育まれます。
- チームで協力する楽しさを味わえます。
- ヒントクイズというゲームも、このジェスチャーゲームと同様にコミュニケーション能力を養うのに最適です。私のブログ記事「SSTの遊び:ヒントクイズ」で、コミュニケーションが苦手な子供でも楽しみながら参加できるヒントクイズを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
遊び③:リアル人狼ゲーム
- どんな遊び?
- 「村人」「人狼」「占い師」「騎士」などの役職を決めます。
- 会話や議論を通して、誰が人狼かを推理し、追放していきます。
- 人狼は、自分が人狼だとバレないように嘘をつく必要があります。
- おすすめポイント
- 論理的思考力、交渉力、洞察力など、様々な能力が養われます。
- 大人数でプレイすると、より奥深く、盛り上がります。
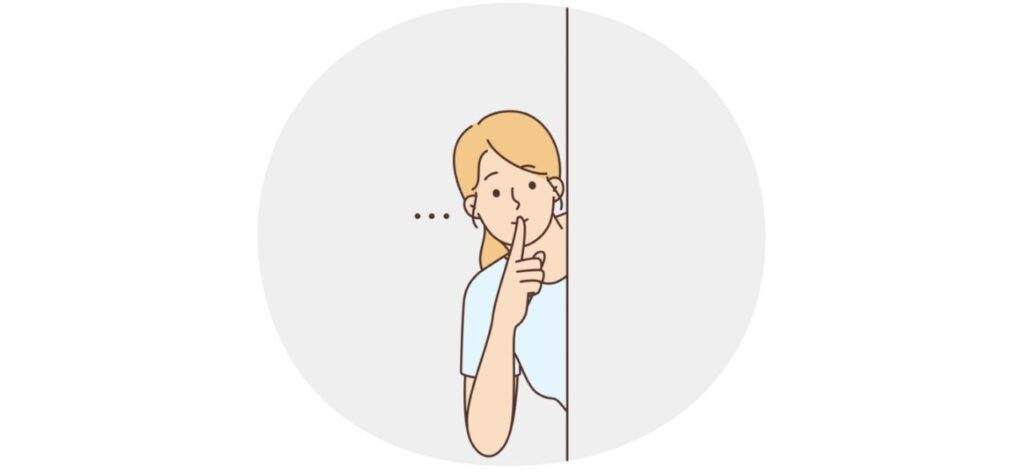
4. 学年を問わず楽しめる!道具なしで盛り上がるゲーム
ここからは、1年生から6年生まで、どんな学年でも楽しめる、道具なしで盛り上がるゲームをピックアップしました。ちょっとしたスキマ時間にもってこいの、教室でできる簡単な遊びです。
遊び①:たけのこニョッキ
- どんな遊び?
- 全員がしゃがみ、1から順番に数を言いながら立ち上がります。
- 同時に立ち上がってしまったら、その2人はアウトです。
- 最後の1人になるまで続けます。
- おすすめポイント
- シンプルなルールですが、駆け引きや予測が面白く、ハラハラドキドキします。
- リズム感も養われます。
遊び②:指スマ
- どんな遊び?
- じゃんけんのように、親と子に分かれます。
- 親が「指スマ!」と掛け声と共に、両手の指を何本か立てます。
- 親以外の子供たちは、その指の合計数を予想して、掛け声と共に指を立てます。
- 親が予想した数と、みんなが立てた指の合計数が一致したら、親の勝ちです。
- おすすめポイント
- 反射神経や瞬発力が試されます。
- 人数が多いほど、予想が難しくなり、盛り上がります。
遊び③:絵しりとり
- どんな遊び?
- 紙や黒板に、絵でしりとりをしていきます。
- 前の人が描いた絵の最後の文字から始まる絵を描きます。
- おすすめポイント
- 発想力や表現力が豊かになります。
- 予想外の絵が出てきて、笑いが絶えません。
遊び④:坊主めくり
- どんな遊び?
- 百人一首の坊主めくり版です。
- 百人一首の札を裏返しにして並べ、順番にめくっていきます。
- 「坊主」の絵を引くと、今まで集めた札を全て没収されてしまいます。
- 「姫」の絵を引くと、他の人から札をもらえます。
- 「殿」の絵を引くと、札をたくさんもらえます。
- おすすめポイント
- 運の要素が強く、みんなで盛り上がれます。
5. 教室でできる遊び:遊びを通して学ぶSST(ソーシャルスキルトレーニング)
小学校の教室でできる遊びは、ただ楽しいだけでなく、ソーシャルスキルトレーニング(SST)としても非常に有効です。遊びを通して、コミュニケーションの仕方や、自分の気持ちを伝える方法を自然と学ぶことができます。
私のブログ記事では、SSTの一環として遊びを紹介しています。
遊び⑤:ストップアンドゴー
- どんな遊び?
- ルールを理解する力や、指示を聞いて行動する力を養う遊びです。
- 「ストップ」と言われたら動きを止める、「ゴー」と言われたら動き始める、というシンプルなルールです。
- 詳細は、ブログ記事「SSTの遊び:ストップアンドゴー」で紹介しています。ぜひご覧ください。
授業や学級活動でちょっとした時間に取り入れられる遊びは、子ども同士の距離をぐっと縮めてくれます。今回紹介した20のゲームは、私が実際に教室で試して「盛り上がった!」と感じたものばかりです。
ただ、「もっとたくさんの遊びを知りたい」「学級経営の中で使い分けたい」という先生も多いと思います。そんな方におすすめなのが、こちらの書籍です。
👉 『仲よくなれる! 授業がもりあがる! 密にならないクラスあそび120 Kindle版』
120種類もの遊びが収録されていて、低学年から高学年まで幅広く活用できます。学級の雰囲気づくりや授業の合間のリフレッシュに役立つので、「困ったときの一冊」として持っておくと安心です。
まとめ|教室でできる遊びで、小学校生活をもっと豊かに
今回は、教室でできる遊びをテーマに、低学年から高学年まで楽しめる簡単で面白いゲームをたくさんご紹介しました。
- 教室でできる遊び 低学年は、シンプルなルールで身体を動かしたり、想像力を働かせたりする遊びがおすすめ。
- 教室でできる遊び 中学年は、少し複雑なルールやチーム戦が楽しめるようになります。
- 教室でできる遊び 高学年は、頭を使う戦略的なゲームや、協力する遊びが人気です。
- 道具なしで盛り上がるゲームは、学年を問わず、いつでもどこでもすぐに始められます。
子供たちが笑顔で過ごせる時間が増えることで、クラスの雰囲気もより良くなります。ぜひ、これらのアイデアを日々の学校生活に取り入れてみてください。




コメント