子どもたちは、自分の「好きなこと」を話すとき、まるで水を得た魚のように生き生きとしています。その熱量と、言葉を紡ぎ出す姿は、まさに学びの原点ではないでしょうか。特に、自閉症・情緒学級の子どもたちの中には、「話すのが苦手」「一方的に話してしまう」「順序立てて話せない」といった発達特性から、自分の思いを「伝える」ことに難しさを抱える子も少なくありません。
子どもたちの“好き”という情熱を起点に、どうすれば「伝える力」を育むことができるか?
本記事では、
この問いに対する一つの実践例として、小学校の自閉症・情緒学級で取り組んだ「目指せYouTuber!」単元をご紹介します。
他にもおススメの「自立活動」の実践記事を多数書いています。「ちょっと見てみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。↓
単元全体のねらいと概要
単元名
つたえよう!ぼく・わたしのスキなこと
対象
自閉症・情緒学級(複数学年・学力差あり)
単元時間
全5〜8時間(1か月程度)
この単元は、
子どもたちの「好き」という純粋な興味関心を原動力に、「相手に伝える力」「自己表現力」「自信」を育むことを最大のねらいとしています。YouTuberという身近な存在に憧れ、その活動を真似ることで、子どもたちは自然と「どうすれば自分の好きが伝わるか」を考え、実践していくことができます。
単元を通して育てたい力
この単元は、様々な領域にわたる力を総合的に育むことを目指します。
| 領域 | 育てたい力 |
|---|---|
| 自立活動 | 自己理解、他者意識、自己表現、対人スキル |
| 国語 | 順序立てた説明、語彙力、発表力 |
| 図工(連携) | 発表資料づくり、イラストやカード作成 |
自立活動の視点から特に育むねらい
本単元は、自立活動の6区分27項目の中でも、特に以下の5つの力を重点的に育むことをねらいとしています。
- 自己肯定的な意識と主体性の育成 自分の「好き」を表現する成功体験を通して、自信と主体性を高めます。
- 自己表現と相手の理解 多様な方法で表現する力を養い、友だちの発表を聞くことで、相手の伝えたいことを理解する力を育みます。
- 課題解決のための計画の立て方と実行 発表準備のステップを通して、目標達成のための計画性と実行力を身につけます。
- 課題解決に必要な情報の選択と活用 伝えたいことを明確にするため、必要な情報を選び、効果的に表現する力を養います。
- 目標達成への意欲の維持と達成感 明確な目標に向かって意欲を維持し、発表をやり遂げた大きな達成感を味わうことで、次の活動へのモチベーションにつなげます。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
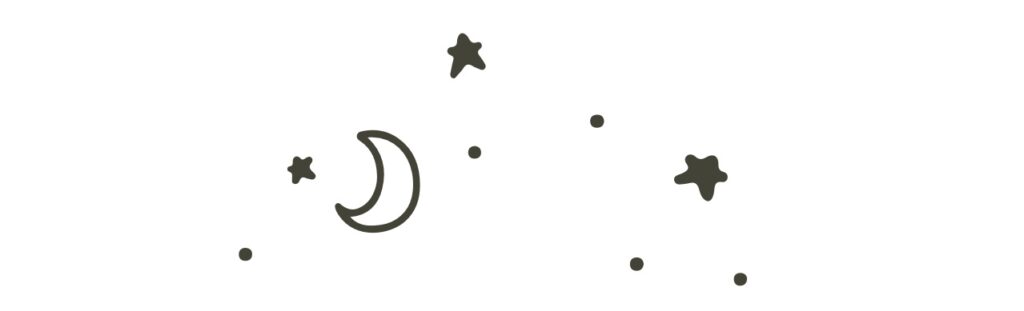
単元構成と授業の進め方
ここからは、実際の授業の進め方を時間ごとに詳しく見ていきましょう。
第1時「自分の“スキ”を見つけよう!」
さあ、いよいよ単元のスタートです。まずは、子どもたち一人ひとりの「好き」に光を当てていきましょう。
- 活動内容 好きなことを言葉や絵で表す
- 導入として、先生が「私は〇〇が好きです!」と身近なもの(好きな食べ物、趣味など)を写真や絵を見せながら紹介し、子どもたちに「先生の好きなものは何でしょう?」と問いかけてみましょう。子どもたちの答えが返ってきたら、「どうして好きだと思いますか?」と理由を尋ねることで、この後の活動につながるヒントを与えられます。
- 次に、子どもたちに「みんなの好きなものは何かな?」と問いかけ、自由に発言する時間を取りましょう。発言が難しい子には、絵や写真などを見せながら「これ好き?」と尋ねるなど、個別の声かけが有効です。
- 支援例 好きなことカード、スキ!シート配布
- 「好きなことカード」 小さめのカードに、子どもたちが好きなものを自由に絵や文字で書かせます。思いつくままにたくさん書いてもらいましょう。
- 「スキ!シート」 大きな用紙の真ん中に「わたしのスキなこと」と書き、周りに好きなものの絵や写真を貼ったり、言葉で書き込んだりするシートを用意します。絵を描くのが得意な子、文字を書くのが得意な子、それぞれが表現しやすいように工夫しましょう。
- 必要であれば、先生が事前に用意した写真やイラスト(動物、乗り物、キャラクター、食べ物など)を見せながら、「これは好き?」と尋ね、子どもが指さしたり、声を出したりする反応を促しても良いでしょう。
- 工夫 ポケモン、レゴ、絵、YouTuber、ゲームなど何でもOK
- 好きなものは、どんなことでも構いません。「ポケモン」や「レゴ」といった遊びから、「絵を描くこと」「ゲーム」「YouTuberを見ること」など、子どもたちが熱中していることであれば、何でもOKです。大切なのは、「自分の好きなこと」を認識し、それを表現する喜びを感じることです。
- 「〇〇君はゲームが好きだね!どんなゲームが好きかな?」のように、具体的に尋ね、子どもの興味をさらに引き出していく声かけを意識しましょう。

第2時「見本を見てみよう&話の構成を学ぼう」
「好き」が見つかったら、次はそれを「どう伝えるか」を学びます。YouTuberの動画を参考にしながら、話の構成について考えていきましょう。
- 活動 教師が模擬発表 or 子ども向け動画を視聴
- 先生が、第1時で見つけた自分の「好き」をテーマに、模擬発表をしてみましょう。「私は(好きなもの)が好きです。なぜかというと…」というように、簡単な構成で話してみます。
- または、子ども向けに作られた、好きなものを紹介するYouTuberの動画や、短編のアニメーションなどを視聴するのも効果的です。事前に、著作権に配慮した動画を選んでおきましょう。
- 動画視聴の際は、ただ見せるだけでなく、「どこが面白いかな?」「どんなふうに説明しているかな?」と、問いかけながら見ることが大切です。
- 視点 「なにが好き?」「どうやって遊ぶ?」「どこが楽しい?」
- 模擬発表や動画視聴後、子どもたちと一緒に、話の構成を分析する時間を取りましょう。
- 「この人は何が好きって言ってた?」
- 「どうやって遊ぶって言ってた?」
- 「どこが楽しいって言ってたかな?」
- これらの視点を明確にすることで、子どもたちは「何を話せば良いのか」の具体的なイメージを持つことができます。
- 模擬発表や動画視聴後、子どもたちと一緒に、話の構成を分析する時間を取りましょう。
- 視覚支援 「説明順カード」を使って順序立てる
- A4程度のカードに、「なにが好き?」「どうやって遊ぶ?」「どこが楽しい?」といった言葉と、それぞれに対応するイラストを大きく描いた「説明順カード」を用意します。
- 先生の模擬発表や動画を見ながら、該当するカードをホワイトボードに貼り、「まず、好きなものの名前を言って、次に遊び方を説明して、最後に楽しいところを話すんだね!」と、視覚的に話の流れを提示しましょう。
- 発達特性のある子どもたちにとって、言葉だけの説明は理解が難しい場合があります。視覚的な支援は、情報の整理と理解を助ける上で非常に有効です。
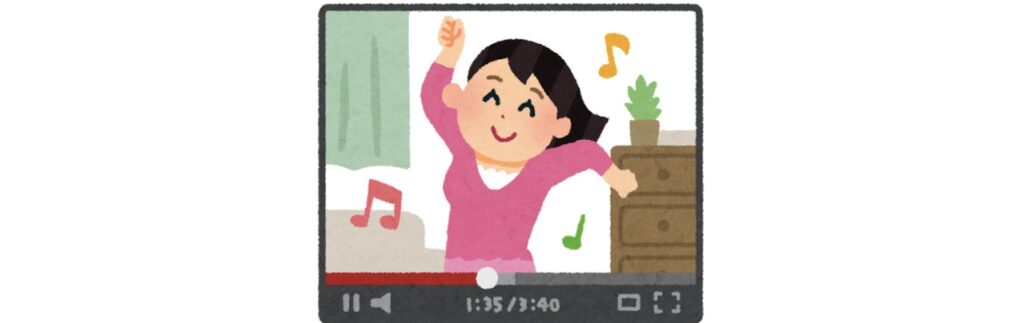
第3時「話す内容を考えよう」
いよいよ、自分の「好き」を伝えるための具体的な内容を考えていきます。第2時で学んだ「説明順カード」を参考に、話の骨組みを作りましょう。
- 活動 話す順番・内容カード作成
- 子どもたちに、第2時で使用した「説明順カード」と同じ構成で、自分用の「話す順番・内容カード」を作成させます。
- 例えば、「なにが好き?」のカードには、自分の好きなものの名前やイラストを描き、「どうやって遊ぶ?」のカードには、遊び方の簡単な絵やキーワードを書き込みます。
- それぞれのカードに、話したい内容を具体的に書き込んでいきましょう。
- 最初は、先生がホワイトボードに例を書きながら、「〇〇ちゃんの好きなものは?」「どうやって遊ぶの?」と、一人ひとりに寄り添って声かけをすることで、内容を深める手助けをします。
- 支援例 文章が書けない子には絵やキーワードだけでもOK
- 文章を書くことが難しい子どもには、絵や写真、キーワードだけでも十分に表現できるように配慮しましょう。先生が代筆しても良いですし、子どもが描いた絵を基に先生が言葉を添えてあげるのも良い方法です。
- iPadなどのタブレット端末が使用できる環境であれば、好きなものの写真を撮ったり、簡単な動画を撮ったりして、それを見ながら話す練習をするのも効果的です。
- 「話す順番・内容カード」を完成させることで、子どもたちは自分の発表内容を具体的にイメージできるようになります。
第4時「発表練習をしよう」
内容がまとまったら、いよいよ発表の練習です。本番に向けて、自信を持って話せるようにサポートしていきましょう。
- 活動 鏡で練習、先生・友だちに向けておためし発表
- まずは、鏡の前で一人で話す練習をしてみましょう。自分の表情や話し方を確認することで、客観的に自分を見つめることができます。
- 次に、先生や少人数の友達に向けて「おためし発表」をしてみましょう。安心できる環境で練習することで、緊張を和らげることができます。
- 発表の際には、話す順番・内容カードを見ながらでもOKです。完璧に覚えることよりも、「自分の言葉で伝える」ことを重視しましょう。
- 先生は、子どもたちの良い点を見つけて具体的に褒めることを意識してください。「〇〇ちゃんの好きなゲーム、楽しそうだね!」「声が大きくて聞き取りやすいよ!」など、具体的なフィードバックは子どもの自信につながります。
- 配慮 緊張が強い子は録画式や少人数でもOK
- 人前で話すことに強い緊張を感じる子どもには、無理に全員の前で発表させず、配慮が必要です。
- 録画式での発表:先生と二人きりの時に、iPadやスマートフォンで発表している様子を録画する形でも良いでしょう。後で、みんなで動画を見る時間を作っても良いですね。
- 少人数での発表:クラス全体ではなく、信頼できる数名の友だちや先生の前だけで発表する機会を作るのも有効です。
- 発表方法の選択制:次章でも詳しく述べますが、発表方法を子ども自身に選択させることで、安心感を持って取り組めるようになります。

第5時〜6時「発表会を開こう!」
練習を重ねた成果を発揮する発表会です。子どもたちが主役となり、自分の「好き」を存分に表現できる場を創りましょう。
- 活動 一人ひとりが順に発表(録画しても◎)
- 準備ができた子から、一人ずつ発表を行います。発表の際には、「話す順番・内容カード」や、自分で作ったイラストや写真などの資料を活用しても良いでしょう。
- 発表中の様子を録画しておくことを強くお勧めします。後で子どもたちと一緒に見返すことで、自分の発表を振り返り、さらに自信を深めることができます。また、保護者の方にも共有することで、家庭での話題にもなり、子どもの成長を実感してもらうことができます。
- 発表会の雰囲気作りとして、拍手や応援の声かけを積極的に行い、子どもたちが安心して発表できる温かい場を創りましょう。
- 聞き手活動 「よかったカード」で聞いた内容を共有
- 発表を聞いている子どもたちにも、積極的に参加してもらうために「よかったカード」を用意します。
- 発表が終わった後、聞き手は「〇〇ちゃんの好きな〇〇が分かったよ」「〇〇の遊び方が面白かったよ」など、発表内容から「よかった」と感じたことをカードに書いたり、絵で表現したりします。
- 書くことが難しい子には、先生が代筆したり、キーワードを選ばせたりするなどの支援を行いましょう。
- このカードを交換したり、発表した子に手渡したりすることで、聞く力と、相手に伝える力の両方を育むことができます。また、発表した側は、自分の発表が相手に伝わったことを実感でき、大きな喜びにつながります。
- 教室掲示や保護者連携にもつながる
- 発表会で使った資料や、「よかったカード」を教室に掲示することで、子どもたちの頑張りを可視化し、いつでも振り返れるようにしましょう。
- 発表会の様子を録画した動画や、作成した資料を保護者の方に共有することで、家庭での会話のきっかけとなり、子どもの成長を共に喜ぶことができます。保護者会や懇談会の際にも、具体的な成果として見せることができます。
第7時「ふりかえりとまとめ」
単元の締めくくりとして、これまでの活動を振り返り、学びを定着させましょう。
- 活動 ふりかえりカード記入
- 「ふりかえりカード」を配布し、以下の内容を子どもたちに記入してもらいます。
- 「この単元で一番楽しかったことは何ですか?」
- 「頑張ったことは何ですか?」
- 「人に伝えるために工夫したことは何ですか?」
- 「次にやってみたいことは何ですか?」
- 絵や短い言葉でも構いませんので、子どもたちが自分の言葉で表現できるような工夫をしましょう。必要であれば、先生が質問を読み上げ、一緒に考える時間を取りましょう。
- 子どもたちが書いたカードを一枚ずつ読み上げ、みんなで共有する時間を持つことで、互いの学びを再確認し、共感する機会にもなります。
- 「ふりかえりカード」を配布し、以下の内容を子どもたちに記入してもらいます。
- 「人に伝えるって楽しい!」「またやりたい!」という言葉が自然と出てくる活動を目指す
- この単元を通して、子どもたちに「自分の好きを人に伝えるって楽しい!」「またやってみたい!」というポジティブな気持ちが芽生えることを目指しましょう。
- 子どもたちの口から、そういった言葉が自然と出てくるような、達成感と喜びを感じられる活動を心がけてください。
- 最後に、「みんなが一生懸命、自分の好きを伝えてくれて、先生はとても嬉しかったよ。みんなの『好き』を伝わるように工夫する力、素晴らしいね!」などと、先生から具体的な言葉で子どもたちの頑張りを認め、称賛の言葉を伝えましょう。
学年差・学力差があるクラスでの工夫
複数学年や学力差がある自閉症・情緒学級において、この単元をより効果的に実践するための工夫をご紹介します。
- 2年 絵や写真メイン/短文カード形式でOK
- 低学年の子どもたちには、絵や写真など視覚的な情報をメインに発表させましょう。
- 「これ、好き!」「これ、楽しい!」のような短文カード形式で、一文ずつ区切って発表してもらうなど、負担の少ない形から始めることが大切です。
- 先生が子どもたちの言葉を補足し、絵や写真に言葉を添えてあげると、より表現が豊かになります。
- 4年 簡単な原稿づくり/1分ほどの説明を目標に
- 中学年の子どもたちには、簡単な原稿づくりにチャレンジさせましょう。
- 「説明順カード」に書いたキーワードや絵をもとに、簡単な文章を組み立てる練習をします。
- 発表時間は1分程度を目標に、短すぎず、長すぎない適切な長さを意識させましょう。
- 単語だけでなく、主語と述語のある文章で表現する練習を促していくと良いでしょう。
- 6年 構成意識+自分のこだわりに理由づけまでチャレンジ
- 高学年の子どもたちには、より深い表現を目指させます。
- 「はじめに」「好きなものの紹介」「理由」「まとめ」といった、より複雑な話の構成を意識させ、発表に緩急をつける練習をしてみましょう。
- 単に「好き」というだけでなく、「なぜそれが好きなのか」「そのこだわりはどこから来ているのか」といった、自分の考えや感情を理由付けして伝えることに挑戦させると、より深い自己表現につながります。
- 発表時間を2〜3分程度に伸ばし、より詳細な説明ができるように促しましょう。
- 学力差対応 発表方法の選択制(声、動画、カード、スライドなど)
- 全員が同じ方法で発表する必要はありません。子どもたちの特性や得意な表現方法に合わせて、発表形式を選択できるようにしましょう。
- 声での発表:基本的な発表形式です。
- 録画した動画の発表:人前で話すのが苦手な子、自分のペースで話したい子に適しています。
- 手持ちのカードや絵を見せながらの発表:言葉での表現が難しい子も、視覚的に訴えることができます。
- タブレット端末やPCを使ったスライド発表:ICT機器の操作が得意な子、より視覚的に分かりやすく伝えたい子に適しています。写真やイラストを効果的に使って、プレゼンテーションの基礎を学ぶ機会にもなります。
- 子ども自身が「これで伝えたい!」と思える方法を選ぶことで、主体的に活動に取り組むことができます。
- 全員が同じ方法で発表する必要はありません。子どもたちの特性や得意な表現方法に合わせて、発表形式を選択できるようにしましょう。
授業で使用した教材・支援ツール例
本単元で使用できる、具体的な教材や支援ツールの例をご紹介します。これらを参考に、子どもたちの実態に合わせて作成・活用してみてください。
- スキなこと記入シート(絵・文字)
- 第1時で活用します。A4用紙に、中央に「わたしのスキなこと」と大きく書き、その周りに絵を描いたり、言葉を書き込んだりするスペースを設けます。
- 絵を描くのが得意な子用、文字を書くのが得意な子用など、複数種類用意しておくと良いでしょう。写真やイラストを貼り付けられるスペースも設けておくと、より表現の幅が広がります。
- 話の構成カード(なに?→どうやって?→なぜ好き?)
- 第2時以降、継続して活用します。
- A4程度のカードに、「なにが好き?」、「どうやって遊ぶ?」、「どこが楽しい?」という見出しと、それぞれに対応するイラストを大きく描きます。
- マジックテープなどをつけて、ホワイトボードや提示板に貼り付けられるようにすると、繰り返し使用できます。
- 必要に応じて、「まとめ」「みんなに伝えたいこと」などのカードを追加しても良いでしょう。
- よかったところカード(相互評価用)
- 第5〜6時の発表会で活用します。
- 名刺サイズ程度のカードに、「〇〇さんの発表で、ここがよかったよ!」という書き出しと、具体的に記入できるスペースを設けます。
- 「〇〇(好きなもの)が分かったよ」「〇〇(遊び方)が面白かったよ」「声が大きくて聞きやすかったよ」など、チェックボックス形式にしておくと、子どもたちが記入しやすくなります。
- 絵を描くスペースも設けることで、文字を書くのが苦手な子でも参加できるように工夫しましょう。
- 視覚支援パネル・スライド型の枠組み
- 発表時に使用できる、視覚的な補助ツールです。
- 厚紙などで作成したパネルに、「なにが好き?」「どうやって遊ぶ?」などの見出しをつけ、その下に発表内容を貼り付けられるようにする。
- パワーポイントやGoogleスライドなどで、あらかじめテンプレートを作成し、子どもたちが文字や絵を挿入していくだけでスライドが完成するような枠組みを用意する。ICT機器を活用することで、より本格的な発表体験ができます。
成果の残し方・活かし方
この単元で得られた子どもたちの成果は、ぜひ様々な形で残し、今後の学習や生活に活かしていきましょう。
- 動画にして保護者に共有(保護者の喜びも大きい)
- 発表会で録画した動画は、ぜひ保護者の方に共有してください。子どもたちの生き生きとした発表姿は、保護者にとって何よりの喜びとなります。
- 家庭での話題となり、子どもの自信をさらに深めるきっかけにもなります。「学校でこんなに頑張っているんだね!」という保護者の方からの声かけは、子どもたちの学習意欲を向上させます。
- 掲示物として「○○さんのスキなことコーナー」
- 子どもたちが作成した「スキなことシート」や「話す順番・内容カード」、発表で使ったイラストなどを、教室や廊下に掲示しましょう。
- 「○○さんのスキなことコーナー」として展示することで、子どもたちは自分の成果が認められたと感じ、自己肯定感を高めることができます。また、他のクラスの子どもたちや先生方にも見てもらうことで、交流のきっかけにもなります。
- 自己紹介・交流会の土台としても活用できる
- この単元で学んだ「自分の好きなことを伝える」というスキルは、自己紹介や交流会の場面で大いに役立ちます。
- 新学期や転入生が来た際、また他の学級との交流活動などで、「自分の好きなことを話してみよう!」という機会に、この単元で作成した資料や学んだ構成をそのまま活用することができます。
- 子どもたちは、安心して自己紹介ができるようになり、自信を持って他者と交流する姿勢を育むことができます。
- 他教科(国語、図工、ICT)と結びつけやすい
- この単元は、単なる特別活動にとどまらず、他の教科との連携も非常にしやすいのが特徴です。
- 国語:順序立てて話す練習、語彙力の向上、表現力の育成など、国語科の目標に直接的に貢献します。発表文の作成は、作文の練習にもなります。
- 図工:発表資料としてのイラスト作成や、カードのデザインなど、視覚的な表現力を養います。
- ICT:タブレット端末やPCを使ってのスライド作成、動画の撮影・編集など、現代の生活に不可欠なICTスキルの習得にもつながります。
- 教科の枠を超えて、子どもたちの総合的な力を育む単元として位置づけることができます。
- この単元は、単なる特別活動にとどまらず、他の教科との連携も非常にしやすいのが特徴です。
おわりに
この「目指せYouTuber!」単元は、子どもたちの「楽しい」という気持ちが、学習の原動力になることを改めて教えてくれます。教科書に書かれたことだけでなく、子どもたちが「もっと話したい!」「もっと伝えたい!」と心の底から思える題材であれば、彼らの秘めた可能性は無限に広がっていくのです。
自閉症・情緒学級の子どもたち一人ひとりが持つ「好き」という輝きを、この単元を通して最大限に引き出し、「伝える喜び」を体感する機会を提供できたなら、これ以上の喜びはありません。先生方が、子どもたちの笑顔と成長のために、この実践を少しでも役立てていただければ幸いです。






コメント