前回の記事では、子どもの怒りの裏にある「本当の気持ち」に気づき、先生が感情を「言葉にして寄り添う」ことの大切さ、そしてそれが子どもとの信頼関係を築く土台になる「感情支援サイクル」についてお話ししました。
※前回の記事はこちら⇩
ここでは、感情の土台ができた後に特におすすめしたい、実践的なSSTのテーマを5つご紹介します。教室や個別の支援で、ぜひ取り入れてみてください。
おすすめの自立活動の実践例はこちら👇
※おすすめ教材を使ったアンガーマネジメント自立活動(SST)はこちらです↓
無料ダウンロード教材・プリントはこちら💁
1.怒りを言葉にするスキル
ねらい
怒りの衝動を「破壊」や「攻撃」といった行動ではなく、「言葉」で相手に伝えられるようにする
感情の爆発は減ってきたけれど、まだイライラしたときにどう伝えていいか分からない…そんな子どもに特に必要なスキルです。怒りを感じたときに、衝動的に手が出たり、物を壊したりする代わりに、言葉で自分の気持ちや要求を表現する方法を学びます。

活動例
①「Iメッセージ」の練習
「〇〇されて嫌だった。だから△△してほしい」という言い方の構造を理解し、練習します。
具体的な場面設定(例:並んでいたのに順番を抜かされたとき、友達にからかわれたとき、貸してほしかったものが借りられなかったとき)などで、それぞれIメッセージでどう伝えるかロールプレイしてみましょう。先生が相手役になり、子どもの言葉を丁寧に受け止めます。
「私は〇〇だと感じた」という主語(I)を意識することで、相手を責めるのではなく、自分の気持ちを伝える練習になります。「〜してほしい」という具体的な要求を伝えることも大切です。
こちらの記事から「感情カード」や「場面カード」のDLができます👇
②「怒りのメーター」で自分の怒りを数値化し、対応を決める
怒りの感情を0から10などのスケールで数値化します。0は落ち着いている状態、10は今にも爆発しそうな状態、といったように子どもと一緒に決めます。(色分けしたり、キャラクターの表情を使ったりするのも効果的です。)
それぞれの温度に応じた具体的な行動選択肢を考えます。(例:レベル3→深呼吸、レベル5→静かに席を立つ、レベル7→先生に話しかける、レベル10→人がいない場所でクールダウンする)
実際に腹立たしい出来事を想定し、「このとき、怒りの温度は何℃? 何をしたら落ち着ける?」と考えてみる練習を繰り返します。日常で「今何℃?」と先生が声かけすることも、子どもが自分の感情を意識する助けになります。
こちらの記事から「怒りメーター」「気持ちカード」の教材がダウンロードできます👇
③ロールプレイで「ムカッとしたときの言い方」を練習
怒りを伝えるとき、「強すぎず・弱すぎず」、相手に伝わる適切な声の大きさやトーン、表情を意識して練習します。
言いにくいことでも、どうすれば相手に不快感を与えすぎずに伝えられるか、様々な言い方を試してみましょう。先生が見本を見せたり、「こんな言い方もあるよ」と提案したりします。
先生へのアドバイス
練習の場で完璧にできなくても大丈夫です。実際に子どもが怒りを感じたときに、「さっき練習した温度計、何℃かな? 何かできることある?」と優しく声かけ、練習したスキルを思い出させるサポートが大切です。成功体験を積み重ねることで、子どもは自信を持って言葉で伝えることを選びやすくなります。
2. 我慢の限界が来る前に「助けを求める」スキル
ねらい
一人で抱え込みすぎたり、突然感情が爆発したりする前に、困っている状況を周囲に「ヘルプ」として伝えられるようにする
つらいことや困ったことを一人で抱え込んでしまい、どうにもならなくなってから衝動的な行動に出てしまう子どもがいます。「助けて」と言うことが苦手な子に、適切なSOSの出し方を教えます。

活動例
①「今、〇〇だから助けてほしい」と具体的に伝える練習
「困っています」「手伝ってもらえませんか」「話を聞いてほしいです」など、具体的な「助けを求めるフレーズ」を練習します。
様々な場面設定(例:宿題が分からないとき、友達との遊びで困ったとき、先生に言いたいことがあるけれど言葉が出ないとき)で、どのフレーズが適切かを考え、声に出す練習をします。
②先生との「SOSサイン」を決める
言葉で伝えるのが難しいときのために、先生と子どもだけの秘密のサインを決めます。
サインは簡単なジェスチャー(例:指を2本立てる、耳に触る)や、特定の持ち物(例:特定の消しゴムを机の隅に置く)など、子どもが無理なくできるものが良いでしょう。
「○○ってサインが出たら、先生は△△するね」と、先生の応答の仕方も具体的に決めておきます。(例:近くまで行く、そっと声をかける、休憩に誘う)
サインを決めることで、子どもは「どうしようもなくなっても、助けを求める手段がある」という安心感を得られます。
③演技付きロールプレイ
具体的な困りごとを想定したシナリオで、助けを求める練習をします。(例:「友達に嫌なことを言われた」→どんな気持ち?→誰に、どう助けを求める?→先生や友達にどう伝える?)
先生が相手役になり、子どもの助けを求める言動にどう応答するかを実際に演じて見せます。子ども自身が先生役や友達役をやってみることも理解を深めます。
先生へのアドバイス
子どもがSOSサインを出したり、「助けて」と言葉にしたりできたときは、素早く、そして温かく対応することが非常に重要です。「よく言えたね」「気づけて良かったよ」といった肯定的なフィードバックを忘れずに伝えましょう。
こちらから教材やプリントのダウンロードできます。👇
3. 感情の波を乗りこなす「クールダウン」スキル
ねらい
感情が高ぶったときに、自分で気持ちを落ち着かせる方法を「言葉化」し、意識的に実践できるようにする
怒りや不安など、強い感情を感じたときに、その波に飲まれてしまうのではなく、自分で「落ち着こう」と働きかけられるスキルです。前回の「感情支援サイクル」の段階で、先生が「落ち着く」ことを促す中で、子どもが自分なりに落ち着く方法を見つけ始めているかもしれません。それをさらに明確にし、意識的に使えるようにします。

活動例
①「こういうとき、こう言うと落ち着けるよ」リストの作成
「イライラしたとき」「悲しいとき」「不安なとき」など、感情別や状況別に、自分で自分に言い聞かせる言葉や行動のリストを子どもと一緒に作成します。
先生がいくつか提案(例:「大丈夫、大丈夫」「まずは深呼吸」「落ち着こう」)し、子ども自身のアイデアも引き出しましょう。絵やイラストで表現するのも子どもには分かりやすい方法です。壁に貼ったり、カードにして持ち歩けるようにしたりするのも良いでしょう。
②具体的なクールダウン方法の練習
「深呼吸して3秒数える」「『いまイライラしてるな』って自分の気持ちを言葉にして自分に言う」など、手軽にできるクールダウン方法を実際にやってみる練習をします。
その他にも、静かな場所に行く、好きな絵を見る、手を洗う、背伸びをする、といった自分に合った方法を見つける手伝いをします。
③グループで「イライラしたときにこうしたら落ち着けたよ体験」を共有
クラスやグループで、イライラしたり困ったりしたときに「こんなことをしたら少し落ち着けたよ」という経験を共有する時間を設けます。
他の子の話を聞くことで、「そういう方法もあるんだ」と新しい発見があったり、「自分だけじゃないんだ」という安心感につながったりします。成功体験だけでなく、「これはうまくいかなかったけど、次はこの方法を試したい」といった振り返りも大切です。
先生へのアドバイス
クールダウンは、感情のピークを過ぎてから練習するのが効果的です。子どもが落ち着いているときに、「もし次イライラしたら、何を試してみる?」と一緒に話し合っておくと、いざというときに実践しやすくなります。
4. 要求を「怒り」や「無言」ではなく適切に伝えるスキル
ねらい
自分の要求やお願いを、怒ったり黙り込んだりするのではなく、相手に伝わる適切な方法で表現する力を育てる
自分の「〜したい」「〜してほしい」という気持ちをうまく伝えられずに、諦めてしまったり、逆に強引な手段に出てしまったりする子どもがいます。相手に受け入れてもらいやすい、上手なお願いの仕方を学びます。

活動例
①「~してもいいですか?」のバリエーション練習
「〜してください」「〜お願いできますか」「もしよろしければ、〜していただけますか」など、相手や状況(先生にお願いする、友達にお願いする、目上の人にお願いする)に応じた丁寧さや言葉遣いのバリエーションを練習します。
声のトーンや表情、アイコンタクトなども意識してロールプレイを行います。
②自分のしたいことを計画しておねがいするワーク
「今日、学校でやりたいこと」などを3つほど書き出します。
それぞれの要望について、「誰に」「いつ」「どんな言葉で」お願いするのが一番良いか、計画を立てるワークをします。例えば、「休み時間に〇〇君と遊びたい」なら、誰に(〇〇君に)、いつ(休み時間になったら)、どんな言葉で(「一緒に遊んでもいい?」と笑顔で)といった具合です。
③上手にお願いできたときの「OKもらえる率」をゲーム感覚で計測
練習したお願いの仕方で、実際に先生や協力してくれる友達にお願いしてみます。
お願いが聞き入れてもらえたら「OK」として、シールを貼ったりグラフにしたりして成功体験を「見える化」します。「〇回お願いして、〇回OKがもらえた!」と、ゲーム感覚で取り組むことで、子どもは楽しみながらスキルを磨くことができます。
先生へのアドバイス
子どもが一生懸命にお願いしている姿が見られたら、結果がどうであれ、「お願いしようと頑張れたね」とプロセスを承認することが大切です。お願いが通らなかった場合も、「別の言い方だったらどうかな?」「誰にお願いしたら良かったかな?」と一緒に振り返り、次に繋げましょう。
5. 言葉にしづらいときの「非言語サイン」で伝える練習
ねらい
パニックで言葉が出ないときや、言葉で表現するのが苦手なときに、言葉以外の代替手段で自分の気持ちや状況を伝えられるようにする
言葉での表現が苦手な子どもや、感情が高ぶると言葉が出なくなってしまう子どもにとって、非言語的なコミュニケーション手段は非常に有効です。自分の状態を周囲に知らせる「別の方法」を身につけます。

活動例
①気持ちカード、フェイスカード、サインカードの活用
「嬉しい」「悲しい」「怒っている」「不安」「疲れた」「助けてほしい」などの気持ちを表す絵カードや、様々な表情が描かれたフェイスカードを用意します。
「休憩したい」「静かにしてほしい」「順番を守ってほしい」といった具体的な要望や状況を表すサインカードも有効です。
これらのカードを使って、今の自分の気持ちや状況を先生や友達に伝える練習をします。「今の気持ちはどのカードかな?」と尋ねてみたり、先生が「先生は今、嬉しい気持ちだよ」とカードを見せたりするのも良いでしょう。
②本人だけの「SOSサイン」の設定と練習
先ほどの「助けを求めるスキル」にも通じますが、特に言葉が出にくい子どものために、先生と一対一で本人だけが使える、言葉以外のサインを決めます。
机の上に特定の色のブロックを置く、ペンケースの向きを変える、特定の場所に立つ、など、目立たず、しかし先生は気づけるようなサインが良いでしょう。
サインを決めたら、「このサインが出たら、先生はどうするね」と応答の仕方を再度確認し、実際にサインを出してみる練習をします。
③教室内に「話せない時はこれを使っていい」安心エリアや箱をつくる
教室の隅などに、他の子から少し離れて落ち着ける「安心エリア」やスペースを設けます。
そこに、気持ちを表現できる道具(気持ちカード、絵の具、粘土、お絵かき帳など)を入れた「気持ちを伝える箱」などを設置します。「言葉で話せない時は、ここに行ってこれを使っていいよ」と子どもに伝えておきます。
言葉にならないモヤモヤした気持ちを、絵や形にすることで表現し、落ち着きを取り戻すことにつながります。
先生へのアドバイス
非言語サインは、言葉でのコミュニケーションが難しい子どもにとって命綱となる場合があります。先生がサインを見落とさないように注意すること、そしてサインが出されたら言葉と同じように丁寧に受け止めることが非常に重要です。
児童の感想と保護者の声
SSTを継続して実践していく中で、子どもたちや保護者の声から見えてきた変化もご紹介します。
私が支援学級でSSTを実践する中で、特に印象的だったのは、子どもたちの自信に満ちた笑顔です。実際に子どもたちからは、『ちゃんと話せるようになるのが嬉しい!』『SST、これ楽しいね!』という喜びの声が多数聞かれました。
また、以前、参観日にIメッセージの授業を行った際には、ある保護者の方から『うちの子が、仲間の前でこんなに楽しそうに話している姿を見たのは初めてです。本当に驚きました』という、感動的な感想をいただきました。
SSTは、子どもたちがコミュニケーションスキルを身につけるだけでなく、自己肯定感を育み、本来持っている力を引き出す素晴らしい機会だと、改めて感じています。
まとめ:土台があるからこそ、スキルは花開く
ここまで、感情理解の土台ができた子どもたちに効果的なSSTテーマを5つご紹介しました。
「怒りを言葉で伝える」「助けを求める」「自分でクールダウンする」「上手にお願いする」「非言語で気持ちを伝える」といったスキルは、どれも子どもたちが社会の中で心地よく生きていくために不可欠なものです。
しかし、これらのスキルは、子どもが「先生は自分の気持ちを分かってくれる」「ここにいても安心だ」と感じられる信頼できる関係性と、自分自身の感情への気づきという「土台」があってこそ、子ども自身の力として根付いていきます。
前回の「感情支援サイクル」で育んだ土台の上に、今回ご紹介したSSTのステップを積み重ねていくことで、子どもたちは感情に振り回されるのではなく、感情を理解し、上手に付き合っていく力を育んでいくでしょう。
SSTは一度やったら終わり、というものではありません。繰り返し練習し、実際の場面で先生が見本を見せたり、励ましたりしながら、子どもが少しずつ「できた!」という成功体験を積んでいくことが大切です。
先生方の温かいまなざしと粘り強い関わりが、子どもたちの未来を拓く力となります。日々の実践の中で、ぜひ今回のアイデアをご活用いただければ幸いです。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

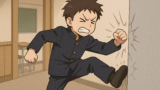







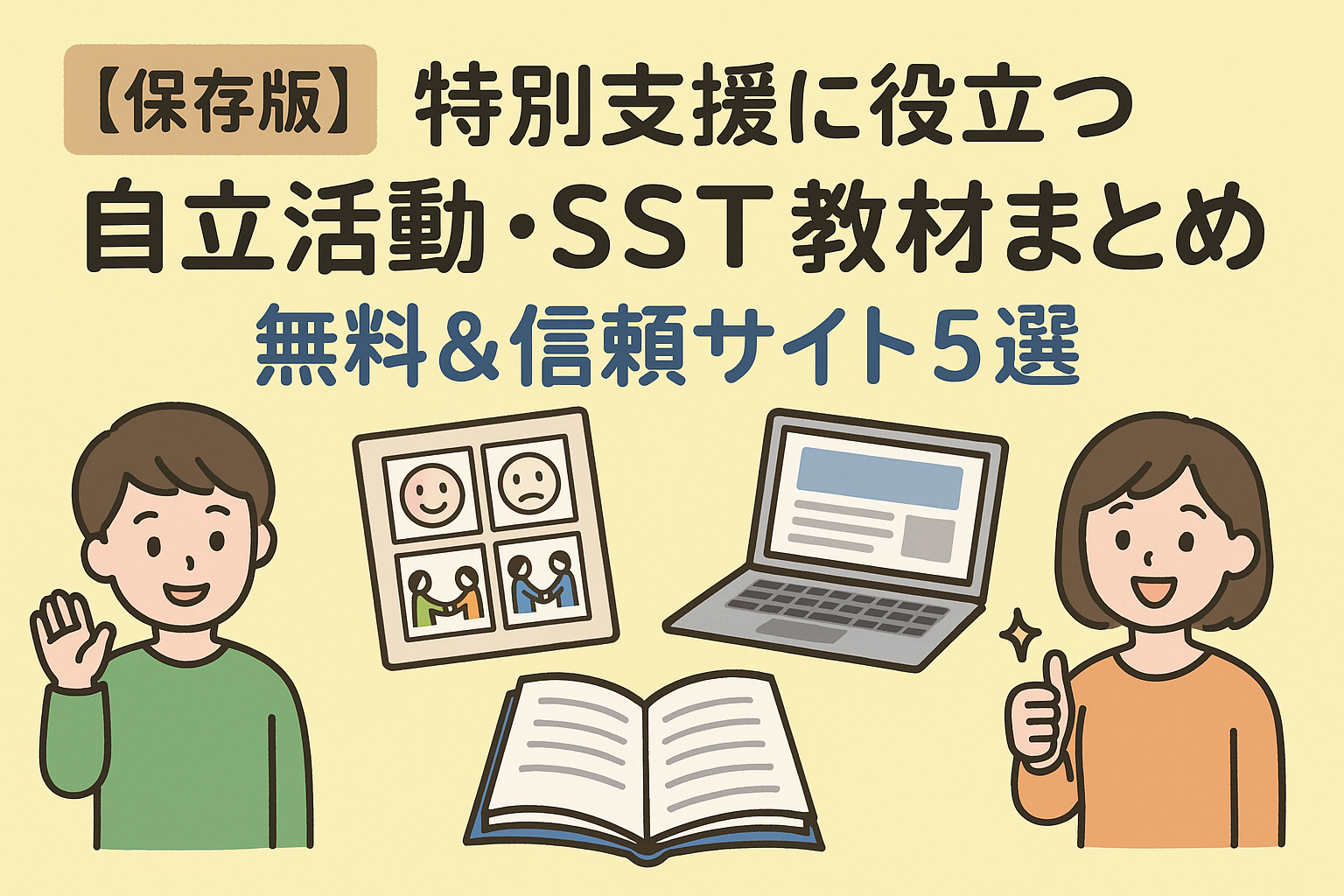
コメント