
「“くやしい”と“かなしい”は違う気持ちなんだね」

「ぶつかられたけど、わざとじゃないって分かったよ」
これは、私の支援学級の子どもたちが、自立活動の時間に口にした言葉です。自分の気持ちをうまく言葉にできず、衝動的に手が出てしまったり、フリーズしてしまったりする子どもたちにとって、「自分の気持ちが伝わった!」と感じる安心感や、「そうか、これは悔しい気持ちなんだ」と理解する経験は、彼らが自己を肯定し、他者と関わる上で非常に重要です。
自己理解や他者理解、そして感情のコントロールは、発達に特性のある子どもたちにとって大きな課題でありながら、日々の生活の中で繰り返し取り組むべきテーマでもあります。
今回は、
私が実際に取り入れている「感情カード」と「場面カード」を使ったSST(ソーシャルスキルトレーニング)をご紹介します。※プリント教材無料ダウンロードできます。
書籍のご案内
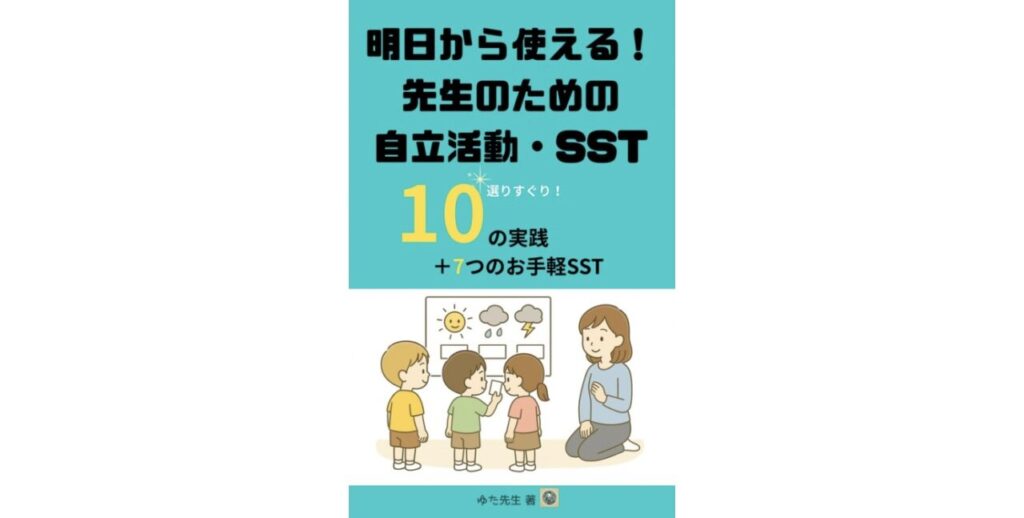
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
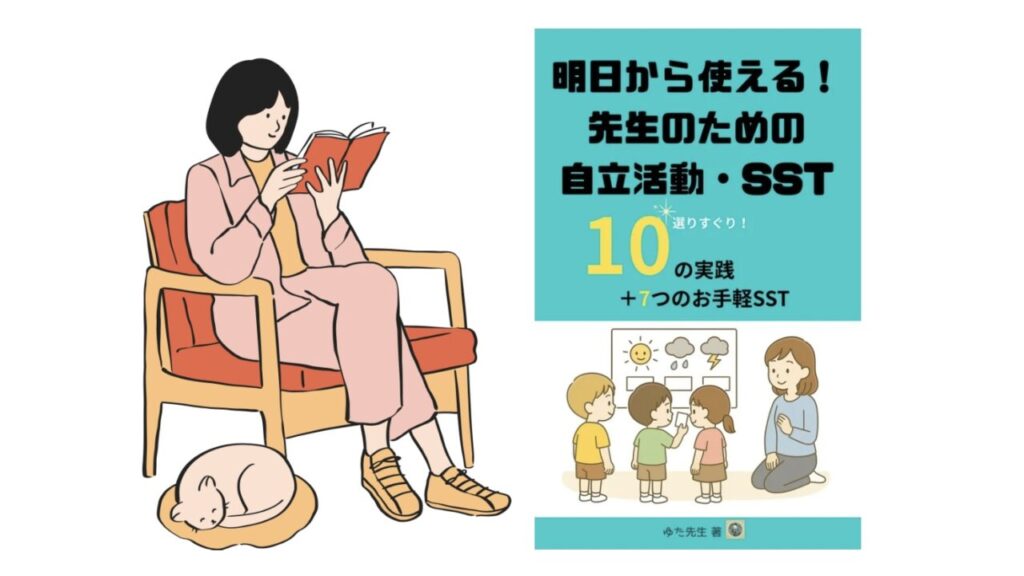
おすすめのワークシートはこちら⇩
自己理解や他者理解にピッタリの自立活動はこちらから👇
50枚のSSTマッチング教材はこちら👇
SSTイラスト50枚➕発問集15000字のDLはこちら
活動で使用する教材【SST無料プリントDLあり】
この実践で使う教材は、どなたでも無料ダウンロードしてすぐに活用できます。
感情カード(ポジティブ+ネガティブ)
感情の言語化を促すために、たくさんの感情を表す言葉をカードにしました。
- ポジティブ感情:「うれしい」「たのしい」「すき」「おちつく」など
- ネガティブ感情:「かなしい」「イライラ」「くやしい」「しんぱい」など

無料ダウンロードはこちら👇
場面カード「学校・家庭・日常」【無料DLあり】
子どもたちにとって身近な具体的な場面を36種類選び、3つのカテゴリーに分けました。
- 「順番を抜かされた時」
- 「兄弟にゲーム機を独り占めされた時」
- 「発表中に笑われた時」など
無料ダウンロードはこちら👇
こころカルタと組み合わせて遊ぶとより楽しめます。こちらに教材紹介しています。👇
活動の流れとねらい|6区分27項目に基づく実践
この活動は、自立活動の「心理的な安定」や「人間関係の形成」をはじめとした6区分の複数の領域を横断して取り組むことができます。
| 活動ステップ | 実施内容 | ねらい(6区分27項目と期待される変化) |
|---|---|---|
| ① 場面カードを引く | 子どもが1枚選び、内容を読み上げる | 【状況の理解】【他者との関係性の理解】【日常生活への適応】 →様々な状況や他者との関係性を客観的に捉える力が育ちます。 |
| ② 感情カードで気持ちを選ぶ | 自分だったらどう思うかを考え、感情を選ぶ | 【情動の理解と調整】【感情表出の調整】【自己認識】 →自分の感情に気づき、それがどんな気持ちなのかを理解できるようになります。 |
| ③ みんなで気持ちを共有 | 他の人がどう感じるかを聞いて比較する | 【自己と他者の理解】【思いやりの態度】【多様な価値観の理解】 →自分と他者の感じ方の違いを知り、多様な感情を受け入れられるようになります。 |
| ④ 対処法を考える | 自分や相手がどう行動すればよかったか考える | 【行動の選択と実行】【自己決定】【課題解決の力】 →感情と行動のつながりを理解し、より良い対処法を自分で見つけられるようになります。 |
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
実際のやりとりの一例
ある日の活動での子どもたちの様子です。
🧒「“給食の配膳中にぶつかられた時”っていうカードが出た!」
👧「私は“くやしい”と“イライラ”を選ぶかな…」
🧑「ぼくは“びっくりした”って思うかも。相手にわざとじゃないって言ってほしい」
先生が「みんな、色々な感じ方があるんだね」と促すと、子どもたちはそれぞれの感じ方に違いがあることを認識し始めます。さらに、教員の「そのときどうしたらよかったかな?」という問いかけで、「ごめんって言ってほしかった」「次から気をつけようって声をかける」など、感情→行動のつながりを理解し、建設的な対処法を考えられるようになっていきます。
カードを使った遊び方アイデア
「感情カード」と「場面カード」は、様々な形で活用できます。いくつかおすすめの遊び方をご紹介します。
遊び方1:基本的なSSTとして(活動の進め方)
先ほど「活動の流れ」でご紹介した基本的なSSTの進め方です。
① 場面カードを1枚引く
まずは1人ずつカードを引きます。カードには、「順番を抜かされた時」「発表中に笑われた時」「兄弟にゲーム機をひとりじめにされた時」など、子どもたちの実生活でよくあるシチュエーションがイラストなし・文章のみで書かれています。

🧒「給食の配膳中にぶつかられた時」って書いてある。
② そのときの気持ちを感情カードから選ぶ
次に、自分だったらどんな気持ちになるかを考え、感情カードから1〜3枚を選びます。例えば以下のような選択肢が出ることがあります。
- がっかり
- くやしい
- イライラ
- しんぱい
- うれしい(←まれにこう答える子も)

👧「私は“くやしい”と“イライラ”を選ぶかな…」
🧑「ぼくは“かなしい”って思うかも」
ここで他の子の意見も聞くことで、感じ方の違いに気づくよいきっかけになります。
③ どうすればよかったか、みんなで考える
「そのとき、どうしたらよかったと思う?」
「次に同じことがあったら、どうする?」
子どもたちは、それぞれの気持ちを受け止めながら、対処の選択肢を増やしていきます。
遊び方2:気持ちを当てるクイズ形式
一人が場面カードを引いて読み上げ、その場面の登場人物(例:「順番を抜かされた子」)がどんな気持ちになるかを、他の子が感情カードから選んで当てます。正解・不正解ではなく、「その気持ちになる理由」を話し合うことで、他者理解が深まります。
遊び方3:ロールプレイングで実践
場面カードと感情カードを選んだ後、実際にその場面を演じてみるロールプレイングを取り入れるのも効果的です。選んだ気持ちを表情や声のトーンで表現したり、考えた対処法を実際にやってみたりすることで、より実践的なスキルを身につけることができます。
この活動が育む力とは?
1. 自分を知る力 感情の「見える化」と「言葉化」
感情カードを繰り返し使うことで、「自分がどんなときに、どんな気持ちになるのか」に気づく力が育ちます。初めは「イライラ」としか言えなかった子が、ある日「イライラっていうより、くやしかった」と言い直した場面もありました。自分の内側で起きている感情を具体的に捉え、言葉にできるようになります。
2. 相手を理解する力 共感と多様性の受容
場面カードには、学校生活や家庭内でよく起こる出来事が具体的に書かれています。同じ場面でも、子どもたちが感じる気持ちはバラバラ。その違いに気づき、「あの人はそう感じるんだ」と認め合うことが他者理解の第一歩となります。
3. 問題を乗り越える力 適切な対処スキルの獲得
「そんなとき、どうすればいい?」を考えることは、自己調整や自己決定のトレーニングにもなります。大切なのは、大人が具体的な提案をするよりも、子どもたち自身がアイデアを出し合うこと。子どもたちの中から生まれた対処法は、実際に活用できるスキルとして定着しやすくなります。
教師が意識したい関わり方
この活動をより実り多いものにするために、教師の関わり方が重要です。
- ❌ 感情をジャッジしない 「そんなことで怒るの?」はNG。子どもの感情に良い悪いをつけず、そのまま受け止めましょう。
- 受容的な声かけ 「そう感じたんだね」「わかるよ」と、子どもの感情を肯定的に受け止める言葉をかけましょう。「〜〜と感じたんだね、教えてくれてありがとう」と感謝を伝えるのも効果的です。
- 違いに気づかせる 「〇〇くんは“かなしい”って言ったね。□□さんは“イライラ”だったね。同じ場面でも、人によって感じ方は様々だね。どれも大切な気持ちだよ」と、多様な感情があることを伝え、受け入れを促しましょう。
- 長くなりすぎないようテンポよく進行 子どもたちの集中が途切れないよう、スピーディーな進行を心がけましょう。
実施タイミングと工夫アイデア
- ☀️ 朝の会で「1日1場面」 今日の気分を尋ねるついでに、気持ちのウォーミングアップとして取り入れると、気持ちの整理にもつながります。
- 週1回のSSTタイム 定期的な活動として設定し、他の自立活動とも連携させながら継続的に取り組みましょう。
- 記録シートを作って「感情のふりかえり帳」に 活動で選んだ感情や考えたことを記録に残すことで、自己理解を深めることができます。
- 保護者との連絡帳にも活用 活動内容を家庭と共有し、ご家庭でも子どもの気持ちに寄り添った対話ができるよう促しましょう。
成功事例:発言が苦手だった子が…
ある男児は、普段なかなか気持ちを言葉にできず、問題行動で表現することが多くありました。しかし、この活動を繰り返す中で、感情カードを選び続けるうちに、自分の気持ちと行動のつながりに気づき始めました。ある日、「くやしかったから、ちょっと怒っちゃった」と自ら説明するようになり、周囲も彼の気持ちを理解しやすくなったことで、適切なサポートができるようになりました。教師は、彼の言葉を丁寧に受け止めることを意識しました。
他の教材との組み合わせもおすすめ
本教材と合わせて活用することで、さらに学びを深められる教材や実践例もご紹介します。
▼ こちらもあわせてチェック ▼
おわりに|“気持ち”を扱う活動に、意味がある
発達に特性のある子どもたちは、「気持ちをうまく伝えられない」「どうしてよいかわからない」という経験を日々しています。だからこそ、「気持ちに気づき」「伝える練習」を積み重ねていくことが、学校生活や人間関係の土台になります。
本記事で紹介したSST教材は、誰でもすぐに取り入れられるシンプルな構成です。ぜひ、ご自身の学級でも取り入れてみてください。子どもたちの「わかった!」という表情に出会えるはずです。


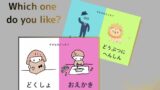

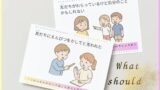





コメント