お子さんの学習で、こんなお悩みはありませんか?
- 「なかなか集中力が続かない…」
- 「書くことに対して苦手意識があるみたい…」
- 「手先の細かい作業がどうも得意じゃない…」
特別支援学級に在籍しているお子さんたちの中には、じっとしていることが苦手だったり、集中が続かなかったり、手先の操作が不器用だったりと、それぞれに特有の困り感を抱えている子が多くいます。
今回は、
実際に私のクラスで効果があった「都道府県の楽しい覚え方」を紹介します。ゲーム感覚で、視覚・聴覚・触覚をフル活用できる学習法は、特に「書くことが苦手な子」「集中が続かない子」に大きな効果がありました。
※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。
集中が続かない子が、都道府県を楽しみながら覚えられた!
現在4年生のある児童。じっとしているのが苦手で、座っての学習は長く続きません。また、「書くこと」に対しても強い苦手意識があり、形の模写が難しい・手先の細かい操作も得意ではないという特徴があります。
しかし、そんな子でも、ある方法を取り入れたことで、都道府県を覚えることができたのです。
それは、以下の3つを組み合わせた学習法です。
1. 音声で楽しく覚える!「遊んで学べる日本地図」アプリ
このアプリでは、都道府県名を音声付きで教えてくれます。子どもは文字を読むより「耳からの情報」が入りやすかったため、「聞いて覚える」ことで学習へのハードルが下がりました。さらに、正解すると楽しい効果音が鳴り、ゲーム感覚で取り組めます。

2. パズルで視覚的にマスター!「日本地名パズル 都道府県と県庁所在地」アプリ
こちらは都道府県のピースを地図の正しい位置にはめるパズル型。形の認識が苦手な子にとって、繰り返し遊ぶことで自然に視覚認知が強化されました。「ここが青森県だったよね!」と、自分の口で言えるようになったことは大きな自信にもつながりました。
3. 実物の都道府県パズル(触って覚える)
アプリだけでなく、手にとって形を触れることができる物理的なパズルも活用しました。アプリとリンクさせながら学習することで、マルチモーダル(視覚・聴覚・触覚)な学習が実現できたのです。
特におすすめなのが、多くの子どもたちに親しまれているくもんの日本地図パズル PN‑33です。
教材はこちらから👇
このパズルは、立体ピースで47都道府県を覚える王道パズルとして、長年多くの子どもたちに愛されています。地方ごとに色分けされた「基本ピース」と、全国が単色になった「発展ピース」の2種類がセットになっており、お子さんの発達に合わせてステップアップしながら長く遊べるのが魅力です。
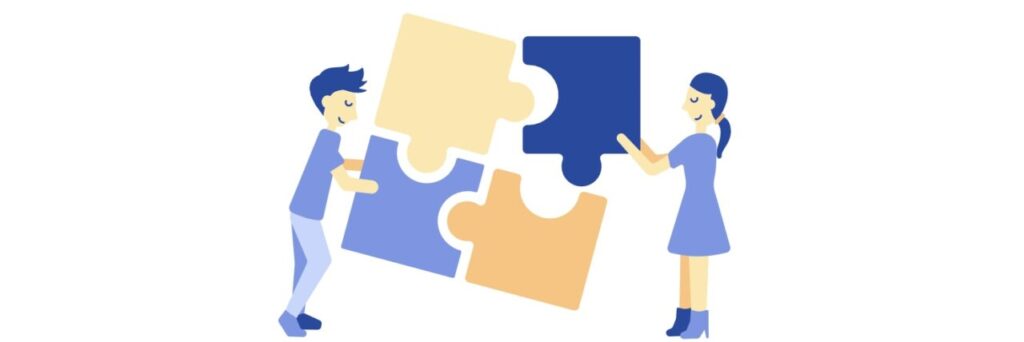
まだ漢字が読めない低学年のお子さんにも配慮されており、ピースに貼れるひらがなシール付き。さらに、付属の都道府県名確認地図や特産物・名所の地図なども活用することで、ただ位置を覚えるだけでなく、興味の幅を広げることができます。
お子さんが集中して取り組める工夫が満載なので、ぜひご家庭での学習に取り入れてみてください。
さらに多くのお子さんに効果が見られた、とっておきの学習法3選
ここからは、上記の成功例以外にも、他の児童で実践して効果のあった学習方法を3つご紹介します。
4. 「都道府県カルタ」で遊ぶ
市販の都道府県カルタ(例:るるぶ地理カルタなど)は、楽しく競いながら都道府県名や特徴を学べる教材です。音読係と取り手に分かれて遊ぶことで、聞く→探す→取るという流れが生まれ、集中力も持続しやすくなります。都道府県の特徴がイラストで描かれているものは、視覚優位の子にも効果的です。


5. 都道府県ソングを活用する
昔ながらの「都道府県の歌」や「県庁所在地のうた」は、メロディに乗せて覚えられるため、聴覚優位の子どもにはぴったり。動画サイトや音楽アプリで簡単に再生できるため、朝の会やすき間時間に活用できます。
特にリズムや繰り返しがある楽曲は、無意識に口ずさむようになり、定着に役立ちます。
6. 自分で「日本地図ぬりえ」や「行ってみたい県リスト」を作る
日本地図の白地図プリントを用意し、「行ってみたい県」「知ってる県」を自分で色分けさせる活動です。地理的な感覚がつかめるうえ、個人の興味に合わせた学びになります。
あらかじめ色鉛筆やスタンプ、シールなどを用意しておくと、楽しみながら活動できます。また「〇〇県にはディズニーランドがある!」「家族旅行で行った!」などのエピソードと結びつけて覚えることも効果的です。
特別支援学級で大切な視点
このようなアプローチでは、「苦手な方法を無理に押し付けないこと」「得意な感覚(耳・目・手)を活かすこと」がとても重要です。
集中が続かない子には、短時間・ゲーム感覚・達成感のある学習が有効。書くことが苦手な子には、書かずに学べる方法を提示することで、学ぶ意欲が損なわれません。
都道府県の学習は、小学生にとってはなじみが薄い分野ですが、楽しい方法を通じて「もっと知りたい!」という気持ちにつなげることが可能です。
さらにステップアップ!おすすめの学習書籍
アプリやパズルで都道府県の基礎が身についたら、次は「書く」学習や、より詳しい情報をインプットする段階へと進むのもおすすめです。ここでは、お子さんが楽しく取り組める一冊をご紹介します。
小学生の日本地図ドリル 楽しく学ぶ 基礎からわかる47都道府県
このドリルは、漫画タッチの解説とクイズ形式で、視覚的にも楽しく都道府県を学べる一冊です。単に知識を詰め込むだけでなく、各都道府県の特色や地理的な情報がイラストやクイズを通して自然と頭に入ってくる構成になっています。
「書き込み式」なので、手を動かすことでより記憶に定着しやすくなります。ユーザーの口コミでも「ストレスなく進められる」「遊びながら学べる」と高評価が多く、飽きっぽいお子さんでも集中して取り組める工夫が満載です。
小学校の社会科の授業の予習・復習はもちろん、中学進学前の基礎固めにも役立ちます。ぜひ、これまでの学習の成果を試す感覚で活用してみてください。
小学生の日本地図ドリル 楽しく学ぶ 基礎からわかる47都道府県 を見てみる
まとめ|都道府県の学びは「楽しく」「得意を活かして」
今回は、特別支援学級での実際の成功例を交えながら、都道府県を覚える楽しい学習法をご紹介しました。
紹介した6つの方法
- 音声で楽しく覚える!「遊んで学べる日本地図」アプリ
- パズルで視覚的にマスター!「日本地名パズル 都道府県と県庁所在地」アプリ
- 実物の都道府県パズル
- 都道府県カルタ
- 都道府県ソング
- 日本地図ぬりえ&行ってみたい県リスト作り
これらの方法は、集中が苦手な子・書くのが苦手な子にとって、まさに「学びの入り口」となる手段です。苦手を無理に克服するのではなく、得意な感覚・楽しい経験を通して、自然に知識を身につけることができるのが最大のポイントです。
この記事が、お子さんの都道府県学習をより楽しく、効果的なものにするための一助となれば幸いです。



コメント