この記事では、6年生の所見で使える国語の表現から、算数、理科、社会、そして行動面(基本的生活習慣、責任感、自主・自立など20項目)に至るまで、具体的で豊富な文例を膨大なボリュームでご紹介します。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- 小学校6年生の通知表の所見で使える、各教科(国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語)の具体的な文例
- 学習面全体(中学校への接続を意識したもの)に関する所見の書き方と文例
- 「行動の記録」で求められる20項目(基本的生活習慣、学習態度、自主・自立、責任感、思いやり・協力など)それぞれに対応した豊富な文例10選(合計200例)
- 特別支援教育における6年生の自立活動の所見文例
- 小学校卒業にあたり、児童の成長を称え、未来を応援する表現のヒント
- 通知表 所見 文例 小学校6年【総論・学習面全体】
- 6年生 所見 文例 【国語】
- 6年生 所見 文例 【社会】
- 6年生 所見 文例 【算数】
- 6年生 所見 文例 【理科】
- 6年生 所見 文例 【音楽】
- 6年生 所見 文例 【図画工作】
- 6年生 所見 文例 【家庭】
- 6年生 所見 文例 【体育】
- 6年生 所見 文例 【外国語(英語)】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【基本的生活習慣】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【学習態度】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【挨拶】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【健康・体力の向上】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【外で元気に遊ぶ】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【給食で好き嫌いなく食べる】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【自主・自立】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【自分の力で考え、行動する】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【粘り強く取り組む】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【目標に向かって取り組む】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【責任感】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【創意工夫】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【思いやり・協力】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【生命尊重・自然愛護】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【勤労・奉仕】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【係活動】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【掃除】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【給食当番】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【公正・公平】
- 6年生 行動の記録 所見 文例【公共心・公徳心】
- 6年生 自立活動 所見 文例
- 各学年各種の所見文例集リンク🔗
- まとめ
通知表 所見 文例 小学校6年【総論・学習面全体】
6年生は、学習内容の深化はもちろん、最高学年としての自覚と中学校への準備が求められる時期です。学習への取り組み方や思考の深まりを評価します。
- 最高学年としての自覚を持ち、すべての学習活動において、下級生の手本となるべく真摯な態度で取り組むことができました。
- 中学校での学習を見据え、予習・復習の習慣が確立しました。特に、自分の苦手分野を把握し、克服しようと計画的に努力する姿が見られます。
- 授業中の集中力は素晴らしく、先生や友達の発言の意図を深く読み取り、自分の考えと比較検討しながら、多角的に物事を考察する力が育ちました。
- 複雑な課題に対しても、既習の知識や技能を総動員し、論理的な道筋を立てて解決しようとする粘り強さがあります。
- グループ学習では、全体の進捗を把握し、意見が対立した際には調整役を買って出るなど、卓越したリーダーシップを発揮しました。
- 自分の将来や社会のあり方について関心を持ち、学習内容と現実社会を結びつけて考える、視野の広がりを感じさせます。
- 学習の進め方が非常に丁寧で、ノートや提出物も、後で見返したときに分かりやすいよう工夫してまとめられています。
- 知識の吸収力が高く、授業で扱った内容を発展させ、自主学習ノートに深く掘り下げたテーマでまとめるなど、知的好奇心が旺盛です。
- 学習に対する意欲は高いものの、教科によって得意・不得意がはっきりしてきました。苦手意識のある分野も、基礎に立ち返って粘り強く取り組むことを期待します。
- 中学校に向けて、学習面での不安を口にすることもありましたが、一つ一つの課題をクリアすることで自信をつけ、意欲的に学習に取り組む姿勢へと変化しました。
6年生 所見 文例 【国語】

論説文の読解、自分の意見の表明、古典や歴史的かなづかいなど、思考力と表現力が問われる6年生の国語。その成長を捉える文例です。
- 論説文の読解において、筆者の主張とそれを支える根拠(事実と意見)を的確に区別し、文章の論理構成を深く理解することができました。
- 「未来への提言」といったテーマの作文では、社会的な問題について自分の意見を明確にし、説得力のある根拠を示しながら論じることができました。
- ディベート活動では、肯定側・否定側それぞれの立場から、多角的に情報を収集し、論理的に反論・再反論を行うなど、思考の瞬発力が光りました。
- 古典(「枕草子」など)の学習では、歴史的かなづかいや当時の人々の感性に触れ、現代との違いを味わいながら音読に親しんでいました。
- 漢字学習の総まとめとして、同音異義語や同訓異字の使い分けを意識し、語彙を豊かに使おうとする意欲が見られます。
- 話し合い活動では、司会者として、時間配分を考えながら議論を整理し、全員が納得できる結論へと導く調整能力を発揮しました。
- 発表の場面では、聞き手の反応を見ながら、声のトーンや間(ま)を工夫し、自分の考えが最も伝わるように表現する力が身につきました。
- 物語文の読解では、登場人物の心情だけでなく、作品全体のテーマや作者が伝えたかったメッセージまで読み解こうと、深く考察していました。
- 文章を書くスピードはありますが、書き言葉と話し言葉の混同や、主語・述語のねじれが見られることがあります。推敲の習慣をつけることが大切です。
- 自分の意見を人前で発表することに緊張が見られましたが、原稿を丁寧に準備し、練習を重ねることで、少しずつ自信を持って発言できるようになりました。
6年生 所見 文例 【社会】

歴史学習の総まとめ(近現代史)や、政治・国際関係など、現代社会につながる重要な単元を学びます。資料活用の能力や多角的な視点を評価します。
- 歴史学習(近現代史)において、様々な出来事が現代の私たちの生活にどのようにつながっているのかを、資料を基に熱心に調べ、自分の考えをまとめました。
- 「日本の政治」の学習では、国会の役割や選挙の仕組みについて深く理解し、模擬選挙活動にも主体的に参加していました。
- 「国際社会に生きる日本」の学習では、グローバル化の進展とそれに伴う課題(環境問題、貧困など)に関心を持ち、自分たちにできることを真剣に議論しました。
- 歴史新聞づくりでは、史実に基づきながらも、当時の人々の視点に立った臨場感あふれる記事を作成するなど、卓越した構成力を見せました。
- 複数の資料(統計、年表、地図)を比較・検討し、そこから読み取れる事実や課題を的確に分析する、高度な情報活用能力が育っています。
- 授業で学んだ社会的な出来事について、家庭でもニュースを見て話し合うなど、社会への関心が非常に高く、主体的な学習態度が見られます。
- 歴史上の人物の功績だけでなく、その人物が生きた時代の背景や苦悩まで想像し、多角的に人物像を捉えようと努めていました。
- 調べ学習の発表では、プレゼンテーションソフトを効果的に活用し、聞き手を引き込む分かりやすい説明ができました。
- 用語や年号を覚えることは得意ですが、それらの出来事が持つ歴史的な意味や背景まで理解が深まると、さらに学びが豊かになるでしょう。
- 自分の意見や感想を持つことはできますが、それを裏付ける客観的な資料やデータを示すことを意識すると、より説得力が増すでしょう。
6年生 所見 文例 【算数】
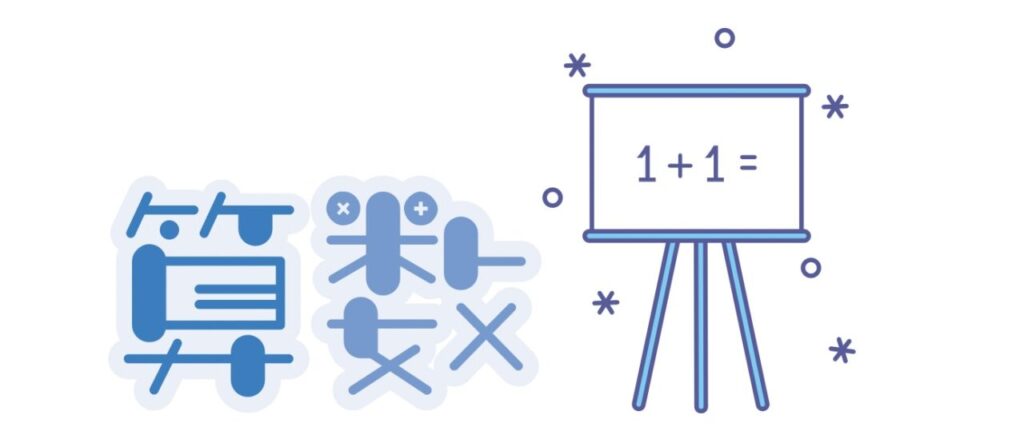
分数のかけ算・わり算、比例・反比例、円の面積、データの活用など、中学校の数学にも直結する重要な単元を学びます。(※ユーザー例の「4年生 所見 算数」は「6年生」として作成)
- 「分数のかけ算・わり算」の学習では、計算方法を理解するだけでなく、なぜ「逆数をかける」のかを図や言葉で説明しようと、意味理解に努めていました。
- 「比例と反比例」の学習では、二つの数量の関係性を表や式、グラフを用いて的確に表現し、その特徴を論理的に説明することができました。
- 「円の面積」の学習では、既習の図形(多角形)に分割して考えるなど、公式を導き出す過程を重視し、応用問題にも粘り強く取り組みました。
- 「データの活用」では、収集したデータを柱状グラフや円グラフに整理し、そのデータから読み取れる傾向や課題について鋭い考察を発表しました。
- 難易度の高い応用問題に対しても、既習の知識(面積の求め方、割合など)を複合的に活用し、論理的な手順で解答を導き出しました。
- 計算ミスを減らすため、途中式を丁寧に書くことや、検算(見直し)を徹底することを意識し、正確性が格段に向上しました。
- 答えが合っているかだけでなく、「もっと効率的な解き方はないか」と別解を探求するなど、数学的な思考を楽しむ姿勢が見られます。
- 問題の意図を正確に読み取り、立式する力はありますが、複雑な計算になるとケアレスミスが出ることがあります。一つ一つの計算を丁寧に行うことが課題です。
- 図形分野(拡大図・縮図、対称)では、作図や空間認識に優れた力を発揮し、意欲的に問題に取り組んでいました。
- 算数に対して苦手意識がありましたが、基礎的な計算ドリルに毎日コツコツと取り組むことで自信をつけ、授業中の挙手も増えてきました。
6年生 所見 文例 【理科】

「ものの燃え方と空気」「水溶液の性質」「生物と環境」「電気の利用」など、より科学的な思考が求められる実験・考察が中心となります。
- 「ものの燃え方」の実験では、対照実験(条件を揃えること)の重要性を深く理解し、燃焼の仕組みを論理的に考察することができました。
- 「水溶液の性質」の実験では、リトマス紙や蒸発などの方法を用いて、水溶液を仲間分けするだけでなく、その性質を生活と関連付けて考察しました。
- 「生物と環境(生態系)」の学習では、生物同士の関わりや環境保全の重要性について深く学び、校庭の生態系マップを作成しました。
- 「電気の利用(プログラミング)」では、試行錯誤を繰り返しながら、センサーライトを意図通りに動かすプログラムを完成させるなど、論理的思考力を発揮しました。
- 実験班のリーダーとして、安全に配慮しながら手際よく準備・操作を進め、メンバーの意見をまとめて的確な結論を導き出しました。
- 実験結果の予想と実際の結果が異なった場合、その原因は何かを粘り強く追究し、再実験に取り組む科学的な探究心は立派です。
- 観察や実験の結果を、グラフや表を用いて分かりやすく整理し、データに基づいた客観的な考察を発表することができます。
- 自然環境や科学技術に関するニュースに関心を持ち、授業で学んだことと関連付けて発言するなど、知的好奇心が旺盛です。
- 実験操作は丁寧ですが、結果をノートにまとめる際に考察が不足することがあります。データから「何が言えるか」を深く考えることを期待します。
- 実験そのものには意欲的ですが、後片付けがやや雑になる場面がありました。器具を大切に扱い、次も安全に使えるよう整えることの重要性を指導しました。
6年生 所見 文例 【音楽】

卒業式や音楽会など、最高学年としての集大成の表現が求められます。合唱や合奏でのリーダーシップや、曲想の深い理解を評価します。
- 卒業式での合唱では、最高学年としての思いを歌声に乗せようと、表現を深く研究し、全体をリードする存在感を示しました。
- 合奏(例:「カノン」)では、自分のパートを完璧に演奏するだけでなく、他のパートの旋律にも耳を傾け、調和の取れた美しい響きを作り出しました。
- 変声期を迎え、声が出しにくい時期もありましたが、自分の声域に合ったパートで、無理なく、しかし真剣に歌おうとする姿が見られました。
- 鑑賞の学習(日本の伝統音楽や世界の音楽)では、多様な音楽文化に触れ、それぞれの音楽が持つ背景や特徴について、自分なりの感想を持つことができました。
- 音楽委員として、朝の音楽や集会での伴奏を責任持って務め上げ、学校全体の音楽活動を支えてくれました。
- リズム感が非常に良く、打楽器パートでは全体の演奏を引き締める、的確なリズムを刻んでいました。
- 楽譜を読む力(読譜力)が高く、新しい曲にも意欲的に挑戦し、すぐに旋律を覚えていました。
- リコーダー演奏では、高音域の指使いもマスターし、なめらかで美しい音色を奏でることができました。
- 音楽会の練習では、技術的なことだけでなく、「聴いている人に感動を届ける」という目的意識をクラス全体で共有しようと働きかけていました。
- 歌うことに少し照れが見られましたが、友達と声を合わせる楽しさを知り、卒業式に向けては大きな声で歌えるようになりました。
6年生 所見 文例 【図画工作】

卒業制作など、小学校生活の思い出や自分の成長をテーマにした作品に取り組みます。表現の意図や技術の向上を評価します。
- 卒業制作(オルゴールボックスなど)では、小学校生活の思い出をテーマに、構図や色彩を深く練り上げ、6年間の成長を感じさせる力作を完成させました。
- 「墨で表す」の学習では、墨の濃淡やかすれ、にじみを効果的に使い、静と動が感じられるダイナミックな作品を生み出しました。
- 「12年後の私」というテーマの自画像(粘土)では、将来の夢を具体的にイメージし、細部の表現にもこだわって生き生きと制作しました。
- 風景画では、一点透視図法などの技法を理解し、校舎の奥行きや立体感を正確に表現することができました。
- 鑑賞の学習では、作者の意図や時代背景まで考察し、美術作品を多角的に読み解く力が育っています。
- デザインの学習では、ポスターカラーの特性を活かし、伝えたいメッセージが明確に伝わる、訴求力のあるポスターをデザインしました。
- 準備や後片付けが非常に手際よく、下級生の手本となるだけでなく、用具の管理も率先して行い、クラスの活動を支えました。
- 自分のイメージを形にするための技術(彫刻刀の使い方、絵の具の混色)が飛躍的に向上しました。
- 作品の構想にじっくりと時間をかけ、一度決まると驚くべき集中力で制作に没頭します。
- 友達の作品の良いところを具体的に見つけ、称賛の言葉をかけることで、クラス全体の創作意欲を高める温かい雰囲気を作りました。
6年生 所見 文例 【家庭】

衣食住の自立、家族や地域との関わり、環境への配慮など、中学校生活にも直結する実践的な内容を学びます。
- 「感謝の気持ちを伝える調理」では、家族の栄養バランスや好みを考えた献立を計画し、手際よく調理実習に取り組むことができました。
- 「まかせてね、今日の食事」の単元で学んだことを活かし、家庭でも朝食づくりに挑戦するなど、実践しようとする意欲が素晴らしいです。
- ミシンを使ったナップザック製作では、難しい曲線部分も、安全に気をつけながら丁寧に縫い上げ、実用的な作品を完成させました。
- 「クリーン大作戦」の学習では、汚れの種類に応じた掃除の方法を理解し、校内の清掃活動で学んだことを実践していました。
- 環境に配慮した生活(エコ活動)に関心を持ち、ゴミの減量やリサイクルの工夫について、家庭でも実践していることを発表しました。
- 自分の生活時間(学習、睡眠、メディア)を見直し、中学校生活に向けて、より充実した時間の使い方を計画することができました。
- 買い物ゲームを通して、予算内で必要なものを選ぶ計画性や、消費者としての賢い選択について学ぶことができました。
- 実習グループでは、常に周りを見て、片付けや配膳など、手が空いている作業を自主的に見つけて動くことができました。
- 裁縫は少し苦手なようでしたが、友達に教えてもらいながら、最後まで諦めずにナップザックを完成させた達成感は大きかったようです。
- 家族の一員としての自分の役割を自覚し、家庭での手伝いにも積極的に取り組もうとする意識が高まりました。
6年生 所見 文例 【体育】

球技(バスケットボール、サッカー)や陸上、水泳など、より高度な技能とチームプレー、フェアプレーの精神が求められます。
- バスケットボールの学習では、チームのキャプテンとして、練習メニューを工夫したり、仲間を励ましたりしながら、全員が活躍できるチーム作りをリードしました。
- 陸上(ハードル走)では、自分の記録更新という目標を掲げ、インターバルや踏み切り位置を研究し、フォームの改善に粘り強く取り組みました。
- 水泳(平泳ぎ)では、手足のタイミングをマスターし、25メートルを美しいフォームで泳ぎきることができました。
- 卒業を前にした体力テストでは、小学校生活の集大成として、全ての種目に自己ベストを目指して全力で取り組みました。
- 運動会の組体操(表現)では、最高学年としての自覚を持ち、土台役も演技役も、仲間を信頼し、支え合いながら見事な演技を完成させました。
- フェアプレーの精神を深く理解し、試合中は熱くなりながらも、ルールの遵守や相手チームへの敬意を忘れない態度は立派です。
- 保健の授業で学んだ「病気の予防」について、自分の生活習慣と照らし合わせ、健康的な生活を送ろうとする意識が高まりました。
- 体育委員として、授業の準備・片付けを率先して行い、授業がスムーズに進むよう貢献しました。
- 運動は得意ではありませんが、苦手な種目にも「まずはやってみよう」と挑戦し、仲間を応援する姿に成長を感じました。
- チームの作戦会議では、自分の意見を主張するだけでなく、仲間の意見にも耳を傾け、より良い戦術を導き出そうと協力していました。
6年生 所見 文例 【外国語(英語)】

「聞く・読む・話す(やり取り・発表)・書く」の5領域をバランスよく学びます。中学校への接続を意識し、自分の考えを表現する力を評価します。
- 「私の小学校生活の思い出」というテーマでのスピーチでは、原稿を見ずに、聞き手に視線を配りながら、自分の体験や感動を堂々と発表できました。
- ALTとの会話活動において、間違いを恐れずに、知っている単語やジェスチャーを駆使して、自分の考えを積極的に伝えようとする意欲は素晴らしいです。
- 「書くこと」の活動では、アルファベットや基本的な文型を正しく使い、自分のプロフィールや将来の夢について分かりやすく記述することができました。
- 「読むこと」の活動では、まとまった長さの英文を読み、大意を掴むだけでなく、詳細な情報も読み取ることができるようになりました。
- ペアでの対話活動では、相手の話に「I see.」「That’s great!」など、適切な相づちを打ちながら、会話を弾ませることができました。
- 中学校の英語学習への期待が高く、授業で習った表現以外にも、自主的に単語やフレーズを調べ、使おうとする姿勢が見られます。
- 英語の歌や物語に親しみ、音声の特徴(リズムやイントネーション)を捉えて、生き生きと表現することができました。
- 異文化理解に関心が高く、世界の様々な国の生活や習慣について、英語で紹介された資料を興味深く読んでいました。
- 最初は発音に自信が持てない様子でしたが、CDやALTの発音をよく聞き、繰り返し練習することで、流暢さが格段に増しました。
- 文法的な正確さにはまだ課題がありますが、コミュニケーションを重視し、まずは「伝えよう」とする積極的な態度を評価しています。
6年生 行動の記録 所見 文例【基本的生活習慣】

- 小学校6年間を通して、早寝・早起き・朝ごはんの習慣が定着し、毎日元気に登校できました。健康管理の意識が非常に高いです。
- 最高学年として、チャイム着席や授業準備の素早さは、常に下級生の手本となっていました。
- 持ち物やロッカーの整理整頓が常に徹底されており、学習環境を自ら整える自己管理能力が身についています。
- 提出物の期限を厳守するだけでなく、内容も丁寧に仕上げようとする責任感があります。
- 服装や頭髪など、身だしなみを常に清潔に保ち、TPOをわきまえた行動がとれます。
- 連絡帳や配布プリントの管理が確実で、家庭との連携もスムーズに行うことができました。
- 学習用具を大切に扱い、6年間使ったランドセルや道具箱もきれいに整頓されています。
- 中学校生活を見据え、自分で起床時間を設定するなど、より自立した生活リズムを確立しようと努力しています。
- 忘れ物もほとんどなく、前日の夜に持ち物を確認する習慣がついています。
- 体調が優れない時も無理をせず、自分から適切に申し出ることができるようになりました。
6年生 行動の記録 所見 文例【学習態度】

- 授業中は常に背筋を伸ばし、発表者の方に体を向けて真剣に聞く「傾聴」の姿勢が素晴らしいです。
- 疑問に思ったことは、授業中であっても的確なタイミングで手を挙げ、質問することができます。知的な探究心が旺盛です。
- ノートの取り方が非常に論理的で、板書に加えて、先生の補足説明や自分の考察を色分けして書き込むなど、復習しやすい工夫が見られます。
- 家庭学習(自主学習)にも意欲的に取り組み、小学校の総復習や中学校の予習など、明確な目的意識を持って学習を進めています。
- グループでの話し合いでは、難解なテーマに対しても、自分の意見を論理的に述べ、議論を深めることに貢献しました。
- 苦手な教科に対しても、逃げることなく、基礎問題に立ち返って粘り強く取り組む姿勢に、精神的な成長を感じます。
- 学習計画表を効果的に活用し、学習時間と休憩時間のメリハリをつけ、効率よく学習を進めることができています。
- 一つの答えに満足せず、「なぜそうなるのか」という本質的な理解を求めて、辞書や資料集で深く調べる姿は立派です。
- 授業中の挙手・発言が積極的で、その的を射た意見は、クラス全体の思考を深めるきっかけとなっています。
- 中学校の学習に対する期待と不安が入り混じる中、まずは小学校の学習内容を完璧にしようと、日々こつこつと努力を続けています。
6年生 行動の記録 所見 文例【挨拶】
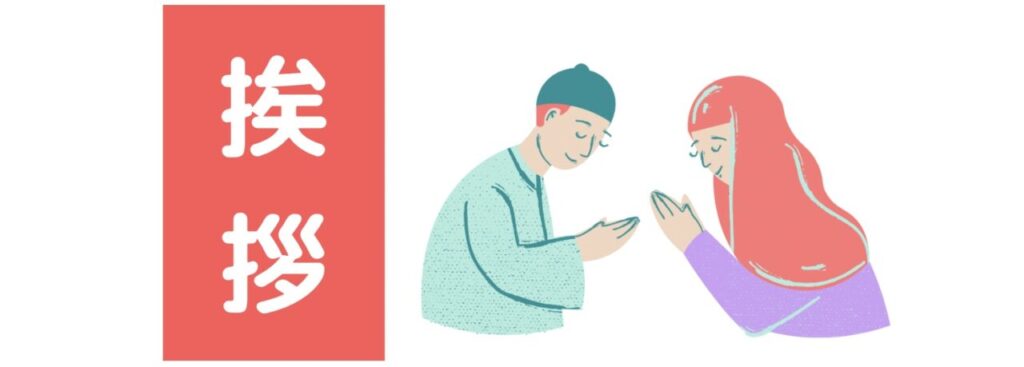
- 毎朝、教室に入ると、最高学年らしい落ち着いた、しかしはっきりとした声で「おはようございます」と挨拶ができます。
- 廊下ですれ違う先生方や来客に対し、必ず立ち止まり、相手の目を見て「こんにちは」と丁寧にお辞儀をすることができます。
- 返事(「はい」)、感謝(「ありがとうございます」)、謝罪(「ごめんなさい」)が、時と場所に応じて適切に言える、社会性の高さがあります。
- 下級生に対しても、自分から優しく挨拶の声をかけ、学校全体の挨拶の雰囲気をリードしてくれました。
- 挨拶運動のリーダーとして、校門に立ち、登校する児童一人ひとりに明るく声をかける姿は、非常に頼もしかったです。
- 日直として、朝の会や帰りの会の号令を、凛とした声で務め、クラスの気持ちを引き締めてくれました。
- 授業の始めと終わりの挨拶に、学習への切り替えと感謝の気持ちがこもっています。
- 地域の方々に対しても、登下校中に進んで挨拶ができ、学校の代表としての自覚が感じられます。
- 照れくささから声が小さくなることもありましたが、卒業を意識し始め、はっきりと相手に伝える挨拶ができるようになりました。
- 友達同士でも、互いを尊重する「ありがとう」の言葉が自然に交わされており、温かい人間関係を築いています。
6年生 行動の記録 所見 文例【健康・体力の向上】

- 小学校6年間、ほとんど休むことなく登校し、規則正しい生活リズムを維持できたことは素晴らしい成果です。
- 休み時間は、学年の枠を超えて、下級生とも元気にドッジボールや鬼ごっこをし、体力の向上に努めていました。
- 体力テストでは、昨年度の自分の記録を超えることを目標に、すべての種目に全力で挑戦しました。
- 保健の授業で学んだ「生活習慣病の予防」や「応急手当て」の知識を、日常生活でも意識しようとする姿が見られます。
- 持久走大会では、苦しい場面でもペースを崩さず、自己ベストを目指して粘り強く走り抜きました。
- 自分の体調の変化に敏感で、無理をせず、適切に休息をとる自己管理能力が身についています。
- 運動の得意・不得意に関わらず、体育の授業には常に意欲的に参加し、体を動かすことを楽しんでいます。
- 中学校の部活動にも高い関心を持ち、自分の適性や興味に合わせて、体力づくりを始めています。
- 感染症予防(手洗い・うがい・換気)の重要性を理解し、クラスでも自主的に声をかけ、実践していました。
- ゲームや動画視聴の時間が長くなりがちな課題を自覚し、自分でルールを決めて時間を管理しようと努力しています。
6年生 行動の記録 所見 文例【外で元気に遊ぶ】

- 天気の良い休み時間は、いつも運動場で友達の中心となり、サッカーやバスケットボールを楽しんでいます。
- 最高学年として、下級生が安全に遊べるよう、運動場の使い方や遊具のルールを優しく教える姿が見られました。
- 学年や性別に関わらず、多くの友達と関わりながら、常にフェアプレーを心がけて遊ぶことができます。
- 鉄棒や一輪車など、難しい技にも諦めずに挑戦し、できるようになった時の喜びを仲間と分かち合っていました。
- 外遊びを通して、体力が向上しただけでなく、ルールを守る大切さや、仲間と協力する楽しさを深く学んでいます。
- ボール遊びが大好きで、休み時間のチャイムと共に、真っ先に運動場へ飛び出していく姿は、クラスの元気の源でした。
- 鬼ごっこなど、体を思い切り動かす遊びでは、低学年の子も仲間に加え、上手にリードしながら遊んでいました。
- 遊具の安全点検や運動場の石拾いなど、みんなが安全に遊べる環境づくりにも貢献してくれました。
- クラスで長縄跳びの最高記録に挑戦した際は、中心となって声をかけ、クラスの結束力を高めました。
- 以前は教室で過ごすこともありましたが、6年生になり、卒業前の思い出作りとして、友達と外で遊ぶ時間を大切にするようになりました。
6年生 行動の記録 所見 文例【給食で好き嫌いなく食べる】

- 6年間を通して、出された給食はほぼ毎日完食し、丈夫な体づくりの基礎ができました。
- 給食当番の仕事は、最高学年として、衛生的かつ迅速に配膳を行い、下級生のクラスの手本となりました。
- 苦手な食べ物(例:キノコ類)も、栄養のバランスを考え、少しずつでも口にしようと努力する姿が見られました。
- 「食」への感謝の気持ちが深く、「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶に、心がこもっています。
- 食べ物の好き嫌いがほとんどなく、バランスよく栄養を摂ろうとする意識が高いです。
- 食事のマナー(箸の持ち方、食器の配置、食べる姿勢)が非常に美しく、同級生の良い見本となっています。
- 「地産地消」や「世界の料理」など、給食の献立に関心を持ち、食文化について学ぶ意欲があります。
- アレルギーを持つ友達への配慮が自然にでき、配膳の際も間違いがないようダブルチェックを行っていました。
- 後片付けが丁寧で、食器の並べ方や食缶の返却も、調理員さんへの感謝が伝わる仕事ぶりでした。
- 以前は牛乳を残すことがありましたが、6年生になり、健康な体で卒業しようと、毎日飲み干すようになりました。
6年生 行動の記録 所見 文例【自主・自立】
- 最高学年としての自覚が芽生え、先生の指示を待つのではなく、常に「今、何をすべきか」を自分で考えて行動できました。
- 朝の会や帰りの会の司会進行も、自分たちで工夫を凝らし、クラスの情報を的確に伝える場として機能させました。
- 自分の持ち物や学習道具の管理が完璧で、家庭学習の計画も自分で立てるなど、高い自己管理能力があります。
- 委員会活動では、委員長として、学校全体のための企画を自主的に提案・実行し、リーダーシップを発揮しました。
- 休み時間に、次の授業の準備を自主的に済ませておくなど、常に見通しを持った行動がとれます。
- 修学旅行の班行動では、班長として、時間やルールを守りながらも、全員が楽しめるよう自主的に計画を調整しました。
- 分からないことがあれば、まずは自分で調べ、それでも解決しない部分を明確にして質問に来るという、自主的な学習態度が確立しています。
- クラスで問題が起きた時も、他人任せにせず、自分たちの課題として捉え、解決策を真剣に話し合いました。
- 自分の意見や考えを、周りの空気に流されず、しっかりと持つことができる「自立した個」として成長しました。
- 中学校生活への期待を胸に、身の回りのこと(制服の管理、通学の準備など)を自分でやろうとする意欲が高まっています。
6年生 行動の記録 所見 文例【自分の力で考え、行動する】
- 問題に直面した時、すぐに他人に答えを求めるのではなく、まずは「自分ならどうするか」を多角的に考え抜く力があります。
- グループ学習では、受け身の姿勢ではなく、自分なりの仮説を立て、それを検証するために必要な情報を集め、議論をリードしました。
- 「卒業プロジェクト」では、「お世話になった学校への恩返し」として何をすべきかを自分たちで考え、清掃活動や花壇の整備を自主的に企画・実行しました。
- 社会科の調べ学習では、与えられたテーマに対し、自分なりの問い(サブテーマ)を設定し、主体的に探究活動を進めていました。
- 友達との意見が対立した際も、感情的にならず、互いの主張の共通点と相違点を整理し、着地点を冷静に探ることができました。
- 運動会の応援団長に自ら立候補し、全校児童をどうすればまとめられるかを深く考え、堂々とした態度で応援をリードしました。
- 学習発表会(劇)では、自分の役柄を深く解釈し、台詞のない場面でも、表情や仕草で感情を表現しようと工夫していました。
- 物事の是非を、その場の雰囲気ではなく、自分の良心と知識に基づいて判断し、行動に移すことができます。
- 自分の考えに自信を持ち、学級会や集会の場でも、大勢の前で堂々と意見を述べることができました。
- 判断に迷うと、信頼できる先生や友達に相談し、多様な意見を参考にした上で、最終的には自分で結論を出すことができます。
6年生 行動の記録 所見 文例【粘り強く取り組む】
- 算数の難易度の高い応用問題に対しても、諦めずに様々な解法を試し、答えにたどり着くまで粘り強く考え抜きました。
- 卒業制作(版画)では、細かい部分も手を抜かず、納得がいくまで彫刻刀を動かし続け、集中力の高さを発揮しました。
- 持久走大会では、小学校生活最後の挑戦として、苦しい表情を見せながらも、最後まで自分のペースを崩さずに完走しました。
- 組体操の練習で、なかなか技が成功しなくても、仲間と励まし合い、原因を分析しながら、できるようになるまで何度も挑戦しました。
- 漢字テストで満点が取れなかった時、間違えた字だけでなく、関連する熟語までノートにびっしりと練習する根気強さを見せました。
- 理科の実験がうまくいかなくても、仮説や手順のどこに問題があったのかを冷静に分析し、再挑戦する姿は立派でした。
- 長縄跳びの練習で、記録が伸び悩んだ時も、「まだやれる」と仲間を鼓舞し、最後まで練習をリードしました。
- 苦手な教科の復習にも、小学校の総まとめとして地道に取り組み、基礎力の定着に努めました。
- 一度決めた目標(例:卒業までに逆上がりをできるようになる)を、周りに流されず、継続してやり遂げる強い意志があります。
- 飽きっぽい面もありましたが、6年生になり、目の前の課題から逃げずに向き合い、最後までやり遂げる精神的な強さが育ちました。
6年生 行動の記録 所見 文例【目標に向かって取り組む】
- 「中学校の定期テストで良いスタートを切る」という目標を掲げ、小学校の総復習を計画的に進めるなど、先を見据えた努力ができています。
- 「陸上大会のリレー選手になる」という目標のため、毎日朝早く登校し、自主的に走り込みを続ける姿は、多くの児童の刺激となりました。
- 学習発表会では、「観客に感動を届ける」というクラス全体の目標に向け、自分の役割を完璧にこなすだけでなく、裏方の仕事も率先して行いました。
- 自分の課題(例:計算ミスが多い)を克服するため、「毎日計算ドリルを1ページやる」という具体的な目標を立て、着実に実行しました。
- 運動会の応援団長として、「〇組を優勝に導く」という強い目標を持ち、その情熱がチーム全体に伝播しました。
- 学習面だけでなく、生活面でも「6年間お世話になった校舎をピカピカにして卒業する」という目標を立て、日々の掃除に真剣に取り組みました。
- 目標達成のために、今何をすべきかを逆算して考え、月間・週間の学習計画を自分で立てて実践することができました。
- 目標が達成できなくても、その過程での努力を振り返り、失敗から学んだことを次のステップに活かそうとする前向きな姿勢があります。
- 個人の目標だけでなく、クラスや学校全体の目標(例:挨拶日本一)にも高い意識を持ち、最高学年として貢献しようと努めました。
- 目標を立てることは得意ですが、持続性に課題がありました。しかし、卒業を意識し、短期目標を確実にクリアすることで、継続する力を身につけました。
6年生 行動の記録 所見 文例【責任感】
- 日直の仕事(朝のスピーチ、健康観察など)を、最高学年として、工夫を凝らしながら最後まで完璧にやり遂げました。
- 卒業アルバム委員として、皆の意見をまとめ、業者との連絡調整など、地道な作業も責任を持って果たしてくれました。
- 学級委員として、クラスの課題(例:授業前の着席)に対し、粘り強く呼びかけを続け、クラスを良い方向に導きました。
- 掃除当番では、時間いっぱいまで黙々と自分の担当場所を磨き上げ、その真摯な姿は下級生の模範となりました。
- グループ学習で発表資料を作る際、自分が担当した部分は、誰よりも早く、そして質の高い内容で仕上げてきました。
- 飼育当番として、6年間続けた生き物の世話を、最後の最後まで愛情と責任を持ってやり遂げました。
- 自分に与えられた役割は、たとえ目立たない仕事であっても、学校の代表としての誇りを持ち、手を抜かずにやり遂げます。
- 自分の失敗や間違いを素直に認め、誠実に謝罪し、どうすれば挽回できるかを考えることができる、真の強さを持っています。
- クラスで問題が起きた時、他人事にせず、「最高学年としてどうあるべきか」を基準に考え、行動していました。
- 約束したことを守るという意識が非常に高く、その誠実な人柄は、クラスメイトや先生方からの厚い信頼につながっています。
6年生 行動の記録 所見 文例【創意工夫】
- 学級会で、卒業プロジェクトについて話し合った際、「地域の方々へ感謝の手紙を送る」という、独創的で温かいアイディアを提案しました。
- 学習発表会では、限られた予算と時間の中で、段ボールを使った大道具を効果的に見せる演出を工夫し、劇の質を高めました。
- 図画工作の卒業制作では、ありふれた材料(ペットボトルキャップなど)を組み合わせ、個性あふれる独創的な作品を完成させました。
- 理科のプログラミング学習で、どうすれば効率的に電気を使えるかを考え、独自の節電プログラムを考案しました。
- 社会科の新聞づくりでは、歴史上の人物になりきったインタビュー記事を掲載するなど、読み手を引き込む紙面を工夫しました。
- 自主学習ノートでは、学んだことを年表形式や相関図にまとめるなど、知識が定着しやすいよう自分なりの工夫を凝らしています。
- 「卒業生を送る会」の出し物として、ただ歌うだけでなく、6年間の思い出をスライドショーにする工夫を提案し、感動的な発表になりました。
- 掃除の時間、限られた時間で効率よく清掃できるよう、掃除用具の配置や分担を見直す工夫を提案しました。
- 既成のやり方にとらわれず、「もっと良い方法はないか」「どうすれば皆が楽しめるか」と常に考えようとする姿勢は、中学校でも活かされるでしょう。
- 運動会のスローガンを考える際、6年間の集大成と未来への希望を込めた、心に響く言葉を紡ぎ出してくれました。
6年生 行動の記録 所見 文例【思いやり・協力】
- 困っている下級生がいると、自分のことのように親身になって話を聞き、一緒に解決策を考えてあげる優しさがあります。
- グループ学習では、意見が言えずにいる子に「〇〇さんはどう思う?」と優しく話を振り、全員が参加できる雰囲気を作りました。
- 重い荷物を持っている先生や友達がいると、さっと駆け寄り、「持ちます」と自然に行動に移せる思いやりがあります。
- 修学旅行の際、体調を崩した友達の荷物を黙って分担して持つなど、言葉以上に態度で優しさを示せる人です。
- クラスで意見が対立し、空気が悪くなった時も、両者の言い分を尊重し、互いを認め合えるような温かい言葉をかけていました。
- 休み時間、一人でいる転入生に積極的に声をかけ、遊びの輪に誘い入れるなど、その気配りに感心しました。
- 運動会の組体操では、土台役として、上の人の安全を第一に考え、必死に仲間を支える姿に胸を打たれました。
- 合唱コンクールでは、パート内で音程が合わない時も、責めるのではなく、「一緒に練習しよう」と前向きな声をかけていました。
- 人の心の痛みが分かり、そっと寄り添うことができる、深い優しさを持っています。クラスの心の支えでした。
- 自分の意見を主張することと、相手の意見を受け入れることのバランスが絶妙で、常に集団の和を大切にできる人です。
6年生 行動の記録 所見 文例【生命尊重・自然愛護】
- 6年間続けた飼育活動を通して、生き物の命の尊さと、世話を続けることの責任感を深く学びました。
- 理科の「生物と環境」の学習をきっかけに、地域の環境保全活動に関心を持ち、自分にできることを真剣に考えていました。
- 修学旅行での自然体験学習では、自然の雄大さと厳しさを肌で感じ、環境を守ることの大切さを実感していました。
- 道徳の授業で「命」について考えた際、自分の体験と重ね合わせ、命あるものすべてを大切にしたいという強い意志を発表しました。
- 給食の「いただきます」の挨拶に、食材となった命や、作ってくれた人々への深い感謝の気持ちを込めることができています。
- 校庭の片隅に咲く花や、小さな虫の命にも目を向け、大切にしようとする優しい心を持っています。
- 「ゴミを減らす」という環境問題に対し、マイボトルを持参するなど、具体的な行動に移していました。
- 学校のウサギが亡くなった時、クラスで一番に涙し、感謝の気持ちを込めてお墓を作ってくれました。
- 動物愛護や環境問題に関するニュースに敏感で、その問題意識の高さに感心させられます。
- 6年間お世話になった校舎や自然に感謝し、卒業前に自主的に草むしりや落ち葉掃きをする姿は立派でした。
6年生 行動の記録 所見 文例【勤労・奉仕】
- クラスのために、人が嫌がるような仕事(例:トイレのスリッパ並べ、配膳台の清掃)も、文句一つ言わずに引き受けてくれました。
- 自分の役割(当番活動)が終わった後も、他に手伝うことはないかと探し、自主的に動くことができる奉仕の精神は素晴らしいです。
- 「働くこと」の意義について学習した際、家族や地域のために働く人々への具体的な感謝の気持ちを作文に綴りました。
- 卒業式や入学式の準備では、最高学年として、重い椅子や机を運ぶ作業を率先して引き受け、下級生をリードしました。
- 委員会活動(例:美化委員会)に6年間熱心に参加し、学校全体が快適に過ごせるよう、縁の下の力持ちとして貢献してくれました。
- 「人の役に立ちたい」という気持ちが強く、ユニセフ募金などのボランティア活動にも積極的に参加していました。
- 作業(例:運動会のテント設営)を、最後まで手を抜かずに丁寧に行う勤勉さがあります。
- 落ちているゴミに気づくと、誰に言われるでもなく拾ってゴミ箱に捨てるなど、小さな奉仕を自然に実践できます。
- みんなが使う共有スペース(手洗い場や図書室)をきれいに使おうと、下級生にも優しく声をかけていました。
- 誰かが見ていなくても、学校のために、クラスのために黙々と働くことができる、真の勤勉さを持っています。
6年生 行動の記録 所見 文例【係活動】
- 〇〇係(例:新聞係)として、卒業に向けた特集号を企画し、6年間の思い出や先生方へのインタビュー記事を作成しました。
- 係の仕事に強い責任感を持ち、活動が円滑に進むよう、仲間への声かけや準備を欠かしませんでした。
- 活動がマンネリ化しないよう、下級生も楽しめるような新しいクイズを企画するなど、創意工夫が見られました。
- 係の仲間と協力し、役割分担を明確にして、効率よく作業を進めるリーダーシップを発揮しました。
- 自分の係だけでなく、他の係の活動にも関心を持ち、連携してクラスを盛り上げようとする視野の広さがありました。
- 活動の振り返りを毎回行い、課題点を次の活動に活かそうとする、PDCAサイクルを意識した動きができました。
- 〇〇係(例:レク係)として、クラス全員が楽しめるルールを工夫し、卒業前の大切な思い出づくりに貢献しました。
- クラス全員の前で、係活動の成果を堂々と発表し、クラス全体への協力を呼びかけることができました。
- 目立たない地味な作業(例:プリントの印刷、掲示物の管理)も、クラスのためにこつこつと続ける真面目さがあります。
- 最高学年として、係活動を「やらされるもの」ではなく、「クラスを自分たちで楽しくするもの」として主体的に捉え、活動していました。
6年生 行動の記録 所見 文例【掃除】
- 掃除の時間、担当場所(例:廊下)を、6年間の感謝を込めて、隅々まで丁寧に磨き上げる姿が見られました。
- 「無言清掃」を高いレベルで実践し、集中して掃除に取り組むその姿は、学校全体の模範でした。
- 自分の担当場所が終わると、すぐに「手伝うところはありますか」と、他の場所の掃除を手伝う協調性があります。
- 掃除道具の管理が完璧で、雑巾をきれいに洗い、次に使う人が気持ちよく使えるよう整頓していました。
- 掃除班の班長として、下級生に掃除の手順を優しく教え、効率よく掃除を進めることができました。
- 机や椅子を運ぶ際、床を傷つけないよう静かに持ち上げて運ぶなど、校舎を大切にする心が育っています。
- 普段は目の届かないような場所(例:窓のサッシ、黒板の上)の汚れにも気づき、自分から進んできれいにしようと努力しました。
- 掃除開始のチャイムと同時に、素早く自分の場所に行き、作業を始める切り替えの早さはさすが最高学年でした。
- 友達とのおしゃべりに流れず、最後まで真面目に掃除に取り組む責任感があります。
- 掃除に対する意識が高く、日常生活でも教室のゴミに気づくと拾うなど、美化意識が習慣化しています。
6年生 行動の記録 所見 文例【給食当番】
- 給食当番の仕事は、最高学年として、衛生的(マスク、手洗い、白衣)かつ迅速に配膳を行い、下級生のクラスの手本となりました。
- クラス全員が公平な量になるよう、量のバランスを考えながら、丁寧によそおうと心がけていました。
- 「いただきます」の時間に間に合うよう、仲間と声をかけ合い、手際よく準備を進めるチームワークは素晴らしかったです。
- 重い食缶や食器カゴも、安全に配慮しながら、仲間と協力して運ぶことができています。
- 配膳台をきれいに拭いたり、牛乳パックを丁寧に片付けたりと、後片付けまで責任を持って行いました。
- おかわりを希望する人の列を上手に誘導し、混雑しないよう配慮するなど、周りを見て行動できていました。
- アレルギーのある友達の配膳には、特に注意を払い、複数人で確認するなど、責任感の強さが見られました。
- 当番の仕事を通して、「食」を支えてくれる人々への感謝の気持ちを、言葉や態度で表現できました。
- 給食室への返却の際、栄養士さんや調理員さんに、6年間の感謝を込めて「ありがとうございました」と挨拶ができました。
- 当番活動を一度も忘れることなく、自分の役割を最後までしっかりと果たすことができました。
6年生 行動の記録 所見 文例【公正・公平】
- クラスで意見が分かれた際、どちらか一方の意見に偏るのではなく、双方の意見の良い点を見つけ、着地点を探る公正な判断ができました。
- 球技大会の際、審判として、自分にも相手にも厳格にルールを適用し、公正な試合運営に貢献しました。
- 係や当番を決める際、人気のある役割に希望が集中しても、皆が納得できるような公平な決め方(話し合いや抽選)を提案しました。
- 友達との間でも、仲の良い友達をえこひいきせず、誰に対しても平等な態度で接することができるため、人望が厚いです。
- グループ分けの際、能力や仲の良さで偏りが生じないよう、クラス全体を見渡した公平な班分けを提案できました。
- 「自分だけが得をする」ことよりも、「クラス全体にとって最善か」を常に考え、行動できる公共心の持ち主です。
- 間違いや不正を許さない強い正義感があり、たとえ相手が上級生や先生であっても、正しいと思ったことを勇気を持って主張できました。
- 掃除の分担など、不公平感が出ないよう、皆の意見を丁寧に聞き取り、調整役を果たしてくれました。
- 多数決で決まったことに対しても、たとえ自分の意見と違っても、クラスの決定として素直に受け入れる公平さがあります。
- 物事の善悪を冷静に判断し、感情論に流されず、常に公平な視点を持とうと努めています。
6年生 行動の記録 所見 文例【公共心・公徳心】
- 教室や廊下、トイレなど、みんなが使う場所を「次に使う人が気持ちよく使えるように」と、常に意識してきれいに使っています。
- 図書室の本や体育館のボールなど、学校の備品を「みんなの財産」として大切に扱い、丁寧に後片付けをしています。
- 水道の水をこまめに止める、教室の電気を最後に消すなど、資源を大切にする公共心が身についています。
- 廊下は静かに右側を歩く、階段は走らないなど、学校のルールを「みんなの安全のため」と理解し、率先して守っています。
- スリッパや傘立ての整頓が常にできており、その姿が下級生の良い手本となっています。
- 地域の一員としての自覚を持ち、登下校中のマナー(挨拶、広がって歩かない)を守り、地域の方からもお褒めの言葉をいただきました。
- 修学旅行の際、公共の宿泊施設でのマナー(時間厳守、消灯後の静寂)を完璧に守り、最高学年としての模範を示しました。
- ゴミの分別を徹底し、リサイクル活動にも積極的に協力するなど、環境問題への意識が高いです。
- 「自分さえ良ければいい」という考えは一切なく、集団生活のルールを守ることの重要性を深く理解しています。
- 落とし物を見つけると、必ず先生に届け出るなど、その誠実な行動は6年間変わりませんでした。
6年生 自立活動 所見 文例
(※個々の児童の課題や目標、中学校への接続を強く意識した内容となります。あくまで一例です)
- (健康の保持・心理的安定)中学校生活への不安について、SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通して言語化する練習を重ねました。自分のストレスサインに気づき、「相談する」「休息する」といった対処法を自分で選択できるようになりました。
- (人間関係の形成)「上手な断り方」「意見の伝え方」など、より高度なコミュニケーションスキルを学習しました。グループ活動で、自分の意見を相手を傷つけずに伝える場面が見られるようになりました。
- (環境の把握・身体の動き)中学校の広い校舎を想定し、地図を見て目的地まで移動する練習を行いました。時間割や教室変更にも、視覚的なスケジュールを確認し、落ち着いて対応する力がつきました。
- (コミュニケーション)板書の書き写しに時間がかかる課題に対し、タブレット端末のカメラ機能やノートアプリの活用法を習得しました。自分に必要な合理的配慮を理解し、中学校でも活用する準備ができました。
- (自己理解と将来設計)自分の「得意なこと」と「苦手なこと」を客観的に分析し、自己紹介カードを作成しました。中学校の先生に自分を理解してもらうための準備ができました。
- (感覚の偏りへの対応)聴覚(視覚)の過敏さに対し、イヤーマフや座席の配慮を「自分から求める」ことができるようになりました。自己決定の力が育っています。
- (学習方法の獲得)学習計画表の作成と振り返り(PDCA)を練習しました。定期テストを想定し、学習の優先順位をつけて取り組むスキルが身についてきました。
- (身体の動き)手指の巧緻性を高めるため、細かい作業(模型づくりなど)に根気強く取り組みました。技術・家庭科の授業にも自信を持って臨めるでしょう。
- (コミュニケーション)場面に応じた言葉遣い(敬語、友達言葉)の使い分けを学習しました。職員室への入室や先生への質問など、実践的な練習の成果が表れています。
- (自己肯定感)6年間でできるようになったこと(例:挨拶、係の仕事)を振り返り、自分の成長を実感することができました。自信を持って中学校へ進学してほしいと願っています。
各学年各種の所見文例集リンク🔗
こちらから、各学年の所見文例の記事を読むことができます💁
まとめ
通知表 所見 文例 小学校6年版として、全教科と行動の記録20項目、さらに自立活動の文例を、1万字をはるかに超えるボリュームでご紹介しました。小学校生活6年間は、子どもたちにとって心身ともに最も大きく成長する時期です。特に6年生は、最高学年としての責任感と、中学生になることへの期待と不安が入り混じる特別な一年です。この記事の豊富な文例が、先生方が一人ひとりの児童の輝かしい成長を捉え、卒業という大きな節目にふさわしい、温かいエールを贈るための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。これらの文例をベースに、ぜひその子「らしさ」が伝わる所見を作成してください。
小学校から中学校への接続に関する学習指導要領の内容については、以下の外部リンクもご参照ください。



コメント