特別支援学級に進級・入学したお子さんを送り出す保護者の方々は、

「新しい環境でうまくやっていけるかな?」

「新しい環境でうまくやっていけるかな?」
と、多くが不安を抱えています。学級通信は、そんな不安を少しずつ和らげる「架け橋」です。
初めての号では、
「この先生なら大丈夫」
「クラスが子どもの居場所になりそう」
と感じてもらえるよう、次の3つを意識しましょう。
- 教師の「人柄」が伝わる自己紹介
- 「具体的な支援」で安心を届けるクラス方針
- 「一緒に育てる」という協働のメッセージ
支援学級「黄金の3日間」の成功の方法が知りたい方は、こちらの記事を参考ください。👇
自立活動に悩んだらこちら💁
第1章 4月の通信で大切にしたい3つの心がけ
1. 自己紹介「等身大の自分を伝える」
堅苦しい経歴よりも、「子どもとどう関わりたいか」を言葉にしましょう。
【例文】
「こんにちは!担任の〇〇です。
昨年度はサッカー教室で子どもたちと汗を流すのが楽しみでした。
今年は、『できた!』を一緒に喜び合えるクラスにしたいと思っています。
お子さんの好きなこと・困っていること、何でも教えてくださいね。」
おすすめの工夫
- 失敗エピソード:「昨年初めて担任した時、お便りの誤字に気づかず…」など、人間らしさを出す
- イラスト付きマンガ:1コマで「先生の一日」を紹介
2. クラス方針『具体的な支援を見える化』
抽象的な目標より、「実際にどんな配慮をするか」を具体的に書きましょう。
【NG例】
「個々の特性に合わせた指導をします」
【GOOD例】
「授業中に集中が切れた時は、
・5分間の休憩スペースで気分転換
・ヘッドフォンを貸し出して音刺激を軽減
などの対応をします。ご家庭での様子も参考にしたいので、ぜひ教えてください」という感じです。
3. 保護者へのメッセージ「不安を受け止める言葉」
【避けたい表現】
「ご協力お願いします」→ プレッシャーに感じる保護者も
【共感を伝える表現例】
「初めての環境で、お子さんも緊張しているかもしれません。
小さな変化でも気になることがあれば、遠慮なくお知らせください。
学校とご家庭で情報を共有しながら、無理のないペースで進めていきましょう。」
第2章 1号目のお手本レイアウト
タイトル:「〇〇さん、ようこそ! にじいろクラスだより」
(クラス名を入れると親しみが湧く)
- 「はじめましてのごあいさつ」
- 先生の自己紹介(写真+趣味)
- 「保護者の方へ」欄:「不安なことはメモでも大丈夫です」と伝える
1.「4月の目標:にこにこで過ごそう」
- スケジュール(絵文字で視覚化)
4/10(月)🌸身体測定 → 着替えの練習します 4/15(土)🎨図工「手形アート」 → 汚れてもいい服で
- 「お願いとお知らせ」
- 「無理のない範囲で」を強調:
「連絡帳は1行だけでも大丈夫です。
忙しい時は『今日は元気でした』と書くだけでも嬉しいです」
- 「子どもたちのひと言」
- 匿名で子どもの声を紹介:
「給食のプリンがおいしかったです!(Aさん)」
- 「編集後記」
- 先生の気持ちを詩的に:
「桜のつぼみがふくらむように、
ゆっくりと、子どもたちの笑顔が咲いていきますように。」
第3章 継続のコツ~信頼を育む5つの習慣
1. 「できた!」を貯金する視点
- 行動目標の進捗をイラスト化:
「あいさつ貯金」→ シール貼りで可視化し、保護者と共有
2. 保護者の「困った」に寄り添うコーナー
【例】「おうちでのできごと」募集
「朝の支度が時間かかるのですが…(Bさんママ)」
→ 先生からの返信:「学校では音楽を流しながら練習中です!ご家庭でも試してみてください」
3. 写真の効果的な使い方
- 個人特定を避けた「幸せの切り取り」:
「給食のおかわりジャンケン(手だけ写す)」
「朝の会で歌を歌う声(後ろ姿)」
4. 予定変更は「理由」とセットで
【NG】「遠足が雨天中止になりました」
【GOOD】「子どもたちと『雨の日遠足ごっこ』を計画中です!お楽しみに」
5. 保護者も教師も「完璧じゃなくていい」
- 通信の最後に一言:
「誤字があっても温かい目で見守ってください…!(笑)」
第4章 こんなときどうする?保護者の不安への応答例
【保護者の声】
「うちの子、友達と遊べるか心配です」
【返信のポイント】
- 事実:「休み時間はブロックで一緒に遊んでいます」
- 配慮:「まずは先生と1対1で関わる時間を作っています」
- 共感:「ゆっくりペースで大丈夫ですね。また様子をお伝えします」
おわりに:通信は「小さな幸せ」のリレー
特別支援学級の通信作りに正解はありません。
「今日は笑顔で過ごせた」
「苦手な粘土に挑戦した」
そんなささやかな事実を積み重ねることが、保護者との信頼を育みます。
最初から完璧を目指さず、
「一緒に子どもの成長を見守りましょう」
という気持ちを、
ぜひ言葉にのせてみてください。
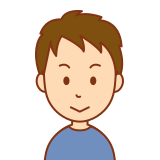
きっと、その温もりは保護者の胸に届きます。





コメント