SST(ソーシャルスキルトレーニング)を始める前に、日常的な支援を見直すことは、トレーニングの効果をより高めるために非常に大切です。特に、通常学級や支援学級で子どもたちを支援する先生方にとって、日々の支援の一つひとつが、その後のトレーニングに繋がる重要な土台となります。
ここでは、
子どもたちの特性を理解し、温かみのある支援を行いながら、SSTを進めるための具体的なアプローチについて考えていきます。
おすすめのSSTゲームはこちら💁
1. 子どもたちの言動に寄り添う
子どもたちの気になる言動があるとき、その背後にどんな理由があるのかを考えることが第一歩です。「なぜこの子はこんなふうに行動してしまうのだろう?」という疑問を持つことから始めてみましょう。もしかしたら、その子の中にまだ表現できない感情や、他者との関わり方に対する不安があるかもしれません。
例えば、ある子どもがクラスで急に声を上げてしまう場合、それは単に注意を引きたかっただけかもしれませんが、もしかすると他の子との関係に不安を感じているのかもしれません。困った行動が見られた時に、ただその行動を注意するのではなく、まずはその子の気持ちや状況に寄り添い、「どうしたらその子が安心できるだろう?」と考えて支援することが大切です。
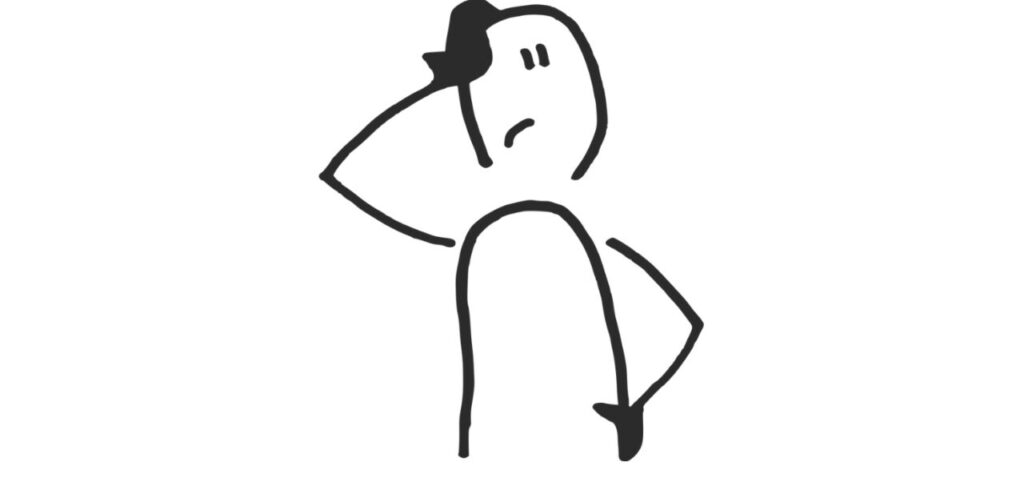
そして、日常的に子どもたちの気持ちに寄り添うことで、トレーニングの時にも安心して自分を表現できるようになります。支援する側が「あなたの気持ちは大事にしている」と伝えることで、子どもたちは信頼感を抱き、より積極的にSSTにも取り組むことができるでしょう。
2. 特性に合わせた支援を意識する
子どもたちは一人ひとり異なる特性やニーズを持っています。SSTを行う際には、子ども一人ひとりの特性に合わせた支援を考えることが重要です。例えば、発達障害を持つ子どもや、社会的なスキルに苦手意識がある子どもには、その子に合ったペースで進めることが求められます。
通常学級でも支援学級でも、クラスの中には様々な背景を持った子どもたちがいます。そんな中で、どのように一人ひとりに寄り添い、適切な支援を提供するかを考えることが、先生方の大きな役割となります。例えば、感覚過敏がある子どもには、静かな場所での活動を増やしたり、視覚的な手助けを加えることで、安心して参加できる環境を作ってあげることができます。

また、注意を集中させるのが難しい子どもには、指示を短く簡潔に伝える方法を試みたり、タイマーを使って時間を視覚的に示すといった工夫が効果的です。子どもたちの特性を理解し、それに応じたサポートを日常的に提供することで、SSTがスムーズに進む基盤が整います。
3. 指示の出し方に温かみを込める
SSTを進めるためには、指示の出し方も重要なポイントです。特に支援が必要な子どもたちに対しては、どんな言葉を使うか、どんなトーンで伝えるかが大切になります。命令口調でなく、優しく、明確に、そして温かみを感じさせる言葉をかけることが、子どもたちが安心して行動に移す手助けになります。
例えば、「これをやりなさい」という命令ではなく、「今、○○をやる時間だよ、一緒にやってみようか?」というふうに、子どもたちに選択肢を持たせつつも、やるべきことを分かりやすく伝える言い方が効果的です。さらに、「よく頑張ったね」「一緒にやってくれてありがとう」といった褒め言葉を積極的に使うことで、子どもたちは自信を持って行動することができます。

また、指示を出す際に、言葉だけでなく視覚的なサポートを加えることで、理解が深まります。絵カードやジェスチャー、掲示物を使うことで、より多くの子どもたちが自分のペースで理解できるようになります。
4. 褒めて支え合う学級づくり
子どもたちが社会的スキルを身につけるためには、学級全体の雰囲気がとても大切です。褒め合い、助け合いながら学んでいくことで、子どもたちは安心して自分を表現し、成長することができます。
褒めることは、子どもたちが自分の努力を認めてもらえる瞬間です。その小さな一歩を大切にし、「よくやったね!」という声をかけることで、子どもたちは「自分はできる」と感じ、次に繋がるモチベーションが生まれます。助け合いを促進するためには、グループ活動やペアワークを通じて、子どもたちが協力することの大切さを学べる場を作ることも有効です。
支援学級でも、通常学級でも、子どもたちが「自分が大切にされている」と感じることができる環境を整えることが、SSTを効果的に行うための第一歩となります。
5. 役割を与えて自己肯定感を育てる
子どもたちに役割を与えることは、その子の自己肯定感を育むためにとても大切です。役割を持つことで、子どもたちは自分が学級の一員として大切な存在であることを実感できます。役割は、その子の特性に合わせて選ぶと良いでしょう。例えば、クラスでお手伝いをする役割や、みんなの前で発表をする役割を与えることで、子どもたちは「自分にできることがある」という自信を持つことができます。
役割を与えるときには、その子のペースや能力を理解した上で、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。成功を重ねることで、子どもたちは自分の存在価値を感じ、自己肯定感が育まれます。
6. 日常的な支援と温かい環境づくり
最後に、日常的な支援を通じて、温かい学級づくりを目指しましょう。子どもたちが安心して自分を表現できるような環境を整えることが、SSTの効果を高める土台となります。そのためには、毎日のやりとりの中で、子どもたち一人ひとりを大切にし、理解し合うことが不可欠です。
子どもたちの困難な行動に対しては、ただ叱るのではなく、その行動の背景を考え、温かく寄り添いながらサポートしていくことが重要です。そして、温かみのある言葉や行動を通じて、子どもたちが自信を持って社会的スキルを身につけていけるように、支援を続けていきましょう。
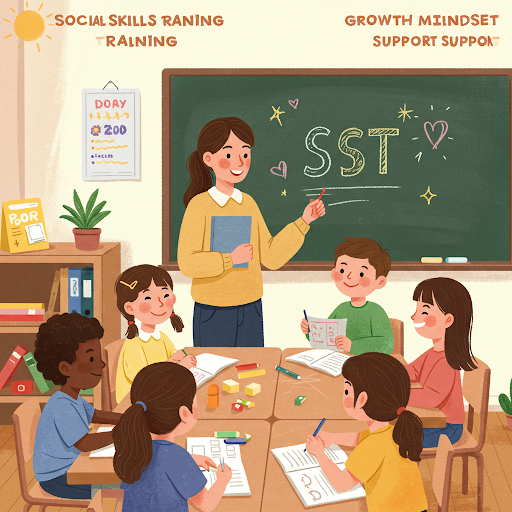




コメント