「特別の教科 道徳」が全面実施され、通知表の所見欄に何を書くべきか、頭を悩ませている先生方は多いのではないでしょうか。数値評価ではなく、児童・生徒の成長を記述で示す必要がある道徳 所見文例は、多くの先生方にとって喫緊の課題です。特に、文科省が示す内容項目をどう反映させるか、あるいは小学校一年生や二年生といった低学年から、3年生、4年生の中学年、そして5年生、6年生の最高学年、さらには中学校へと続く発達段階に応じて、どのような言葉を選べばよいのか。この記事では、そのような悩みを解決するため、膨大な数の道徳 所見文例を、学年別・内容項目別に徹底的にご紹介します。20000字を超える圧倒的なボリュームで、明日からの所見作成を強力にサポートします。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- 「特別の教科 道徳」の評価(所見)の基本的な考え方
- 文科省が示す4つの視点(内容項目)に基づいた所見の書き方と文例
- 小学校低学年(一年生・二年生)向けの、具体的な行動や発言に基づいた道徳所見文例
- 小学校中学年(3年生・4年生)向けの、他者意識や集団生活に着目した道徳所見文例
- 小学校高学年(5年生・6年生)向けの、内省的な思考や社会との関わりを捉えた道徳所見文例
- 中学校(1年・2年・3年)向けの、思春期の特性や自己の生き方を踏まえた道徳所見文例
- すぐに使える「ポジティブな側面」と「成長を促す側面」の双方の文例
各学年の所見文例集はこちら💁
道徳 所見文例【総論】「特別の教科 道徳」の評価の基本
2018年度(中学校は2019年度)から全面実施された「特別の教科 道徳」は、従来の「道徳の時間」とは異なり、「考え、議論する道徳」へと転換しました。これに伴い、評価のあり方も大きく変わりました。
最大のポイントは、「数値による評定(5段階評価など)は行わない」という点です。道徳性は、個人の内面に関わる部分が大きく、それを点数で評価することは馴染まないからです。
その代わりに、「学習状況」と「道徳性に係る成長の様子」を一体的に見取り、その成果を文章で記述すること(=所見)が求められています。つまり、道徳の授業中に児童・生徒がどのようなことを考え、どのように議論に参加し、その結果どのような変容が見られたかを、具体的な言葉で保護者に伝える必要があります。

所見作成時の注意点は以下の通りです。
- 個人の内面(道徳心)そのものを評価・断定しない。(例:「〇〇さんは優しい心を持っている」ではなく、「〇〇さんは『親切』の授業で、相手の気持ちを深く想像し、自分ならどうするかを真剣に発表できた」と記述する)
- 児童・生徒の「良い点」や「可能性」、「努力している点」に光を当てる。(短所を指摘するのではなく、成長のプロセスを記述する)
- 他の児童・生徒と比較した評価は行わない。(あくまでその子自身の成長の様子を記述する)
- 具体的な「授業中の姿」(発言、ノートの記述、グループ活動の様子、表情など)を根拠にする。
この記事では、これらの基本原則を踏まえた上で、具体的な文例を紹介していきます。
道徳所見文例 文科省の示す「内容項目」と所見の視点
文科省の学習指導要領では、道徳科の内容項目を4つの大きな視点で分類しています。所見を作成する際も、この4つの視点を意識することで、バランスの取れた評価(記述)が可能になります。

- A 主として自分自身に関すること(自己):自主、自律、自由と責任、節度、節制、向上心、正直、誠実、希望、勇気など
- B 主として人との関わりに関すること(他者):親切、思いやり、感謝、尊敬、友情、信頼、礼儀、謙虚さ、相互理解、寛容など
- C 主として集団や社会との関わりに関すること(集団・社会):規則の尊重、公正、公平、正義、社会参画、公徳心、勤労、奉仕、家族愛、郷土愛、愛国心など
- D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること(生命・自然・崇高):生命尊重、自然愛護、感動、畏敬の念、よりよく生きる喜びなど
以下に、それぞれの視点に基づいた所見文例の「型」をいくつか紹介します。
A視点(自己)の所見文例の型
- 「正直・誠実」の学習では、(具体的な授業内容)を通して、自分の弱さと向き合うことの大切さを〇〇さん自身の言葉で語っていました。
- 「節度・節制」について、自分の生活(例:メディア時間)を振り返り、目標を立てて改善しようとする前向きな姿勢がノートから伝わってきました。
- 「向上心」に関する資料を読み、〇〇さん自身が挑戦している(例:習い事、苦手教科)ことと重ね合わせ、努力を続ける意義を真剣に考えていました。
- 役割演技で「勇気」ある行動をとる役を演じ、正しいと信じることを行うことの難しさと尊さを実感したようです。
- 自分の長所と短所について考える活動で、自分自身を客観的に見つめ、短所を克服しようとする意欲的な記述が見られました。
B視点(他者)の所見文例の型
- 「親切・思いやり」の授業で、相手の立場に立って考えることの重要性に気づき、グループ討議では積極的に意見を交換していました。
- 「感謝」の学習をきっかけに、日頃お世話になっている人々への感謝の気持ちを、具体的なエピソードと共に振り返る姿が見られました。
- 「友情・信頼」について、友達と意見が対立した際の登場人物の心情を深く読み取り、互いを理解しようと努めることの大切さを学んでいます。
- 「礼儀」の重要性について、なぜ挨拶が必要なのかを自分の言葉で説明しようと努め、学習後はよりはっきりとした挨拶ができるようになりました。
- 「相互理解・寛容」のテーマでは、自分とは異なる意見を持つ他者を受け入れることの難しさを感じつつも、粘り強く対話しようとする姿勢が見られました。
C視点(集団・社会)の所見文例の型
- 「規則の尊重」について、なぜルールが必要なのかをグループで深く議論し、集団生活における自分の責任を自覚した発言がありました。
- 「公正・公平」な態度とは何かについて、具体的な場面を想定しながら真剣に考え、〇〇さんなりの正義感の強さがうかがえました。
- 「勤労・奉仕」の学習後、日々の清掃活動や係活動への取り組み方がより真剣になり、集団のために働く喜びを感じているようです。
- 「家族愛」の資料を読み、普段は照れくさくて言えない家族への思いを、真摯な言葉でワークシートに綴っていました。
- 「社会参画」について学び、自分たちが社会の一員として何ができるかを考え、身近な問題(例:地域のゴミ問題)に関心を持つようになりました。
D視点(生命・自然・崇高)の所見文例の型
- 「生命尊重」の資料を通して、命のかけがえのなさを実感し、授業後も深く考え込む様子が見られました。豊かな感性を持っています。
- 「自然愛護」の学習では、美しい自然の映像を見て素直に感動し、環境を守るために自分にできることを真剣に考えていました。
- 「感動・畏敬の念」について、偉人の生き方や芸術作品に触れ、人間の力の素晴らしさや努力の尊さに心を動かされていました。
- 「よりよく生きる喜び」について、困難を乗り越えた人々の姿を通して、自分が今ここにいることの意味を問い直す姿が見られました。
- 動植物の世話や観察を通して、命の不思議さや力強さに気づき、生き物を大切にしようとする気持ちが育っています。
道徳 所見文例 一年生(低学年)
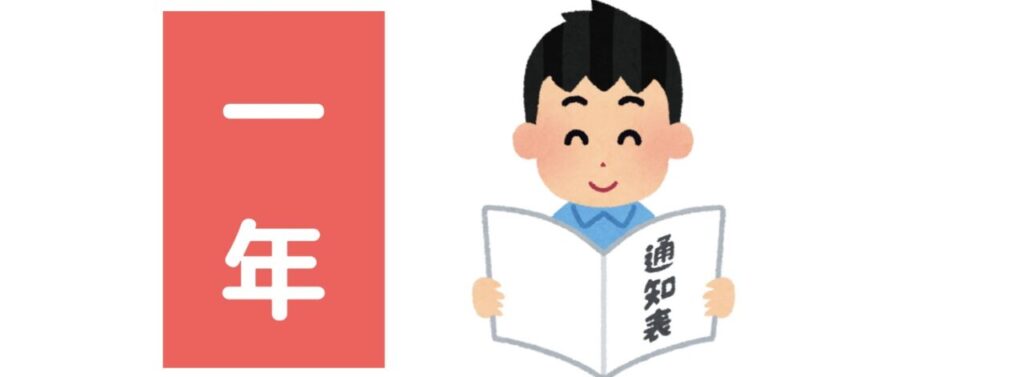
一年生は、具体的な行動や素直な感情表現が中心です。「学校は楽しい」「友達と仲良くする」といった基本的な生活習慣や他者との関わりを、道徳の授業を通して学んでいく時期です。授業中の元気な発言や、役割演技での素直な反応を捉えます。
一年生:A視点(自己)文例
- 「きもちのよいあいさつ」の学習では、主人公の気持ちを考え、自分から元気に挨拶することの良さに気づき、翌朝から実践しようと張り切っていました。
- 「しょうじきに」の資料を読み、嘘をついた時のドキドキした気持ちに共感し、「ごめんなさい」と言う勇気の大切さを感じ取ったようです。
- 「じぶんのことは じぶんで」の学習で、役割演技を通して、自分の役割を果たすことの充実感を味わっていました。
- 「がっこう だいすき」の活動では、学校の好きなところをたくさん見つけ、生き生きとした表情で発表することができました。
- 「わるいことをしたら」というテーマで、素直に謝ることの大切さを学び、友達との関わり方を見直すきっかけとなったようです。
- 「ものをたいせつに」の学習後、自分の使っている鉛筆や消しゴムを丁寧に扱う姿が見られるようになりました。
- 「がまんすること」について、自分の経験を思い出しながら、少し我慢できた時の嬉しさを発表できました。
- 「はやね はやおき あさごはん」の大切さを学び、自分の生活を振り返るワークシートに、意欲的に取り組んでいました。
- 「すききらいしない」の学習で、給食を残さず食べようと努力する主人公に共感し、自分も頑張ってみようという気持ちが芽生えたようです。
- 「できるようになったこと」を発表する活動で、自分の成長を素直に喜び、自信を深めることができました。
一年生:B視点(他者)文例
- 「しんせつに すると きもちいい」の学習で、親切にされた時の温かい気持ちを自分の言葉で表現し、自分もそうしたいと意欲を見せていました。
- 「ともだちと なかよく」の話し合いで、友達の良いところを見つける活動に熱心に取り組み、〇〇さんの良さを発表していました。
- 「かぞくの みんな」というテーマで、家族への感謝の気持ちを作文に書き、お家の人に「ありがとう」と伝えたいと話していました。
- 「ありがとうの きもち」の学習では、様々な「ありがとう」の場面を思い浮かべ、感謝を伝えることの素敵さに気づきました。
- 役割演技で「ごめんね」と謝る役を演じ、相手の気持ちを想像しながら、素直に気持ちを伝える練習ができました。
- 「おじいさん おばあさんへ」の学習で、お年寄りを大切にしようとする優しい気持ちが育っていることが、発言から伝わってきました。
- 「せんせいや がっこうの ひとたち」への感謝を考える授業で、自分たちが多くの人に支えられていることに気づいたようです。
- 友達と喧嘩する場面の役割演技で、「いやなきもち」に共感し、どうすれば仲直りできるかを一生懸命考えていました。
- 「おれいを いおう」の学習後、給食の配膳員さんや先生に、以前よりもはっきりとした声でお礼を言う姿が見られます。
- 「みんな なかよし」のテーマで、自分と違う友達とも一緒に遊ぶ楽しさについて、自分の体験を発表できました。
一年生:C視点(集団・社会)文例
- 「みんなの ものを たいせつに」の学習で、教室のロッカーや本を丁寧に扱うことの理由を考え、実践しようと努めています。
- 「じゅんばんを まもる」ことの大切さについて、公園の滑り台の絵を見ながら、みんなが楽しく遊ぶためのルールだと理解しました。
- 「きょうしつは みんなの ばしょ」という意識が高まり、授業後に机を整頓したり、小さなゴミを拾ったりする姿が見られます。
- 「がっこうの きまり」について、なぜチャイムで着席するのかを考え、時間を守ることの良さを学びました。
- 「こうつうルールを まもる」学習では、安全に登下校するために大切なことを真剣に考え、手を挙げて横断歩道を渡る練習にも熱心でした。
- 「うそを つかない」という学習で、正直に話すことで、周りの人との信頼関係が作られることに気づき始めています。
- 「やくそくを まもる」ことの重要性を学び、友達との小さな約束も大切にしようとする気持ちが芽生えています。
- 「しょくいんしつへの はいりかた」など、学校での基本的なマナーを学び、礼儀正しい態度を身につけようと努力しています。
- 「にほんの よいところ」として、桜や富士山の写真を見て、「きれい」と素直に感動していました。
- 「おしごとして いる ひと」の資料を見て、様々な仕事が自分たちの生活を支えていることに気づき、働く人への感謝の気持ちを持ちました。
一年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- アサガオの世話を通して、植物が成長する様子を日々観察し、命の不思議さや力強さを実感していました。
- 「いきている って すてき」の学習で、動物や虫にも命があることを学び、「むやみにとらない」と優しく話す姿が見られました。
- 「たべる ことは いのちを もらうこと」という学習で、給食を残さず食べようとする意識が高まりました。
- 雨上がりの虹や、きれいな夕焼けを見て、「わあ、すごい」と素直に感動を口にする豊かな感性を持っています。
- 「どうぶつと なかよく」の学習で、ウサギの触り方を学び、優しくなでる姿から命への慈しみを感じました。
- 「うみや やまを きれいに」というテーマで、ゴミを捨てることが生き物にいかに悪い影響を与えるかを学び、ポイ捨てはしないと決意していました。
- 「すごいな と おもう ひと」として、スポーツ選手の努力する姿に感動し、自分も頑張りたいと目を輝かせていました。
- 「いのちは ひとつ」という資料を読み、自分も友達も、かけがえのない命を持っていることを真剣な表情で聞いていました。
- 「おひさまや あめのおかげ」で野菜が育つことを学び、自然の恵みへの感謝の気持ちを持ちました。
- 「きれいな こえだね」と、小鳥のさえずりや風の音に耳を傾け、自然の美しさを感じる心が育っています。
道徳 所見文例 二年生(低学年)
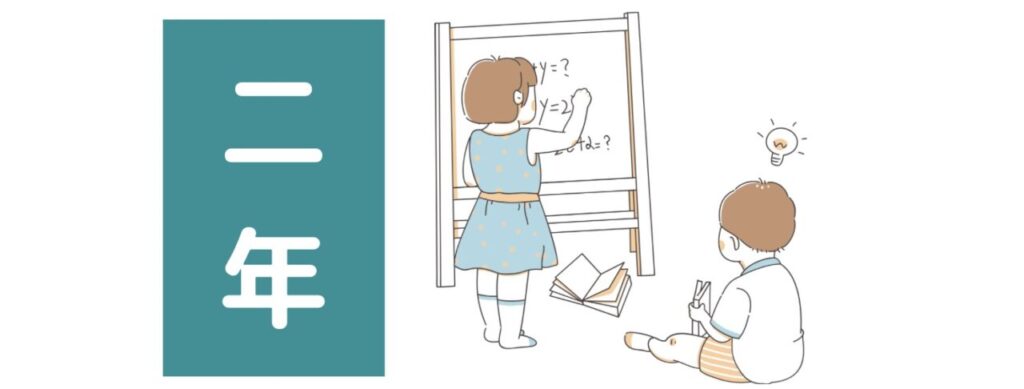
二年生になると、一年生での経験を基に、「自分」と「他者」の違いをより明確に意識し始めます。役割演技や簡単な話し合い活動で、友達の考えを聞いたり、自分の考えを伝えたりする姿に注目します。
二年生:A視点(自己)文例
- 「がまんづよい こころ」の学習で、自分の弱い気持ちと向き合い、最後までやり遂げることの大切さを感じ取っていました。
- 「じぶんの よいところ」を見つける活動で、友達から長所を教えてもらい、照れながらも自信を深めている様子でした。
- 「ゆうきを だして」の資料を読み、間違ったことを「違うよ」と言うことの難しさと大切さを、自分の体験と重ねて考えていました。
- 「もっと じょうずに なりたい」と、苦手なことにも挑戦する主人公に共感し、自分も練習を頑張ろうという意欲をノートに書いていました。
- 「せいりせいとん」の学習をきっかけに、自分の机の中やロッカーをきれいに使おうと意識する姿が見られます。
- 「あかるい こころで」の授業で、失敗してもくよくよせず、前向きに考えることの良さを学びました。
- 「じぶんらしさ」について、〇〇さん自身の好きなことや得意なことを、堂々と発表することができました。
- 「正直な心」について、嘘をつきそうになる心の葛藤を話し合い、正直でいることの清々しさを学びました。
- 「目標をもって」努力することの大切さを知り、漢字練習や計算カードなど、日々の学習への取り組み方がより丁寧になりました。
- 「節約」について、水の出しっぱなしや電気のつけっぱなしに気づき、資源を大切にしようとする意識が芽生えています。
二年生:B視点(他者)文例
- 「ともだちと なかよく」の話し合いで、自分の意見だけでなく、友達の考えも最後まで聞こうとする姿勢が育っています。
- 「おもいやりの こころ」の学習で、困っている人にかける言葉を具体的に考え、温かい発言が多く聞かれました。
- 「あいさつは こころの かけはし」の資料を読み、挨拶が持つ力に気づき、地域の人にも自分から挨拶しようと意気込んでいました。
- 「かぞくへの かんしゃ」の授業で、いつもしてもらっていることを思い出し、自分もお手伝いを頑張りたいと発表しました。
- 「けいごを つかおう」の学習で、職員室での言葉遣いを練習し、目上の人への敬意を態度で表そうと努力しています。
- 「ともだちの よさ」を見つける活動で、〇〇さんの観察力の鋭さが光り、友達も気づかなかった長所をたくさん見つけていました。
- 「ゆるす こころ」について、喧嘩の後の仲直りの難しさを話し合い、相手の気持ちを想像することの大切さを学びました。
- 「しんらい」の学習で、約束を守ることが信頼につながることを知り、日々の生活でも意識しようとする姿が見られます。
- 「こまっている ひとが いたら」の役割演技で、車椅子の人や目の不自由な人にどう接するかを真剣に考え、行動に移そうとしています。
- 「ちがいを みとめる」学習で、自分と違う考えの友達がいても、それを「おもしろい」と受け止めようとする心の広がりが見えました。
二年生:C視点(集団・社会)文例
- 「きまりを まもる」ことの理由を考え、みんなが気持ちよく過ごすためにルールがあるのだと、自分の言葉で説明できるようになりました。
- 「こうへいな こころ」の学習で、じゃんけんや当番活動などで、えこひいきせずに公平に接することの大切さを学びました。
- 「みんなの ために はたらく」ことの喜びについて、係活動の仕事と関連付けながら、自分の役割を果たすことの充実感を語りました。
- 「まちの すてきな ひと」として、交通指導員さんやお店の人への感謝の気持ちを発表し、地域への関心を高めました。
- 「こうきょうの ばしょでの マナー」について、図書館や電車の中での過ごし方を具体的に考え、実践しようと努めています。
- 「おにいさん・おねえさん として」一年生に優しく接することの意味を考え、上級生としての自覚が芽生え始めています。
- 「にほんの ぶんか」として、お正月やお祭りの意味を学び、伝統を大切にしようとする気持ちを持ちました。
- 「はたらく ことの たのしさ」について、パン屋さんの仕事を通して、人の役に立つ喜びを感じ取っていました。
- 「ちいきの あんぜん」を守る人々の努力を知り、自分たちも安全に気をつけて生活しようとする意識が高まりました。
- 「かぞくの いちいん として」の役割について話し合い、自分もお手伝いを分担することの重要性に気づきました。
二年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- 「いのちの ふしぎ」の学習で、赤ちゃんが生まれるまでの様子を知り、自分が大切に育てられてきたことを実感し、感動していました。
- 「いきものを かう せきにん」について、最後まで世話をすることの大切さを学び、生き物への愛情を深めています。
- 「しぜんの めぐみ」として、野菜や果物が育つ過程を知り、太陽や水の力に感謝する気持ちをノートに綴っていました。
- 「うつくしい ものに ふれて」の活動で、きれいな音楽や絵画に触れ、〇〇さんなりに感じたことを素直な言葉で表現できました。
- 「いのちを たべる」ことの意味を考え、給食の「いただきます」に、より一層感謝の気持ちを込めるようになりました。
- 「むしと なかよし」の学習で、小さな虫にも命があることを知り、大切に扱おうとする優しい心が育っています。
- 「がんばる ひとって かっこいい」と、オリンピック選手の姿に感動し、自分も努力することの素晴らしさを感じたようです。
- 「ふしぎだな と おもう きもち」を大切にし、空の青さや星の輝きに興味を持つ、知的好奇心の高まりが見られます。
- 「ありがとう いのち」というテーマで、自分を支えてくれる全ての命への感謝の気持ちを、絵と文で表現しました。
- 「おじいちゃんの ちえ」のような、昔からの言い伝えや知恵に触れ、先人のすごさに感心していました。
道徳 所見文例 3年生(中学年)

3年生からは中学年となり、抽象的な思考が少しずつできるようになります。「自分」と「他者」の視点から一歩進み、「集団の中の自分」を意識し始めます。グループでの話し合い活動が増え、友達の意見を聞いて自分の考えを深める姿が見られるようになります。
3年生:A視点(自己)文例
- 「正直・誠実」について、自分の体験と重ね合わせ、勇気を持って正しいことを行うことの難しさと大切さを、真剣な表情で発表しました。
- 「自分のことは自分で」という意識が高まり、学習の準備や宿題など、言われる前に自分で考えて行動しようとする姿に成長を感じます。
- 「わがままな心」と向き合う資料を読み、自分の気持ちをコントロールすることの大切さを学び、日常生活で実践しようと努めています。
- 「目標に向かって」努力する主人公の姿に共感し、自分が頑張っている習い事や勉強への意欲を新たにしていました。
- 「失敗してもあきらめない」というテーマで、失敗から学ぶことの重要性に気づき、前向きに挑戦しようとする気持ちが芽生えています。
- 「健康な生活」について、睡眠や栄養のバランスを考え、自分の生活習慣を見直すワークシートに熱心に取り組んでいました。
- 「自分らしさ」について、自分の長所を活かして何ができるかを考え、自信を持って発言することができました。
- 「正しいと信じること」を行う勇気について、グループで活発に議論し、〇〇さんなりの考えを深めていました。
- 「時間を大切に」使うことについて、自分の時間の使い方を振り返り、計画的に行動しようと意識し始めました。
- 「つつましい生活」について、物やお金を大切に使うことの意味を考え、無駄遣いをしないよう心がけようとしています。
3年生:B視点(他者)文例
- 「相手の気持ちを考える」学習で、グループの友達の意見に真剣に耳を傾け、「なるほど」と共感しながら自分の考えを深めていました。
- 「本当の友達」とは何かを話し合い、上辺だけではない、互いを思いやることの大切さに気づいたようです。
- 「親切」の授業で、相手が本当に求めていることを考えて行動することの難しさを知り、深い思いやりについて学んでいます。
- 「家族への感謝」の授業で、家族が自分のためにしてくれていることを具体的に思い出し、感謝の気持ちを手紙に綴っていました。
- 「礼儀正しいふるまい」について、TPOに応じた言葉遣いや態度を学び、日々の挨拶がより丁寧になりました。
- 「ちがう意見もたいせつに」というテーマで、自分と異なる考えを尊重し、話し合いで合意点を見出すことの重要性を学びました。
- 「お年寄りへのいたわり」について、具体的な行動を考え、地域の方々との関わり方を見直すきっかけとなりました。
- 「信頼される人」になるために、約束を守ることや正直であることの大切さを、自分の言葉でしっかりと発表できました。
- 「謙虚な心」について、自分の力をひけらかさず、他人の良さを素直に認めることの素敵さを学びました。
- 「国際理解」の第一歩として、外国の文化に触れ、自分たちとの違いを「面白い」と肯定的に受け止めていました。
3年生:C視点(集団・社会)文例
- 「みんなのために」働くことの喜びについて、係活動や当番活動での自分の役割と重ね合わせ、責任感を持って取り組む意欲が高まりました。
- 「きまりはなぜあるの」という問いに、集団生活をスムーズにするための「共通のルール」だと理解し、主体的に守ろうとする姿勢が見られます。
- 「公平な分け方」について議論し、全員が納得できる方法を粘り強く考える姿から、公正さへの意識の芽生えを感じました。
- 「地域の人々とのつながり」について学び、自分たちが多くの人に支えられていることを実感し、感謝の気持ちを深めました。
- 「公共の場所でのマナー」について、自分たちの行動が周りにどう影響するかを想像し、責任ある行動を心がけようとしています。
- 「家族の一員として」の役割を考え、自分も家事を分担しようとするなど、家庭での責任感を持ち始めています。
- 「日本の伝統文化」として、地域の祭りの意味を調べ、郷土への愛着を深めている様子がうかがえました。
- 「働くことの意義」について、様々な職業の人の話を聞き、社会が多くの仕事で成り立っていることを学びました。
- 「正義」について、いじめや差別は許されないことだと強く感じ、勇気を持って行動することの大切さを議論しました。
- 「ボランティア活動」に関心を持ち、自分たちにもできる身近な奉仕(ゴミ拾いなど)について考えることができました。
3年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- 「命のつながり」について、食べ物を通して多くの命をいただいていることに気づき、残さず食べようとする意識が一層高まりました。
- 「生きていることのすばらしさ」を感じる資料を読み、自分が今、元気でいられることへの感謝の気持ちをノートに綴っていました。
- 「自然のめぐみ」の学習で、水や空気が当たり前ではないことに気づき、節水や節電を心がけようとする姿が見られます。
- 「美しいもの」に触れる活動で、〇〇さん自身が「きれいだ」と感じる風景や音楽について、その理由を自分の言葉で表現できました。
- 「動物や植物もともだち」という意識が芽生え、校庭の草花や虫にも優しく接する姿は、心が温かくなります。
- 「偉人(いじん)の生き方」に触れ、困難にも負けずに努力を続けた姿に感動し、自分も頑張ろうと目を輝かせていました。
- 「いのちのたんじょう」の学習で、自分が生まれてきたことの奇跡を知り、命の大切さを深く感じ入っていました。
- 「自然を大切に」する活動で、リサイクルの重要性を学び、環境問題に初めて関心を持ったようです。
- 「人間の知恵」として、昔の道具や建物の工夫に驚き、先人たちへの尊敬の念を抱いていました。
- 「感動する心」を大切にし、友達の素晴らしい発表やスポーツ選手の活躍に、素直に「すごい」と拍手を送ることができます。
道徳 所見文例 4年生(中学年)

4年生は、中学年のまとめの時期です。物事を多角的に見たり、公正さや正義感といった、より抽象的な概念についても深く考えられるようになります。グループでの議論も活発になり、自分の考えを整理して述べたり、友達の意見と比較検討したりする姿を捉えます。
4年生:A視点(自己)文例
- 「目標に向かって」努力することの価値を学び、自分の苦手なこと(例:跳び箱)にも諦めずに挑戦しようとする意欲がノートから伝わってきました。
- 「自分の弱さ」と向き合う主人公の姿に、自分の体験を重ね合わせ、「勇気とは何か」について深く考察していました。
- 「節度ある生活」について、メディアとの付き合い方をグループで話し合い、自分でルールを決めることの重要性に気づきました。
- 「自分らしさを伸ばす」というテーマで、自分の個性や長所を認め、それをどう活かしていくかを前向きに考えることができました。
- 「正直な心」について、嘘がもたらす結果を想像し、誠実であることの難しさと大切さを、真剣な議論を通して学んでいました。
- 「あきらめない心」を持つことの意義について、失敗を恐れずに挑戦し続けるスポーツ選手の姿から学び、感銘を受けていました。
- 「希望をもって」未来を考える学習で、自分の将来の夢について、生き生きとした表情で語る姿が印象的でした。
- 「自律的な生活」を意識し、学習計画を自分で立てるなど、自己管理能力を高めようと努力する様子が見られます。
- 「謙虚さ」について、自分の成果を誇るのではなく、支えてくれた人への感謝を忘れないことの大切さを学びました。
- 「よりよく生きる」とは何かを考え始め、日々の生活をただ過ごすのではなく、目的意識を持つことの大切さに気づき始めています。
4年生:B視点(他者)文例
- 「友情・信頼」について、友達と意見がぶつかった時の対応を真剣に考え、相手を理解しようと努めることの大切さを発表しました。
- 「親切」の授業で、「おせっかい」と「本当の親切」の違いについて深く議論し、相手の立場に立つことの重要性を再認識していました。
- 「感謝の気持ちを伝える」ことの大切さを学び、日頃の感謝を具体的な行動で示そうと、学級活動でも積極的に動くようになりました。
- 「異文化理解」の学習で、外国の習慣や考え方に触れ、多様性を受け入れることの面白さや難しさについて考えることができました。
- 「礼儀」の授業で、言葉遣いだけでなく、態度や表情が相手に与える影響について考え、コミュニケーションの奥深さを学びました。
- 「寛容な心」を持つことについて、自分と違う意見を頭ごなしに否定せず、まずは最後まで聞く姿勢が身についてきました。
- 「尊敬する心」について、身近な人(家族や先生)の良いところを見つけ、それを素直に尊敬できる〇〇さんの心の素直さを感じました。
- 「友達との協力」の重要性を学ぶ活動で、一人ではできないことも、力を合わせれば達成できるという喜びを実感したようです。
- 「思い込みや偏見」がもたらす問題について学び、物事を多面的に見ることの重要性に気づきました。
- 「温かい人間関係」を築くため、日常的に「ありがとう」「ごめんね」を素直に言い合えるクラスの雰囲気づくりに貢献しています。
4年生:C視点(集団・社会)文例
- 「公正・公平」な態度とは何かを議論し、多数決だけが最善の解決方法ではないと気づき、少数意見を尊重する姿勢を学びました。
- 「規則の意義」について、自分たちのクラスのルールを見直し、なぜそれが必要なのかを主体的に考えることができました。
- 「社会への貢献」として、地域の清掃活動やボランティアに参加した人の話を聞き、自分にもできることを探し始めました。
- 「家族の一員」としての役割について、3年生の時よりも一歩進んで、自分が家族を支えるという視点を持つようになりました。
- 「郷土の伝統」を守る人々の努力を知り、自分たちの住む町への誇りと愛着を深めている様子がうかがえました。
- 「情報モラル」について、インターネットの便利な点と危険な点を学び、責任ある情報発信の重要性を理解しました。
- 「正義の実現」について、いじめを見過ごさない勇気や、困っている人を助ける行動力について、熱心に議論を交わしていました。
- 「働くことの尊さ」について、様々な職業の人の苦労ややりがいを知り、将来の自分の姿を想像していました。
- 「国や郷土を愛する心」について、日本の良いところや文化の素晴らしさを再発見し、日本人としての自覚を持ち始めています。
- 「公徳心」の学習で、公共の物を大切に使うことや、周りの人に迷惑をかけない行動を、具体的に実践しようと努めています。
4年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- 「生命の尊さ」について、病気と闘う人の姿を通して、今、自分が生きていることの奇跡と感謝の気持ちを深く感じていました。
- 「自然の偉大さ」に触れ、台風や地震などの自然災害の恐ろしさと、それに対する人間の知恵や備えの大切さを学びました。
- 「環境保全」の学習で、地球温暖化やゴミ問題が、自分たちの生活と密接に関わっていることを知り、節電やリサイクル活動に意欲を見せています。
- 「美しいものへの感動」として、芸術作品や音楽に込められた作者の思いを想像し、〇〇さんなりに受け取った感動を言葉で表現しました。
- 「人間の力を超えたもの」への畏敬の念として、宇宙の広がりや生命の誕生の神秘に触れ、知的好奇心を高めていました。
- 「先人の努力」によって今の便利な生活があることに気づき、歴史や伝統を受け継ぐことの大切さを感じ取っています。
- 「生きる喜び」について、日々の小さな幸せ(友達との会話、美味しい給食など)を見つける活動を通して、前向きな気持ちを育んでいます。
- 「動植物への愛情」が深く、理科の観察などでも、生き物を丁寧に扱い、その命を尊重する態度が見られます。
- 「困難を乗り越えた人の生き方」に感動し、自分も困難に直面した時に、希望を失わず努力したいと強く感じたようです。
- 「死」という重いテーマにも真剣に向き合い、限りある命をどう大切に生きるかについて、深く考えるきっかけとなりました。
道徳 所見文例 5年生(高学年)

5年生になると、高学年としての自覚が芽生え、より内省的な思考や、社会的な視点からの考察が深まります。抽象的な議論にも主体的に参加し、自分の生き方や社会との関わりについて、自分の言葉で論理的に表現しようとする姿が見られます。
5年生:A視点(自己)文例
- 「自由と責任」の学習で、自由には責任が伴うことを深く理解し、高学年としての自分の行動を見直すきっかけとなったようです。
- 「自主・自律」の精神について、人に言われて行動するのではなく、自分で判断し、責任を持って行動することの重要性を学んでいます。
- 「自分の弱さの克服」というテーマで、自分の短所を客観的に分析し、それをどう乗り越えていくかを具体的にノートに記述していました。
- 「向上心」を持ち、現状に満足せず、さらに高い目標に向かって努力することの価値について、真剣に議論していました。
- 「誠実な生き方」とは何かを問い、目先の利益にとらわれず、良心に従って行動することの大切さを、資料を通して学んでいました。
- 「希望と勇気」を持ち、困難な状況でも前向きに生きようとする主人公の姿に、〇〇さん自身の悩みと重ね合わせ、深く共感していました。
- 「節度ある生活」について、情報機器との適切な距離の取り方を真剣に考え、自分なりのルールを確立しようと努力しています。
- 「個性の伸長」について、自分の良さを認めると同時に、他者の個性も尊重することの重要性を、グループ討議で深めていました。
- 「将来の夢」について、憧れだけでなく、その実現のために今何をすべきかを具体的に考え、学習意欲の向上にもつながっています。
- 「自己肯定感」を高める活動で、自分の存在価値を認め、自信を持って行動しようとする前向きな姿勢が見られました。
5年生:B視点(他者)文例
- 「本当の友情」について、友達を信じること、そして時には厳しく指摘し合うことの重要性を、熱心な議論の中で見出していました。
- 「家族への感謝」の授業で、普段は照れくさくて言えない家族への思いを、自分の言葉で真剣に綴っており、内面の成長を感じました。
- 「相互理解と寛容」について、文化や価値観の違いを乗り越えて理解し合うことの難しさと尊さを、国際的な視点から学んでいました。
- 「礼儀」の授業で、形だけではない、相手への敬意や思いやりが伴ってこそ本物であると、深く理解した発言がありました。
- 「謙虚な心」について、実力があってもおごらず、他者の意見に耳を傾けることの大切さを、偉人の姿から学んでいました。
- 「思いやり」の学習で、相手の立場を深く想像し、「自分ならどうするか」を具体的に考え、行動に移そうとする意欲が見られます。
- 「信頼」を築くことの難しさと、それを失うことの重さを知り、日々の言動に責任を持とうとする意識が高まりました。
- 「言葉の重み」について、何気ない一言が人を傷つける可能性を学び、相手を思いやるコミュニケーションを心がけようとしています。
- 「尊敬」の念について、年齢や立場に関わらず、その人の素晴らしい行いや生き方に対して素直に敬意を表せる、〇Oさんの心の豊かさを感じます。
- 「温かい人間関係」を築くため、クラス内で孤立しがちな友達にも積極的に声をかけるなど、リーダーシップを発揮し始めています。
5年生:C視点(集団・社会)文例
- 「社会参画」について学び、自分たちが社会の一員として何ができるかを真剣に議論し、アルミ缶回収などの活動に主体的に取り組んでいます。
- 「公正・公平」の実現について、社会の中にある不平等な問題に目を向け、自分なりの考えを論理的に述べることができました。
- 「規則の意義」について、高学年として下級生の手本となるため、学校のルールを主体的に守り、その意味を問い直していました。
- 「勤労の尊さ」について、様々な職業の人の社会的な役割と苦労を知り、働くことへの感謝と尊敬の念を深めました。
- 「郷土愛」の学習で、地域の歴史や文化の素晴らしさを再発見し、それを未来に伝えていきたいという思いを強く持ったようです。
- 「情報モラル」について、フェイクニュースの見分け方やSNSの適切な使い方を学び、情報を正しく活用する力を高めています。
- 「法やきまりの尊重」について、なぜ法律が必要なのかを、社会の秩序維持という観点から理解を深めました。
- 「家族の一員として」の役割を深く考え、家庭内での自分の責任を果たそうと、お手伝いにも意欲的に取り組んでいます。
- 「正義」の実現のため、いじめなどの問題に対して「傍観者にならない」という強い意志を、グループ討議で表明しました。
- 「愛国心」について、日本の伝統や文化の良さを学ぶだけでなく、国際社会における日本の役割についても考えることができました。
5年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- 「生命の尊さ」について、医療現場や災害救助の資料を通して、命を救うために尽力する人々の姿に深く感動していました。
- 「自然環境の保全」について、地球規模での環境問題を自分事として捉え、節水やゴミの分別など、実践的な行動に移しています。
- 「感動する心」の豊かさを持ち、音楽や芸術作品に触れた際、その背景にある作者の思いまで想像しようと努めていました。
- 「畏敬の念」について、宇宙の神秘や生命の誕生の奇跡に触れ、人間の知識には限界があることを謙虚に受け止めていました。
- 「人間の気高さ」について、私利私欲を捨てて他者のために尽くした人物の生き方に感銘を受け、自分の生き方を見つめ直していました。
- 「生きる喜び」とは何かを問い、困難な中でも希望を見失わずに生きることの価値を、自分なりに解釈しようと努力していました。
- 「科学技術の進歩と倫理」について、便利さの裏にある問題点(例:AIと人間の関係)についても、批判的に考える視点を持っています。
- 「死」というテーマにも真摯に向き合い、限りある命を精一杯生きることの大切さを、静かに受け止めている様子でした。
- 「自然との共生」について、人間の都合だけでなく、他の生物の生きる権利も尊重することの重要性を学んでいます。
- 「崇高な生き方」に触れ、自分も将来、誰かの役に立てるような人間になりたいという、高い志を持つようになりました。
道徳 所見文例 6年生(高学年)

6年生は、小学校生活の集大成です。道徳の授業を通して、これまでの学びを統合し、「自分の生き方」について深く考察します。中学校への進学や将来の夢を見据え、最高学年としての責任感や、他者・社会への感謝と貢献の意識を、自分の言葉で表現する姿を捉えます。
6年生:A視点(自己)文例
- 「自分の弱さを乗り越える」というテーマで、卒業を前にした自分の課題(例:人前で話すこと)と向き合い、誠実に努力しようとする姿は立派です。
- 「最高学年としての自覚」を持ち、自主的に行動することの意義を深く理解し、学校行事などでもリーダーシップを発揮しました。
- 「誠実な生き方」について、たとえ誰も見ていなくても、自分の良心に従って行動することの価値を、6年間の学びの集大成として語りました。
- 「未来への希望と勇気」を持ち、中学校生活への不安と期待を語り合い、困難も乗り越えていこうとする前向きな姿勢を見せました。
- 「感謝の心」を忘れず、6年間お世話になった人々への思いを、卒業文集や発表会で、自分の言葉で堂々と表現できました。
- 「個性の尊重」について、自分らしさを大切にすると同時に、多様な他者とどう協働していくかという、高度な議論ができました。
- 「克己心」の重要性を学び、誘惑に負けそうな自分を律し、目標(例:受験勉強)に向かって努力を続ける強い意志が育っています。
- 「謙虚な心」を持ち、自分の成長は多くの支えがあったからこそだと理解し、驕らない態度で物事に取り組むことができます。
- 「より高い目標を目指す」向上心があり、現状に満足せず、常に自分を高めようとする知的な探究心は、中学校でも大いに伸びるでしょう。
- 「自己の生き方」を真剣に問い直し、将来どのような人間になりたいか、そのために今何をすべきかを、深く内省していました。
6年生:B視点(他者)文例
- 「本当の友情」について、6年間の思い出を振り返り、時にはぶつかり合いながらも、互いを尊重し合うことの本当の意味をかみしめていました。
- 「家族への深い感謝」を胸に、思春期特有の照れくささを乗り越え、自分の言葉で家族への思いを真摯に伝えようと努力していました。
- 「寛容の精神」について、自分と異なる意見や立場の人を排除するのではなく、どうすれば共生できるかを、粘り強く議論していました。
- 「礼儀」の根底にある「相手への敬意」を深く理解し、下級生に対しても、また先生方に対しても、模範となる態度で接することができました。
- 「思いやり」の行動を、偽善と批判されることを恐れずに実行することの勇気について、熱心に討議しました。
- 「相互理解」のために、言葉だけでなく、文化や背景の違いを学ぶことの重要性を、国際的なニュースと関連付けて考察しました。
- 「信頼される人間」として、最高学年としての役割(例:委員会活動)を、責任を持って最後までやり遂げる姿は頼もしかったです。
- 「言葉の力」を信じ、人を励まし、勇気づけるポジティブなコミュニケーションを、クラス全体に広げようと努めてくれました。
- 「尊敬」する人物について、その人の生き方や哲学を学び、自分のロールモデルとして目標にしようとする姿勢が見られます。
- 「下級生への思いやり」として、縦割り活動などで優しくリードし、良き先輩としての姿を示すことができました。
6年生:C視点(集団・社会)文例
- 「より良い社会を築くために」という議論で、最高学年として、下級生や学校全体のために何ができるかを主体的に考え、実行に移しました。
- 「公正・公平と正義」について、社会にある差別や偏見の問題に目を向け、自分たちに何ができるかを真剣に議論する姿に成長を感じました。
- 「規則の尊重と創造」について、既存のルールを守るだけでなく、必要に応じてより良く変えていくことの重要性にも気づきました。
- 「勤労と社会奉仕」の意義を深く理解し、卒業プロジェクトとして、お世話になった地域や学校への感謝を形にする活動をリードしました。
- 「郷土の発展に尽くした先人」の努力を知り、自分も将来、地域社会に貢献したいという高い志を持つようになりました。
- 「情報社会における責任」として、SNSでの発信が社会に与える影響を考え、デマや誹謗中傷に加担しない強い倫理観を育んでいます。
- 「法やルールの遵守」が、自分たちの自由や権利を守るために不可欠であることを、具体的な事例を通して深く理解しました。
- 「家族の一員としての責任」を自覚し、中学校進学を前に、家庭内での自分の役割を積極的に見直そうとしています。
- 「国際社会における日本の役割」について、平和や環境問題など、地球規模の課題解決にどう貢献すべきかを考察しました。
- 「愛国心」について、自国の文化や伝統を誇りに思うと同時に、他国への敬意も忘れない、バランスの取れた考えを持つことができました。
6年生:D視点(生命・自然・崇高)文例
- 「かけがえのない生命」というテーマで、6年間の成長を振り返り、自分を支えてくれた全ての命への感謝の気持ちを、感動的に発表しました。
- 「自然との共生」について、環境問題が未来の自分たちに直結する課題であると捉え、持続可能な社会のために行動しようと決意しています。
- 「崇高なものへの畏敬の念」に触れ、人間の力を超えた存在や、先人たちの偉業に対する謙虚な尊敬の念を深めていました。
- 「芸術の力」について、音楽や絵画が人々の心を癒し、勇気づける役割を持つことを、自分たちの合唱コンクールの経験と重ねて語りました。
- 「人間の気高さ」とは、困難な状況でも他者への思いやりを失わないことだと学び、そのような強く優しい心を持ちたいと強く願っています。
- 「生きる喜び」について、卒業を前に、友達と過ごす何気ない日常の尊さに気づき、一日一日を大切にしようとする姿が見られます。
- 「科学技術の発展と倫理」について、命の操作やAIの進化など、難しい問題にも、自分なりの倫理観を持って向き合おうと努めていました。
- 「死」と向き合った資料を通し、残された時間をどう生きるか、自分の「使命」は何かを、深く内省するきっかけとなりました。
- 「先人の知恵」や「文化遺産」の価値を理解し、それらを次世代に引き継ぐ責任があることを自覚しました。
- 「よりよく生きる」とは何か、その答えを道徳の授業だけでなく、小学校生活全てを通して探し続けてきた、その探究心に大きな成長を感じます。
道徳 所見文例 中学校

中学校の道徳は、小学校での学びを基盤とし、思春期特有の悩みや自己同一性の確立、より複雑化する社会問題と向き合います。抽象的な議論が中心となり、自己の内面と深く向き合い、自分の生き方を確立しようとする姿を、多角的・多面的に捉えることが重要です。(ここでは、中学校1年・2年・3年の特徴と、視点別の文例をまとめて紹介します)
中学校:A視点(自己)文例
- (中1)「個性の伸長」について、自分らしさと集団の調和の間で悩みながらも、他者との違いを認め、自己を確立しようと真剣に模索しています。
- (中1)「節度ある生活」について、部活動と勉強の両立の難しさに直面し、タイムマネジメントの重要性を自覚し、改善しようと努力しています。
- (中2)「自主・自律」の精神が芽生え、校則や親の意見に対し、自分の考えを論理的に述べようとする姿に、精神的な自立が見られます。
- (中2)「克己心」の学習では、誘惑に負けそうな自分の弱さを客観視し、それを乗り越えるための具体的な方策を、グループで真剣に議論していました。
- (中3)「将来の生き方」について、進路選択という現実的な問題と向き合い、社会的な意義と自分の適性を真剣に考察していました。
- (中3)「誠実さ」について、受験勉強のプレッシャーの中で、公正な努力を続けることの価値を、自分に言い聞かせるように語っていました。
- (全学年)「向上心」を持ち、自分の限界を決めつけず、知的な探究心を持って学習や部活動に取り組む姿勢は、他の生徒の模範となっています。
- (全学年)「希望と勇気」を失わず、困難な課題(例:友人関係、学習の壁)に直面しても、粘り強く解決の糸口を探ろうと努力しています。
- (全学年)「自己肯定感」について、自分の短所も含めて受け入れ、自分らしい生き方を模索しようとする内面的な強さが育っています。
- (全学net)「哲学的な問い」(例:なぜ勉強するのか)にも、自分なりの答えを見出そうと、深く内省する姿が見られます。
中学校:B視点(他者)文例
- (中1)「本当の友情」について、小学校とは異なる多様な人間関係の中で、うわべだけではない、信頼に基づいた関係を築こうと努力しています。
- (中1)「異性理解」について、思春期特有の照れくささを乗り越え、互いの人格を尊重し合う態度を学んでいます。
- (中2)「相互理解と寛容」について、SNS上のすれ違いや対立の事例を通し、相手の背景を想像することの重要性を、痛感したようです。
- (中2)「謙虚な心」を持ち、自分の意見を主張しつつも、異なる意見の妥当性にも耳を傾ける、バランスの取れた議論ができるようになりました。
- (中3)「家族への感謝」について、自立への意識が高まる一方で、自分を支えてくれる家族の存在の大きさを再認識し、素直に感謝を表現できました。
- (中3)「恋愛と人間関係」について、相手の人格を尊重することの重要性を学び、誠実な関係性について深く考えていました。
- (全学年)「礼儀」の本質が、相手への敬意にあることを理解し、先輩・後輩、教師との間で、適切なコミュニケーションを実践できています。
- (全学年)「思いやり」の行動が、時に「偽善」と捉えられる難しさについて議論し、それでも行動する勇気の大切さを確認しました。
- (全学年)「信頼」関係の構築のため、日々の約束や責任を果たすことの積み重ねが不可欠であることを、体験的に学んでいます。
- (全学年)「多様性の尊重」について、性的マイノリティや障害の有無など、様々な違いを「個性」として受け入れる、成熟した視点が育っています。
中学校:C視点(集団・社会)文例
- (中1)「集団生活のルール」について、なぜ校則が必要なのかを主体的に議論し、自分たちの手でより良い学校生活を創ろうとする意欲が見られます。
- (中1)「家族の一員として」の役割を自覚し、自分の進路や生活態度について、家族と真剣に話し合おうとする姿勢が見られます。
- (中2)「社会正義」について、世の中の不合理な点(例:貧困、差別)に目を向け、自分たちに何ができるかを熱く議論する姿に、社会意識の高まりを感じます。
- (中2)「勤労の意義」について、職場体験学習を通して、働くことの厳しさとやりがいを実感し、将来の職業観を深めました。
- (中3)「社会への貢献」について、自分の進路選択が「誰かの役に立つ」こととどう結びつくのかを、真剣に考察し、発表しました。
- (中3)「法やルールの遵守」について、選挙権年齢の引き下げなども視野に入れ、社会のルール作りに参画する意識が芽生えています。
- (全学年)「情報モラル」について、情報の真偽を見極める力(メディアリテラシー)の重要性を、具体的な事例から学んでいます。
- (全学年)「郷土愛・愛国心」について、自国の文化や伝統を誇りに思うと同時に、グローバルな視点で他国との協調の必要性も理解しています。
- (全学年)「公正・公平」な社会の実現のため、身近な場面での差別や偏見を見過ごさない、強い倫理観を持っています。
- (全学年)「ボランティア活動」の意義を理解し、自己満足ではなく、本当に相手のためになる支援とは何かを深く考えています。
中学校:D視点(生命・自然・崇高)文例
- (中1)「生命の尊さ」について、思春期の心の揺れ動きの中で、自己の存在価値について悩み、命の大切さを改めて見つめ直していました。
- (中1)「自然との触れ合い」を通して、デジタル社会から離れ、五感で自然の美しさや厳しさを感じる体験の重要性に気づきました。
- (中2)「感動・畏敬の念」について、芸術作品や偉人の生き方に触れ、その圧倒的な存在感に心を揺さぶられる豊かな感受性を持っています。
- (中2)「環境問題」を、地球規模の課題として捉え、持続可能な開発目標(SDGs)と関連付け、自分たちの生活を見直す活動に意欲的です。
- (中3)「人間の気高さ」について、困難な運命に立ち向かい、他者のために生きた人々の姿に深く感銘を受け、自分の生き方を問い直していました。
- (中3)「科学技術の進歩と倫理」について、遺伝子操作やAIの進化がもたらす光と影について、批判的な視点を持って議論することができました。
- (全学年)「死生観」について、身近な人の死や災害のニュースを通して、限りある命をどう充実させるか(Well-being)を真剣に考えています。
- (全学年)「文化や伝統の継承」の意義を理解し、先人たちが築き上げてきたものへの尊敬の念を深めています。
- (全学年)「生きる喜び」とは何か、日常の小さな出来事にも感謝し、前向きに生きようとする哲学的な思索を深めています。
- (全学年)「人間の力を超えたもの」への謙虚な気持ちを持ち、科学だけでは説明できない領域があることを認め、多角的に物事を捉えようとしています。
まとめ
15000字を超えるボリュームで、道徳 所見文例を小学校一年生から中学校まで、学年別・視点別にご紹介しました。「特別の教科 道徳」の所見は、児童・生徒を「評価」するためではなく、その子の内面的な成長を認め、励まし、次のステップへと導くための「メッセージ」です。
この記事で紹介した多くの文例は、あくまで「型」です。大切なのは、これらの文例を参考にしつつも、目の前にいる「その子」の具体的な授業中の発言、ノートの記述、友達との関わり、そして表情の変化を思い出し、その子「だけ」の成長の物語を、先生自身の言葉で綴ることです。
道徳の所見作成は、児童・生徒一人ひとりと真剣に向き合う、教師にとって非常に重要で、やりがいのある仕事です。この記事が、先生方のその尊い仕事の一助となることを心から願っています。
「特別の教科 道徳」の学習指導要領や詳細については、以下の文部科学省の公式サイトも合わせてご参照ください。
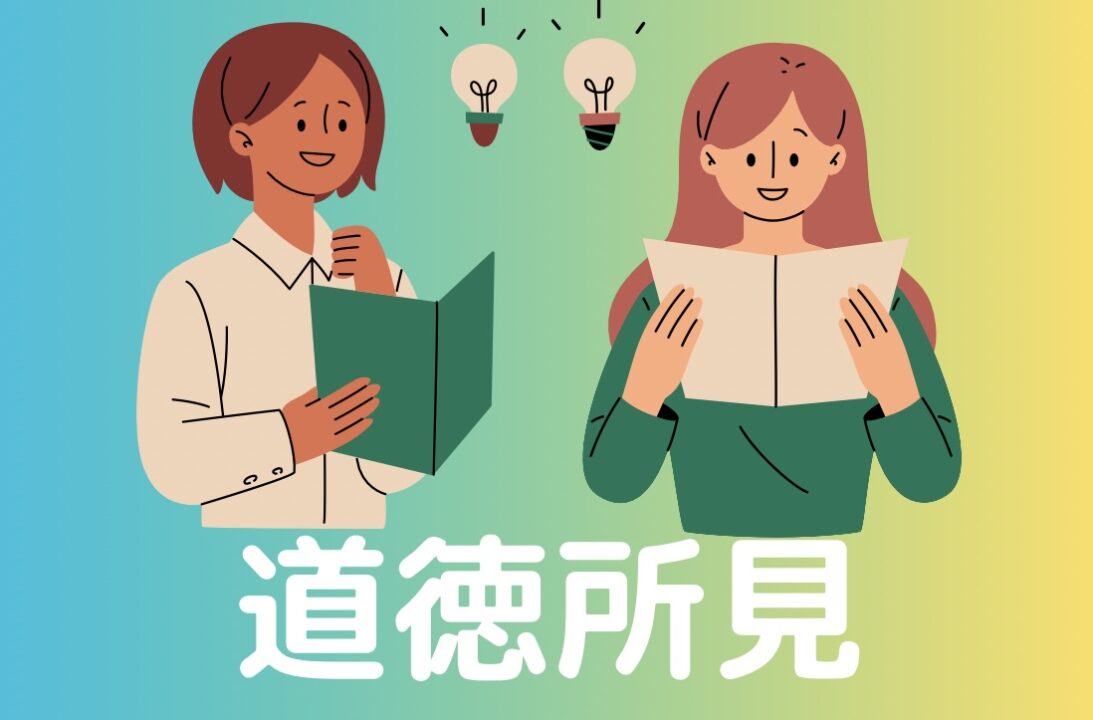


コメント