朝の会は、子どもたちが笑顔で1日を始めるための大切な時間です。特に、環境の変化に敏感だったり、自分の気持ちをうまく表現するのが苦手な子どもたちにとって、ここで気持ちを整えることが、その後の学習や友達との関わりに大きく影響します。
「今日はなんだか気持ちが落ち着かないな…」「友達との関わりで少し不安を感じている子がいるな…」。先生方は、きっとそんな子どもたちの小さなサインに気づいているはずです。そんな時、どうすれば子どもたちが安心して、ポジティブな気持ちで1日をスタートできるでしょうか?
この記事では、
- 朝の会にぴったりの特別支援学級の自立活動に活用できるSST(ソーシャルスキルトレーニング)ゲーム(ネタ)を5つ紹介します。
- どれも短時間(5分程度)で実施でき、感情理解やコミュニケーション力を育む内容を中心に厳選しました。
※他のSSTゲームの紹介記事もあります。詳しくはこちら👉 【感情の理解】自立活動におすすめのSSTゲーム5選〜気持ちを知る・伝える
自立活動ネタ1「今日の気持ち天気」
ねらい
自分の気持ちに気づき、言葉や視覚的な手がかりで表現する練習。感情の言語化、自己開示の促進。
やり方
ホワイトボードや模造紙に「晴れ」「くもり」「雨」「雷」などの天気マークを用意します。子どもたちは、今日の自分の気分に一番近い天気マークを一つ選び、もし可能であれば「なぜその気持ちなのか」を一言伝えてもらいます。例えば、「今日は遠足だから、気持ちは晴れです!」や、「ちょっと眠いから、くもりかな…」といった具体的な理由でも構いません。
ポイント
天気マークという視覚的な選択肢があるため、まだ言語での表現が難しい低学年の子どもや、言葉にするのが苦手な子どもも抵抗なく参加しやすいのが特長です。毎日続けることで、子どもたちが自分の気持ちの変化に気づき、感情のグラデーションを理解するきっかけにもなります。「今日は雨だったけど、明日は晴れるといいね」といった声かけで、気持ちの切り替えや未来への希望を育むこともできます。
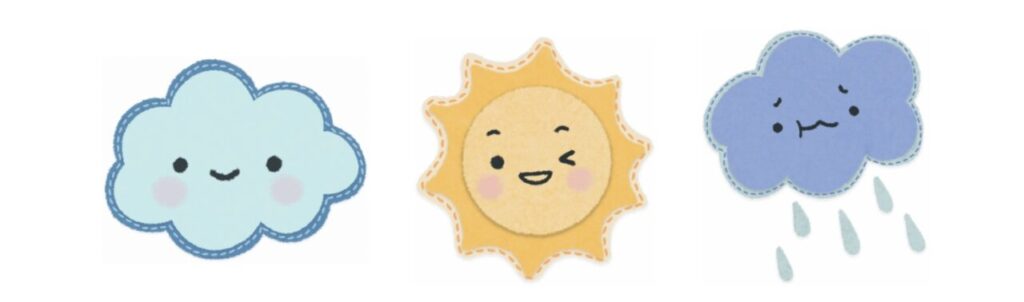
実践例
ある日、いつも元気に挨拶してくれるA君が、珍しく「雨」のマークを選びました。理由を聞くと「昨日、おもちゃが壊れちゃったんです…」と小さな声で教えてくれました。先生が「そっか、それは悲しいね。でも、今日は楽しいことを見つけて、少しでも気分が晴れるといいね」と声をかけると、少しだけ顔が明るくなりました。このように、子どもの小さな心のサインに気づき、寄り添うきっかけにもなります。
参考記事
自立活動ネタ2「 わたしのトリセツミニ発表」
ねらい
自己理解と他者理解の促進、互いの個性を尊重する姿勢の育成。
やり方
事前に用意した「わたしのトリセツ」ワークシート(※)をもとに、朝の会で毎日1人ずつ「ぼくの好きなこと」「こういう時に助けてほしい」「苦手なこと」など、項目の中から一つだけ選んで紹介してもらいます。発表時間は1人1分程度で十分です。
(※「わたしのトリセツ」ワークシートは、あらかじめ子どもたちに記入してもらい、自己分析を促すものです。例えば、「得意なこと」「苦手なこと」「好きな食べ物」「困ったときにどうしてほしいか」などの項目があります。)
※下記の参考記事からワークシートのDL ができます。
ポイント
毎日少しずつクラスメイトのことを知っていることで、お互いへの理解が深まり、安心感が生まれます。自分のことを話す練習になるだけでなく、友達の多様な「トリセツ」を知ることで、「そうか、この子にはこんな得意なことがあるんだな」「こういう時、こう声をかけてあげたら喜ぶんだな」といった発見があり、お互いを理解し、尊重する気持ちを育みます。クラスのつながりがより一層深まること間違いなしです。
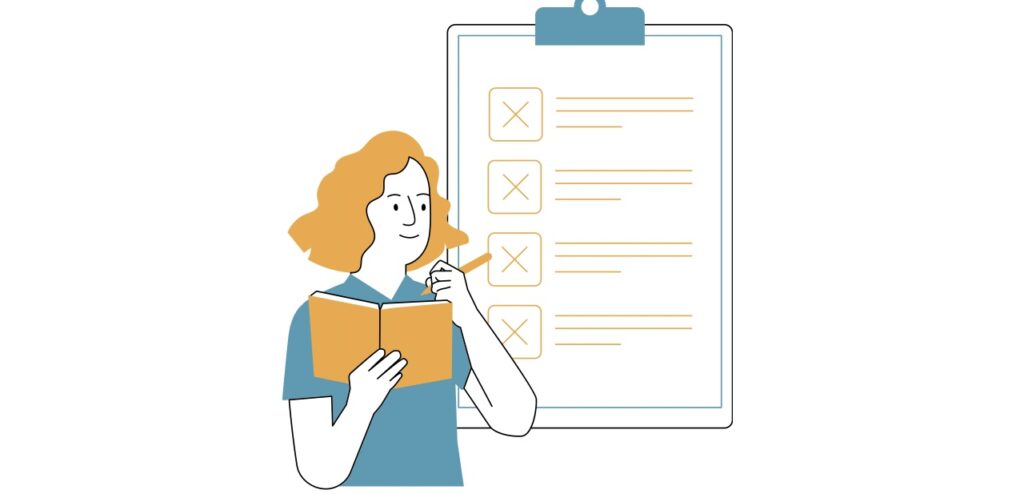
実践例
「僕のトリセツは、絵を描くのが大好きです!」と発表したB君。それまで彼の絵の才能に気づいていなかった友達から、「すごい!今度見せてほしい!」と声がかかり、B君はとても嬉しそうでした。また、「僕は大きな音にびっくりしやすいから、急に大声を出されると困ります」と発表したC君には、それ以降、周りの友達が声をかける際に少し気を配るようになるなど、具体的な行動の変化が見られました。
参考記事
自立活動ネタ3「こんなときどうする?」ミニクイズ
ねらい
問題解決スキルの向上、多様な意見を受け入れる姿勢の育成、対話を通じたコミュニケーション能力の向上。
やり方
日常生活で起こりうる短い場面設定を提示し、「こんなとき、あなたならどうする?」と全員で考え、意見を出し合います。例えば、「友達に文房具を貸してほしいと頼まれたけど、今自分も使っているとき、どうする?」や、「廊下で困っている様子の先生を見かけたら、どうする?」など、具体的なシチュエーションを提示します。

ポイント
このゲームの最も大切なポイントは、答えは一つではないということです。子どもたちが出す様々な意見を「いいね!」「そんな考え方もあるね!」と肯定的に受け入れる姿勢を先生が示すことで、安心して自分の意見を発信できる場が生まれます。多様な考え方に触れることで、子どもたちの視野が広がり、問題解決能力や臨機応変に対応する力が育まれます。短い時間で気軽に取り組めるので、毎日異なるシチュエーションを提示するのもおすすめです。
実践例
「友達が悲しそうな顔をしているとき、どうする?」というお題に対し、「元気づける」「そっとしておく」「話を聞いてあげる」など、様々な意見が出ました。先生はそれぞれの意見に耳を傾け、「どれも友達を思いやる素敵な行動だね。相手の様子を見て、一番良いと思うことを選ぶのが大切だね」と伝えました。これにより、子どもたちは状況に応じた判断力や、相手への配慮について深く考える機会を得られました。
自立活動ネタ4「ちいさなありがとうをさがそう」
ねらい
ポジティブな視点を持つこと、感謝の気持ちを表現すること、人との関係性を育むこと。
やり方
「昨日ありがとうと思ったこと」や「今朝うれしかったこと」など、身の回りの小さな幸せや感謝の気持ちを思い出してもらい、一言ずつ発表してもらいます。「給食の準備を手伝ってくれた友達にありがとう」「朝、家族が『いってらっしゃい』と言ってくれて嬉しかった」など、日常のささやかな出来事で構いません。
ポイント
無理に全員が話さなくても大丈夫です。「今日は話を聞くだけ」という参加もOKにすることで、発表が苦手な子どもも安心して参加できます。ポジティブな言葉のシャワーを浴びることで、クラス全体の雰囲気が明るくなり、感謝の気持ちが自然と育まれます。日々の生活の中で、良いことや感謝できることに目を向ける習慣が身につき、幸福感の向上にもつながります。
実践例
「朝、お母さんがおいしいお味噌汁を作ってくれて嬉しかったです」という発表に、クラス中が和やかな雰囲気に包まれました。また、ある子が「消しゴムを貸してくれた○○さんにありがとう」と発表すると、名前を呼ばれた子も嬉しそうな顔をしていました。このように、ポジティブな言葉は、話す側も聞く側も温かい気持ちにさせ、クラス全体の人間関係をより良いものにしていきます。
自立活動ネタ5『朝の「Iメッセージ」練習』
ねらい
自分の気持ちを相手に伝える適切な言い方を学ぶこと、感情表現と人間関係を育むこと。
やり方
「Iメッセージカード」(※)を1枚選び、「私は〜と思います」「私は〜と感じました」といった「I(私)」を主語にした形で発表してもらいます。カードの例としては、「私は、友達と遊べて楽しかったです」「私は、昨日テストで良い点が取れて嬉しかったです」「私は、朝起きるのが苦手なので、もう少し早く寝ようと思います」など、様々な感情や状況を表す文章が書かれていると良いでしょう。
(※「Iメッセージカード」は、様々な感情や状況を表す短い文章が書かれたカードです。例えば、「私は、○○の音が大きくてびっくりしました」「私は、友達が手伝ってくれて助かりました」など、具体的な場面を想定した文章があると、子どもたちがより実践的に学ぶことができます。)
ポイント
「相手を責めない伝え方」を少しずつ身につける練習になります。自分の気持ちを適切に伝えることで、人間関係のトラブルを未然に防ぎ、より良いコミュニケーションを築く基礎となります。特に、怒りや不満などのネガティブな感情を伝える際に、相手を攻撃するのではなく、「私はこう感じた」と表現する練習は、子どもたちのソーシャルスキルを大きく向上させるでしょう。日々の生活の中で、様々な感情をIメッセージで表現する機会を設けることが大切です。
実践例
「私は、友達が急に鬼ごっこを始めてびっくりしました」と発表したD君に、先生は「それは驚いたね。どうしてびっくりしたか、もう少し詳しく話せる?」と促しました。D君は、「準備運動してないのに、急に走り出したから、怪我しないか心配になりました」と続け、それまで言葉にできなかった心配の気持ちを表現することができました。この練習を通じて、子どもたちは自分の感情の背景にある考えや願いを掘り下げ、より深く自己理解を深めることができます。
参考記事
おわりに
朝の時間を「心を整える時間」として活用することで、子どもたちの1日がグッと過ごしやすくなります。今回ご紹介したSSTゲームは、特別支援学級だけでなく、通常学級でも朝の会に取り入れやすいものばかりです。
「今日もやってよかった」と感じられる朝の会の工夫として、ぜひ取り入れてみてください。子どもたちの「できた!」という笑顔、そして先生方の「やってよかった!」という達成感が、きっと日々の大きな喜びとなるはずです。ぜひ、今日から一つでも取り入れて、子どもたちとの豊かな朝の時間を育んでみてください。
他にも、
などもぜひご覧ください。
この記事が、先生方と子どもたちの毎日を、より豊かにする一助となれば幸いです。もし、何か実践に関する疑問や、さらに知りたいことがあれば、いつでもご相談ください。
各おすすめの自立活動は、特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。








コメント