私は,子どもたちが主体的に楽しく取り組めるツールとして、ボードゲーム、特に協力型ボードゲームを勧めています。
協力型ボードゲームの最大の魅力は、プレイヤー同士で「勝ち・負け」を競うのではなく、「みんなで共通の目標達成」を目指すところにあります。この構造が、子どもたちの間に自然な助け合いや話し合いを生み出し、自立活動で育みたい様々な力、例えば協調性、コミュニケーション能力、問題解決能力、そして気持ちの調整などを育むのに非常に適しています。
今回は、
自立活動で特に「使える!」と感じた、おすすめの協力型ボードゲームを5つご紹介します。
※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。
いずれも、先生が実際に子どもたちとプレイして手応えを感じたものばかりです。
協力型ボードゲームの中でも、特に情緒面や対人関係の力を育てるうえで効果的だったのが 『スペースエスケープ』 です。実際の授業での活用例や、子どもたちの反応、教師の関わり方のコツについては、こちらの記事で詳しく紹介しています👇
自立活動におすすめの協力型ボードゲーム5選
ここでは、各ゲームの簡単な紹介と、自立活動で特に期待できる効果、そして私が感じたおすすめポイントをお伝えします。
1. おばけキャッチジュニア(Geister Geister Schatzsuchmeister)
かわいいおばけたちと力を合わせて宝探し!

- 対象年齢: 6歳以上
- 特徴: プレイヤー全員でおばけの屋敷を探検し、協力して「呪われた宝物」を運び出すゲームです。サイコロの指示に従っておばけを進めたり、部屋のドアを開けたりしながら進みます。おばけに見つからないように進むための戦略的な相談が鍵となります。
- 自立活動での活用のねらい:
- コミュニケーション力・他者との共感:「次はどのおばけを進める?」「そっちの部屋、大丈夫そう?」など、状況を共有し、お互いの行動に共感する会話が自然に生まれます。
- 焦りのコントロール: おばけが迫ってくるスリル感の中で、慌てずに最善の手を考え、落ち着いて行動する練習になります。
- おすすめポイント: ルールは比較的シンプルで、小さなお子さんでも理解しやすいです。ゲーム展開にスリルがありながらも、イラストが可愛らしく親しみやすい雰囲気なので、楽しく取り組めます。テンポが良いため、集中が続きやすいのも魅力です。
2. ゾンビキッズ(Zombie Kidz Evolution)
学校にゾンビが襲来!みんなで協力して守りきれるか?

- 対象年齢: 7歳以上
- 特徴: ゾンビ(可愛いイラストです)が学校に攻めてくるのを、子どもたちが協力して撃退し、ゲートを閉めるゲームです。最大の特徴は、繰り返しプレイするたびにゲームのルールや内容が進化していく「キャンペーン型」であること!特定の回数プレイしたり、特定のミッションをクリアしたりすると、封筒を開けて新しいルールやカードが追加されます。
- 自立活動での活用のねらい:
- ルール理解の継続: ゲームが進化しても、新しいルールに対応し、理解し続ける力。
- チーム戦略: 増加するゾンビに対し、誰がどこに行くべきか、どのゲートを優先すべきかなど、より複雑なチーム戦略を立てる練習。
- 継続する力: 一度のプレイだけでなく、継続して取り組むことでゲーム全体を進めていく達成感を味わえます。
- おすすめポイント: ゲームが進化するという仕掛けが、子どもたちの「次もやりたい!」という内発的な動機付けを強く刺激します。飽きずに長く楽しめるため、年度を通して取り組む自立活動のテーマとしても適しています。難易度が徐々に上がることで、子どもたちのチームとしての成長も感じられます。
3. にじいろのへび(Regenbogen-Schlange)
カラフルなヘビを長くつなげよう!低学年にもおすすめです。

- 対象年齢: 4歳以上
- 特徴: サイコロの色に従って、ボード上のヘビの頭としっぽを同じ色でつなげていくゲームです。全員で協力して、途切れることなくできるだけ長~いへびを完成させることを目指します。ルールは「サイコロを振る」「同じ色のところにつなげる」と非常にシンプルです。
- 自立活動での活用のねらい:
- 色の認識: 色を正確に見て、同じ色を探す練習になります。
- 順番を待つ練習: 自分の番が来るまで待つ、基本的な活動のルールを学ぶのに最適です。
- 完成を喜ぶ共感: どんどん長くなるへびを見て、「わー!つながった!」「すごーい!」など、協力して一つのものが完成する喜びをみんなで分かち合う経験ができます。
- おすすめポイント: ルールがとても簡単なので、ボードゲームにあまり慣れていないお子さんや、特別支援学級の低学年の子どもたちでもすぐに楽しめます。使用するコマもカラフルで大きめなので、視覚的にも分かりやすいです。協力して何かを作り上げるシンプルな楽しさを味わえます。
4. フォレストアドベンチャー(Outfoxed!)
森のきつね泥棒は誰だ?みんなで協力して手がかりを集めよう!

- 対象年齢: 5歳以上
- 特徴: 森でパイが盗まれました!プレイヤーは探偵となり、みんなで協力して手がかりを集め、犯人のきつねを見つけ出す推理ゲームです。サイコロを振って進み、手がかりマスに止まったら、特別なデコーダーを使って犯人候補から容疑者を絞り込んでいきます。
- 自立活動での活用のねらい:
- 情報整理・記憶: 集めた手がかりを覚えたり、整理したりする練習になります。
- ロジカルシンキング: 「この手がかりから、このきつねは犯人じゃないな」のように、論理的に考え、情報を結びつける力を養います。
- 相談する力: どのマスに進むべきか、どの容疑者を調べるべきかなど、チームで話し合い、意見を出し合うプロセスが非常に重要です。
- おすすめポイント: 推理ゲームですが、子ども向けにアレンジされており、運の要素もありつつ、協力して謎を解く達成感を味わえます。トークンやボードのデザインが可愛らしく、子どもが直感的に理解できるような工夫がされています。「犯人は誰だ!?」というワクワク感が、子どもたちの集中力と相談への意欲を引き出します。
5. パンデミック:ジュニア(Pandemic: Rapid Response または ジュニア版)
力を合わせて世界の危機を救う!本格協力ゲームの入口に。

- 対象年齢: 8歳以上
- 特徴: 世界中で病気が発生!プレイヤーは医療チームとなり、それぞれが持つ特殊能力(役割)を活かしながら、協力して治療薬を届け、病気の蔓延を食い止め世界を救うゲームです。通常版のパンデミックよりもルールが分かりやすく、小さなお子さん向けになっています。(※ラピッドレスポンス版は時間制限あり)
- 自立活動での活用のねらい:
- 役割理解・協力: 各プレイヤーが異なる役割を持ち、自分の役割を理解し、他のプレイヤーの役割と連携して動く練習になります。
- 時間管理・焦りのコントロール: (ラピッドレスポンス版の場合)時間制限がある中で、チームとして効率的に動くための計画性と、焦りすぎずに冷静に判断する力が必要です。
- 他者への配慮: 自分の動きだけでなく、他のプレイヤーがどう動けばチーム全体にとって良いかを考えて提案するなど、他者を思いやる気持ちが育まれます。
- おすすめポイント: 有名な協力型ボードゲーム「パンデミック」の子ども向けバージョンなので、協力ゲームの本格的な面白さを味わえます。各自に明確な役割があるため、自分がチームの一員として貢献しているという意識を持ちやすいです。時間制限のあるラピッドレスポンス版は、特に集中力や瞬時の判断力を養うのに役立ちます。
「めあて」と「振り返り」のフレームワークで学びを深める
今回ご紹介したどの協力型ボードゲームも、前回の記事で解説した「めあての設定」と「振り返り」のフレームワークと組み合わせることで、その教育効果を最大限に引き出すことができます。
例えば、
- 「にじいろのへび」で「順番を待つ」をめあてにする。
- 「おばけキャッチジュニア」で「友達に〇〇しようと言葉で伝える」をめあてにする。
- 「アニマルアポカリプス」で「ゲームがうまくいかなくても、大丈夫と言葉に出す」をめあてにする。
- 「フォレストアドベンチャー」で「友達の意見を聞いて、『いいね』と言う」をめあてにする。
- 「パンデミック:ジュニア」で「自分の役割のカードを、友達に見せて説明する」をめあてにする。
のように、ゲームの内容や子どもたちの状況に合わせて、様々な「めあて」を設定し、活動後にしっかりと振り返ることで、遊びが確かな学びへと繋がっていきます。
おわりに:教室に「協力する楽しさ」を!
協力型ボードゲームは、子どもたちがリラックスした楽しい雰囲気の中で、社会性やコミュニケーション能力といった自立活動で培いたい力を自然に育むことができる素晴らしい教材です。勝ち負けにこだわらず、みんなで力を合わせるという成功体験は、子どもたちの自己肯定感や他者との関わりへの意欲を高めてくれます。
今回ご紹介したゲームが、先生方の自立活動の実践において、子どもたちの「協力するって楽しいね!」というキラキラした笑顔を引き出すきっかけとなれば幸いです。ぜひ、先生の教室にぴったりのゲームを見つけて、子どもたちとの豊かな学びの時間を楽しんでください。



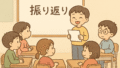
コメント