📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!
「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。
登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。
PDFの受け取りは、たったの30秒!
以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。
所見の作成がぐっと楽になると思います。
▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼
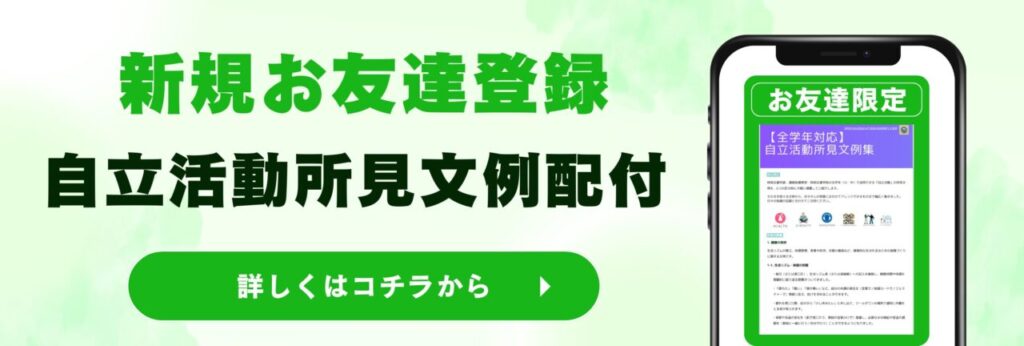
書籍のご案内
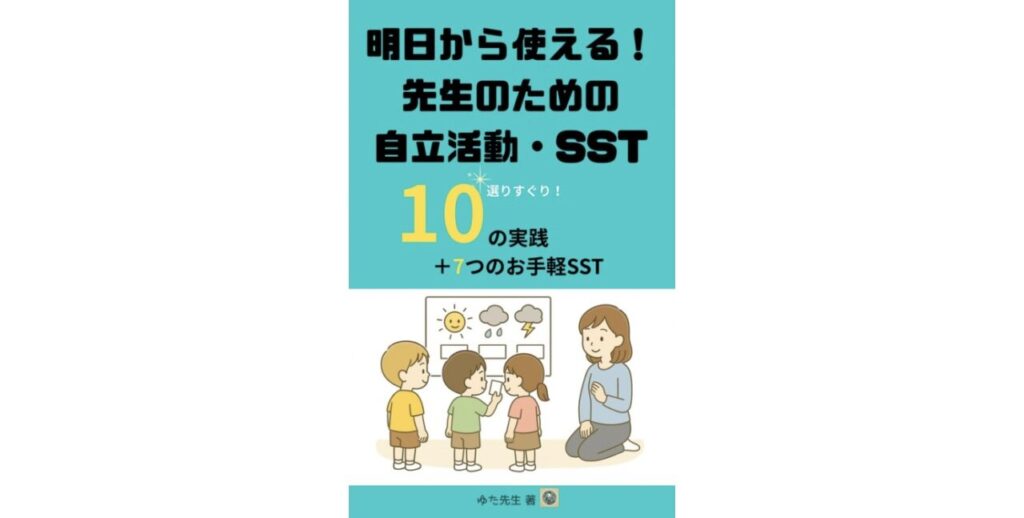
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
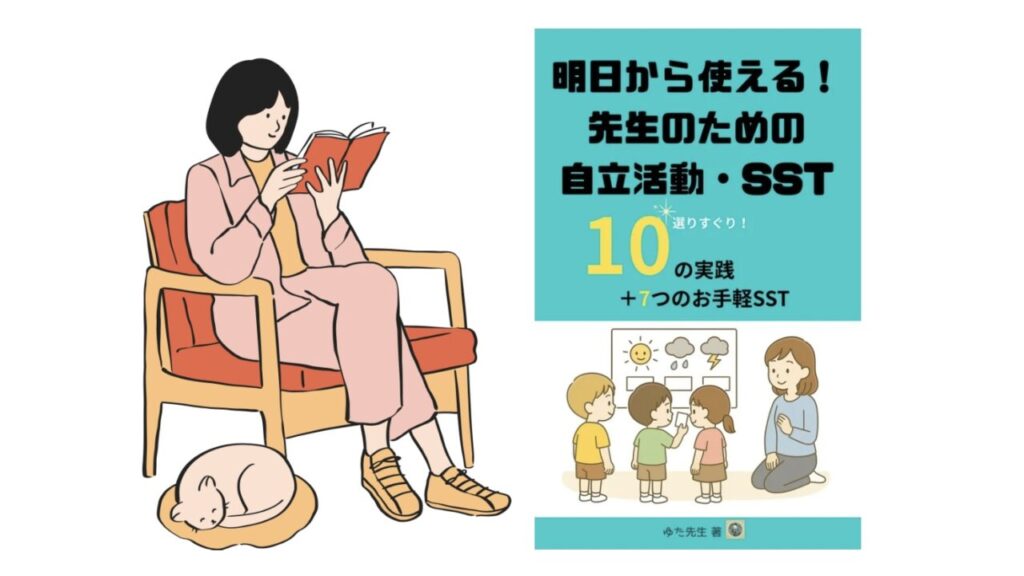
この記事を読むと分かること
- 思春期の中学生にとってソーシャルスキルトレーニングとは何か、その重要性が分かります。
- ロールプレイングやディスカッションなど、具体的なソーシャルスキルトレーニングの例を知ることができます。
- SSTを効果的に進めるための5つの手順を学び、実践に活かせます。
- 人気の「中学生のソーシャルスキルトレーニングゲーム」として、なぜワードウルフが最適なのかが理解できます。
- SSTに使える「SST教材」としてのワードウルフの活用法や、盛り上がる「ワードウルフのお題」が手に入ります。
- 教育的な視点から、ワードウルフが「自立活動」のどのようなねらいに繋がるのかを学べます。
中学生のソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?
まず、「ソーシャルスキルトレーニング(Social Skills Training, SST)」とは何か、特に中学生にとってなぜ重要なのかを理解することから始めましょう。
ソーシャルスキルとは「社会の海を渡る航海術」
ソーシャルスキルとは、一言で言えば「社会の中で他者と円滑な人間関係を築き、維持していくための知識と技術」のことです。
挨拶をする、相手の話に耳を傾ける、自分の意見を伝える、困ったときに助けを求める、意見が対立したときに折り合いをつける…。これらはすべてソーシャルスキルです。私たちは、これらのスキルを生まれつき持っているわけではなく、成長の過程で経験を通して少しずつ学んでいきます。
このスキルは、まるで広大な社会という海を渡っていくための「航海術」のようなものです。優れた航海術を身につけていれば、嵐(困難な対人関係)が来ても上手く乗り越え、仲間(友人)と協力しながら楽しく航海(社会生活)を続けることができます。
なぜ「中学生」にSSTが必要なのか?
小学校時代までは比較的単純だった人間関係は、中学生になると一気に複雑化します。その背景には、思春期特有の心と体の変化があります。
- 自己意識の高まりと他者からの評価への敏感さ:
「自分は周りからどう見られているんだろう?」という意識が強くなり、他人の言動に過敏になりがちです。これにより、些細なことで傷ついたり、逆に相手を傷つけてしまったりすることが増えます。 - 所属集団(仲間)の重要性の増大:
親や先生よりも、友人との関係が最も重要になります。「仲間外れにされたくない」という気持ちが強まり、自分の意見を言えずに我慢したり、逆にグループ内で過剰に同調したりすることがあります。 - 抽象的な思考の発達:
物事を多角的に考えられるようになる一方で、「言葉の裏」を読みすぎたり、相手の意図を誤解して悩んだりすることも増えます。SNSの普及により、文字だけのコミュニケーションでのすれ違いも深刻な問題となっています。
このような発達段階にある中学生にとって、SSTは単なる「お勉強」ではありません。彼らが直面している「今、ここ」にある悩みを解決し、自信を持って学校生活を送るための、実践的なライフスキルなのです。SSTを通して、生徒たちは自分の感情をコントロールする方法、相手の気持ちを想像する力、そして対立を乗り越え、より良い関係を築くための具体的な方法を学びます。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)の具体的な例は?
SSTには様々なアプローチがあります。ここでは、代表的な手法をいくつかご紹介します。大切なのは、対象となる生徒の特性や課題に合わせて、これらの手法を組み合わせて用いることです。
1. ロールプレイング(役割演技法)
ロールプレイングは、SSTの代表的な手法です。具体的な対人関係の場面を設定し、生徒たちがそれぞれの役割を演じることで、疑似体験を通してスキルを学びます。
【ロールプレイングの例】
- 「友人に遊びに誘われたが、宿題が終わっていないので断る」場面
- 「グループ活動で自分の意見と違う意見が出たときに、どう伝えるか」という場面
- 「友人がSNSで悪口を言われているのを見つけたとき、どう対応するか」という場面
ただ演じるだけでなく、演じた後に「どう感じたか」「もっと良い言い方はなかったか」などを全員で話し合う(フィードバックする)ことが重要です。
2. モデリング(観察学習)
モデリングは、先生や他の生徒が「お手本(モデル)」となる行動を見せることで、適切な行動を視覚的に学んでもらう手法です。
【モデリングの例】
- 先生同士が「上手な頼み方」「上手な断り方」のスキットを見せる。
- コミュニケーションが上手な生徒の会話をビデオに撮り、良い点をみんなで分析する。
特に、どう行動していいか分からない生徒にとって、具体的なお手本を見ることは、行動の第一歩を踏み出すための大きな助けとなります。
3. ディスカッション(話し合い)
特定のテーマについてグループで話し合う活動です。自分の意見を表明するスキルだけでなく、他者の意見を尊重し、合意形成を目指すプロセスを学ぶことができます。
【ディスカッションのテーマ例】
- 「本当の友達とは何か?」
- 「スマホの適切な使い方とは?」
- 「クラスのルールを決めよう」
単なるおしゃべりで終わらせず、司会者を立てたり、時間を区切ったりと、ルールを決めて行うことで、より効果的なトレーニングになります。
4. ゲーム(遊戯療法)
「ソーシャルスキルトレーニング 中学生 ゲーム」は、SSTを導入する上で非常に有効なキーワードです。中学生にとって、最も抵抗なく、かつ主体的に参加できる方法がゲームです。
【ゲームのメリット】
- 楽しさ: 「学習」という堅苦しさがなく、楽しみながら取り組める。
- 自発性: ルールの中で、生徒が自ら考えて行動する場面が多い。
- 安全性: ゲームの中での失敗は「負け」で済み、現実の人間関係のように傷つくリスクが低い。失敗を恐れずに挑戦できる。
ボードゲーム、カードゲーム、そして後ほど詳しく紹介する「ワードウルフ」のような会話型ゲームなど、様々な種類があります。これらのゲームには、自然な形でコミュニケーションや協調性、問題解決能力が求められる要素が組み込まれています。
5. 教材の活用(ワークシートなど)
「ソーシャルスキルトレーニング教材」として、市販されているものや自作のワークシートを活用するのも効果的です。
【教材の例】
- 感情カード: 様々な表情のイラストが描かれたカードを使い、「この人はどんな気持ち?」「どんな時にこの気持ちになる?」と話し合う。
- 状況イラストカード: 対人関係で起こりがちな場面(例:廊下でぶつかる、貸したものを返してもらえない)のイラストを見て、どう対応するかを考える。
- 自己紹介シート: 自分の好きなものや得意なことを書き出し、他者理解・自己理解を深める。
これらの教材は、会話のきっかけを作ったり、目に見えない「気持ち」や「状況」を可視化したりするのに役立ちます。
ソーシャルスキルトレーニングを効果的に進める5つの手順
SSTをただ闇雲に行っても、スキルは定着しません。効果を最大化するためには、確立された指導手順を踏むことが重要です。ここでは、SSTの基本的な流れである5つのステップをご紹介します。
SSTの5ステップ
手順1:教示 (Instruction)
「何を、なぜ学ぶのか」を明確に伝える段階です。
まず、その日のトレーニングで獲得を目指すスキル(例:「上手な断り方」)を具体的に提示します。そして、そのスキルがなぜ大切なのか、身につけるとどんないいことがあるのか(例:「断れるようになると、自分の時間も大切にできるし、友達との関係も壊れない」)を説明し、生徒の学習意欲を引き出します。
手順2:モデリング (Modeling)
「良いお手本を見せる」段階です。
指導者や他の生徒が、手順1で示したスキルを実際にやって見せます(ロールプレイング)。このとき、成功例だけでなく、あえて「悪い例(良くない断り方)」も見せることで、両者の違いが明確になり、生徒の理解が深まります。行動だけでなく、その時の表情や声のトーンなども含めてモデルを示すことが重要です。
手順3:リハーサル (Rehearsal)
「実際にやってみる」段階です。
生徒自身が、モデリングで見たスキルを模倣し、練習します。ロールプレイング形式で、複数の生徒がペアやグループになって実践します。最初は指導者のサポートを受けながら、徐々に自分たちの力でできるように促していきます。ここでは、完璧にできることよりも、まずは挑戦してみることが大切です。
手順4:フィードバック (Feedback)
「良かった点と改善点を伝える」段階です。
リハーサルでの生徒の行動に対して、具体的で肯定的なフィードバックを与えます。指導者が一方的に評価するのではなく、「今の言い方、すごく丁寧で良かったね」「次は、もう少し相手の目を見て言えると、もっと気持ちが伝わるかもね」というように、まずは良かった点を褒めてから、改善点を提案する「サンドイッチ法」などが有効です。他の生徒からもフィードバックをもらうことで、多角的な視点を得ることができます。
手順5:般化 (Generalization)
「日常生活で使ってみる」段階です。
トレーニングで学んだスキルを、教室の中だけでなく、実際の学校生活や家庭で使えるように促す、最も重要な段階です。
「今日学んだ『上手な断り方』、今週中に一度でも使えたら先生に教えてね」といった形で宿題(チャレンジ課題)を出すなど、実践への橋渡しを行います。そして、実際に使えた経験をクラスで共有し、成功体験を積み重ねていくことで、スキルが本当にその生徒のものとして定着していきます。
ゲームで楽しくSST!最強の教材「ワードウルフ」の紹介
- ここからは、この記事の核心である「ソーシャルスキルトレーニング 中学生 ゲーム」としての「ワードウルフ」の魅力と活用法を詳しく解説していきます。

ワードウルフとは?- 会話の中から仲間外れを探すスリル満点のゲーム
ワードウルフは、複数人(4人〜)で遊ぶ会話型の推理ゲームです。ルールは非常にシンプル。
- 参加者全員に、ある「お題」が配られます。
- しかし、参加者のうち一人(あるいは少数派)だけ、他の人とは微妙に違うお題が与えられています。この少数派が「ワードウルフ(人狼)」です。
- 参加者は、自分がワードウルフではないことを証明し、誰がワードウルフなのかを探るために、制限時間内でお題について自由に話し合います。
- 話し合いが終わったら、全員で「誰がワードウルフか」を指差し投票し、最多票を集めた人が追放されます。
<ゲーム例>
お題: 市民(3人)は「うどん」、ワードウルフ(1人)は「そば」
話し合い:
- Aさん:「温かいのも冷たいのも美味しいよね」
- Bさん:「うんうん。七味をかけると味がしまる!」
- Cさん(ウルフ):「年越しによく食べるイメージかな」
- Dさん:「天ぷらとの相性は最高だよね」
この会話から、「年越し」というキーワードに違和感を覚えた他のメンバーがCさんを怪しみ始める…といった具合にゲームが進行します。
このシンプルなルールの中に、SSTに繋がる無数の要素が詰まっているのです。
ワードウルフの基本的な進め方(ルール)
学校の授業や活動で実施することを想定した、基本的な流れをご紹介します。
- 準備:
- 司会者(先生)を決めます。
- お題カード(市民用とウルフ用)を人数分用意します。スマホアプリを使っても手軽にできます。
- 話し合いの制限時間を決めます(最初は3〜5分が目安)。
- お題の確認(1分):
- 司会者は、各プレイヤーに自分のお題を他の人に見られないように確認させます。
- 自分が市民なのかウルフなのかを把握します。
- 話し合い(3〜5分):
- タイマースタート!全員、自分のお題について自由に会話します。
- ポイント:
- 市民は、会話の中から「何か話が噛み合わない人」を探します。
- ウルフは、会話から市民のお題が何かを推測し、話を合わせながら自分の正体がバレないように振る舞います。
- 直接的にお題の単語を言うのは原則NGです。(「3文字だよね?」などはOK)
- 投票(1分):
- 話し合い終了後、司会者の「せーの」の合図で、全員がワードウルフだと思う人を一斉に指差します。
- 最も多くの票を集めた人が追放されます。
- 結果発表:
- 追放された人が、自分がウルフだったか市民だったかを明かします。
- 市民側の勝利条件: ワードウルフを追放できれば勝利。
- ウルフ側の勝利条件: 自分が追放されなければ勝利。さらに、追放されたウルフが市民のお題を当てることができれば、ウルフの逆転勝利となる特別ルールもあります。
なぜワードウルフが中学生のSSTに効果的なのか?
ワードウルフは、ただ楽しいだけではありません。ゲームのプロセスそのものが、中学生に必要なソーシャルスキルを総合的に鍛える、非常に優れたトレーニングツールなのです。
- 傾聴力と情報整理能力の向上:
ワードウルフを探すためには、他のプレイヤーの発言を一言一句聞き漏らさず、その内容を注意深く吟味する必要があります。「A君はさっきこう言っていたけど、Bさんの発言とは少し違うな…」というように、会話の中からヒントとなる情報を拾い上げ、頭の中で整理する力が自然と養われます。 - 質問力と推論力の発達:
核心に迫りすぎず、かつ相手の情報を引き出すような「絶妙な質問」を考える必要があります。「それはどんな色?」「どこで売ってる?」といった直接的な質問ではなく、「それって、朝ごはんに食べることもある?」のように、相手の反応を探るための戦略的な質問力が鍛えられます。また、断片的な情報から「この人はウルフかもしれない」と仮説を立て、論理的に推理する力も身につきます。 - 語彙力と説明力の強化:
自分のお題を直接言えないという制約があるため、プレイヤーは比喩を使ったり、別の言葉で言い換えたりして、自分の考えを表現しようと試みます。この過程で、「それをどう表現すれば、仲間には伝わり、ウルフにはバレないか」と頭をフル回転させるため、語彙力や説明力が飛躍的に向上します。 - 協調性とチームワークの醸成:
市民側のプレイヤーは、「ワードウルフを見つける」という共通の目標に向かって協力する必要があります。「〇〇さんのあの発言、どう思った?」「みんなでこの質問をしてみよう」といったように、チームで戦略を練る中で、協調性や集団での問題解決能力が育まれます。 - 多様性の受容と視点取得能力:
ワードウルフは、意図的に「少数派」の立場を体験するゲームです。「みんなと話が合わない…」「自分だけが違うのかもしれない」というウルフの不安や焦りを疑似体験することで、現実世界で少数派の立場にいる人の気持ちを想像するきっかけになります。これは、他者の視点に立って物事を考える「視点取得能力」や、多様性を受け入れる心を育む上で非常に重要です。 - 失敗への心理的安全性(心理的耐性):
SSTのロールプレイングでは、失敗を恐れて発言できない生徒もいます。しかし、ワードウルフはあくまで「ゲーム」です。間違えて市民を追放してしまっても、自分がウルフだとバレてしまっても、笑って「もう一回やろう!」となります。この「失敗しても大丈夫」という心理的安全性が確保された環境が、生徒たちが安心して発言し、コミュニケーションに挑戦するための土台となるのです。
ワードウルフをSSTで活用するためのポイントと「お題」
ワードウルフをSSTとして最大限に活用するためには、進行役となるファシリテーター(先生や保護者)の役割と、生徒の発達段階や関係性に合わせた「お題」選びが鍵となります。
ファシリテーター(進行役)の重要な役割
- 安心できる雰囲気作り:
何よりも大切なのが、誰もが安心して発言できる雰囲気を作ることです。「どんな意見もOK」「間違えても大丈夫」というルールを最初に全員で確認しましょう。特に、特定の生徒を責めたり、からかったりする言動には、すぐに対応する必要があります。 - 丁寧なルール説明:
初めて行う場合は、実際にファシリテーターがお手本を見せながら(モデリング)、ゆっくりとルールを説明します。1〜2回練習ゲームを行うと、生徒たちはすぐにルールを理解できます。 - 適切な介入(ファシリテーション):
話し合いが停滞してしまった場合や、特定の生徒だけが話している場合には、適切に介入します。「〇〇さんはどう思う?」「さっき△△さんが言っていたことについて、もう少し詳しく聞いてみようか」など、全員が会話に参加できるよう促します。 - 振り返りの時間を設ける:
ゲームが終わったら、やりっぱなしにせず、必ず振り返りの時間を設けましょう。これがSSTとしての効果を飛躍的に高めます。【振り返りの問いかけ例】
- 「今のゲームで、難しかったことは何?」
- 「誰のどんな発言が、ウルフを見つけるヒントになった?」
- 「ウルフ役の人は、どんな気持ちだった?」
- 「次にやるとき、もっとうまくやるにはどうしたらいいかな?」
こうした問いかけを通して、生徒たちは自身のコミュニケーションを客観的に見つめ直し、学びを深めることができます。
盛り上がる!SSTに使える「ワードウルフのお題」集
「ワードウルフのお題」は、参加者の興味や知識レベルに合わせて調整することが成功の秘訣です。ここでは、SSTで使いやすいお題をレベル別に紹介します。これらは「ソーシャルスキルトレーニング教材」としてそのまま活用できます。
【初級編】中学生の身近なテーマ
まずは、全員がイメージしやすく、共通の話題で盛り上がれるお題から始めましょう。
| 市民 (多数派) | ワードウルフ (少数派) | ポイント |
|---|---|---|
| 給食 | 弁当 | 「温かい?」「メニューは選べる?」などの質問が出やすい。 |
| 体育 | 部活 | どちらも体を動かすが、目的や頻度が異なる。 |
| LINE | 主な機能や使い方、コミュニケーションの取り方の違いが鍵。 | |
| シャーペン | 鉛筆 | 書き心地や使い方、削るかどうかが大きな違い。 |
| ポテトチップス | フライドポテト | 形状、食感、食べる場所などの違いでボロが出やすい。 |
| 先生 | 塾の先生 | 教える内容は似ているが、立場や関係性が異なる。 |
【中級編】少し知識や思考力が必要なテーマ
生徒の趣味や興味に合わせてお題を設定すると、会話がさらに活発になります。
| 市民 (多数派) | ワードウルフ (少数派) | ポイント |
|---|---|---|
| 漫画 | アニメ | 静止画か動画か、音があるかどうかが大きな違い。 |
| J-POP | K-POP | 言語やダンスの激しさ、グループの構成などで探り合える。 |
| YouTube | TikTok | 動画の長さや特徴、流行りのコンテンツが異なる。 |
| 犬 | 猫 | 鳴き声や性格、散歩の必要性など、比較しやすい。 |
| サッカー | 野球 | 人数、使う道具、試合の展開などが全く違う。 |
| マクドナルド | モスバーガー | 看板商品や店の雰囲気、注文方法の違いがヒントになる。 |
【上級編】抽象的・概念的なテーマ
対話を通して、生徒たちの価値観や考え方に触れることができるお題です。振り返りの時間をしっかり取ることで、深い学びに繋がります。
| 市民 (多数派) | ワードウルフ (少数派) | ポイント |
|---|---|---|
| 友情 | 愛情 | 似ているが対象や深さが違う。自分の経験を語る中で差が出る。 |
| 自由 | 平和 | どちらも望ましい状態だが、意味するものが違う。抽象的な議論になる。 |
| 努力 | 才能 | 成功に必要な要素として対比されやすい。どちらが重要か、などの議論に発展。 |
| 正義の味方 | ヒーロー | ニュアンスの違いを言葉でどう表現するかが試される。 |
| 学校のルール | 社会のルール | 守るべき対象や範囲、破った場合の結果が大きく異なる。 |
お題作成のポイント
- 「似ているけど、決定的に違う」ものを選ぶ。
- 参加者全員が知っている、共通の土台があるテーマにする。
- ポジティブなテーマを選ぶ(悪口やネガティブな話題に繋がるお題は避ける)。
自立活動の視点から見るワードウルフのねらい
特別支援教育の観点では、SSTは「自立活動」の一環として位置づけられます。ここでは、学習指導要領に示されている「自立活動6区分27項目」に基づき、ワードウルフという活動がどのような教育的「ねらい」を持って設定できるのかを解説します。
「自立活動」とは、障害による学習上または生活上の困難を主体的・積極的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うための指導です。ワードウルフは、この自立活動の目標を達成するための、非常に有効な手段となり得ます。
【区分2】人間関係の形成
この区分は、他者と良好な関係を築き、集団の一員として適切に行動する力を育むことを目指します。ワードウルフは、この区分と非常に関連が深いです。
- 項目(10) 他の者とのコミュニケーションの基礎に関すること:
ねらい: ゲームのルールの中で、他者の発言に注意を向け、意図を汲み取ろうとする態度を養う。 - 項目(11) 集団への参加の基礎に関すること:
ねらい: 「ワードウルフを見つける」という共通の目的に向かって、他のプレイヤーと協力し、自分の役割を果たそうとする態度を養う。 - 項目(12) 自己の理解と行動の調整に関すること:
ねらい: ウルフ役になった際に、自分の焦りや不安な気持ちをコントロールし、冷静に振る舞おうとすることで、自己の感情と行動を調整する力を育む。
【区分6】コミュニケーション
この区分は、言語機能やコミュニケーション手段の活用能力を高めることを目指します。ワードウルフは、まさにこの区分の中核をなす活動と言えます。
- 項目(22) 言語の受容に関すること:
ねらい: 他のプレイヤーの発言を聞き、その内容からお題に関する情報を正確に理解する力を養う。 - 項目(23) 言語の表出に関すること:
ねらい: 自分のお題について、他者に伝わるように言葉を選び、分かりやすく説明しようとする力を育む。 - 項目(24) 言語の形成と活用に関すること:
ねらい: 比喩や言い換えなど、多様な表現を用いて自分の考えを伝えたり、会話の流れに応じて的確な質問をしたりするなど、言語を柔軟に活用する力を養う。 - 項目(25) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること:
ねらい: 言葉だけでなく、声のトーンや表情、ジェスチャーなどを効果的に使い、自分の意図を伝えようとする態度を養う。 - 項目(26) 状況に応じたコミュニケーションに関すること:
ねらい: 話し合いの流れや場の雰囲気を読み取り、自分が今どのような発言をすべきか(情報を出すべきか、質問すべきか、黙って聞くべきか)を判断する力を育む。
このように、ワードウルフという一つのゲーム活動の中に、自立活動の多様なねらいを設定することが可能です。指導者は、参加する生徒一人ひとりの課題に合わせて、「今日は特に『質問する力』を意識してみよう」といったように、個別のねらいを意識して関わることが大切です。
まとめ:ゲームで開く、未来への扉
この記事では、「ソーシャルスキルトレーニング 中学生」というテーマに対し、会話型推理ゲーム「ワードウルフ」を活用した非常に効果的なアプローチをご紹介しました。
- 中学生のSSTは、複雑化する人間関係を乗り越え、自己肯定感を育むために不可欠なライフスキルです。
- SSTにはロールプレイングやディスカッションなど様々な例がありますが、中学生にはゲームを用いた方法が特に有効です。
- SSTを効果的に進めるには、「教示」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「般化」という5つの手順が重要になります。
- ワードウルフは、傾聴力、質問力、説明力、協調性などを楽しみながら総合的に鍛えられる、まさに理想的なSST教材です。
- 身近なテーマから抽象的なテーマまで、工夫次第で無限のお題が作れ、生徒の興味を引きつけ続けることができます。
- 教育的な視点からも、ワードウルフは自立活動における「人間関係の形成」や「コミュニケーション」の力を育む上で、明確なねらいを持って活用できる優れた活動です。
思春期という多感な時期を過ごす中学生にとって、コミュニケーションの成功体験は、自信を持って未来へ踏み出すための大きな原動力となります。
堅苦しい「トレーニング」ではなく、みんなで笑い合える「ゲーム」から始めてみませんか。
ワードウルフという小さなゲームが、お子さんや生徒たちのコミュニケーション能力を開花させ、豊かな人間関係を築くための、大きな一歩となるはずです。ぜひ、ご家庭で、学校で、試してみてください。
おすすめのSSTこんな時どうする?の無料教材はこちら👇
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。





コメント