「人間知恵の輪」という活動をご存じでしょうか?
これは、数人で手を取り合って絡まり合い、手を離さずにほどいていくゲームです。単なるレクリエーションに見えて、実は子どもたちの協力、思いやり、自己調整力といった、生きる上で大切なスキルを育むための奥深い活動です。教室でできるゲームなのでアイスブレイクにも室内自立活動にもぴったりです。
この記事では、
私が特別支援学級で実践してきた「人間知恵の輪」の具体的な記録を、自立活動の6区分27項目やSST(ソーシャルスキルトレーニング)の視点と絡めてご紹介します。
2人での『人間知恵の輪』の記事はこちらから👇
おすすめの室内SSTはこちらから👇
室内自立活動のねらい
この活動を通じて、子どもたちには以下のような力を育んでほしいと願っています。
自立活動の観点から
- 【人間関係の形成】協力する経験を通して、他者と円滑に関わるための基礎を学ぶ。
- 【心理的な安定】楽しく安全な体験を通じて、安心感と大きな達成感を得る。
- 【身体の動き】バランス感覚、空間認知能力、そして柔軟な体の動かし方を身につける。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
SSTの観点から
- 「協力する」「声をかける」「譲る」「助けを求める」など、実践的な社会的スキルを練習する。
- 状況を冷静に判断し、行動を自己調整する(先走らず、立ち止まって考える)練習。
教室でできる「人間知恵の輪」の流れと工夫
1. 導入 安心して取り組める雰囲気を作る
- まずは教師がペアになって活動の楽しさを見本で示す。
- 「人の手を握るのが苦手な人はスカーフを使ってもOK」と伝え、安心できる選択肢を提示する。
- 活動の目的は「ほどくこと」ではなく、「みんなで楽しく挑戦すること」だと明確に強調する。

2. 活動の手順 みんなで知恵を出し合う時間
- 5〜6人で円になる。
- 目を閉じた状態でランダムに右手・左手を別の人とつなぐ。
- 目を開けて、活発に声をかけ合いながらほどいていく。
- 教師は後ろから支援(声かけ、安全確認)し、必要に応じてヒントを与える。
3. 振り返りの時間 学びを深めるための大切なステップ
活動後にはワークシートや口頭で、以下のような問いかけを行い、子どもたちの気づきを促します。
- 活動中、どんな気持ちになった?
- 自分から積極的に声をかけられた?
- 誰かのアイデアをじっくり聞いて動けた?
- 難しかったことは何?それをどうやって乗り越えた?
成功した事例と変化
ある5年生の自閉スペクトラム症の児童は、活動当初は「人と手をつなぐのが嫌だ」「声を出すのが恥ずかしい」と話していました。しかし、数回の実践を重ねる中で、スカーフを使うという代替策で手をつなぐことに成功。そして3回目には、なんと自ら「〇〇くん、右に回って!」と、具体的な指示を出すことができるようになったのです。
この成功体験は、その後の学級活動における友達との関わり方にも前向きな変化をもたらしました。以前よりも積極的に話しかけたり、困っている友達に手を差し伸べたりする姿が見られました。
よくある課題と効果的な対応策
| 課題 | 対応策 |
|---|---|
| 人との接触が苦手な場合 | ハンカチやスカーフを間に挟むことで、直接的な接触を避けつつ活動に参加できるようにする。 |
| 声が出せない、コミュニケーションが苦手な場合 | 絵カードやジェスチャーを活用して指示や動きを伝える練習をする。教師が間に入り、伝言ゲームのようにサポートすることも有効です。 |
| 見通しがもてず不安になる場合 | 写真やイラストを使い、活動の全体像や次のステップを視覚的に提示する。事前に手順を確認する時間を設けるのも良いでしょう。 |
| 意見の衝突やケンカになる場合 | 「怒ってもいいけど、ことばで伝えよう」というルールを共有し、感情を適切に言葉で表現する練習を並行して行う。教師が仲介に入り、それぞれの気持ちを代弁することも大切です。 |
アンガーマネージメントについてはこちらの記事にまとめています👇
人間知恵の輪が育む!自立活動との関連マップ
| 自立活動の区分 | 関連項目 | 活動中に育まれる力 |
|---|---|---|
| 人間関係の形成 | 他者との協力・共感 | 声をかけ合い、譲り合う姿勢を通して、他者との協調性を育む。 |
| 身体の動き | 姿勢・空間認知・柔軟性 | 自分と他人の位置関係を把握し、身体を柔軟に動かす力を養う。 |
| 心理的な安定 | 楽しい体験・達成感 | 成功体験を通じて大きな達成感と安心感を味わい、自信を育む。 |
| 自己理解と自己調整 | 感情のコントロール | 困難な状況で自分の気持ちを調整し、冷静に問題解決に取り組む力を培う。 |
まとめ 人間知恵の輪は「心」と「からだ」の学びの宝庫
「人間知恵の輪」は、一見するとシンプルなゲームですが、その中には子どもたちの自己理解、他者理解、協調性、そして感情調整といった、将来にわたって必要となる多くの力を育む可能性が秘められています。
特別支援教育の現場で、形式にとらわれず、子どもたちが楽しみながら、自ら気づきを得られるSST・自立活動として、ぜひ「人間知恵の輪」を取り入れてみてください。この活動が、子どもたちの成長を促す一助となることを心から願っています!
この記事を読んで「人間知恵の輪」を試してみた方は、ぜひコメントで感想を教えてください。



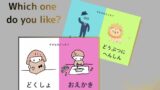


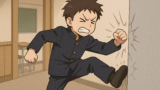


コメント