子どもたちのコミュニケーション能力や社会性を育むSST(ソーシャルスキルトレーニング)。その有効な手法の一つとして、多くの教育現場で「伝言ゲーム」が取り入れられています。この記事では、SSTとして伝言ゲームを活用したい先生方へ向けて、その教育的価値から具体的な進め方までを網羅的に解説します。
この記事を読めば、
単なる遊びではない、教育的意図に基づいた伝言ゲームのねらいや目標が分かります。また、「幼児向けの伝言ゲームのお題から、「面白い 小学生向けの伝言ゲームのお題や 高学年向けの難しいお題や、さらには、早口言葉のお題を取り入れたユニークなアイデアまで、豊富なお題をご紹介。基本的なルールだけでなく、子どもたちを飽きさせないための「伝言ゲームのアレンジ」や「伝言ゲームのバリエーション」も多数提案し、明日からの実践に役立つ情報を提供します。
おすすめのSST教材はこちら💁
📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!
「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。
登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。
PDFの受け取りは、たったの30秒!
以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。
所見の作成がぐっと楽になると思います。
▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼
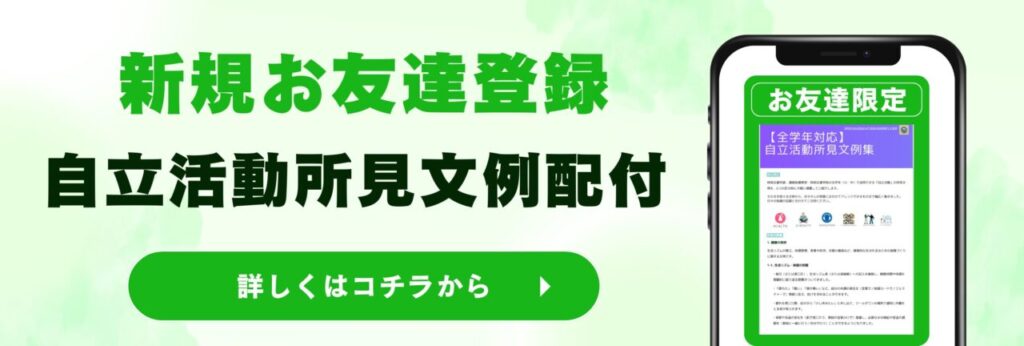
書籍のご案内
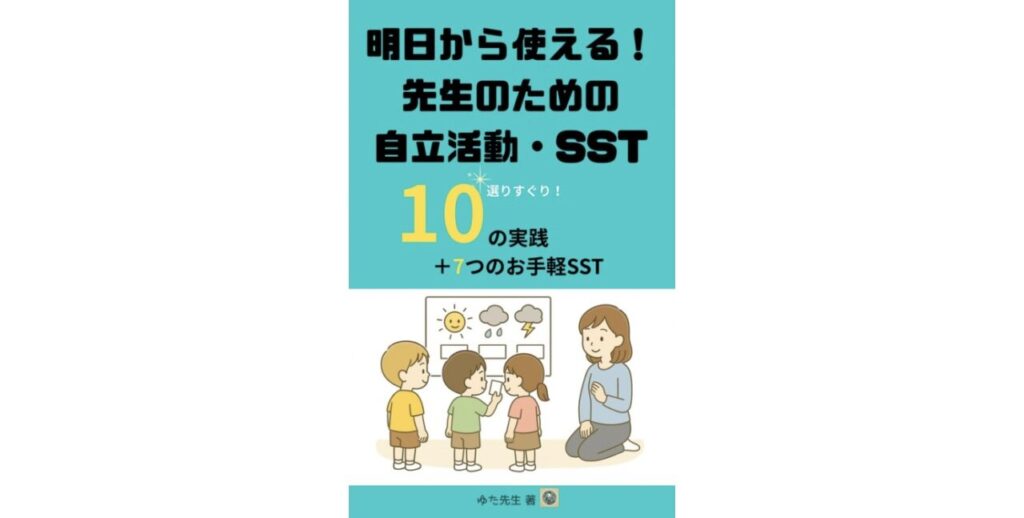
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。👇
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
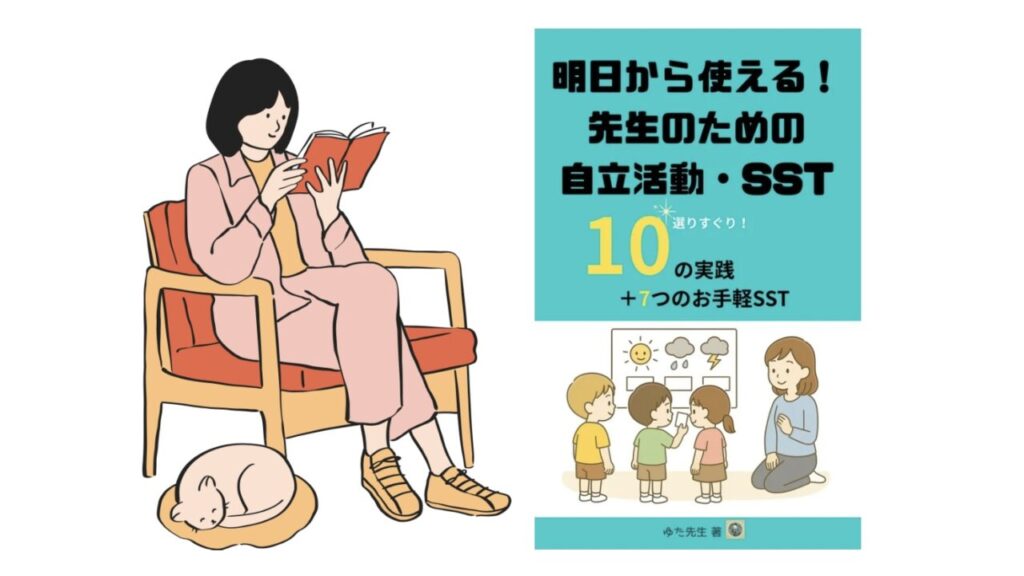
SSTとしての伝言ゲームの重要性とねらい
伝言ゲームは、楽しさの中にSSTの重要な要素が凝縮された活動です。子どもたちはゲームに夢中になる中で、自然とソーシャルスキルを学んでいきます。ここでは、特別支援教育における「自立活動」の観点から、伝言ゲームが持つ教育的なねらいと目標を詳しく解説します。
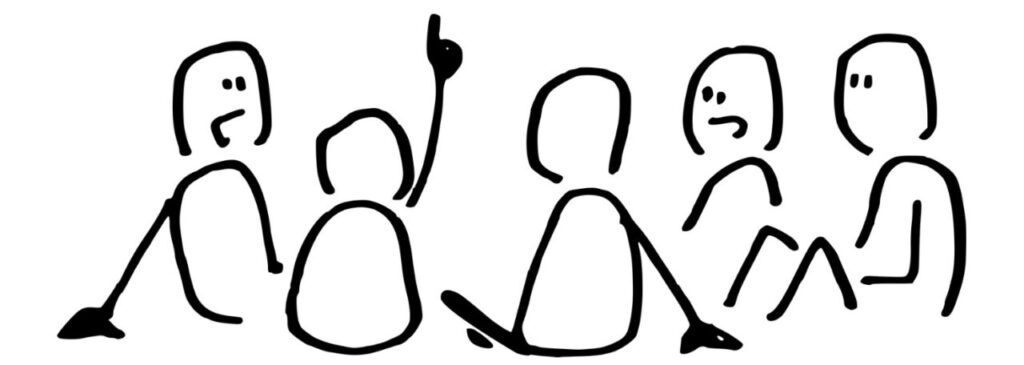
自立活動6区分27項目と伝言ゲームの関連性
自立活動は、「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的(※)に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」(学習指導要領)ことを目的としています。伝言ゲームは、この自立活動における特に以下の区分・項目と深く関連しています。
(※)主体的に:文部科学省の解説では、「障害による困難性を改善・克服しようと主体的に取り組む態度」とされています。
【関連の深い区分・項目】
- 3. 人間関係の形成
- (10) 他者とのかかわりの基礎に関すること。
順番を守る、相手の顔を見て話す・聞くといった基本的なルールを学びます。 - (11) 他者の意図や感情の理解に関すること。
言葉だけでなく、伝えてくれる相手の表情や口の動きから情報を読み取ろうとします。 - (12) 自己の理解と行動の調整に関すること。
「早く伝えたい」「間違えたらどうしよう」という自分の気持ちをコントロールし、落ち着いて次の人に伝える練習になります。 - (13) 集団への参加の基礎に関すること。
チームの一員としての役割を理解し、協力してゴールを目指す経験を積みます。間違えても責めない、面白い変化を楽しむといった集団のルールを学びます。
- (10) 他者とのかかわりの基礎に関すること。
- 6. コミュニケーション
- (22) 言語の受容や表出に関すること。
「聞く(受容)」と「話す(表出)」という言語活動の最も基本的なサイクルを繰り返します。 - (23) 言語の形成と活用に関すること。
聞いた言葉を記憶し、意味を考えながら正確に再現しようとすることで、語彙力や文章構成能力の基礎を養います。 - (24) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
相手に分かりやすく伝えようとする工夫(声の大きさ、速さ、明瞭さ)を学びます。 - (25) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
言葉がうまく伝わらない時に、身振り手振りを加えるなど、非言語的なコミュニケーションを試すきっかけにもなります。
- (22) 言語の受容や表出に関すること。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
伝言ゲームの具体的なねらいと目標
上記の項目を踏まえ、SSTとして伝言ゲームを行う際の具体的な「ねらい」と「指導目標」の例を以下に示します。
【ねらい】
- 他者の話を集中して聞く力(傾聴力)を養う。
- 聞いた情報を記憶し、正確に再現しようとする態度を育てる。
- 相手に分かりやすく伝えようとする表現力・伝達力を高める。
- 集団のルールを守り、仲間と協力して活動する楽しさを味わう。
- 情報の変化を楽しみ、失敗を許容する柔軟な心を育む。
【指導目標(例)】
- レベル1: 教師や友だちの話に顔を向けて耳を傾けることができる。
- レベル2: 3語程度の短い言葉を聞いて記憶し、次の人に伝えようとすることができる。
- レベル3: 最後の人が発表するまで、静かに待つことができる。
- レベル4: 5語以上の少し長い文章を聞いて、主要な単語を覚えていることができる。
- レベル5: 伝わった言葉が元のお題と違っていても、その変化を笑って楽しむことができる。
- レベル6: より正確に伝えるために、声の大きさや話す速さを意識することができる。
これらのねらいと目標を意識して活動を計画・実行することで、伝言ゲームは単なるレクリエーションから、子どもたちの成長を促すための意図的・計画的なSSTプログラムへと昇華します。
【幼児向け】伝言ゲームお題!簡単で楽しい言葉選びのポイント
幼児期の子どもたちにとって、伝言ゲームは「聞く」「覚える」「話す」という基本的なコミュニケーションの練習に最適な活動です。お題選びでは、子どもたちがイメージしやすく、発音しやすい言葉を選ぶことが成功の鍵です。

【幼児向けお題のポイント】
- 短く、リズミカルな言葉(2〜4語文程度)
- 子どもたちの生活に身近な言葉(動物、食べ物、乗り物など)
- 擬音語・擬態語を含んだ楽しい言葉
- 発音が簡単な言葉
幼児向けお題 具体例
【動物シリーズ】
- ぞうさんが みずあそび
- ぴょんぴょん うさぎさん
- わんわん ないてる
- がおー ライオンだ
- きいろい ひよこ
【食べ物シリーズ】
- あまい いちご
- おおきな おにぎり
- ばななを むしゃむしゃ
- つめたい あいすくりーむ
- ほかほか ごはん
【乗り物シリーズ】
- ぶーぶー じどうしゃ
- がたんごとん でんしゃ
- ぱおーん きゅうきゅうしゃ
- しゅっぱつ しんこう
【生活シリーズ】
- きらきら おほしさま
- ふわふわ くも
- こんにちは
- ありがとう
- いってきます
これらの簡単なお題から始め、子どもたちが自信を持って参加できるように促しましょう。最初は教師が隣について、小声でヒントを与えるなどのサポートも有効です。
【小学生向け】伝言ゲームの面白いお題
小学生になると、語彙力も理解力も格段にアップします。少しひねりのあるお題や、思わず笑ってしまうような面白いお題を取り入れることで、クラス全体が一体となって盛り上がることができます。

伝言ゲーム お題 笑える!低学年でも大爆笑のお題
低学年-には、日常の「あるある」や、ちょっとおかしな組み合わせの言葉がウケます。
- 校長先生が 廊下で スキップした
- 給食のプリンが ふるえている
- ぼくの消しゴムが 空を飛んだ
- 算数のノートに ラーメンをこぼした
- カラスが 僕の帽子を 持っていった
- おならをしたら 犬がびっくりした
- 体育の先生が バナナの皮で すべった
高学年が盛り上がる!ちょっとシュールで面白いお題
高学年には、少し想像力が必要なシュールな設定や、大人びた言葉を入れると面白みが増します。
- 宇宙人が うちの冷蔵庫の プリンを狙っている
- 隣のクラスの山田くんは 本当は スーパーサイヤ人らしい
- AIに 今日の宿題を やらせてみた
- 徳川家康が スマホの操作に 苦戦している
- うちの猫が 関西弁で 話しかけてきた
- 満員電車で 足がくさいのは たぶん僕のせいじゃない
- 来週の月曜から 給食が 全部カレーになるらしい
これらの「笑える」「面白い」お題は、子どもたちの緊張をほぐし、コミュニケーションへの積極性を引き出します。多少間違って伝わっても、それがまた新たな笑いを生むのが、この種のお題の醍醐味です。
【面白い!難しい!】伝言ゲームお題。高学年も楽しめる挑戦的なお題
ゲームに慣れてきた高学年や、さらに挑戦したいクラスには、難易度を上げたお題が効果的です。難しさの種類も様々で、「文章が長い」「似た言葉が入っている」「状況が複雑」など、工夫次第でいくらでも難しくできます。

長文・複雑な状況設定のお題
- きのうの放課後、理科室の前の廊下で、カエルが緑色の液体が入ったビーカーを片手に、難しい顔で窓の外を眺めていた。
- 体育倉庫の隅っこでホコリをかぶっていた真っ赤なボールは、実は百年に一度だけ、願いを三つ叶えてくれる伝説のボールらしい。
- 来週行われる町内会の運動会では、パン食い競争のパンがすべて激辛カレーパンに変更されるという噂が流れている。
- 図書室で一番分厚い歴史の本の38ページに、未来へ行けるタイムマシンの設計図がこっそり挟まっているそうだ。
似ている言葉・紛らわしい言葉のお題
- 庭には二羽、裏庭にも二羽、ニワトリがいる。
- 生麦生米生卵、隣の客はよく柿食う客だ。
- この寿司は少し酢が効きすぎた。
- シャンソン歌手が新春シャンションショーを開催する。
- 肩たたき機と肩たたき券を肩たたきされた肩に渡す。
カタカナ語・専門用語のお題
- プログラミングでアルゴリズムを最適化し、ユーザビリティを向上させる。
- 光合成は、二酸化炭素と水から有機物を作り出す。
- ミニマリストのミニマルなライフスタイルに密着する。
- アボカドのディップソースはワカモレという。
これらの難しいお題は、集中力、記憶力、そして語彙力をフル活用する必要があり、子どもたちの知的好奇心を刺激します。クリアできた時の達成感は格別です。
伝言ゲーム お題 早口言葉で難易度アップ!滑舌トレーニングにも
伝言ゲームに早口言葉を取り入れると、難易度が飛躍的に上がり、ゲーム性が一気に高まります。正確に聞き取り、はっきりと発音する必要があるため、滑舌のトレーニングにもなり一石二鳥です。

初級編:短い早口言葉
- 赤パジャマ 青パジャマ 黄パジャマ
- バスガス爆発
- かえるぴょこぴょこ みぴょこぴょこ
- 老若男女(ろうにゃくなんにょ)
- 坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた
中級編:少し長めの早口言葉
- 東京特許許可局長今日急遽休暇許可却下
- すもももももももものうち
- この竹垣に竹立て掛けたのは竹立て掛けたかったから竹立て掛けた
- お綾や親にお謝り、お綾や八百屋にお言い
上級編:超難解な早口言葉
- よど殿もよど殿なら、ねね殿もねね殿だ
- 輸出車、湯呑み茶碗、輸出酢、ゆず酢
- 派出所の巡査の調査は最新式の写真照合装置を使った
早口言葉をお題にする際は、全員が一度声に出して練習する時間を設けるのも良いでしょう。「言いにくさ」そのものを楽しむ雰囲気を作ることが大切です。
伝言ゲーム アレンジで広がる楽しさ!ルールを変えてみよう
基本的な伝言ゲームに慣れてきたら、ルールを少しアレンジするだけで、全く新しい楽しさが生まれます。子どもたちの実態や、育てたいスキルに合わせて様々なアレンジを試してみましょう。
1. ジェスチャー付き伝言ゲーム
- ルール: 言葉と一緒に、その言葉を表すジェスチャーも伝えます。
- ねらい: 非言語的コミュニケーション能力の育成、表現力・観察力の向上。
- お題例: 「大きな口をあけるカバ」「ボールを投げるゴリラ」「敬礼するおまわりさん」
2. 感情伝言ゲーム
- ルール: 「嬉しい声で」「悲しい声で」「怒った声で」など、感情を込めて伝言します。
- ねらい: 感情の理解と表現、声のトーンや表情から意図を読み取る力の育成。
- お題例: 「(嬉しい声で)宝くじが当たった!」「(悲しい声で)アイスを落としちゃった…」
3. 口パク伝言ゲーム
- ルール: 声を出さずに、口の動きだけで伝えます。
- ねらい: 集中力、観察力(読唇)の向上。
- ポイント: 短く、口の動きが分かりやすい言葉(例:「おはよう」「バナナ」)から始めると良いでしょう。
4. 後ろ向き伝言ゲーム
- ルール: 全員が前を向いて一列に座り、最後の人から先頭に向かって、肩を叩いて振り向かせ、伝言していきます。
- ねらい: 聞き逃さないようにする集中力の向上、ドキドキ感を楽しむ。
- ポイント: 誰に伝えるかが明確になり、周りの声に惑わされにくくなるメリットもあります。
伝言ゲームバリエーション豊かな遊び方でSST効果を高める
アレンジが「ルールの変更」だとすれば、バリエーションは「ゲームの形式そのものを変える」遊び方です。より多角的に子どもたちのスキルにアプローチできます。
1. イラスト伝言ゲーム
- ルール: 最初の人だけがお題(言葉)を見て、それを絵に描きます。次の人はその絵を見て何が描いてあるかを推測し、また絵に描いて伝えていきます。最後の人が、最終的な絵を見てお題が何だったかを当てます。
- ねらい: 情報を非言語的に解釈・表現する力、想像力、観察力の育成。
- ポイント: 文章ではなく、「飛んでいるタコ」「怒っている猫」のような簡単な名詞+動詞/形容詞がお題に適しています。
2. 多方向・同時伝言ゲーム
- ルール: 2〜3チームを作り、同時にスタートします。他のチームの声に惑わされずに、自分のチームの伝言を正確に伝えることを目指します。
- ねらい: 選択的注意(必要な情報だけを聞き分ける力)の育成。
- ポイント: 教室の端と端を使うなど、チーム間の距離を少し離すとやりやすくなります。
3. 穴埋め伝言ゲーム
- ルール: 最初の人に「〇〇が 公園で △△した」のような、一部が空欄になった文章を見せます。伝える人は、空欄に好きな言葉を入れて次の人に伝えます。これを繰り返し、最後にはユニークな文章が完成します。
- ねらい: 語彙力、発想力、文章構成能力の育成。
- 例:
最初の人:「(犬)が 公園で (昼寝)した」
次の人:「(猫)が 公園で (ダンス)した」
最後の人:「(ゴリラ)が 公園で (宿題)した」→ みんなで爆笑!
伝言ゲームをSSTとして成功させるための教師の関わり方
伝言ゲームの教育効果を最大限に引き出すためには、教師の関わり方が非常に重要です。以下の点を意識して、子どもたちが安心して活動できる環境を作りましょう。
- ポジティブな雰囲気作りを徹底する
伝言ゲームの醍醐味は、お題がだんだん変わっていく面白さにあります。「間違えたらダメ」という雰囲気ではなく、「どんな風に変わったかな?」「面白い間違いだね!」と、変化そのものを楽しめるような声かけを心がけましょう。失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性が、子どもたちの自発的なコミュニケーションを促します。 - ルールの明確化と視覚的支援
特に活動に慣れていない子どもたちや、指示の理解が難しい子どもたちのためには、ルールを明確に、そしてシンプルに伝えることが大切です。「お口はチャック」「聞くときはお耳をダンボに」といったキャッチーな言葉を使ったり、イラストで手順を示したりする視覚的な支援も有効です。 - 振り返りの時間を大切にする
ゲームが終わったら、それで終わりではありません。「どこから言葉が変わったんだろう?」「どうしてそう聞こえたのかな?」と全員で振り返る時間を作りましょう。このプロセスを通じて、子どもたちは「『さかな』と『たかな』は音が似ているな」「早口で言うと伝わりにくいんだな」といった、コミュニケーションにおける具体的な気づきを得ることができます。これは、自分たちのコミュニケーション行動を客観的に見るメタ認知能力を育む上でも重要です。 - 個々の目標に合わせたスモールステップ
すべての子どもが同じようにできるわけではありません。話すのが苦手な子、聞くのが苦手な子、様々です。教師は一人ひとりの実態を把握し、「今日は最後まで座って参加できたらOK」「一言でも次の人に伝えようとしたら素晴らしい」など、個別の目標(スモールステップ)を設定し、その子の頑張りを具体的に認め、褒めてあげることが自己肯定感を育みます。
まとめ
伝言ゲームは、ルールが簡単で準備もほとんど必要ないにもかかわらず、子どもたちの多様なソーシャルスキルを育むことができる、非常に優れたSST教材です。
本記事で紹介したように、自立活動の「人間関係の形成」や「コミュニケーション」の項目と深く結びついており、明確なねらいを持って実施することで、その教育的価値は飛躍的に高まります。
幼児向けの簡単な言葉から、小学生が爆笑する面白いお題、高学年が頭を悩ませる難しいお題、そして滑舌のトレーニングにもなる早口言葉まで、お題を工夫するだけで子どもたちの反応は大きく変わります。さらに、ジェスチャーやイラストを取り入れたアレンジ・バリエーションを加えることで、活動はマンネリ化することなく、常に新鮮な学びの場であり続けるでしょう。
最も大切なのは、教師がファシリテーターとして、失敗を笑い飛ばせる温かい雰囲気を作り、子ども一人ひとりの小さな成長を見逃さずに価値づけていくことです。この記事が、先生方のSSTの実践の一助となり、子どもたちの笑顔と成長につながることを心から願っています。




コメント