何を言ってもクイズ」難問100選でコミュニケーション力UP!SST/学級レク実例集
「クラスが盛り上がるレクを探している」「SST(ソーシャルスキルトレーニング)に使える簡単なゲームはないかな?」
そんなお悩みを持つ先生や支援者の方に、今回自信を持っておすすめするのが「何を言ってもゲーム」です。
このゲームは、「言わんのバカクイズ」としても知られ、ルールは至ってシンプル。相手に特定の言葉を何度も言わせて、最後にうっかり言い間違いを誘う言葉遊びです。しかし、その単純さの裏には、子どもたちの様々な能力を引き出す奥深い要素が隠されています。
この記事では、
「何を言ってもゲーム」の基本的なルールから、思わず笑ってしまう面白い問題、頭を抱えるほど難しい超難問まで、具体的な問題例を豊富にご紹介します。
さらに、この記事の最大の特徴は、「何を言ってもゲーム」がなぜSSTや特別支援教育における「自立活動」に非常に効果的なのかを、学習指導要領の「6区分27項目」に基づき、専門的かつ分かりやすく徹底解説する点です。
この記事を読めば、以下のことがすべて分かります。
- 「何を言ってもゲーム」の詳しいルールと遊び方
- SSTの専門的な観点から見た、このゲームが持つ驚くべき教育効果
- 支援学級(自立活動)で実践する際の具体的な進め方と配慮点
- 通常学級(学級レク)でクラス全員が盛り上がるための工夫
- 初心者向けから超上級者向けの何を言ってもクイズ 難問・面白い問題例まで100選
おすすめのSST教材はこちら💁
📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!
「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。
登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。
PDFの受け取りは、たったの30秒!
以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。
所見の作成がぐっと楽になると思います。
▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼
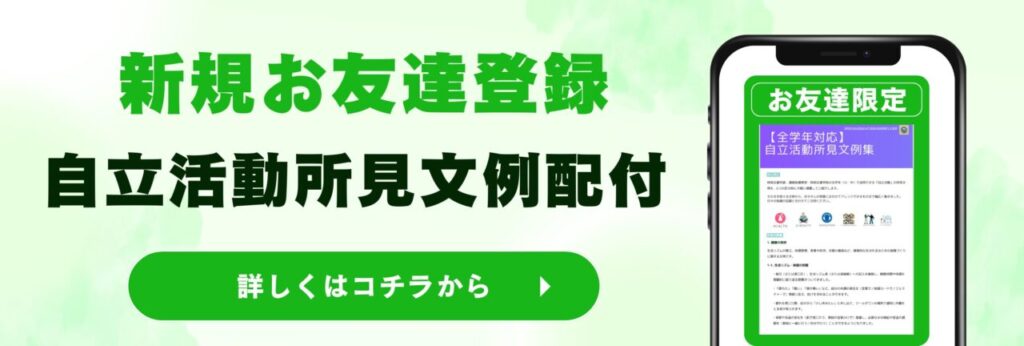
書籍のご案内
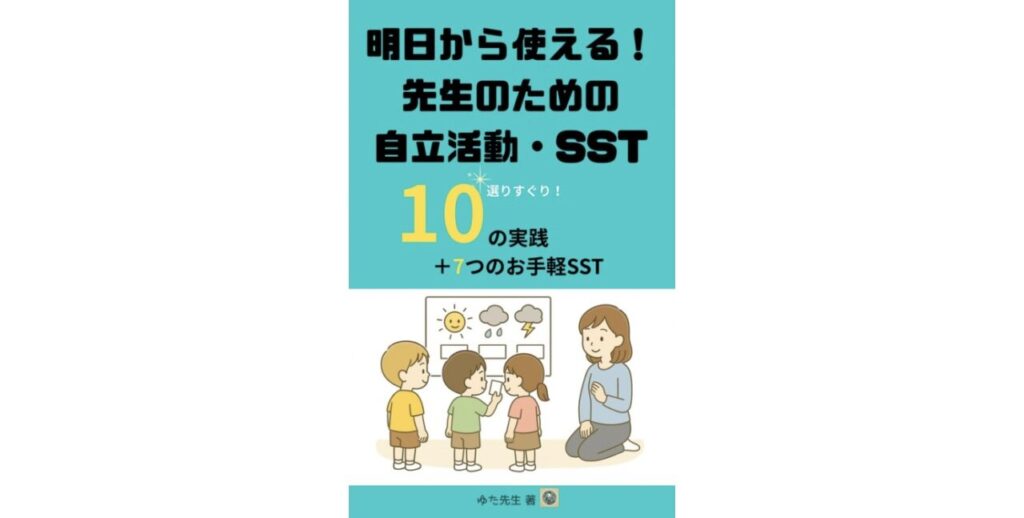
私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。
知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。
✨おすすめの【note教材セット】
noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。
これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇
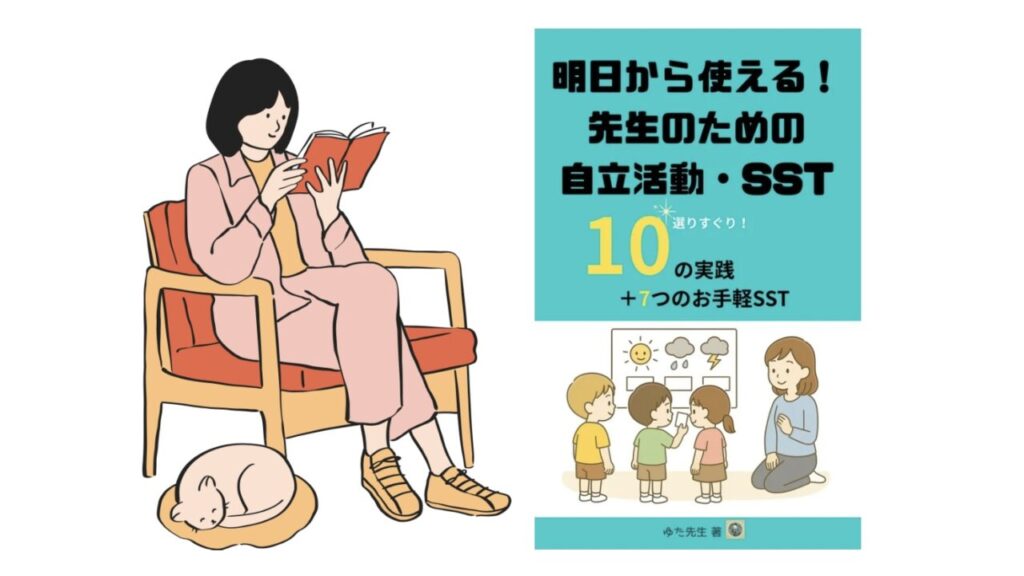
「何を言ってもゲーム」とは?基本ルールと魅力
「何を言ってもゲーム」は、1990年代にラジオ番組の人気コーナーから生まれた言葉遊びです。当時は「言わんのバカクイズ」という名前で親しまれていました。
ルールは非常にシンプルで、2人以上いればいつでもどこでも楽しむことができます。
基本的なルール
1. 出題者を決める: 最初にクイズを出す人(出題者)を1人決めます。
2. お題の言葉を宣言する: 出題者は、解答者に対して「これから私が何を言っても、『〇〇』とだけ答えてください」と、繰り返してほしいキーワード(お題)を伝えます。
3. 質問を繰り返す: 出題者は、解答者に様々な質問を投げかけます。解答者は、どんな質問をされても、ひたすらお題の言葉を繰り返します。
4. 引っ掛け問題を出す: 解答者がお題を言うことに慣れてきたタイミングで、出題者は意図的にお題の言葉そのものを答えさせるような質問(引っ掛け問題)をします。
5. 言い間違えたら負け: 解答者がうっかりお題以外の言葉(質問の答え)を言ってしまったら、出題者の勝ちです。

【例:お題が「ピザ」の場合】
• 出題者: 「君の名前は?」
• 解答者: 「ピザ」
• 出題者: 「昨日の晩御飯は?」
• 解答者: 「ピザ」
• 出題者: 「僕が今一番食べたいものは、ピザだけど何だっけ?」
• 解答者: 「ピザ!」
• 出題者: 「じゃあ、これは?」と肘(ひじ)を指さす。
• 解答者: 「ひじ!」→ 言い間違い!出題者の勝ち!
この例では、「ピザ、ピザ、ピザ…」と繰り返させた後、全く関係のない「ひじ」を答えさせています。脳が「ピザ」と繰り返すことに慣れているため、つい違う単語が出てきてしまうのです。この「うっかり」を誘うのが、このゲームの醍醐味です。
シンプルなのに奥深い!ゲームの魅力
このゲームの魅力は、単なる言葉遊びに留まらない点にあります。
• 準備が不要: 紙やペンなどの道具は一切必要ありません。思い立ったらすぐに始められます。
• 年齢を問わず楽しめる: お題の言葉を簡単なものにすれば、幼児から大人まで一緒に楽しむことができます。
• 心理戦の要素: 出題者は「どうやって相手を引っ掛けようか」と考え、解答者は「次は何で引っ掛けてくるだろう」と予測します。この駆け引きがゲームを盛り上げます。
• コミュニケーションの活性化: 質問と応答を繰り返す中で、自然と会話が生まれます。笑いが起きやすく、場の雰囲気を和ませる効果も抜群です。
そして何より、このゲームはSST(ソーシャルスキルトレーニング)や自立活動の教材として、非常に優れた側面を持っています。次の章では、その教育的価値について詳しく掘り下げていきましょう。
【SSTゲームに最適】「何を言ってもゲーム」が自立活動を促す理由
「何を言ってもゲーム」は、ただ面白いだけでなく、特別支援教育における「自立活動」の目標を達成するための優れた教材となり得ます。ここでは、自立活動の「6つの区分」と「27の項目」に沿って、このゲームが子どもたちのどのような力を育むのかを具体的に解説します。

自立活動とは?
自立活動とは、障害による学習上または生活上の困難を主体的・積極的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うための指導です。以下の6つの区分に分けられています。
1. 健康の保持
2. 心理的な安定
3. 人間関係の形成
4. 環境の把握
5. 身体の動き
6. コミュニケーション
「何を言ってもゲーム」は、これらの区分に含まれる多くの項目に働きかけることができるのです。
1. 健康の保持への貢献
• 項目:心身の健康状態の維持・改善
• ストレスの軽減: ゲーム中の笑いは、心身の緊張を和らげ、ストレスを軽減する効果があります。楽しい活動を通して、気分を転換し、リフレッシュすることができます。
• 健康的な生活リズムの形成: 活動と休息の切り替えを学ぶきっかけになります。集中してゲームに取り組む時間と、終わってリラックスする時間のメリハリをつける練習にもなります。
2. 心理的な安定への貢献
• 項目:状況に応じた適切な行動
• ゲームのルールを守って遊ぶことを通して、その場の状況や文脈に合わせた行動をとる練習になります。「今はふざけていい時」「今は集中して聞く時」といった状況判断能力を養います。
• 項目:欲求や感情の調整
• 負けた時の悔しさや、勝った時の嬉しさなど、ゲームを通して生まれる様々な感情をコントロールする訓練になります。「負けても相手を責めない」「勝っても威張らない」といった、感情の適切な表出を学ぶ良い機会です。
• 項目:自己の理解と行動の調整
• 「自分は引っかかりやすいな」「意外と集中力が続くな」など、ゲームを通して自分自身の特性に気づくことができます。自分の得意・不得意を理解し、次からはどうすれば上手くいくかを考える(作戦を立てる)ことは、自己理解と行動調整の第一歩です。
3. 人間関係の形成への貢献
• 項目:他者との関わりの基礎
• 出題者と解答者という役割を交互に体験することで、相手の立場を理解し、円滑な人間関係を築く基礎を学びます。視線を合わせる、相手の話を聞くといった基本的な社会的スキルも自然と促されます。
• 項目:自己の役割の遂行
• 出題者、解答者、あるいは応援する人など、自分がその場で果たすべき役割を理解し、責任をもって行動することを学びます。
• 項目:集団への参加
• チーム対抗戦などのルールを導入すれば、仲間と協力する、応援するといった集団参加の態度を育てることができます。チームの勝利のために貢献する喜びや、仲間と気持ちを分かち合う経験は、社会性を育む上で非常に重要です。
4. 環境の把握への貢献
• 項目:感覚の基本的な機能の向上
• 出題者の言葉を正確に聞き取る「聴覚」や、表情やジェスチャーを読み取る「視覚」をフル活用します。特に、引っ掛け問題に備えて相手の言葉や様子に注意を向けることは、感覚機能を統合的に使う良い訓練になります。
• 項目:認知や行動の手掛かりの活用
• 「そろそろ引っ掛けが来そうだ」「この流れは怪しいぞ」といった、相手の意図や状況の「手掛かり」を見つけて、自分の行動(応答)を判断する練習になります。これは、危険予知や状況判断能力に繋がる重要なスキルです。
• 項目:物との関わりと空間の認知
• ゲームの中で「あれ取って」と物を指さしたり、「あっち向いて」と方向を示したりする質問を取り入れることで、物や空間を正しく認知する力を養うこともできます。
5. 身体の動きへの貢献
• 項目:姿勢と運動・動作の基本
• 話を聞く時の姿勢や、はっきりと発音するための口の動きなど、基本的な身体のコントロールが求められます。特に、発話に課題のある子どもにとっては、楽しみながら発声練習ができる機会となります。
• 項目:身体のイメージの形成
• 「ひじ」「ひざ」など、身体の部位を引っ掛け問題に使うことで、自分の身体の各部分を意識し、ボディイメージを豊かにすることに繋がります。
6. コミュニケーションへの貢献
このゲームが最も直接的に効果を発揮するのが、この区分です。
• 項目:受容・表出
• 相手の言葉を正確に聞き取る(受容)、お題の言葉をはっきりと発音する(表出)という、コミュニケーションの最も基本的なキャッチボールを何度も繰り返します。
• 項目:言語の形成と活用
• 様々な質問に触れることで、語彙を増やし、文脈を理解する力を養います。また、出題者になることで、相手に伝わるように質問を工夫する言語活用能力も育ちます。
• 項目:コミュニケーション手段の選択と活用
• 言葉だけでなく、表情や声のトーン、ジェスチャーといった非言語的なコミュニケーションも重要な要素となります。引っ掛ける側は意図的に声色を変えたり、解答者は相手の表情から意図を読み取ろうとしたりします。
このように、「何を言ってもゲーム」は遊びの中に学びの要素が豊富に含まれており、子どもたちが楽しみながら自然と社会性やコミュニケーションスキルを身につけていける、非常に優れたSST教材なのです。
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。
支援学級での「何を言ってもゲーム」進め方【SST・自立活動編】
支援学級で「何を言ってもゲーム」を自立活動として行う際は、楽しむことを第一に、子ども一人ひとりの実態に合わせたスモールステップでの導入と、意図的・計画的な指導が重要になります。
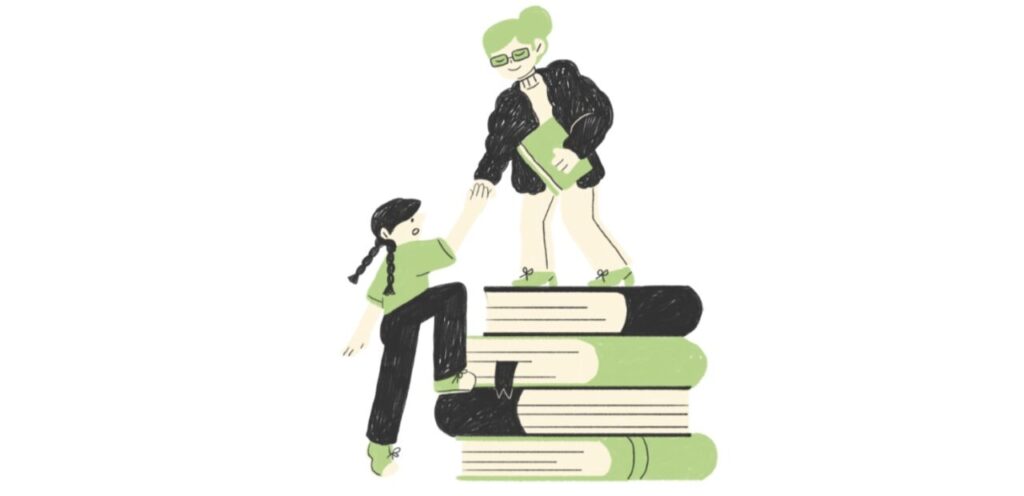
ねらい(指導目標)の明確化
まず、この活動を通して、どの子にどんな力をつけたいのか、具体的なねらいを定めます。
• 例1(注意・集中に課題がある子): 5回連続で指示された言葉を言い続けることができる(注意の持続)。
• 例2(衝動的に答えてしまう子): 引っ掛け問題に対して、一呼吸おいてから答えることができる(衝動性のコントロール)。
• 例3(他者との関わりが苦手な子): 友達とペアになり、笑顔で活動に参加できる(コミュニケーションへの意欲)。
• 例4(負けを受け入れるのが難しい子): ゲームで負けても、気持ちを切り替えて「もう一回やろう」と言うことができる(感情の調整)。
ねらいを明確にすることで、指導者の声かけや支援の仕方が具体的になります。
ゲームの進め方と配慮点
1. ルールの丁寧な説明とデモンストレーション
• 口頭での説明だけでなく、指導者同士や、理解の早い子と指導者でやってみせる(モデリング)ことが非常に効果的です。
• 「〇〇って言ってね」という指示を、ホワイトボードに書いたり、絵カードで提示したりする視覚支援も有効です。「今は『りんご』の時間」ということが一目で分かると、子どもたちは安心して活動に取り組めます。
2. スモールステップで成功体験を積ませる
• ステップ1:簡単な単語から始める
• 「いぬ」「ねこ」「りんご」など、子どもにとって身近で言いやすい1〜2音節の単語から始めましょう。
• ステップ2:回数を少なくする
• 最初は質問2〜3回ですぐに引っ掛け問題を出します。ルールを理解し、成功体験を積むことを優先します。
• ステップ3:引っ掛けを分かりやすくする
• 「これは何?」と明らかに違うものを見せるなど、最初は誰でも分かるような簡単な引っ掛けにします。
• ステップ4:徐々に難易度を上げる
• 慣れてきたら、お題の言葉を長くしたり、質問の回数を増やしたり、引っ掛けを巧妙にしたりしていきます。
3. ポジティブな雰囲気作り
• 一番大切なのは**「間違えても大丈夫」**という安心感のある雰囲気です。
• 引っかかってしまった子に対して、「あー、引っかかっちゃったね!おしかった!」「〇〇って言いたくなるよね、わかるわかる!」と、笑いに変えるような声かけをしましょう。
• 出題者がうまく引っ掛けられたら、「ナイスプレー!」「引っ掛け上手だね!」と褒めます。解答者が引っ掛からなかったら、「すごい集中力だ!」「よく我慢できたね!」と、その過程を称賛します。
• 勝敗よりも、ルールを守って楽しく参加できたこと自体を価値づけることが重要です。
4. 振り返りの時間を設ける
• ゲームが終わったら、簡単な振り返りを行いましょう。
• 「どこが面白かった?」「どんな時に引っかかりそうになった?」「次はどんな言葉でやってみたい?」などと問いかけることで、子どもたちは活動を客観的に捉え、次への意欲に繋げることができます。
• ここで、「悔しかったけど、次は頑張ろうと思った」「友達が応援してくれて嬉しかった」といった気持ちを言葉にさせることで、感情の言語化や自己理解を促します。
支援学級での実践は、子どもたちの「できた!」という自己肯定感を育む絶好の機会です。一人ひとりのペースに合わせて、焦らずじっくりと取り組んでみてください。
通常学級での「何を言ってもゲーム」進め方【学級レク編】
通常学級で学級レクとして行う場合は、クラス全体の一体感を高め、誰もが楽しめるような工夫を取り入れると、さらに盛り上がります。

ねらい
• クラスの仲間と笑い合い、楽しい時間を共有することで、人間関係を深める。
• ルールを守って遊ぶことの大切さを学ぶ。
• 友達の面白い一面を発見し、互いの理解を深める。
おすすめの進め方
1. アイスブレイクとして個人戦
• まずは先生が出題者となり、数人の生徒を指名してデモンストレーションを行います。クラス全体でゲームのルールと面白さを共有しましょう。
• その後、隣の席の友達とペアになって、お互いに出題し合う活動も手軽でおすすめです。
2. チーム対抗戦で盛り上がる!
• クラスをいくつかのグループ(班)に分け、チーム対抗戦にすると非常に盛り上がります。
2. 【チーム対抗戦ルール案】
• 各チームから代表者を1人ずつ出す。
• 出題者(先生または各チームの代表)が、代表者全員に同じお題で質問をしていく。
• 最初に言い間違えた人から抜けていき、最後まで残った人のチームにポイントが入る。
• これを繰り返し、最終的な合計ポイントで優勝チームを決める。
3. 司会者(出題者)を工夫する
• 先生が出題者を務めるのも良いですが、子どもたちの中から「司会者役」を立てるのもおすすめです。人前で話す練習になりますし、子どもならではのユニークな質問が飛び出して、予想以上に盛り上がることもあります。
• 司会者は、ただ質問するだけでなく、解答者の様子を実況したり、大げさなリアクションをとったりして、場を盛り上げる役割も担えるとさらに良いでしょう。
4. 学年別の難易度調整
• 低学年: 「パン」「つくえ」など、身近な2〜3文字の言葉がおすすめです。引っ掛けも、「これなあに?」と物を指さすなど、視覚的に分かりやすいものが良いでしょう。
• 中学年: 少し長めの言葉(「チョコレート」「フライドポテト」)や、同音異義語(「かき(柿・牡蠣)」)などを入れると面白くなります。質問も少しひねったものを入れてみましょう。
• 高学年: 早口言葉(「生麦生米生卵」)、ことわざ(「猿も木から落ちる」)、歴史上の人物(「織田信長」)など、知識や思考力が必要なお題に挑戦させると、知的なゲームとして楽しめます。引っ掛けも、より巧妙で心理的な駆け引きが楽しめるようなものが良いでしょう。
学級レクで大切なのは、全員が参加でき、疎外感を感じる子がいないように配慮することです。内気な子も、出題者になったり、チームの応援をしたりと、何らかの形で関われるような役割を用意してあげると、クラス全体の満足度が高まります。
【決定版】何を言ってもクイズ 問題例 大集合!
お待たせしました!ここでは、様々なレベルの「何を言ってもゲーム」の問題例を100個、一挙にご紹介します。これさえあれば、もうお題に困ることはありません!

ウォーミングアップ!簡単な問題例(子ども向け)
まずは誰でも楽しめる簡単な単語から。
1. パン → 引っかけ:「これはフライパンだけど、何だっけ?」
2. いぬ → 引っかけ:「君は犬派?猫派?」
3. りんご → 引っかけ:「アップルパイの中身って何?」
4. バナナ → 引っかけ:「信号の黄色って、進め?止まれ?」
5. くるま → 引っかけ:「救急車を呼ぶ番号は?」
6. でんしゃ → 引っかけ:「自転車に乗れる人?」
7. つくえ → 引っかけ:「これは何?」(自分の靴を指す)
8. ごはん → 引っかけ:「朝、昼、晩に食べるものは?」
9. うさぎ → 引っかけ:「カメと競争して負けたのは誰?」
10. ねこ → 引っかけ:「ニャーと鳴く動物は?」
11. さかな → 引っかけ:「お寿司のネタで好きなものは?」
12. えほん → 引っかけ:「図書室で借りるものは?」
13. みかん → 引っかけ:「こたつで食べたくなる果物は?」
14. いちご → 引っかけ:「ショートケーキの上に乗っている赤いものは?」
15. たいよう → 引っかけ:「夜空に輝くのは月だけど、昼間輝くのは?」
【何を言ってもゲーム 面白い】笑いを誘う傑作問題例
思わず笑ってしまうような、面白いキーワードや引っ掛けの組み合わせです。
1. おしり → 引っかけ:「桃太郎が生まれたのはどこから?」
2. ブラジル → 引っかけ:「日本の首都はどこ?」
3. カツカレー → 引っかけ:「昨日のお昼、何食べたんだっけ?」
4. なんでやねん → 引っかけ:「今の気持ちをツッコミでどうぞ!」
5. 校長先生 → 引っかけ:「この学校で一番偉い先生は誰?」
6. Youtuber → 引っかけ:「君の将来の夢は何?」
7. 給食費 → 引っかけ:「保護者の皆様、ご協力をお願いします!」
8. 宿題 → 引っかけ:「夏休みの最終日に焦ってやるものは?」
9. ヘディング → 引っかけ:「サッカーで手を使っちゃダメなのは当たり前だけど、頭は?」
10. おなら → 引っかけ:「(真顔で)今、なんか臭くない?」
11. まゆげ → 引っかけ:「目の上にある毛のこと、なんて言う?」
12. 鼻毛 → 引っかけ:「マスクで隠れている部分のお手入れ、してる?」
13. すいません → 引っかけ:「(わざとぶつかって)あっ、ごめんなさい!」
14. 大丈夫 → 引っかけ:「(心配そうに)顔色悪いけど、どうしたの?」
15. 筋肉 → 引っかけ:「(力こぶを作って)俺のこのパワーの源は?」
16. タピオカ → 引っかけ:「黒くて丸くてモチモチした飲み物、何だっけ?」
17. 推ししか勝たん → 引っかけ:「君の座右の銘を教えて!」
18. ぴえん → 引っかけ:「悲しい時、どんな気持ちになる?」
19. 課長 → 引っかけ:「部長の一個下の役職って何?」
20. おつかれさま → 引っかけ:「仕事終わりの挨拶は?」
【何を言ってもクイズ 難しい】上級者向け!難易度MAXの問題例
早口言葉や似た音の言葉、長いカタカナ語などを使った、難易度の高い問題です。
1. 東京特許許可局 → 引っかけ:「日本の首都はどこ?」
2. 赤巻紙青巻紙黄巻紙 → 引っかけ:「この紙の色、何色?」
3. かえるぴょこぴょこみぴょこぴょこ → 引っかけ:「雨の日に出てくる緑の生き物は?」
4. 肩たたき券 → 引っかけ:「母の日にあげると喜ばれるものは?」
5. シチュー → 引っかけ:「これは何?」(指で数字の「4」と「2」を作る)
6. シャンソンショー → 引っかけ:「有名な歌手のことを何て言う?」
7. マサチューセッツ州 → 引っかけ:「アメリカの首都はワシントンD.C.だけど、ここはどこ?」
8. プログラミング → 引っかけ:「コンピューターに指示を出すことを何て言う?」
9. アクアパッツァ → 引っかけ:「魚介類を煮込んだイタリア料理の名前、何だっけ?」
10. サブスクリプション → 引っかけ:「月額料金を払って利用するサービスのこと、何て言う?」
11. スタグフレーション → 引っかけ:「景気が悪いのに物価が上がる現象って何?」
12. コンプライアンス → 引っかけ:「企業が法律やルールを守ることを何て言う?」
13. バスガス爆発 → 引っかけ:「隣の客はよく柿食う客だ。じゃあこれは?」
14. きゃりーぱみゅぱみゅ → 引っかけ:「『にんじゃりばんばん』を歌っている歌手は誰?」
15. 万有引力 → 引っかけ:「リンゴが木から落ちるのを発見した法則は何?」
16. しょうゆ → 引っかけ:「醤油、ソース、味噌、お寿司につけるのは?」
17. シカ → 引っかけ:「奈良公園にたくさんいる動物は?」
18. イルカ → 引っかけ:「水族館でジャンプする賢い動物は?」
19. ケンタッキー → 引っかけ:「クリスマスの定番チキンといえば?」
20. ピスタチオ → 引っかけ:「緑色でナッツの女王と呼ばれるのは?」
【何を言ってもクイズ 難問】頭をフル回転させる超難問に挑戦!
知識、発想力、そして強い意志がなければクリアできない超難問です。
1. 二酸化炭素 → 引っかけ:「植物が光合成で吸うものは?」
2. 平方根 → 引っかけ:「ルートって日本語で言うと何?」
3. 徳川家康 → 引っかけ:「江戸幕府を開いた人は誰?」
4. モナ・リザ → 引っかけ:「レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた有名な絵画は?」
5. 円周率 → 引っかけ:「3.141592… この数字は何?」
6. 右 → 引っかけ:「(相手の左手を指さして)こっちの手はどっち?」
7. いいえ → 引っかけ:「あなたはこのゲームで絶対に引っかかりませんか?」
8. 白 → 引っかけ:「パンダの体の色は何色と何色?」
9. 10回 → 引っかけ:「『好き』って10回言ってみて。じゃあ、これは何回目?」
10. マグマ → 引っかけ:「火山の噴火で出てくる熱い液体は?」
11. ピラミッド → 引っかけ:「エジプトにある三角形の巨大な建物は何?」
12. ひらがな → 引っかけ:「あ、い、う、え、お。これは何?」
13. 日本 → 引っかけ:「私たちが住んでいる国はどこ?」
14. チョキ → 引っかけ:「(自分はグーを出しながら)じゃーんけーん…」
15. 水曜日 → 引っかけ:「今日は火曜日だけど、明日は何曜日?」
まだまだあります!お題ライブラリー(71〜100)
1. ドラえもん
2. ジャンケンポン
3. メリークリスマス
4. あけましておめでとう
5. アンパンマン
6. スマートフォン
7. リモートワーク
8. 鬼滅の刃
9. エビデンス
10. アジェンダ
11. ロジカルシンキング
12. モチベーション
13. ダイバーシティ
14. インフルエンサー
15. SDGs
16. ペペロンチーノ
17. ミネストローネ
18. ティラミス
19. ガトーショコラ
20. モンブラン
21. パエリア
22. ビビンバ
23. トムヤムクン
24. タンドリーチキン
25. 生春巻き
26. シンギュラリティ
27. ベーシックインカム
28. ブロックチェーン
29. メタバース
30. AI(エーアイ)
ゲームをさらに面白くするアレンジルール
基本的なルールに慣れてきたら、少しアレンジを加えることで、ゲームの楽しさがさらに広がります。
• スピードアップルール: 出題者は徐々に質問のテンポを速くしていきます。解答者はそれに合わせて素早く答えなければならず、焦りが言い間違いを誘います。
• ジェスチャー付きルール: お題の言葉を言う時に、決められたジェスチャーをしなければならないルール。「りんご」なら丸を作る、「ねこ」なら猫のポーズなど。頭と体を同時に使うため、難易度が上がります。
• 声色変化ルール: 「怒った声で」「悲しい声で」「ロボットみたいに」など、出題者が指示した声色でお題を言わなければならないルール。演技力が試され、見ている方も楽しめます。
• サバイバルルール: 全員で立ち、一人の出題者に対して全員が答えます。間違えた人から座っていき、最後まで立っていた人が勝ち、という勝ち残り方式です。大人数でやる時に一体感が生まれます。
まとめ
今回は、シンプルながらも非常に奥深く、SSTや学級レクに最適な「何を言ってもゲーム」について、その魅力から教育的効果、具体的な進め方、そして豊富な問題例まで、徹底的に解説しました。
このゲームの最大の魅力は、誰もが笑顔になれることです。
引っ掛ける方も、引っかかる方も、見ている周りの人も、みんなで笑い合える。この共有体験は、子どもたちの心の距離をぐっと縮め、温かい人間関係の土台を築きます。
特に、SSTや自立活動の観点からは、楽しみながら**「聞く力」「集中力」「感情をコントロールする力」「状況を判断する力」**など、生きる上で大切なスキルを自然と育むことができる、まさに理想的な教材と言えるでしょう。
今日ご紹介した問題例やアレンジルールを参考に、ぜひ明日の活動から取り入れてみてください。きっと、子どもたちのこれまで見えなかった一面や、素晴らしい笑顔に出会えるはずです。




コメント