夏休みが近づくと、特別支援学級を担任する先生にとって悩ましいのが「宿題をどうするか」ということではないでしょうか。学力の定着はもちろん大切ですが、それだけではない、子どもたちの安心感や自己肯定感、そして家庭と学校のつながりを育む視点が何よりも重要です。
このブログ記事では、
特別支援学級の担任としての経験と、保護者の声、そして子どもたちの姿から見えてきた、夏休みの宿題のあり方について深掘りしていきます。
夏の課題にぴったりの教材はこちらから👇
夏休みの宿題も個別の指導計画からです👇
なぜ宿題を出すのか?特別支援学級ならではの視点
一般的に宿題は「学習習慣の維持」や「復習による定着」が目的とされます。しかし、特別支援学級においては、さらに多角的な意味を持つと私は考えています。
- 学習習慣の維持 長期休みの間、学習にまったく触れない生活を送ると、学校生活へのスムーズな復帰が難しくなることもあります。毎日少しでも「学びの時間」を作ることで、リズムを保てます。
- 家庭と学校のつながり 宿題は、学校とのつながりを感じられる大切な手段です。「できたよ!」「先生に見せたい!」という気持ちは、子ども自身の自己肯定感にもつながります。
- 親子の関係を深める機会 絵日記やお手伝いカードなど、親子で会話しながら取り組める課題は、家庭でのコミュニケーションのきっかけになります。特に「親子で一緒にできた」「話を聞いてもらえた」という体験は、何よりも価値のある“宿題の成果”と言えるでしょう。
保護者の「学習への不安」とどう向き合うか
実際には、保護者の方から「国語や算数のプリントも出してほしい」と要望されることも少なくありません。
その背景には、「周りに遅れてほしくない」という不安や、「何かしてほしいが、どう支援すればいいかわからない」という戸惑い、「他の家庭と比べられたくない」という焦りがあるように感じます。
こうした声に応えることも大切です。ただし、一律に“普通学級と同じ”プリントを出すことが正解とは限りません。むしろ、「量や形式は工夫しながら、目的に応じた学習課題を用意する」ことが必要不可欠です。
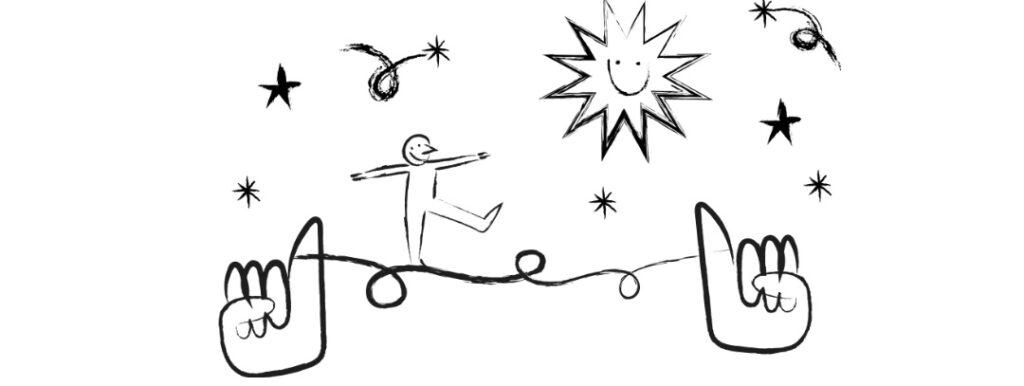
宿題は“訓練”ではなく“自信と安心”の材料に
支援学級の子どもたちにとって、宿題は成功体験につながるものであってほしいと私は思っています。
書くことが苦手な子に「毎日日記を書きなさい」は大きな負担ですし、算数が苦手な子に「10問ずつ計算プリントを10枚」では、むしろ嫌になってしまうかもしれません。
大切なのは、「これならできそう!」と思える分量と形式で提示すること。たとえ1日1枚のプリントでも、最後までやりきったときの達成感は、子どもにとって大きな自信になります。
【提案】教師の負担感を考慮した「基本+選択+自由」の3段階構成と、見通し・管理の工夫
宿題の設計として、私は教師の負担を軽減しつつ、子どもたちのニーズに応えられる次のような3段階構成をおすすめしています。さらに、子どもたちが無理なく取り組めるための、見通しと管理の工夫を加えます。
基本セット(全員共通・学習面中心)
これは、学習習慣の維持と基礎学力の定着を目的とした、全ての児童が取り組む共通課題です。
- 国語・算数のプリント:計10枚(1日1枚ペースで無理なく取り組める量)
- 教師の負担軽減ポイント: 丸付け用の答えを添付し、自己完結型にすることで、個別の採点作業を減らせます。
- 「できたら○」をつける記録表:日々の達成感を視覚的に実感できる工夫です。
【IEPとの連動と個別最適化の視点】
基本セットのプリントも、個々の発達段階や個別の教育目標に合わせて、必要に応じて難易度を調整したり、枚数を加減したりする柔軟な対応が理想です。例えば、特定の単元に苦手意識がある子には、その部分を重点的に、得意な子には少し発展的な内容を取り入れるなど、先生が無理のない範囲でカスタマイズできる余地を残しておきましょう。
選べる課題(個別ニーズや親子で選択)
子どもたちの興味や特性、家庭の状況に合わせて選択できる課題です。
- 音読カード(親子での読み合いもOK)
- 日記・絵日記(書くのが苦手な子には「ひとこと」や「絵のみ」も可とし、無理なく取り組めるようにします)
- お手伝いシート・生活スキルチェック表

【学習以外の側面の具体例とICTの活用】
- 「今日のいいこと3つ」話すカード:家族との会話のきっかけになるだけでなく、ポジティブな感情に目を向ける練習にもなります。
- お手伝いシートの工夫:ただ「お手伝いをした」だけでなく、「お手伝いをした時の気持ち」や「誰に感謝されたか」を書き込む欄を設けることで、感情の認識や他者とのコミュニケーションを促します。
- 「こんな時どうする?」シチュエーションカード:自分の気持ちを表現する練習として、様々な状況に対する対処方法や感情のコントロールについて考えるきっかけを作ります。
- QRコード付きの読み聞かせ動画:視聴してスタンプを押す形式で、読書に親しむきっかけを提供します。
- ICT活用例:
- 「音声で記録する課題」:好きな場所の写真を撮って、その場所について調べたことや感じたことを音声で記録します。書くことが苦手な聴覚優位の子どもに特に有効です。
- 簡単なプログラミングアプリ:夏休みの思い出をアニメーションで表現したり、簡単なゲームを作成したりして、論理的思考力や表現力を育みます。
子どもが「これならできそう」「これが好き」と思えるものを親子で一緒に選ぶことで、主体的な学習を促し、教師の個別課題作成の負担も分散できます。
自由課題(提出自由・安心して取り組める内容)
子どもたちの自主性や創造性を育むための、提出が自由な課題です。
- 夏の思い出を絵や写真にまとめる
- 好きなこと調べ(虫・電車・工作・料理など、子どもの興味を深掘りできるテーマ)
- 作ったものを紹介(写真や作品を持参する形式)
「やらなきゃ」というプレッシャーではなく、「やってみたい」という気持ちを引き出せる自由課題は、夏休みならではの豊かな経験につながります。先生はアイデアを提示するだけでよく、個別指導や評価の負担が少ないのも魅力です。
宿題の見通しを立てやすく、管理しやすくする工夫
特別支援学級の子どもたち、特にADHDの特性を持つお子さんにとって、宿題の物理的な整理と「やるべきこと」の可視化は非常に重要です。
- 「宿題セット」として封筒に収納 バラバラと渡すのではなく、全ての宿題を一つの大きな封筒(またはクリアファイルなど)にまとめて渡しましょう。こうすることで、「これを開けば夏休みの宿題が全て入っている」という安心感が生まれます。
- チェックリストを表紙に! 封筒の表に、宿題のチェックリストを大きく印刷して貼り付けます。
- 視覚的に分かりやすく: 項目ごとに簡単なイラストを添えたり、終わったらチェックマーク(✔)をつけられるスペースを設けたりすると、達成感にもつながります。
- やることを可視化: ADHDの特性を持つお子さんの中には、複数のタスクを同時に管理するのが難しい場合があります。リスト化することで「次に何をすればいいか」が明確になり、混乱を防ぎます。
- 保護者も安心: 保護者の方も、全体像を把握しやすくなり、支援がしやすくなります。
夏休み前に「取り組み方」を練習する
夏休みに入る直前、できれば終業式の1週間〜数日前に、夏休みの宿題の一部を使って「宿題の取り組み方」を学校で練習する時間を設けましょう。
- 宿題セットを開けるところから 封筒から宿題を取り出し、チェックリストを見ながら、最初の課題に取り組む一連の流れを先生と一緒にやってみます。
- 丸付けや記録の仕方も 自己完結型の宿題であれば、丸付けや記録表への記入の仕方も実際に練習しておくと、家庭での戸惑いを減らせます。
- 「困ったらどうするか」も確認 宿題でつまずいた時に「保護者に聞く」「一旦休憩する」など、具体的な対処法を子どもと一緒に確認しておくことも大切です。
この事前練習は、子どもたちにとって「安心して夏休みの宿題に取り組める」という見通しを与え、新学期へのスムーズな移行にもつながります。先生方の準備の手間はかかりますが、夏休み中の問い合わせやトラブルを減らすことにもなり、結果的に負担軽減につながるはずです。

保護者への説明・合意形成の進め方と夏休み明けのフォロー
宿題の意図や構成については、事前に保護者にわかりやすく伝えることが非常に大切です。誤解や不安を防ぎ、協働関係を築くために、私は次のようなメッセージを伝えるようにしています。
「夏休みの宿題は、お子さんの学習習慣を維持しながら、無理なく楽しく家庭で過ごせるように考えました。宿題は全てこの封筒にまとまっており、表紙のチェックリストを見ながら進められます。やり方や内容についてご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。ご家庭のご希望もお聞きしながら、お子さんに合ったかたちで取り組んでいきたいと考えています。」
「宿題ができなかった」場合の温かいフォロー
夏休み明けに宿題が「できなかった」子どもや保護者への配慮も忘れてはなりません。
- 決して責めない 宿題を提出できなかった場合でも、教師は決して子どもを責めず、「夏休み中に頑張ったこと、楽しかったことを教えてね」といったポジティブな声かけで、登校再開を温かく迎える姿勢が大切です。
- 完成度よりも経験を重視 宿題の完成度や量よりも、宿題を通して得た経験や、親子での会話、そして夏休みを楽しく過ごせたかどうかを大切にする旨を保護者にも事前に伝えておきましょう。これにより、保護者の「完璧にこなさなければ」というプレッシャーも軽減されます。
おわりに|「提出」がゴールではない宿題を
特別支援学級における夏休みの宿題は、単なる学習課題ではありません。それは、子どもたちが「自分なりにできた」「家族と一緒に取り組めた」「先生に見せたい」と思える、大切な“経験の記録”でもあります。
学習だけに偏らず、家庭での過ごし方に寄り添い、子どもが見通しを持って自信をもって取り組める。そして、先生の負担も考慮されたそんな宿題が、子どもたちの夏の生活をより豊かにし、新学期への希望へとつながると信じています。
この夏、子どもたち一人ひとりに寄り添った、実りある夏休みの宿題をデザインしてみませんか?
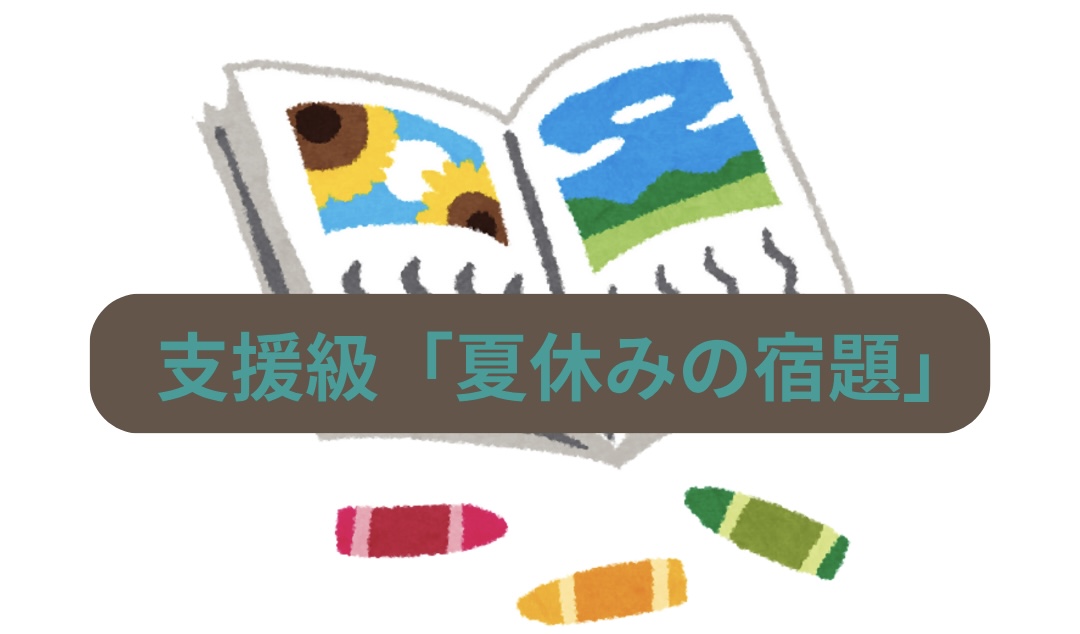





コメント