はじめに
「運動会、出たくない……」
そんなふうに子どもがつぶやいたとき、あなたならどう返しますか?
運動会は学校生活の中でも大きな行事のひとつ。でも、すべての子が楽しみにしているとは限りません。むしろ、緊張や不安、苦手なことへのプレッシャーを感じて、「できれば行きたくない」と思っている子も少なくないのです。
この記事では、子どもがそう感じている背景を丁寧に探りながら、保護者としてどのように寄り添い、関わるかを具体的にご紹介します。
【ステップ①】まずは「なぜ出たくないのか?」を探ることから
心の奥にある“困りごと”を見つける対話を
子どもが「行きたくない」と言うとき、それは単なるわがままではありません。
何かしら“困っていること”や“不安に思っていること”があるからこそ、そう感じているのです。
まず大切なのは、「なぜそう思っているのか」を一緒に探ってみること。
「出たくないなら出なくていい」とすぐに結論を出すのでもなく、「出なきゃダメ」と押しつけるのでもなく、まずは気持ちを聞く時間をつくりましょう。
【ステップ②】声をかけるときの“言葉”と“タイミング”
気持ちを受け止める言葉がスタートライン
子どもが「出たくない」と言ったときにかけたい言葉の例:
- 「そう思ってるんだね。ちゃんと話してくれてありがとう」
- 「運動会、しんどいなって思ってるんだね」
- 「どんなところが嫌なのか、教えてもらってもいい?」
これらの言葉は、子どもが自分の気持ちを整理しやすくなるきっかけになります。
NGワードの例:
- 「みんな頑張ってるのに、なんであなただけ……」
- 「どうせ楽しいから、大丈夫!」
- 「行かないと、恥ずかしいよ」
これらの言葉は、子どもの気持ちを否定することになってしまうため、注意が必要です。
聞くタイミングにも配慮を
- 疲れているとき(帰宅後など)は避ける
- 寝る前やリラックスしているときに声をかける
- 書いたり描いたりするツール(絵・カード)も活用する
【ステップ③】よくある“参加したくない理由”とその背景
保護者があらかじめ、子どもが運動会に苦手意識を持つ理由を知っておくと、対話もしやすくなります。
1. 大きな音が苦手(感覚過敏)
ピストルの音、応援の声、マイク音などに強い不快感を感じる子がいます。
対策例:
- イヤーマフや耳栓を使う
- 鳴る前に知らせる
- 拍手スタートなどに変更をお願いする

2. 人前に立つのが苦手
注目されると恥ずかしくて固まってしまう、失敗が怖いという子もいます。
対策例:
- 人が多い場面を見学だけにする
- 短時間だけ参加する
- 写真・ビデオ撮影は控えるようお願いすることも選択肢
3. チーム競技が苦手/勝ち負けに敏感
協調が苦手、ミスを責められるのが不安という子は、リレーや団体競技が大きなストレスになります。
対策例:
- 個人競技だけにする
- 成績より「やりとげたこと」にフォーカス
4. 練習疲れや体調不良
猛暑や繰り返される練習で、体力的・精神的に疲れているケースもあります。
対策例:
- 練習を部分的に休む
- 担任と連携しながら「できる範囲」を調整する
【ステップ④】保護者にできること5選
1. “完全な参加”だけがゴールじゃないことを伝える
子どもには、こう伝えてみてください。
「全部やらなくていいよ。できそうなところだけで大丈夫」
この安心感が、子どもを少し前に進ませてくれることもあります。
2. 学校に配慮をお願いする
担任の先生に、こう伝えてみましょう。
- 「本人が〇〇に強い不安を感じています」
- 「こういった対応があると、安心できるかもしれません」
先生も味方です。一緒に工夫を考えてくれることが多いです。
3. 当日の居場所をつくる
「競技には出ないけれど、見に行く」という形も選択肢です。
- 陰にテントを立てる
- 先生の近くにいてもらう
- 観客の少ない場所で見学
4. 子どもの“感じたこと”を一緒に振り返る
当日の様子を終わったあとに振り返ることで、次回につながります。
「あのとき頑張ってたね」
「出られなかったけど、話せたのがすごかったね」
5. 同じように悩んでいる保護者の声を探す
SNSやブログなどには、同じような悩みを持つ保護者の体験談があります。
「うちの子もそうだった」
「こういう対応でよかったよ」
そんな声が、あなた様を支えてくれることもあります。
おわりに
子どもが「運動会、出たくない」と言ったとき、戸惑いながらも向き合っている保護者の方へ。
きっと、あなた様の寄り添いが、子どもにとっての安心になります。
無理をさせないこと。
気持ちを尊重すること。
一緒に考えていくこと。
それが、子どもがまた一歩踏み出す力になります。
【あとがき】
もしこの記事を読んで、「これでよかったのかな?」と不安なままの気持ちが少しでも軽くなったなら、それが何よりです。
「できることは限られていても、思いは届く」
そう信じて、今日も子どもに寄り添うあなたを、心から応援しています。
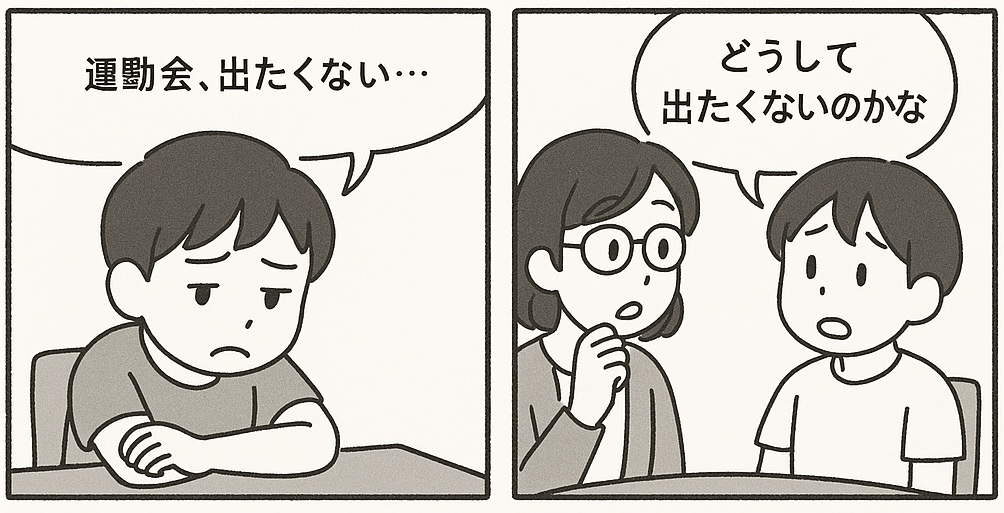


コメント