【2025年最新】通級とは?対象者は20万人超え!通級指導教室のキホンから支援級との違い、デメリットまで徹底解説

「最近、学校の先生から通級を勧められたけど、一体どんなところ?」
「うちの子、少し周りと違うかも…通級が必要な子ってどんな子?」
「通級って、もしかして恥ずかしいことなの…?」
先日、「通級指導を受ける小中高校生が初めて20万人を超えた」というニュースが発表されました。これは、お子さんの発達や学習について、多くの保護者の方が向き合い、新たな支援の形を求めている表れと言えるでしょう。
この記事では、
そんな関心が高まる「通級」について、基本的な知識から保護者の方が抱えるリアルな疑問まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事で解決できる疑問
- 通級とはどういう学級ですか?
- 通級と支援級の違いは何ですか?
- 通級が必要な子、通級判定基準は?
- 「グレーゾーン」でも利用できる?
- 通級のデメリットや、「恥ずかしい」という気持ちとの向き合い方
「通級とはどういう学級ですか?」急増する通級指導教室の基本
まず、一番の疑問である「通級とはどういう学級ですか?」にお答えします。
通級指導教室(通称:通級)とは、
小学校・中学校の通常学級に在籍しながら、一部の時間だけ別の教室へ移動して、個別の課題に応じた特別な指導を受けるための場所です。
あくまで在籍は「通常学級」にある、というのが大きなポイントです。国語や算数など、ほとんどの授業は在籍しているクラスでみんなと一緒に受けます。そして、週に数時間、決められた時間に「通級指導教室」へ通い、専門の先生からマンツーマン、または少人数でのサポートを受けます。

その目的は、子どもが抱える発達上の課題や学習のつまずきを改善・克服し、学校生活をより円滑に送れるようにすること。苦手な部分を補い、持っている力を最大限に発揮できるよう、いわば「オーダーメイドの学習支援」を行う場所とイメージしてください。
通級では、一人ひとりが「個別の指導計画」によって力を伸ばすことができるよう計画されます👇
「通級が必要な子はどんな子ですか?」対象となる子どもの特徴と通級判定基準
では、「通級が必要な子はどんな子ですか?」という疑問について見ていきましょう。
文部科学省によると、通級指導の対象となるのは、以下のような困難さを持つ子どもたちです。
- 言語障害:発音に誤りがある、吃音(どもり)があるなど。
- 自閉症スペクトラム(ASD):コミュニケーションが苦手、特定のことに強いこだわりがあるなど。
- 注意欠如・多動性障害(ADHD):集中力が続かない、忘れ物が多い、じっとしていられないなど。
- 学習障害(LD):知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」などの能力に著しい困難がある。
- 情緒障害:場面緘黙(特定の状況で話せなくなる)や、不安が強いなど。
- 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由:障害の程度が比較的軽い場合。
「グレーゾーン」の子どもも対象になる?
診断名はなくても、「集団行動が苦手」「読み書きに少し時間がかかる」といった、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる子どもたちも、通級指導の対象となるケースが増えています。大切なのは診断名ではなく、「その子自身が学校生活で何に困っているか」です。
気になる「通級判定基準」
「うちの子も対象になるの?」と気になったとき、基準となるのが「通級判定基準」です。
この基準は全国一律ではなく、お住まいの市区町村の教育委員会が定めています。一般的な流れは以下の通りです。
- 相談:保護者が担任の先生やスクールカウンセラーに相談する。
- 校内での検討:学校内の就学支援委員会などで、子どもの状況について情報共有・検討する。
- 就学相談・教育相談:市区町村の教育センターなどで、専門家(臨床心理士など)がお子さんの様子を見たり、保護者と面談したりする。
- 判定:教育委員会の審議会などで、提出された資料や面談結果をもとに通級利用の必要性を判断する。
- 決定・利用開始:保護者の同意のもと、通級の利用が決定します。
医師の診断書が必須というわけではありませんが、判断材料の一つとして提出を求められることもあります。まずは学校の先生に「通級について相談したいのですが」と伝えてみることが第一歩です。
「通級 どの程度?」利用頻度と具体的な指導内容
「通級 どの程度?」という利用頻度や時間も気になるところですよね。
利用頻度は、子どもの状況や学校の方針によって様々ですが、一般的には週に1〜2時間(1コマ45分〜60分)程度から始まることが多いです。年間で定められた時間数(例:年間35〜280時間)の範囲内で、個別指導計画に基づいて決められます。

指導内容は、一人ひとりの困りごとに合わせてカスタマイズされます。
指導内容の例
- 学習障害(LD)の子どもには…
- 文字と音を結びつける練習
- 文章をスラスラ読むためのトレーニング
- 計算の手順を視覚的に分かりやすく示す
- 自閉症スペクトラム(ASD)やADHDの子どもには…
- ソーシャルスキルトレーニング(SST):友達との関わり方、気持ちの伝え方などをカードやロールプレイングで学ぶ。
- 感情のコントロール方法(アンガーマネジメント)を学ぶ。
- 時間管理や整理整頓のスキルを身につける練習。
- 言語障害の子どもには…
- 正しい発音のための口の動かし方の練習。
- スムーズに話すための呼吸法や会話の練習。
このように、通常学級の一斉授業では難しい、きめ細やかなサポートを受けられるのが通級の大きな特徴です。
具体的な学習内容はこちらにまとめています👇
「通級と支援級の違いは何ですか?」在籍先と目的でスッキリ比較
通級とよく比較されるのが「特別支援学級(支援級)」です。この二つの「通級と支援級の違いは何ですか?」という疑問を、表で分かりやすく整理してみましょう。
| 項目 | 通級指導教室(通級) | 特別支援学級(支援級) |
|---|---|---|
| 在籍学級 | 通常学級 | 特別支援学級 |
| 主な目的 | 在籍学級での困難を改善・克服する | 子どもの実態に合わせた教育課程で学ぶ |
| 授業を受ける場所 | ほとんどの授業は通常学級で受け、一部の時間だけ通級教室に通う | ほとんどの授業を支援学級で受ける(交流学級として通常学級の授業に参加することもある) |
| 対象となる子 | 比較的、障害の程度が軽い子どもが中心 | 通級よりも手厚い支援が必要な子どもが中心 |
| イメージ | 学校内の「個別指導塾」のような存在 | 子どもに合わせたカリキュラムで学ぶ「少人数のクラス」 |
一番の違いは「学級籍がどこにあるか」です。通級はあくまで通常学級の一員であり、支援級は支援学級そのものが一つのクラスとして存在します。どちらが良い・悪いではなく、お子さんの特性や必要な支援の量によって選択肢が変わってきます。
通級と支援学級の違いはこちらに詳しくまとめています💁
「通級は恥ずかしい?」保護者が抱える不安と知っておきたいメリット
ここまで読んで、「内容は分かったけど、やっぱり特別な目で見られないか心配…」「通級 恥ずかしいと思ってしまう」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。その気持ちは、決して特別なものではありません。
しかし、20万人以上の子どもたちが利用している今、通級は決して「特別なこと」ではなくなっています。むしろ、子どもの個性に合わせた学びの機会を積極的に活用する、「賢い選択」と捉える見方が広がっています。
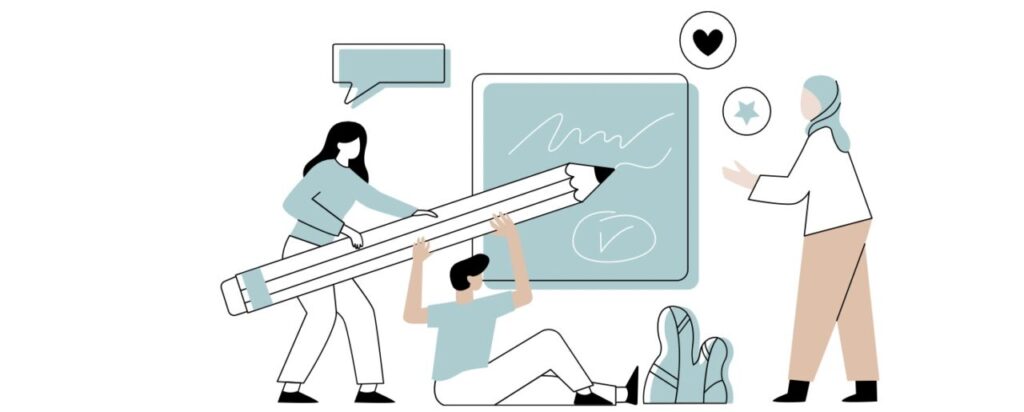
通級には、心配を上回るたくさんのメリットがあります。
- 専門的な支援:専門知識を持つ教員から、子どもの特性に合った指導を受けられる。
- 自己肯定感の向上:苦手なことに向き合い、「できた!」という成功体験を積むことで、自信がつく。
- 通常学級での適応力UP:通級で学んだスキルを活かし、通常学級での学習や友人関係がスムーズになる。
- 安心できる居場所:少人数で落ち着いた環境が、子どもの心の安定につながる。
- 保護者の安心:子どもの一番の理解者である通級の先生に、家庭での悩みや関わり方について相談できる。
通級は「できないことを指摘される場所」ではなく、「その子の強みを伸ばし、可能性を広げる場所」なのです。
知っておきたい「通級デメリット」とその対処法
メリットだけでなく、事前に知っておきたい「通級デメリット」も存在します。しかし、これらは事前に対処法を考えることで、影響を最小限に抑えることができます。
- デメリット①:通常学級の授業を一部受けられない
- 音楽や図工など、本人が好きな授業の時間と重なってしまうと、子どもが通級に行くのを嫌がることがあります。
- 対処法:学校側と相談し、時間割を調整してもらえないか検討しましょう。また、抜けた授業の内容は、担任の先生にフォローをお願いしたり、家庭で補ったりするなどの連携が大切です。
- デメリット②:周りの目が気になる
- 子ども自身が「自分だけ違う」と感じてしまったり、クラスメイトからからかわれたりする可能性はゼロではありません。
- 対処法:事前に担任の先生に相談し、クラスの子どもたちへ「誰にでも苦手なことはあり、それをサポートしてもらうのは当たり前の権利(合理的配慮)」という視点で、上手に説明してもらうようお願いするのが有効です。
- デメリット③:担任と通級担当との連携不足
- 情報共有がうまくいかず、通常学級での様子が通級の先生に伝わっていなかったり、その逆が起きたりすることがあります。
- 対処法:連絡帳などを活用し、保護者からも積極的に両方の先生へ情報を伝えることが重要です。「通級でこんな練習をしました」「クラスでこんなことができるようになりました」など、具体的な情報を共有することで、連携はよりスムーズになります。
まとめ:通級は、お子さんの可能性を広げるための「心強い味方」
今回は、今まさに利用者が急増している「通級」について、基本から具体的な内容、メリット・デメリットまでを詳しく解説しました。
- 通級とは、通常学級に在籍しながら、一部の時間、専門的な支援を受ける場所。
- 対象は、LDやASD、ADHDなどの診断がある子だけでなく、グレーゾーンの子も含まれる。
- 支援級との違いは、学級籍が通常学級にあること。
- 「恥ずかしい」という気持ちを持つ必要はなく、子どもの自信と可能性を伸ばすための有効な選択肢。
- デメリットもあるが、学校との連携で乗り越えられる。
通級指導の対象者が20万人を超えたという事実は、それだけ多くの子どもたちが個別の支援を必要とし、また、その支援によって学校生活をより豊かに送っている証拠です。
もし今、お子さんのことで少しでも悩んでいたり、学校から通級を勧められたりしているのであれば、まずは一度、学校の先生や地域の教育相談窓口に話を聞いてみてください。
通級は、お子さん一人ひとりが自分らしく輝くための「心強い味方」となってくれるはずです。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。







コメント