特別支援学級で日々子どもたちと向き合っていると、「学び」の形は本当に一人ひとり違うことを痛感します。理解のスピード、得意なこと、苦手なこと、興味の対象、集中力の持続時間…その多様性は、通常の学級以上に様々です。だからこそ、「みんな同じ」という一律の指導や課題では、すべての子どもたちの学びを保障することはできません。
特に「宿題」については、その子にとって本当に意味のある、そして負担になりすぎない形を丁寧に考える必要があると強く感じています。
以前、ある保護者の方と宿題についてお話していた際、「〇〇くんの今の学びのペースだと、この内容と量なら前向きに取り組めると思います」とお伝えしたところ、「そんなふうに丁寧に見て考えてくださるなんて…ありがたいです」と、とても安心した表情をされたのが印象的でした。
今回は、私が特別支援学級の担任としてどのように宿題と向き合っているか、なぜ「みんなと同じ」にしなくていいのか、そして保護者の方との連携の中で大切にしていることをお話しさせてください。
「みんな同じ」の宿題が馴染まない理由
私たちの特別支援学級には、発達の特性や学習に関する様々なニーズを持った子どもたちがいます。読むことに困難がある子、特定の感覚が過敏で集中を保つのが難しい子、鉛筆を持って文字を書くことに大きな負担を感じる子、体力が少なく学校で疲れ切ってしまう子…。
もし、こうした一人ひとりの特性や状態を考慮せず、内容も量も「クラス全員一律」の宿題を出したとしたら、どうなるでしょうか。
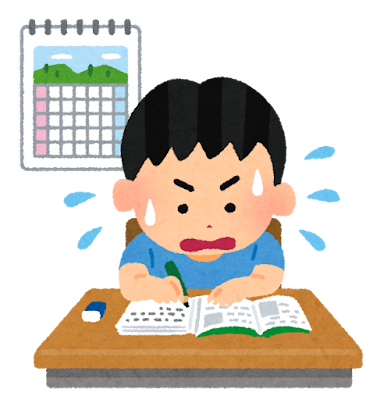
多くの時間をかけても終わらなかったり、難しすぎて全く手が進まなかったりするかもしれません。そして、それは「できない」「自分はだめだ」というネガティブな経験として、子どもの心に深く刻まれてしまいます。宿題を巡って、家庭が毎晩のように子どもと衝突する場になってしまい、子どもだけでなく保護者の方も精神的に追い詰められてしまうケースを耳にすることも少なくありません。
「宿題は、みんながやっているからやるもの」「やらないと頑張っていないことになる」といった、ある種の“常識”やプレッシャーが、かえって子どもたちの本来持っている学びへの興味や意欲の芽を摘んでしまい、家庭の安心できるはずの時間を奪ってしまうことがあるのです。
私は、「宿題をやる」こと自体が目的化してしまい、本来の「学びを深め、力をつける」という目的から離れてしまうような宿題は、支援学級の子どもたちには合わないと考えています。
個別支援計画と「その子のための宿題」
私が特別支援学級の宿題で何よりも大切にしているのは、「今、目の前にいる『この子』にとって、必要で意味のある学びにつながっているか」という視点です。私たちの学級の子どもたちは、一人ひとり異なる「個別支援計画」に基づき、それぞれの目標を持って学んでいます。宿題もまた、この個別の目標を達成するための、家庭でもできる支援・学習ツールであるべきだと考えています。
そのため、宿題の内容や量は、クラスの子どもたち全員が同じである必要は全くありません。むしろ、違っていて当然です。その子の今の学力、発達段階、特性、興味関心、そして何よりも「無理なく、できそうだなと感じながら取り組めるか」という、達成感や安心感をもって取り組めるか、という点を重視しています。
宿題は、「みんなに課せられる義務」というよりは、「この子の成長を後押しするための、オーダーメイドの学習機会」なのです。
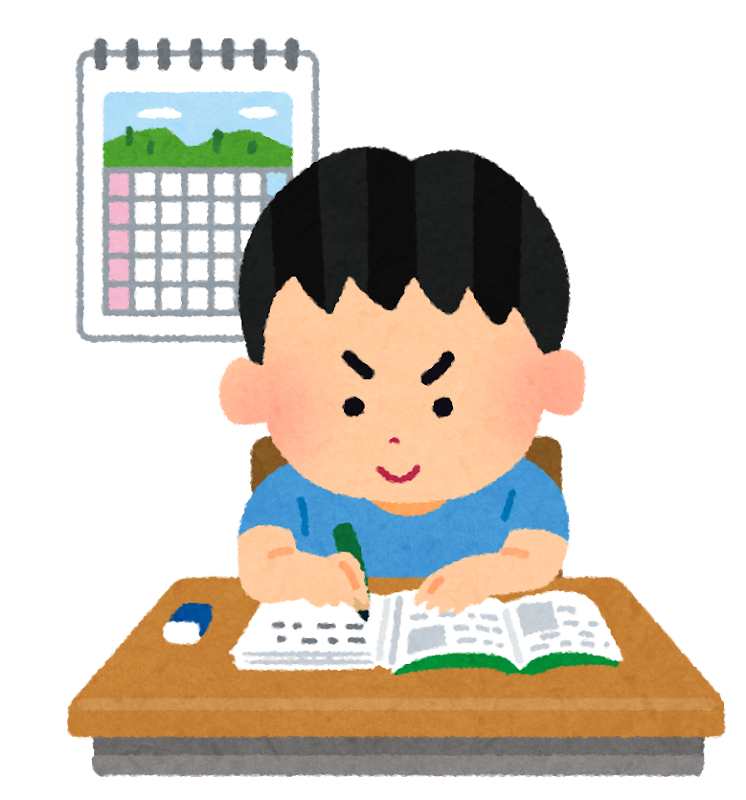
宿題は、保護者の方と共に考えるもの
この「その子のための宿題」を実現する上で、最も欠かせないのが保護者の方との密な連携です。私たちは学校で子どもたちの学習の様子を見ていますが、家庭での生活リズム、放課後の疲れ具合、宿題に対する本人の気持ち、そして保護者の方のサポート体制などは、保護者の方にしか分かりません。
私は、一方的に宿題を決めて出すのではなく、必ず保護者の方にご相談させていただきながら、一緒に宿題の形を決めるようにしています。最初にご家庭での宿題に関する状況や、お子さんの様子(疲れ具合、集中できる時間、宿題に対する気持ちなど)を丁寧に伺います。その上で、学校での学習状況や、個別支援計画におけるその子の目標を伝え、「この目標のためには、家庭でこんな取り組み方が考えられますが、いかがでしょうか?」「これくらいの量なら、無理なく続けられそうですか?」といった具体的な提案をしながら、一緒に無理なく続けられる現実的な方法を探っていきます。

保護者の方からは、「やらせなきゃと思っていたけど、こういうやり方でもいいんですね」「子どもの負担を気にしていたので、相談できて安心しました」といったお声をいただくことも少なくありません。家庭と学校が、「宿題を『やらせるか/やらせないか』」という対立構造になるのではなく、「どうすればこの子の学びにつながるか」という、子どもの育ちという中心軸で協力できる関係を築くこと。これが、支援学級における宿題の最も大切な前提だと感じています。
「その子のための宿題」具体的な調整例
実際、私のクラスでは、子どもたちの特性や学力、その時の状況に応じて、宿題の内容や量、やり方などを柔軟に調整しています。いくつか例を挙げます。
計算に不安がある子
計算のスピードや一度に解く量ではなく、「繰り上がり・繰り下がりの概念を理解する」「正しく筆算の形を書く」など、その子が今習得すべきポイントに絞ります。問題数を大幅に減らしたり、数図ブロックなどの具体的な教具やタブレット教材を併用することを提案したりすることで、計算そのものへの苦手意識を必要以上に高めることを防ぎ、概念理解に集中できるようにします。
書字に大きな負担がある子
鉛筆を持って文字を書くことが難しい場合、国語の音読の宿題は、声に出して読む練習をした後、保護者の方に内容を口頭で説明する形式にしたり、その様子を短く録音して提出してもらったりします。書くことの負担を減らしつつ、内容理解や要約力、表現力を養うことに焦点を当てます。
疲れやすく、日によって調子にムラが大きい子
毎日決まった量を課すのではなく、「今週中にこのプリントを〇枚、体調の良い日にやってみよう」としたり、日々の声かけで「今日はできそうだったら、まず1問やってみようか」「しんどかったら無理しなくていいよ」と伝えたりするなど、柔軟なスタイルにしています。「やらなければ」というプレッシャーを減らし、できる時にできる量に取り組むことで、学びから完全に離れてしまわないようにします。
特定の学習に強い苦手意識がある子:
漢字練習など、どうしても始めるまでにハードルが高い課題については、まずその子が比較的取り組みやすい、あるいは興味を持てる内容(好きなキャラクターの絵を添える、得意な計算ドリルから始めるなど)から始めて、小さな「できた!」という成功体験を積み重ねられるような構成にすることで、少しずつ自信を取り戻し、他の学習への意欲につなげていくことを目指します。
いずれの調整も、「みんなと同じ」にすることではなく、「今のその子の状態(できること、難しいこと)」と「この宿題で何を身につけてほしいか(学びの目的)」、そして「ご家庭の状況」に合っているか、そして「子どもの負担が大きすぎないか」を最も大切にしています。
「常識」よりも、「その子の育ち」に目を向けたい
「みんなと同じようにやらせるべきだ」「宿題をやらないと将来困るのは子ども自身だ」といった言葉を耳にすることがあります。もちろん、一般的な教育においては、そうした側面も否定できません。しかし、特別支援教育において、画一的な「常識」に囚われすぎると、かえって子どもたちの学びの機会を奪ったり、成長を妨げたりすることになりかねません。
私たち教師は、子どもたちの「できた!」という喜びや、学びたいという気持ちを何よりも大切にしたいと考えています。宿題の量ややり方を変えることは、決して「甘やかし」ではありません。むしろ、「今のあなたには、このような方法で、この部分を学ぶのが、力をつける上で一番の近道なんだよ」「あなたは、この方法ならできるようになる力を持っているんだよ」と、その子の状態を肯定し、自己肯定感や次につながる学習意欲を育むための、その子に合った、オーダーメイドの支援なのです。

そして、子どもが育つのは、学校の中だけではありません。家庭生活があってこそです。宿題を巡って家庭が疲弊してしまうことは、子どもの安心できる場所を奪うことにも繋がりかねません。だからこそ、私たちは「子どもの育ち」を真ん中に置き、必要であれば保護者の方の困りごとにも耳を傾け、学校としてできる範囲で“家庭も支援の対象”として捉え、共に歩んでいく姿勢が大切だと感じています。
おわりに
特別支援学級における宿題は、「みんなと同じ」という枠にとらわれる必要は全くありません。むしろ、その子が自分らしいペースと方法で学び、小さな「できた!」を積み重ね、自己肯定感を育んでいくための、オーダーメイドの学習機会であるべきです。
保護者の方との密な連携なくして、その子にとって本当に意味のある宿題は成り立ちません。これからも、一人ひとりの子どもたちの声、保護者の方の声に丁寧に耳を傾けながら、「この子に今、一番必要な学びの形は何だろう?」と問い続け、安心して取り組める、そして未来につながる宿題を提案していきたいと思います。子どもたちの笑顔と、ご家庭の安心のために、学校としてできる支援を続けていくこと。それが、特別支援学級担任としての私の何よりの願いです。

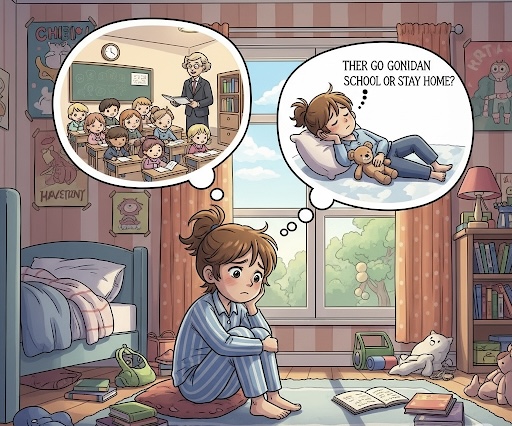
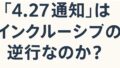

コメント