「特別支援学級の担任はしんどい?」教員の悩みとストレスの正体。孤独な戦いを乗り越えるヒント
特別支援学級の担任という仕事は、計り知れないやりがいがある一方で、重い責任と独特の困難さを伴います。
「もう特別支援学級担任を辞めたい」「自分は特別支援学級担任として仕事ができないのかもしれない」と悩み、強い特別支援学級担任のストレスを抱えている先生が数多く存在します。
特に、学校に支援学級が一つしかない場合、その孤独感と負担感は想像を絶するものがあります。
この記事では、
特別支援学級の教員が抱える具体的な悩みを深掘りし、その背景にある構造的な問題点、そして明日から少しでも心を軽くするためのヒントを、具体的な体験談を交えながら徹底的に解説します。
この記事を読むと分かること
- 特別支援学級の担任が抱える具体的な悩み(児童理解、人間関係、業務量、専門性、心理的側面)
- 「仕事ができない」「辞めたい」と感じてしまう心理的背景
- なぜ、特に「学校で一人」の支援学級担任が孤立しやすいのか
- 教員がしんどい時期はいつなのか、その具体的な理由
- 特別支援学級の教員に向いている人の特徴と、困難を乗り越えるための視点
- 今すぐできる、ストレスや悩みを軽減するための具体的な対処法
特別支援学級担任のストレス:なぜ「しんどい」と感じるのか
特別支援学級の担任が感じるストレスは、通常学級のそれとは質が異なります。その根底にあるのは、多様すぎるニーズへの「個別対応」と、成果の「見えにくさ」です。
1. 終わりなき「児童理解」と「指導法」の悩み
特別支援学級には、自閉スペクトラム症、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)、知的障害、情緒障害など、異なる特性を持つ子どもたちが在籍しています。時には、複数の特性を併せ持つ子もいます。
「Aさんには視覚的な指示が有効だけど、Bさんには聴覚的な指示の方が響く。Cさんは特定の音に過敏で、Dさんは触覚的な刺激を常に求めている…」
一人ひとりの「最適解」を探し続ける日々は、終わりのない実験のようです。
【体験談:A先生(30代・支援学級担任5年目)】
「私のクラスには、発語がほとんどないA君と、自分の気持ちを言葉で表現しすぎるあまりトラブルになりがちなB君がいます。A君がやっと集中して課題に取り組めたと思った瞬間、B君が些細なことで癇窼を起こし、その声でA君がパニックになってしまう。私は文字通り、自分の体を二つに裂きたいような気持ちになります。B君の気持ちも受け止めたい、でもA君の静かな環境も守りたい。どちらの指導も中途半端になっている気がして、毎日『これでよかったのか』と自問自答しています。」
2. 成果が見えにくいことによる心理的負担
通常学級であれば、「テストの点数が上がった」「リレーで勝った」といった目に見える成果があります。しかし、支援学級の子どもたちの成長は、非常にゆっくりとした、目に見えにくいものです。
「昨日までできなかった靴紐結びが、今日は片方だけできた」
「いつもは教室を飛び出すのに、今日は5分間座っていられた」
これらは教員にとっては感動的な「前進」ですが、周囲から見れば「当たり前」のことかもしれません。特別支援学校教員が大変なことは何ですか?と聞かれたら、多くの教員がこの「成果の非可視性」と「長期的な視点が必要なこと」を挙げるでしょう。自分の努力が報われているのか分からなくなり、無力感を覚えることは、深刻なストレス源となります。

「特別支援学級担任は仕事できない」?「やめたい」と感じる瞬間の心理
真面目で、子どもたちのために全力を尽くそうとする先生ほど、「自分は仕事ができないのではないか」という自己不信の罠に陥りやすくなります。そして、その感情が限界に達した時、「辞めたい」という考えが頭をよぎります。
1. 圧迫する業務量と時間管理の悩み
特別支援学級の担任は、純粋な「授業」以外の業務が非常に多いのが特徴です。
- 個別の指導計画(IEP)の作成・更新: 在籍する児童全員分の、詳細なアセスメントに基づいた計画作成。
- 膨大な指導記録: 日々の小さな変化やトラブル対応をすべて記録。
- 教材準備: 児童一人ひとりの認知特性や興味に合わせて、教材を個別に作成・調整。
- 関係機関との連携: 放課後等デイサービス、病院、療育機関との情報交換。
- 煩雑な事務作業: そして見落とされがちなのが、学級経営に関わる事務作業です。特に、一人ひとりの進度や目標に合わせた教材費の管理、校外学習の個別対応、補助金申請など、「一人ひとりに応じた会計処理と報告書」の作成は、多大な時間と精神力を奪います。
これらの業務に追われ、「本来やりたかったはずの子どもと丁寧に関わる時間」が削られていく。このジレンマが、「私は教員として『仕事ができていない』」という感覚を生み出します。

【体験談:B先生(20代・支援学級担任2年目)】
「定時は17時ですが、記録と明日の教材準備を終えると、いつも20時を過ぎます。特に学期末は、個別の指導計画の評価と次学期の計画作成、通知表の所見、さらには学級費の精算報告書が重なります。昨日は、会計報告書の数字が10円合わなくて、深夜まで残業しました。こんな事務作業のために、子どもたちの『できた!』の瞬間を見逃しているんじゃないか。授業準備の質が低下しているんじゃないか。そう思うと、情けなくて、『もう辞めたい』と思ってしまいます。」
2. 教員がしんどい時期はいつですか?
教員が特にしんどいと感じる時期は、明確に存在します。
- 4月(新学期): 新しいクラス編成、児童理解のやり直し、大量の計画書作成、家庭訪問、保護者との関係構築。すべてがゼロからスタートする最も多忙な時期です。
- 学期末(7月・12月・3月): 成績処理、通知表作成、個別の指導計画の評価・更新、各種報告書の締め切りが集中します。
- 行事前後(運動会・学芸会など): 全校参加の行事において、支援学級の児童が安心して参加できるよう、通常学級の何倍もの事前準備と調整が必要になります。
しかし、支援学級の担任にとっては、「トラブルが続いた時」が最も予測不可能な「しんどい時期」と言えるでしょう。児童の情緒が不安定になり、不適応行動が連鎖すると、教員は常に対応に追われ、心身ともに急速に疲弊します。
特別支援学級の「見えない壁」:孤立と人間関係の悩み
業務量以上に支援学級担任を苦しめるのが、「孤独感」です。特に、学校に支援学級が一つしかなく、担任が自分一人という状況は、深刻な心理的負担をもたらします。
1. 保護者対応の難しさ
多くの保護者は最大の理解者であり、協力者です。しかし、中には、子どもの障害受容に葛藤を抱えている方や、学校への要望が非常に高い方もいます。
「先生の指導方針は分かりますが、うちの子には合わないようです」
「なぜ、うちの子だけがトラブルになるんですか」
支援の必要性を説明し、家庭との連携を築こうとしても、理解や協力を得るのが難しい場合、担任は「自分の説明能力が低いからだ」と自分を責めてしまいがちです。
2. 他教員との「温度差」と連携の壁
これが、最も大きな悩みのタネかもしれません。通常学級の教員も多忙であり、特別支援教育に関する専門的な知識を十分に持っていない場合があります。
- 「交流学級(通常学級)に行かせても、結局教室の隅で座っているだけ…」
- 「通常学級の先生に『あの子、もう少しなんととなりませんか?』と、支援の必要性ではなく『問題行動の鎮圧』を求められている気がする」
- 「チームで情報共有や協力をしたいのに、支援学級の事情を話す時間も、聞いてもらえる雰囲気もない」
特別支援学級の問題点は?と問われれば、それは「学級そのもの」ではなく、「学校全体における支援体制の不十分さ」や「教員間の理解の格差」にあると言えます。

【体験談:C先生(40代・支援学級担任(1人職場)10年目)】
「うちの学校では、支援学級は私一人です。管理職も『専門家だから』と任せきり。職員会議で、支援が必要な子の特性や配慮事項を説明しても、他の先生方は自分のクラスのことで手一杯。『C先生のところは少人数でいいね』と悪気なく言われた時、全身の力が抜けました。相談できる同僚がいない。喜びも、苦しみも、共有できる相手がいない。この『孤立感』が、何よりも重くのしかかります。私はこの学校で、たった一人で戦っている気分です。」
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
日々の膨大な業務、そして何より「一人ひとりに合わせた教材準備」の大変さに、心が折れそうになっているかもしれません。
「もっと子どもと丁寧に関わる時間が欲しい」
「教材準備に追われて、本来の指導ができていない気がする…」
B先生のように「教材準備で深夜まで残業…」という体験談は、決して他人事ではないはずです。
そんな先生の「孤独な戦い」を、具体的なツールでサポートします。
ここでは、先生方の負担を少しでも軽くし、子どもたちの「できる!」を引き出すために開発された「自立活動の教材」をご紹介します。明日からすぐに使える自立活動の教材はこちらです。先生方の負担軽減の力になれると思います👇
個別の支援計画の文例もよければ活用ください💁
「特別支援学級担任が優秀」と言われる人の特徴と「向いている人」
ここまで困難な側面を多く書いてきましたが、もちろん、この仕事には計り知れない喜びと、専門職としての誇りがあります。では、「優秀」と評されたり、困難な中でもやりがいを見出して続けていける「特別支援学級の教員に向いている人」とは、どのような人なのでしょうか。
1. 自分の支援方法に自信が持てない(専門性・成長の悩み)
まず、多くの先生が抱える「自分の支援方法が正しいのか、自信を持てない」という悩み。これは、真剣だからこその悩みです。「発達障害や心理的支援に関する知識・スキルをもっと深めたいが、研修や学習の時間が取れない」というジレンマも深刻です。
「優秀」な先生とは、最初から完璧な支援ができる人ではありません。むしろ、「自分の支援は間違っているかもしれない」と常に疑い、児童の反応を見ながら柔軟にアプローチを変えていける人です。
2. 特別支援学級の教員に向いている人の5つの特徴
- 観察力と分析力がある人
言葉でうまく表現できない子どもの、小さな表情の変化、視線の動き、手の震えから、その子の「困り」や「ニーズ」を読み取ろうと努力できる人。 - 「待つ」ことができる人
成果を急がず、子どものペースを信じて待てる人。数ヶ月、あるいは1年かかって見えた小さな成長を、心から喜べる人。 - 切り替えがうまく、引きずらない人
トラブルや保護者からの厳しい言葉があっても、それを「個人の問題」として抱え込まず、「職務上の課題」として客観的に捉え、適切に感情をリセットできる人。 - 「巻き込み力」がある人
一人で抱え込まず、管理職や通常学級の担任、スクールカウンセラー、外部機関を「使えるものはすべて使う」という姿勢で、積極的に巻き込んでいける人。 - 学び続ける意欲がある人
「長く勤務する中で『同じような課題の繰り返し』と感じ、成長ややりがいを見出しにくい」という中堅の悩みもありますが、支援方法は日々アップデートされています。「この子には、あの新しいアプローチが効くかもしれない」と、知識の更新を楽しめる人は向いています。
悩み解決へのステップ:一人で抱え込まないために
もし今、あなたが「辞めたい」ほど追い詰められているなら、まずは自分の心身の安全を最優先してください。その上で、状況を少しでも改善するためにできることを提案します。
1. 「見えない仕事」を可視化する
あなたの多忙さや専門性は、周囲に伝わっていません。
「支援学級担任は、放課後何をしているのか?」を、具体的にリスト化し、管理職や同学年の教員に(愚痴ではなく)「相談」の形で提示してみましょう。
「個別の指導計画の作成に、一人あたり〇時間かかっています。この時間を確保するため、〇〇会議の資料作成を軽減できませんか?」と具体的に交渉することが第一歩です。
2. 「校外」に仲間を見つける
校内に相談相手がいないなら、校外に求めるしかありません。
- 地域の特別支援教育の研修会や研究サークルに参加する。
- SNS(X(旧Twitter)など)で、鍵付きのアカウントを作り、同じ立場の教員と繋がる。(個人情報の取り扱いには最大限の注意を払ってください)
- 教育委員会の指導主事や、特別支援教育コーディネーターに、匿名で現状を相談する。
「自分だけじゃない」と知るだけで、孤独感は大きく軽減されます。
3. 専門機関のリソースを徹底的に活用する
あなたの専門性を高め、悩みを裏付けるためのリソースを活用しましょう。研修に行く時間がなくても、オンラインで学べることはたくさんあります。
【おすすめの外部リンク】
- 国立特別支援教育総合研究所(NISE)
https://www.nise.go.jp/
日本における特別支援教育の研究・研修の中核機関です。発達障害に関する最新の研究成果や、具体的な指導事例、オンライン研修資料などが豊富に揃っています。自分の支援に迷った時、理論的な支柱となってくれるはずです。
4. 「完璧」を目指さない勇気を持つ
最後に、最も大切なことです。
すべての子どもに、100%完璧な支援を提供しようとしないでください。それは不可能です。あなたは神様ではありません。
8人の児童がいれば、今日はAさんとBさんに注力する日、明日はCさんの教材準備を頑張る日、と優先順位をつける勇気を持ってください。60%の力で「継続できる」ことの方が、120%の力で燃え尽きてしまうことより、子どもたちにとってはずっと価値があるのです。
まとめ
特別支援学級の担任は、学校の中で「通訳者」であり、「防波堤」であり、「専門家」であり、「最後の砦」でもあります。その重圧は、経験した者にしか分かりません。
あなたが日々感じている「しんどさ」や「仕事ができない」という感覚は、あなたの能力が低いからではなく、あまりにも多くの役割と責任を、たった一人(あるいは少人数)で背負わされているからです。
どうか、自分を責めないでください。あなたの存在そのものが、教室の子どもたちにとって、そしてその保護者にとって、どれほど大きな支えになっているかを忘れないでください。
この記事が、あなたの重い荷物を少しでも軽くし、明日もう一度子どもたちの前に立つための、小さな力になれば幸いです。

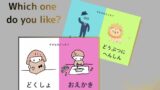
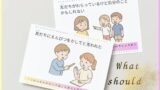



コメント