教育実習、本当にお疲れ様です。
慣れないスーツ、朝早くからの通勤、そして夜遅くまで続く教材研究。心も体もクタクタになっていることでしょう。その中で、重くのしかかるのが「教育実習日誌」の存在ですよね。
「今日一日、何を書けばいいんだろう?」
「『頑張りました』しか言葉が出てこない……」
そんな風にペンが止まってしまう実習生を、私は指導教官として何人も見てきました。言語化が苦手なのは、あなたが悪いわけではありません。ただ、「視点」と「書き方の型」を知らないだけなのです。
この記事では、私が多くの実習生を見てきた経験、そして「もっとこう書いてくれたら指導しやすいのに!」「ここを変えるだけでグンと伸びるのに!」と感じた本音を交えながら、評価されるだけでなく、あなたの教師力を確実に高める日誌の書き方を伝授します。温かく、時には少し厳しく(愛を込めて)、解説していきますね。
この記事を読むと分かること
- 教育実習日誌 書き方の基本構成と、評価される文章の「型」
- 教育実習日誌 書き方 例 小学校・中学校・高校別の具体的な「良い例・悪い例」
- 教育実習日誌 書くことないと悩んだ時に使える「視点の変え方」とネタ探し
- 教育実習日誌 いつ書くのが正解か、睡眠時間を確保するためのタイムマネジメント
- 実習日誌に何を書けばいいですか?という疑問への明確な答えと、実習記録に書いてはいけないことは?というタブー
- 指導教官が思わず唸る教育実習生へのメッセージの例文は?(所感欄の活用法)
教育実習日誌 書き方の基本とは?実習日誌に何を書けばいいですか?
まず、根本的な問いである「実習日誌に何を書けばいいですか?」についてお答えします。
結論から言います。
「事実(Fact)」ではなく、「気付き(Insight)」と「次の一手(Action)」を書いてください。
私が指導担当をしていた時、一番もったいないと感じた日誌は「スケジュール帳の書き写し」でした。「1時間目は国語を見学した。2時間目は算数をやった。給食はおいしかった」……これでは、小学生の日記と同じです。
教育実習日誌の書き方の基本フォーマットは、以下の3ステップです。
- 事実(何が起きたか):客観的な出来事(短く!)
- 考察(なぜそうなったか):あなたの分析、子供の反応、心の動き
- 実践(次はどうするか):具体的な改善策、明日試したいこと
指導教官の目線:私が日誌で見ていたポイント
私が実習生の日誌を読む時、チェックしていたのは「文章の上手さ」ではありません。「子供をどう見ているか」と「自分の課題に向き合えているか」です。
失敗してもいいんです。授業で沈黙が起きてもいい。重要なのは、「なぜ沈黙が起きたのか」をあなたがどう分析し、「明日は発問をこう変えてみよう」と前向きなプランを持っているかどうか。それが見える日誌には、私もアドバイスを書きたくなりました。

💡 考察力を高めたい方へ:指導教官が求める視点をインストール
指導教官が日誌で最も見ているのは、「子供をどう見ているか」、つまりあなたの考察の深さです。
この「プロの視点」は、ただ観察するだけでは身につきません。
学級経営や生徒指導に関する知識を事前にインプットしておくことで、目の前の事象を「ただの出来事」ではなく「教育的な意味」として捉えられるようになります。日誌の考察の質が劇的に向上し、指導教官からの評価にも直結します。
Amazonリンク:学級経営の心得―担任の不安が自信に変わる 150のメソッド
実習が終わってから「これを知っておけばよかった」と後悔する前に、ぜひご活用ください。
教育実習日誌 書き方 例 小学校:児童の反応を細かく拾う
小学校の実習では、授業の進行以上に「児童との関わり」や「生活指導」が重要になります。
悪い例
今日の算数は割り算の筆算でした。子供たちは静かに話を聞いていて、練習問題も解けていました。私も机間巡視をして、分からない子に教えることができました。全体的に落ち着いていてよかったと思います。
良い例(書き方のポイント:具体性と個への視点)
【事実】 算数の割り算の筆算の導入にて。Aさんが鉛筆を止め、窓の外を見ていることに気づいた。机間巡視の際、すぐに答えを教えるのではなく「どこまで進んだ?」と声をかけた。
【考察】 「静かに話を聞いている」=「理解している」ではないと痛感した。Aさんは計算の手順以前に、九九の段でつまずいているようだった。全体への説明スピードが速すぎたため、思考が追いついていない子が数名いた可能性がある。
【実践】 明日の授業では、説明の後に「隣同士で確認する時間」を1分設ける。また、机間巡視では正解している子だけでなく、手が止まっている子のノートの「どの部分」で止まっているかを見極めてから声をかけるようにする。
解説
教育実習日誌 書き方 で大切なのは、子供の具体的な姿です。「Aさんが」と名前(イニシャル)が出るだけで、あなたが子供一人ひとりをちゃんと見ていることが伝わります。
【言語化の壁を乗り越える裏技】
この記事で「視点」は学べましたが、「文章に変換する作業」は疲れますよね。
「〜と思いました」を教師らしい言葉に言い換える作業を、もう終わりにしませんか?
言語化が苦手な実習生のために、『コピペOK』の所感・考察フレーズ100選をNoteにて公開中です。
- ✅ 「楽しかった」をプロの言葉に言い換える変換辞書
- ✅ 場面ごとの文章テンプレート(失敗した日、平和な日など)
- ✅ 日誌作成の時間を半分に短縮
忙しいあなたのために、考える手間を丸ごと省けるツールを用意しました。ぜひご活用ください。
→【コピペOK】教育実習日誌の「所感・考察」言い換えフレーズ集&場面別テンプレート
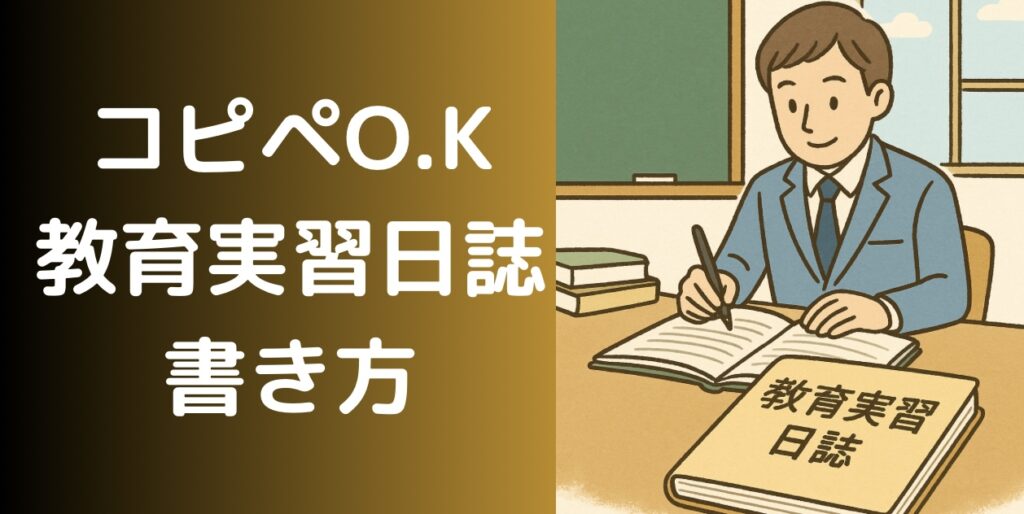
教育実習日誌 書き方 中学:思春期の心の機微と教科指導
中学校では、教科担任制になります。また、思春期特有の生徒との距離感が課題になります。教育実習日誌 書き方 中学のポイントは、「教科指導の専門性」と「生徒指導(関係構築)」のバランスです。
悪い例
休み時間に男子生徒たちとバスケをして楽しかった。生徒との距離が縮まった気がする。英語の授業では、文法の説明が難しくて生徒が寝てしまった。もっと分かりやすく説明したい。
良い例
【事実】 昼休み、教室で一人で本を読んでいるB君に「何読んでるの?」と声をかけたが、「別に」と素っ気ない返事だった。英語の授業中、関係代名詞の説明で、黒板を背にして話す時間が長く、生徒の視線が手元に落ちていることに気づいた。
【考察】 昼休みの件は、無理に会話を続けようとして焦ってしまった。沈黙を共有するだけでも信頼関係の第一歩だったかもしれない。授業に関しては、私の「教えたい欲」が先行し、生徒の「考える時間」を奪っていた。板書しながら説明したため、声が通りにくかったのも原因だ。
【実践】 休み時間は、無理に話しかけすぎず、生徒の空間を尊重しつつ「いつでも話せる位置」にいることを意識する。授業では「書く時間」と「説明を聞く時間」を明確に分け、説明時は必ず生徒の目を見て話すことを徹底する。
解説
「楽しかった」「難しかった」という感情語を、「なぜそう感じたか」という分析語に変換しましょう。指導教官は、あなたが「生徒の反応(素っ気ない態度など)」をどう受け止めているかを心配しています。
教育実習日誌 書き方 例 高校:専門性と進路への意識
高校生は大人に近いです。実習生の実力不足をシビアに見抜きます。教育実習日誌 書き方 例 高校では、高い教材研究のレベルと、生徒を大人として尊重する姿勢が求められます。
悪い例
世界史の授業を行いました。フランス革命の流れを説明しましたが、反応が薄かったです。もっと面白い雑談を用意するべきだったと思います。生徒は受験勉強で疲れているようでした。
良い例
【事実】 世界史のフランス革命。「なぜ民衆は立ち上がったのか?」という発問に対し、Cさんが現代の税制と絡めた鋭い意見を言ったが、「そうだね」と流して次の説明に移ってしまった。
【考察】 生徒の方が知識が定着している部分もあり、私が「正解」を言わせようとするあまり、生徒の思考の芽を摘んでしまった。Cさんの発言はクラス全体の議論を深めるチャンスだったのに、台本通りの進行に固執してしまった自分の余裕のなさが露呈した。
【実践】 明日は、生徒の発言を一度板書し、「なぜそう思った?」と全体に問い返す時間を必ず作る。自分が教えるのではなく、生徒の知識を引き出してつなげる「ファシリテーター」としての意識を持つ。教材研究では、用語の暗記ではなく因果関係のロジックを再確認する。
教育実習日誌で「書くことない」と悩んだ時のネタ探し
実習中盤になると、「毎日同じことの繰り返しで教育実習日誌 書くことない」という壁にぶつかります。
でも、断言します。ネタがないのではありません。「解像度」が荒いのです。
カメラのレンズをズームインする感覚で、以下の教育実習日誌 ネタを探してみてください。
1. 「指導教官」を観察する(真似る技術)
- 先生は教室に入った瞬間、まずどこを見たか?
- 生徒を叱る時、どんな声のトーンだったか?
- 授業の開始と終了で、板書はどのように完成されていたか?
- ネタ例: 「先生が指示を出す前に、一瞬沈黙を作って注目させたテクニックについて」
2. 「特定の生徒」を定点観測する
- 一番後ろの席のD君は、授業開始5分後と30分後でどう姿勢が変わったか?
- いつも元気なEさんが、今日は誰とも話していなかった理由は?
- ネタ例: 「一人の生徒の1時間の集中力の変化をグラフ化してみた考察」

3. 「環境」に目を向ける
- 教室の掲示物はいつ、誰が貼り替えているのか?
- 黒板の溝はきれいか?(誰が掃除したのか?)
- ネタ例: 「教室環境が学習意欲に与える影響についての気付き」
指導教官の体験談
私が担当したある実習生は、日誌に「今日は先生の『チョークの置き方』を見ました。大切なことを書く時だけ、新品の太いチョークに持ち替えていました」と書いてきました。これには驚きました。「こいつ、よく見てるな」と感心し、その後の指導にも熱が入ったのを覚えています。
教育実習日誌はいつ書くのがベスト?睡眠時間を確保するコツ
教育実習日誌 いつ書くかは、あなたの健康を守るための最重要課題です。
多くの実習生が、家に帰ってから、夜遅くに日誌を書き始めます。しかし、疲れ切った脳で文章を書くのは非効率です。
おすすめのタイムスケジュール
- 休み時間・空きコマ(メモ書き)
- 記憶が鮮明なうちに、箇条書きで「事実」だけメモする。
- キーワードだけでもOK。(例:2限目、A君あくび、板書見にくいかも)
- 放課後すぐ(構成)
- 生徒が帰った直後の30分で、メモを文章化する。
- 指導教官に見せる前に、下書きを完成させてしまう。
- 帰宅後(清書・推敲はしない!)
- 家では教材研究に時間を使い、日誌は誤字脱字チェックのみにする。
睡眠は教材研究の一部
実習生の皆さん、これだけは約束してください。日誌のために睡眠時間を削らないでください。
睡眠不足の先生は、不機嫌に見えます。思考力が鈍り、とっさの生徒のトラブルに対応できません。完璧な日誌を書いてフラフラな先生より、日誌は70点でも笑顔で元気な先生の方が、子供たちは好きです。

実習記録に書いてはいけないことは?守るべきルールとマナー
日誌は公文書に近い性質を持ちます。感情のままに書いてはいけないことがあります。実習記録に書いてはいけないことは?と迷ったら、以下を確認してください。
1. 生徒や先生のプライバシー・悪口
- NG: 「F先生の授業はつまらないから生徒が寝ていた。」
- OK: 「生徒の集中力が途切れた場面があった。自分ならここで発問を変える工夫をしたい。」
- 批判ではなく、「自分ならどうするか」という建設的な意見に変えましょう。
- NG: 「G君の家庭は複雑らしく、服が汚れていた。」
- 個人情報に関わるセンシティブな内容は、日誌(多くの人の目に触れる可能性)には書かず、口頭で指導教官に相談してください。
2. 根拠のないネガティブ発言
- NG: 「もう教師に向いていないと思いました。辛いです。」
- 弱音を吐くなとは言いません。でも、日誌に残すなら「辛いと感じた。だからこそ、明日は一つだけこれを達成して自信を取り戻したい」と、前を向く姿勢をセットにしてください。
3. 誰かのせいにする言葉(他責)
- NG: 「生徒がうるさくて授業にならなかった。」
- OK: 「生徒を静かにさせる技術が私に不足していた。」
教育実習生へのメッセージの例文は?指導担当から実習生へ
日誌の最後にある「所感」や「指導教官へのメッセージ」欄。ここを空白にしたり、「ありがとうございました」の一言で済ませていませんか?
ここは、指導教官との「交換日記」の核心部分です。以下の型を使ってみてください。
例文1:指導への感謝と決意(学びを深める)
本日は、私の板書の文字の小ささについてご指摘いただき、ありがとうございました。後ろの席から確認した際、確かに見えづらいことに衝撃を受けました。明日は、「一番後ろの生徒に届ける」意識で、チョークを強く握り、大きく書くことを意識します。また見ていただけると嬉しいです。
例文2:質問を投げかける(意欲を見せる)
先生の授業を拝見し、騒がしかった生徒が一瞬で静かになった「間の取り方」に感動しました。あの時、先生はどのようなタイミングを計っていらっしゃったのでしょうか? 明日の朝の会で少し試してみたいので、もしよろしければコツを教えていただけますでしょうか。
例文3:素直な心境の吐露(信頼関係を築く)
正直、今日の授業は準備不足で悔しい結果に終わりました。生徒に申し訳ない気持ちでいっぱいです。週末にもう一度教材研究を一からやり直します。来週は、生徒が「分かった!」と言える授業を必ずします。
指導教官の本音:
私たちが嬉しいのは、「私の指導が伝わっている」と感じられる時です。「先生のアドバイスのおかげで、ここがうまくいきました!」と書かれていると、忙しい中でも「よし、明日ももっと教えてやろう!」という気持ちになるものです。
教育実習日誌の書き方をマスターして、実りのある実習にしよう
ここまで読んで、「やっぱり難しそう……」と思いましたか? それとも「これなら書けるかも!」と思えましたか?
教育実習日誌は、毎日提出する義務的な書類かもしれません。しかし、書き方ひとつで、あなたの「教師としての目」を養う最強のトレーニングツールになります。
言語化が苦手でも大丈夫です。
美しい文章である必要はありません。
「子供の事実」を見つけ、「自分の頭」で考え、「明日への希望」を書く。
その泥臭い思考の跡こそが、あなたの成長の証です。
私が指導した実習生の中に、最初は日誌が一行しか書けなかった子がいました。でも、彼は毎日必死に生徒を観察し続けました。実習最終日、彼の日誌は枠からはみ出るほどの熱い文章で埋め尽くされていました。彼は今、素晴らしい小学校の先生として活躍しています。
あなたもきっと、素敵な先生になれます。
今日の日誌から、ほんの少し視点を変えてみてください。
応援しています。
さて、この記事で日誌の「型」は掴んでいただけたかと思います。この型を毎日、疲れ果てた頭で埋める作業を「ツール」としてサポートするのが、私のNote記事です。
「思考はできたけれど、書く言葉が見つからない…」
そんなあなたのための『言い換えフレーズ集100選』は、下記リンクよりご確認いただけます。日誌作成の負担を減らし、残りの実習期間を「未来の自分への投資」に集中しませんか?
→【コピペOK】教育実習日誌の「所感・考察」言い換えフレーズ集&場面別テンプレート
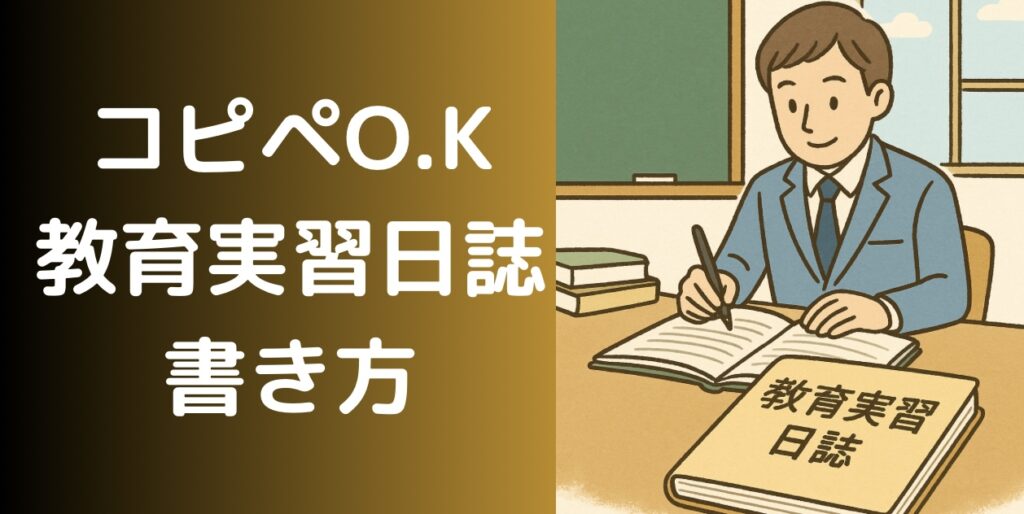
関連記事はこちら
教育実習が終わりましたら、お礼状の書き方の記事が参考になると思います💁
役立つ外部リンク
- 文部科学省:教育実習について
教育実習の意義や目的、法的な位置づけなどが確認できる公式サイトです。迷った時の原点回帰として役立ちます。
https://www.mext.go.jp/
(※具体的な実習の手引きは各大学や教育委員会の資料も参照してください)




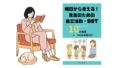
コメント