教員の退職金、勤続15年で辞めるといくら?10年・20年・定年と比較シミュレーション!自己都合退職の損得勘定とキャリア戦略
勤続10年を超え、中堅と呼ばれるようになった教員のあなた。「このまま定年まで続けるべきか」「民間への転職や独立も、年齢的にそろそろリミットかもしれない」…そんな迷いの中で、ふと頭をよぎるのが「お金」の問題、特に「退職金」ではないでしょうか。
勤続15年という節目で辞めた場合、いったいいくらもらえるのか? もし教員が自己都合で退職したら、どれくらい損をするのか?
この記事は、まさに今、キャリアの岐路に立っているあなたのために、教員の退職金について徹底的に解説します。
特に「公務員で15年勤務した場合退職金はいくら?」といった具体的な金額、「退職金の15年ルールとは?」という噂の真相、そして「教員退職金計算シミュレーション」の活用法まで、あなたの「知りたい」に真正面から向き合います。
この記事を読むと分かること
- 勤続15年(自己都合)の教員がもらえる退職金のリアルな金額目安
- 定年+再任用 vs 15年で転職・独立 の「人生の損得勘定」
- 勤続10年・14年・15年・20年・定年退職の「教員 退職金 勤続年数」別 徹底比較
- なぜ15年が重要?「14年で辞める」のと「15年で辞める」ので大違いな理由
- 「教員退職金 自己都合」で辞めた場合の金銭的デメリットのすべて
そもそも教員の退職金(退職手当)はどう決まる?
まず大前提として、公立学校の教員は「地方公務員」です(国立大学法人の場合は異なります)。したがって、退職金(正式には「退職手当」)は、各都道府県や政令指定都市が定める「退職手当条例」に基づいて支給されます。
とはいえ、その計算方法は全国でほぼ共通化されており、以下の式で算出されます。
退職手当 = 基本額 + 調整額
1. 基本額:勤続年数と退職理由で決まる
基本額は、退職金の大部分を占める主要な部分です。
基本額 = 退職日の俸給月額 × 支給率
- 退職日の俸給月額:
いわゆる「基本給」です。勤続年数が長く、号俸が上がるほど高くなります。 - 支給率(支給月数):
これが最も重要です。「勤続年数」と「退職理由(定年か、自己都合か)」によって、あらかじめ月数が決められています。
教員がキャリアに悩む最大の理由がここにあります。「自己都合」で退職すると、この「支給率」が「定年退職」に比べて著しく低く抑えられてしまうのです。

2. 調整額:在職中の「貢献度」を反映
調整額は、少し複雑な計算(在職中の職務の級や号俸を点数化し、上位60ヶ月分を合計する)で算出されます。簡単に言えば「在職中の役職や貢献度に応じた加算金」のようなものです。
しかし、ここにも「自己都合」の壁があります。
人事院の資料(地方公務員も概ね準拠)によれば、勤続10年以上24年以下の自己都合退職者は、この調整額が「半額」に減額されてしまいます(勤続9年以下ではゼロ)。
つまり、15年で自己都合退職を選ぶと、「基本額の支給率」と「調整額」の両方で大きな金銭的デメリットを被ることになるのです。
【本題】教員退職金 勤続年数ごとの比較:10年・15年・20年・定年の違い
では、実際に勤続年数によってどれくらいの差が出るのでしょうか。総務省の「令和5年 地方公務員給与の実態」などのデータを基に、一般的な教員(一般行政職・大卒)の平均値を見てみましょう。
▼ 勤続年数・退職理由別 退職手当の平均支給額
| 勤続年数 | 退職理由 | 平均支給額(目安) | 比較コメント |
|---|---|---|---|
| 10~14年 | 自己都合 | 約 277 万円 | 10年勤めても、まだ「まとまった額」とは言い難い。 |
| 15~19年 | 自己都合 | 約 526 万円 | 注目! 14年と15年の間に大きな壁がある。 |
| 20~24年 | 自己都合 | 約 933 万円 | 1,000万円がようやく見えてくるライン。 |
| 35~39年 | 自己都合 | 約 1,951 万円 | 定年間近の自己都合でも、定年よりは低い。 |
| 35~39年 | 定年退職 | 約 2,100~2,300 万円 | 自己都合(15年)の約4~5倍。これが現実。 |
(※注:上記はあくまで全地方公務員の平均データであり、最終学歴、俸給月額、自治体によって大きく変動します)
最大の分岐点:「14年で辞める」か「15年で辞める」か
この表を見て、衝撃的な事実に気づかないでしょうか。
- 勤続10~14年(自己都合):約 277 万円
- 勤続15~19年(自己都合):約 526 万円
勤続14年で辞めた場合(277万円)と、勤続15年で辞めた場合(526万円)では、たった1年の違いで、退職金が約250万円、ほぼ2倍近くも変わる可能性があるのです。
これは、多くの自治体で「勤続15年」を境に、自己都合退職の「支給率テーブル」が大きく切り替わる(優遇される)設定になっているためです。
あなたの「辞めどき」の損得勘定において、これは最も重要な情報の一つです。もし「もう限界だ」と思っていても、勤続14年8ヶ月目なのであれば、あと数ヶ月待って15年を迎えてから退職届を出すだけで、将来の転職活動や独立の「軍資金」が250万円も変わってくるかもしれないのです。

退職金 15年 いくら? 公務員で15年勤務した場合の退職金を具体的にシミュレーション
「平均値は分かった。じゃあ、自分の場合は?」という疑問に答えるため、より具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
教員退職金計算シミュレーションの活用法と注意点
ここで、教員退職金計算シミュレーションの考え方を使います。
【モデルケース】
- 年齢: 38歳(23歳で新卒採用)
- 勤続年数: 15年
- 退職理由: 自己都合
- 退職日の俸給月額(基本給): 36万円
(大卒・教諭・15年勤務の標準的な号俸と仮定)
【計算ステップ】
(※計算方法は自治体ごとに異なります。あくまで概算の「考え方」です)
1. 基本額の計算
- 俸給月額: 36万円
- 支給率: 勤続15年(自己都合)の場合、約10ヶ月分~12ヶ月分程度と仮定します。(※定年の場合は約47ヶ月分)
計算: 36万円 × 10ヶ月分 = 360万円
2. 調整額の計算
- 在職中の職位(等級)に応じて計算されますが、複雑です。
- 仮に、計算上の調整額(満額)が200万円だったとします。
- しかし、前述の通り「勤続10~24年の自己都合」は半額になります。
計算: 200万円 × 50% = 100万円
3. 退職手当 合計
計算: 360万円(基本額) + 100万円(調整額) = 460万円
【シミュレーション結果】
このモデルケースでは、勤続15年の自己都合退職金は約460万円となりました。
これは、先ほどの平均データ「15~19年で約526万円」とも近い数字です。
つまり、教員が勤続15年で自己都合退職した場合の退職金は、おおむね「450万〜550万円」あたりが現実的な相場と言えそうです。
外部リンク:あなたの退職金を試算してみよう

もちろん、これは一つのモデルケースに過ぎません。あなたの正確な俸給月額や自治体の条例によって金額は変わります。
よりご自身の状況に近い数字を知りたい場合は、以下のシミュレーションサイトが参考になります。公務員の退職金計算は複雑ですが、大まかな目安を掴むことができます。
- 参考サイト: 地方公務員の退職金の計算シミュレーション! | 株式会社アルビノ
(注:このサイトはあくまで一例であり、正確な金額は必ずご自身の所属する教育委員会や共済組合にご確認ください)
教員退職金 自己都合の場合の「本当のコスト」
シミュレーションで「約460万円」という数字が出ました。
この金額を見て、あなたはどう感じたでしょうか。
「意外ともらえるな」と思ったでしょうか。それとも「15年も働いて、たったこれだけ?」と思ったでしょうか。
ここで冷静に比較すべきは、「もし定年まで働いたら」の金額です。
- 15年(自己都合): 約 460万円
- 定年(勤続38年): 約 2,200万円
その差は、約1,740万円です。
これが、あなたが38歳で「教員を辞める」というキャリアを選択するために支払う、「機会費用のコスト」です。
「自己都合退職は損だ」とよく言われますが、その「損」の正体は、この1,740万円という「未来にもらえるはずだった権利」を放棄することにあるのです。
「退職金の15年ルール」とは?
この記事を読んで、あなたは「退職金の15年ルール」の正体に気づいたはずです。
世間で言われる「15年ルール」とは、法律や条例で明確に「15年」と定められた制度のことではありません。
それは、
「勤続14年以前」と「勤続15年以後」とで、自己都合退職金の支給率テーブル(あるいは調整額の計算)が大きく変わり、もらえる金額がジャンプアップする「実務上の分岐点」
のことなのです。
この「分岐点」を知っているか知らないかで、数百万円単位の損得が分かれます。「辞めたい」という感情がピークに達していても、勤続年数を「15年」に乗せるかどうかは、キャリア戦略上、極めて重要な判断となります。
15年で辞める損得勘定:再任用や民間転職と比較
さて、あなたは今、1,740万円という「失うもの」の大きさを知りました。
その上で、あなたの目の前には大きく分けて3つの道があります。
定年まで勤め上げ、再任用で働く
- 金銭的メリット: 満額の退職金(約2,200万円)+ 定年後の再任用による安定収入。金銭的な生涯設計は最も盤石です。
- デメリット: あと20年以上、現在の職場で働き続ける必要があります。「辞めたい」という気持ちを抱えたまま、残りのキャリアを過ごすことになります。
15年で辞め、民間企業へ転職する
- 金銭的メリット: 退職金(約460万円)を元手に、転職活動に専念できます。もし38歳で転職し、年収が上がる企業(例:IT、コンサル、大手メーカーなど)に入れた場合、生涯賃金は定年まで教員を続けるより高くなる可能性もゼロではありません。
- デメリット: 教員からの民間転職は、専門スキルが問われるため簡単ではありません。転職活動が難航すれば、退職金は「生活費」としてあっという間に消えていきます。
15年で辞め、独立・起業する(塾、フリーランスなど)
- 金銭的メリット: 成功すれば青天井。教員時代の年収を大きく超える可能性があります。退職金(約460万円)は貴重な「事業の種銭」になります。
- デメリット: 最もハイリスク・ハイリターン。成功する保証はどこにもありません。退職金と貯蓄を切り崩し、事業が軌道に乗らなければ、金銭的にも精神的にも追い詰められます。
「損得勘定」の結論
金銭面だけで言えば、定年まで勤め上げ、再任用で働くのが「最も得」です。これは間違いありません。
しかし、あなたの人生の「得」は、お金だけでしょうか?
もし、あなたが「1,740万円を失ってでも、手に入れたい未来がある」と本気で思うなら、15年という節目は、キャリアチェンジに踏み切る「合理的」なタイミングの一つと言えます。
なぜなら、
- 「14年で辞める」より、約250万円も「お得」に辞められるから。
- 38歳という年齢は、民間転職や独立において「まだ間に合う」ギリギリのラインだから。
- 手にする460万円は、定年組の2,200万円に比べれば少ないですが、人生をリセットし、次のステージに挑戦するための「軍資金」としては、決して小さくない額だからです。
結論:教員15年目の決断は「退職金」より「未来」で選ぶべき
この記事では、勤続15年の教員の退職金について、現実的な数字をシミュレーションしてきました。
「15年で辞めると、約460万円」
「定年まで勤めると、約2,200万円」
この差額(1,740万円)を見て、「やっぱり辞めない方が得だ」と考えるのも、一つの賢明な判断です。
しかし、もしあなたが「やめたいかも」と一度でも真剣に考え、この記事にたどり着いたのであれば、その「1,740万円」をコストとして支払ってでも、残りの約30年間の「働き方」「生き方」を選び直したい、という心の叫びがあるのではないでしょうか。
退職金の損得勘定は、キャリアを考える上での「入り口」にすぎません。本当に重要なのは、その「辞めた後」のキャリアをどう設計するか、です。
中堅教員のキャリアチェンジを本気で考えるなら
「退職金の計算は分かった。でも、教員しかやったことがない自分が、本当に民間や独立でやっていけるのか?」
「教員のスキルって、外で通用するのか?」
その不安は、当然です。教員からの転職は、一般的な転職とは異なる「特殊な思考法」と「戦略」が必要です。
感情論で「えいや!」と辞表を出す前に、まずは「教員からの転職とは何か」を体系的に学ぶことが、1,740万円のコストを「未来への投資」に変えるための第一歩です。
『やめたいかもと一度でも思ったら読む 教員の転職思考法』は、まさに今、あなたと同じようにキャリアに悩む教員のために書かれた一冊です。
「教員が転職で陥りがちなワナ」
「教員の経験を『強み』に変える翻訳術」
「公務員マインドから抜け出し、市場価値を高める方法」
こうした、教員専門のキャリアチェンジのノウハウが詰まっています。退職金の計算を終えたあなたが、次に手に取るべき「思考の羅針盤」となるでしょう。
あなたの15年間の貴重な経験と、これから手にするかもしれない460万円を、どう活かすか。その答えを見つけるために、まずは情報武装から始めてみませんか。
▼ あなたの「次の一歩」を具体的にする一冊
やめたいかもと一度でも思ったら読む 教員の転職思考法 (新流舎株式会社) はこちら (Amazon)
関連記事
まとめ
教員の勤続15年は、キャリアの大きな分岐点であると同時に、退職金の面でも「14年以前」とは一線を画す重要な節目です。
- 15年(自己都合)の退職金目安は、約450万〜550万円。
- 14年で辞めるより、15年で辞める方が圧倒的に「金銭的にお得」。
- ただし、定年退職(約2,200万円)と比べれば、約1,700万円以上の「機会費用」を支払う覚悟が必要。
この数字を冷静に受け止め、あなたの「これからの30年」にとって、何が本当の「得」になるのかを、ぜひ深く考えてみてください。


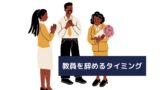



コメント