「教員を10年で辞めたら、退職金はいくらもらえるんだろう?」
キャリアチェンジやライフスタイルの変化を考えたとき、教員退職金がいくらになるのかは、次のステップに進むための重要な資金計画になります。特に「10年」という節目は、キャリアの中でも大きな決断の時期です。
しかし、退職金制度は非常に複雑です。特に公立学校の教員の場合、「自己都合」で辞めるのか、勤続年数が「5年」の場合と「10年」の場合でどう違うのか、そしてよく耳にする「退職金の10年ルール」とは何なのか、正確に理解している人は少ないかもしれません。
また、退職金(一時金)とは別に、2015年(平成27年)10月から始まった「年金払い退職給付」(いわゆる退職年金)についても、「10年で辞めた場合」にどうなるのか、知っておく必要があります。
この記事では、教員を10年で早期退職した場合のリアルな退職金額と、知っておかないと損をする重要な注意点について、分かりやすく解説します。
この記事を読むと分かること
- 教員を勤続10年・自己都合で退職した場合の退職金(一時金)のリアルな概算金額
- 退職金が「基本額」と「調整額」で計算される仕組み
- 勤続5年で辞めた場合との具体的な金額の比較
- 絶対に知っておくべき「退職金の10年ルール」の正体(9年と10年では大違い!)
- 退職年金(年金払い退職給付)の「10年受取」と「20年受取」はどちらが得か
教員10年目で退職したら退職金はいくらもらえる?

まず結論から。公立学校の教員を勤続10年・自己都合で退職した場合、受け取れる退職手当(一時金)の概算金額は、約240万円〜270万円程度が一つの目安となります。
「思ったより少ない」と感じた方も多いかもしれません。これは、退職理由が「自己都合」であること、そして勤続年数が10年であることが大きく影響しています。
リアルなシミュレーション(勤続10年・自己都合)
公立学校教員の退職手当は、以下の計算式で決まります。
退職手当 = 基本額 + 調整額
この2つの要素を、具体的なモデルケースで計算してみましょう。
【モデルケース】
・大卒後、正規教員として採用
・勤続10年(例:22歳→32歳)
・退職理由:自己都合
・退職時の給料月額(基本給):30万円
(※給料月額は自治体や号給によって異なりますが、ここでは仮の金額として設定します)
1. 基本額の計算
基本額は「退職日の給料月額 × 支給率」で計算されます。この「支給率」は、勤続年数と退職理由によって決まっています。
勤続10年・自己都合の場合の支給率は「5.022」(※)です。
基本額 = 300,000円 × 5.022 = 1,506,600円
(※支給率は国家公務員の規定に準じている場合がほとんどです)
2. 調整額の計算
調整額は、在職期間中の「貢献度」に応じて加算される金額です。在職中の役職(等級)に応じて月額が定められており、そのうち金額が多いものから60ヶ月分(5年分)を合計した額が基礎となります。
仮に、調整月額が平均して20,000円だったと仮定します。
調整額(基礎)= 20,000円 × 60ヶ月 = 1,200,000円
ここが重要なポイントです。
自己都合で退職した場合、この調整額が減額されます。勤続10年〜24年の自己都合退職の場合、調整額は「半額(1/2)」になります。
調整額 = 1,200,000円 × 1/2 = 600,000円
3. 合計金額
退職手当 = 1,506,600円(基本額) + 600,000円(調整額) = 2,106,600円
先ほどの目安(240万〜270万)より低い金額になりました。これは、退職時の給料月額や調整月額(役職)によって大きく変動するためです。もし退職時の給料月額が35万円であれば、それだけで基本額が約175万円となり、合計は約235万円になります。管理職に近い等級であれば調整額も増えます。
あくまで「10年・自己都合」では、満額の定年退職とは比べ物にならないほど少ない金額になる、という現実を知っておくことが重要です。
10年 退職金 どれくらい?勤続年数と退職理由がすべて
「10年で退職金はどれくらい?」という疑問に対する答えは、結局のところ「退職理由」と「勤続年数」の2大要素に尽きます。特に「自己都合」で辞める場合のインパクトは甚大です。
「自己都合」vs「勧奨退職」
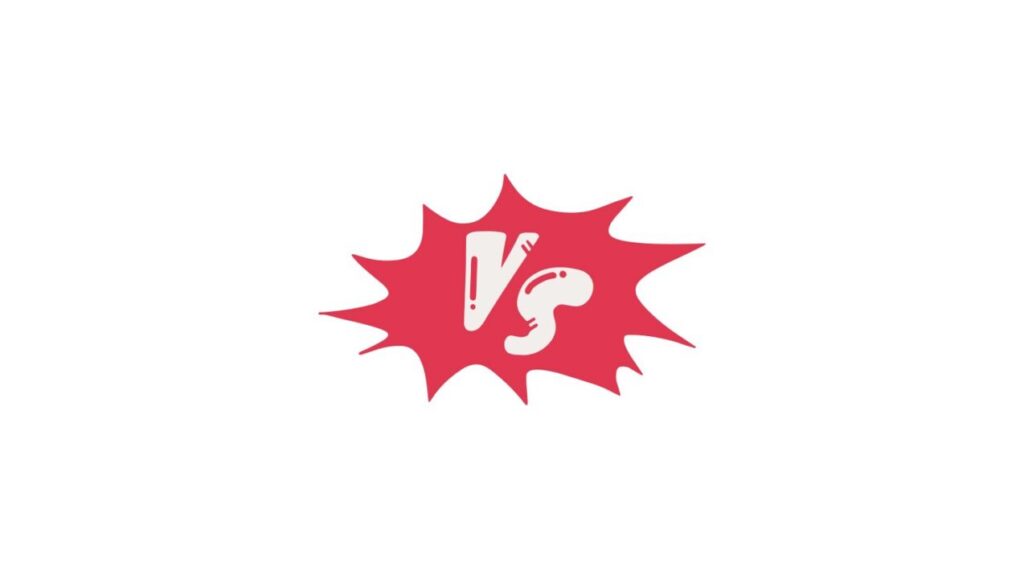
退職理由には、大きく分けて「自己都合」「勧奨退職(定年含む)」「懲戒免職」があります。
- 自己都合:転職や結婚、引っ越しなど、自分自身の都合による退職。支給率が大幅に低く設定されます。
- 勧奨退職:いわゆる「肩たたき」や、早期退職募集制度(割増退職金が出る場合)など、学校・自治体側の都合による退職。定年退職とほぼ同等の高い支給率が適用されます。
- 懲戒免職:不祥事などによるクビ。退職金は原則として支給されません。
先ほどの「勤続10年」のケースでも、「勧奨退職」であれば支給率が「5.022」ではなく「10.584」程度(※自治体による)に跳ね上がります。これだけで基本額が2倍以上変わるのです。
【比較】教員退職金、5年で辞めた場合
10年という節目と比較するために、「教員退職金 5年」の場合も見てみましょう。もし勤続5年・自己都合で辞めた場合、どうなるでしょうか。
【モデルケース】
・勤続5年・自己都合
・退職時の給料月額:26万円
1. 基本額の計算
勤続5年・自己都合の支給率は「2.511」です。
基本額 = 260,000円 × 2.511 = 652,860円
2. 調整額の計算
ここが最大のポイントです。後述する「10年ルール」に直結しますが、勤続9年以下の自己都合退職では、調整額は 0円(ゼロ)です。
調整額 = 0円
3. 合計金額
退職手当 = 652,860円(基本額) + 0円(調整額) = 約65万円
いかがでしょうか。勤続年数が半分(10年→5年)になっただけですが、退職金額はシミュレーション上、約210万円→約65万円と、1/3以下になってしまいました。これは、調整額がゼロになる影響が非常に大きいためです。
退職金の10年ルールとは?自己都合退職の大きな壁
教員の早期退職を考える上で、絶対に知っておかなければならないのが、通称「退職金の10年ルール」です。これは、教員退職金が自己都合の場合に適用される、調整額に関するペナルティ規定のことを指します。
先ほどの「5年」の例で触れた内容の核心部分です。
「調整額」の支給ルール(自己都合の場合)
自己都合で退職する場合の「調整額」は、勤続年数によって以下のように厳しく制限されています。
- 勤続 9年以下: 調整額 = 0円(支給なし)
- 勤続 10年~24年: 調整額 = 算定額の 1/2(半額)
- 勤続 25年以上: 調整額 = 算定額の満額
重要:9年11ヶ月と10年1ヶ月の壁
このルールが意味するのは、「勤続9年11ヶ月」で辞めるのと、「勤続10年1ヶ月」で辞めるのとでは、退職金額が天と地ほど変わる可能性がある、ということです。
9年11ヶ月(勤続9年扱い)の場合、調整額は0円です。
10年1ヶ月(勤続10年扱い)の場合、調整額が半額(60万円~)が支給されます。たった数ヶ月の違いで、数十万円単位の差が生まれる。これが「10年ルール」の正体です。
もしあなたが今、勤続9年目で退職を考えているなら、この「10年の壁」を越えるかどうかで、手取り額が大きく変わることを強く認識してください。
勤続年数のカウント方法にも注意
勤続年数は「1年未満の端数は切り捨て」が原則です(自治体により異なる場合あり)。
例えば、4月1日採用の人が、翌々年の3月31日に退職すれば「勤続2年」です。しかし、3月30日に退職すると「勤続1年11ヶ月」となり、退職金計算上は「勤続1年」扱いになってしまう可能性があります(※)。
特に10年の節目を狙う場合は、自分の正確な勤続期間(「〇年〇ヶ月」)を事務(教育委員会)に確認し、「10年」としてカウントされる退職日を正確に把握することが不可欠です。
(※多くの自治体では月単位で計算し、12ヶ月=1年と換算しますが、最終的な支給率の適用において端数処理のルールが存在するため、確認が必要です)

退職年金は10年と20年どちらが得?
ここまで解説してきたのは、退職時に一括で受け取る「退職手当(一時金)」の話です。
公立学校教員(共済組合員)は、これとは別に、2015年(平成27年)10月以降に加入した期間分の「年金払い退職給付」(通称:退職年金)という制度の対象となります。
これは、在職中に保険料(掛金)を積み立て、退職後に年金として受け取る「第3の年金」とも言えるものです。勤続10年で辞めた場合でも、組合員期間が1年以上あれば、将来(原則65歳から)受け取る権利が発生します。
この「年金払い退職給付」は、半分が「終身年金(生きている限りもらえる)」、残り半分が「有期年金(受け取り期間が決まっている)」で構成されます。
ご質問の「10年と20年どちらが得?」というのは、この「有期年金」の受取期間を指しています。
有期年金の受取期間「10年」と「20年」の比較
有期年金は、原則「20年(240回)」受け取る設定ですが、希望すれば「10年(120回)」で受け取る(または一時金で一括受取する)ことを選択できます。
【前提】
この年金は、自分が積み立てた額(給付算定基礎額)に利息(基準利率)を付けて運用され、それを原資として支払われます。
■ 20年受取 を選んだ場合
- メリット:運用される期間が長くなるため、利息が多く付き、受け取る総額は10年受取より多くなる。
- デメリット:1回あたりの受取額は少なくなる。
■ 10年受取 を選んだ場合
- メリット:1回あたりの受取額は多くなるため、65歳~75歳の間のキャッシュフローが厚くなる。
- デメリット:運用期間が短くなるため、利息が少なくなり、受け取る総額は20年受取より少なくなる。
結論としては、「受取総額」で見た場合、20年受取のほうが「得」になります。
ただし、勤続10年で辞めた場合、この退職年金の原資(積立額)自体がそこまで多くありません。そのため、65歳になったときの家計の状況を見て、「総額は減ってもいいから、月々の足しにしたい」と考えるなら10年受取を選ぶ、という判断になります。
なお、この年金払い退職給付の詳細は、公立学校共済組合のWebサイトで確認するのが最も正確です。
【外部リンク】
年金払い退職給付について | 公立学校共済組合
まとめ:10年の退職は「ルール」の理解が不可欠
教員を10年で早期退職する場合の退職金について解説しました。
- 勤続10年・自己都合の退職金(一時金)目安は、約240万~270万円。給与月額や役職(調整額)によって変動する。
- 退職金は「基本額」+「調整額」で計算される。
- 「自己都合」の場合、支給率が大幅に下がり、調整額もペナルティを受ける。
- 「10年ルール」とは、自己都合退職時に、勤続9年以下だと調整額が0円、10年以上だと半額支給になるルールのこと。9年で辞めるか10年で辞めるかで数十万円の差が出る。
- 教員退職金 5年(自己都合)の場合は、調整額が0円のため、約65万円程度が目安となり、10年次点より大幅に少なくなる。
- 「退職年金」の有期年金部分は、受取総額では「20年受取」が「10年受取」より得になる。
早期退職は、その後の人生設計に大きな影響を与えます。特に退職金は、次のキャリアへの「つなぎ資金」として非常に重要です。ご自身の正確な退職金額を知りたい場合は、必ず所属の教育委員会や給与担当者に問い合わせ、試算してもらうようにしてください。


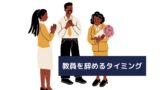



コメント