「教員、バカバカしい」と感じる瞬間7選。心が折れる“くだらない”業務と不人気な理由
この記事は、なぜ多くの現場教師が「教員 バカバカしい」と感じてしまうのか、その構造的な問題を紐解きながら、心の叫びに寄り添うために書きました。
「教員が不人気な理由」は明確に存在し、それこそが「教員不足 当たり前」の現状を生んでいます。「教員 嫌になった」「教員やってられない」と感じるあなたの感覚は、正常な感覚です。
この記事では、以下の点について詳しく解説していきます。
- なぜ「教員はバカバカしい」と感じてしまうのか、その具体的な「7つの瞬間」
- 「教員が不人気な理由は何ですか?」という問いへの明確な答え
- 「いい先生ほど辞める」と言われる皮肉な現実
- 「教員 嫌になった」「教員 心が折れる」と感じた時の危険なサイン
- 「教員 適当でいい」と割り切る考え方と、それがもたらすもの
- 「教員はいつ辞めるのがベストですか?」に対する現実的な回答
あなたが「もう限界だ」と感じているのなら、どうか自分を責めないでください。まずは現状を客観的に知り、あなたの心を守るための選択肢を一緒に考えていきましょう。
「教員 バカバカしい」と感じる、くだらない仕事の数々【7選】
「教員 くだらない」と感じる瞬間。それは、子どもたちと向き合う時間ではなく、それ以外の「謎の業務」に忙殺されている時ではないでしょうか。現場の教師たちが直面する「バカバカしい」と感じる瞬間を、7つの代表的な業務から見ていきます。
1. 誰が読むかわからない「書類地獄」

体験談①:A教諭(30代・小学校)
「教員になって一番驚いたのは、書類の多さです。特に『学校評価アンケート』の結果報告書。保護者や地域からの意見を集約するのですが、結局『昨年同様、貴重なご意見として今後の参考にいたします』という一文で終わる。指導要録(生徒の成績や所見を記録する公文書)は、いまだに手書きを求められる欄があり、間違えれば二重線で訂正印。PCで管理すれば一瞬なのに、なぜこの時代に……と虚しくなります。
月末に提出する『学級経営案の振り返り』は、年度初めに立てた計画通りに進んでいるかを確認するものですが、実態は目の前の子どもたちに合わせて日々変化しています。形式だけの書類を作るために、子どもたちと向き合う時間が削られるのは、本当にバカバカしいと感じます。」
2. 専門外でも対応必須「理不尽すぎるクレーム対応」

体験談②:B教諭(40代・中学校)
「『教員やってられない』と本気で思うのは、保護者対応です。もちろん、協力的な保護者が大半です。しかし、一部の理不尽な要求には心が折れそうになります。『うちの子が鉛筆を忘れたのに、先生が貸してくれなかった。学習権の侵害だ』
『体育祭の練習で少し日焼けした。どうしてくれるんだ』
『隣の席の子が気に入らないから、今すぐ席替えをしてほしい。応じないなら教育委員会に言う』こうした電話が、夜の8時や9時にかかってくることも珍しくありません。謝罪し、対応策を練り、また別の保護者からは『えこひいきだ』と言われる。私たちは何でも屋ではありません。この消耗戦は、本当にくだらないと感じます。」
3. 実質強制の「ボランティア扱い部活動」
体験談③:C教諭(20代・高校)
「私は英語教師として採用されましたが、なぜか週末は野球部の顧問をしています。もちろん未経験です。土日の練習試合の引率、遠征の手配、保護者会との連携。すべてが『自主的・自発的な活動』という名のボランティアです。平日は授業準備と分掌業務で深夜まで働き、土日は朝からグラウンド。
先日、生徒に『先生、今のノック下手すぎ』と笑われました。当たり前です、専門外なのだから。生徒の安全を守る責任だけを負わされ、専門性も手当も無視される。この制度自体がバカバカしくて、情熱も何もなくなりました。」
4. 承認のためだけに出勤・出張「ハンコ文化」
デジタル化が進む現代において、学校現場はいまだに「紙」と「ハンコ」が主流です。簡単な承認を得るためだけに、複数の教員(担任→学年主任→教務→教頭→校長)のハンコを順番にもらって回る「ハンコラリー」。
ひどい場合には、遠くの教育委員会まで「ハンコをもらうためだけ」に出張することも。その移動時間と交通費こそ、最大の無駄でありバカバカしいと感じる瞬間です。
5. 誰も本気で聞いていない「形式的な職員会議」
週に一度、あるいは頻繁に行われる職員会議。しかし、その実態は「すでに決まったことの報告」や「校長の長い訓話」に終始することが多くあります。
「何か意見は?」と聞かれても、ここで反対意見を述べれば「会議が長引く」と煙たがられる。活発な議論ではなく、ただ座って時間を浪費するだけの会議は、生産性のない「くだらない」時間と感じてしまいます。
6. 改善を阻む「前年度踏襲」という絶対ルール
学校現場には「前年度踏襲(ぜんねんどとうしゅう)」という言葉が深く根付いています。これは「とにかく、去年と同じようにやっておけば間違いない」という考え方です。
「このやり方は非効率だ」と若手が改善案を提案しても、「前例がないから」「今までこれでやってきたから」という一言で却下される。子どもたちも時代も変化しているのに、やり方だけが昭和のまま。この硬直した組織体制に「バカバカしさ」を感じ、情熱を失う教員は少なくありません。
7. 人権意識を疑う「時代錯誤な校則運用」
「下着は白のみ」「ツーブロック禁止」「地毛証明書(生まれつきこの髪色だという証明)の提出」。
世間では「ブラック校則」として問題視されているルールが、いまだに現場では運用されています。教員自身も「こんな指導、何の意味があるんだ?」と疑問に思いながら、校則だからという理由だけで生徒に指導しなければならない。自分の良心に反する指導を強制される時、教員という仕事そのものが「くだらない」と感じてしまいます。
教員が不人気な理由は何ですか?「教員不足 当たり前」の構造

「教員が不人気な理由は何ですか?」と聞かれれば、答えは明白です。それは、「仕事の量」と「責任の重さ」に対して、「待遇」と「裁量権」があまりにも釣り合っていないからです。
「教員不足 当たり前」という言葉がトレンドになるほど、この職業は魅力を失いました。
1. 「定額働かせ放題」という名の給特法
教員の給与体系は「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」に基づいています。これは、「残業代を支払わない代わりに、給料月額の4%を『教職調整額』として上乗せする」という法律です。
これが制定されたのは1971年。当時の残業時間は月平均8時間程度でした。
しかし、現代はどうでしょう。文科省の調査ですら、過労死ライン(月80時間)を超える残業をしている教員が多数存在します。月100時間残業しても、200時間残業しても、支給されるのはたった「4%」です。
これは実質的な「サービス残業の合法化」であり、「定額働かせ放題」プランに他なりません。この構造的な問題を放置していること自体が、この国の教育に対する姿勢を表しており、バカバカしいと感じざるを得ません。
2. 無限に広がる「責任」の範囲
教員の仕事は「授業をすること」だけではありません。
- 生徒指導:いじめ、不登校、家庭環境の問題、SNSトラブル。
- 安全管理:登下校の安全、部活動での怪我、アレルギー対応、災害時の避難誘導。
- 心のケア:発達障害の特性を持つ子への対応、スクールカウンセラーとの連携。
これらすべてに「先生の責任」が問われます。子どもの命を預かる重圧は凄まじいものがあります。しかし、それだけの重責を負いながら、教員一人ができることには限界があります。専門家(カウンセラーやソーシャルワーカー)の圧倒的な不足。そのしわ寄せがすべて現場の教員に来ているのです。
3. 社会からの過剰な期待と監視
「先生なんだから、立派であって当然」
「先生のくせに、そんなことも知らないのか」
社会は教員に対して「聖職者」であることを求めます。しかし、ひとたび不祥事が起これば、個人の問題としてではなく「教員全体」の問題として激しく非難されます。
SNSの普及により、保護者や生徒からの「監視の目」は常に光っています。授業中のちょっとした失言、服装、プライベートの行動までが評価対象です。この息苦しさが、「教員 楽しくない」と感じさせる大きな要因となっています。
「いい先生ほど辞める」は本当か?「教員 楽しくない」と感じる瞬間
現場では「いい先生ほど辞める」という言葉が、半ば常識のように語られています。これは単なる噂ではなく、構造的な真実を含んでいます。
「いい先生」とは、多くの場合、以下のような特徴を持つ人です。
- 子どもへの情熱が強い:一人ひとりの生徒と真剣に向き合おうとする。
- 真面目で責任感が強い:任された業務を完璧にこなそうと努力する。
- 問題意識が高い:古い慣習や非効率な業務を「おかしい」と感じ、改善しようとする。
皮肉なことに、この「真面目さ」と「情熱」こそが、彼らの心を折っていくのです。
体験談④:D教諭(30代・元小学校教諭)「情熱が燃え尽きた日」
「私は、子どもたちと一緒に新しいことに挑戦するのが大好きでした。プログラミング教育が始まると聞けば自費で研修に行き、授業で使えるアプリを夜な夜な研究しました。でも、現実は違いました。新しい取り組みを提案しても、職員会議で『前例がない』『準備が大変』と却下される。子どもたちと向き合う時間を確保しようとすればするほど、山積みの書類仕事が終わらない。
ある日、生徒のアンケートに『先生、最近疲れてるね』と書かれていたんです。ハッとしました。一番やりたかった『子どもたちと楽しく学ぶ』ことができず、くだらない雑務に追われてイライラしている自分に気づいたんです。
『このままでは、子どもたちのことも、自分のことも嫌いになる』。そう思い、退職を決めました。今は教育系のベンチャー企業で、教材開発をしています。皮肉ですが、学校の外に出た今の方が、よっぽど『教育』に貢献できていると感じます。」
情熱があり、真面目な人ほど、理想と現実のギャップに苦しみます。
「教員 楽しくない」と感じる瞬間は、子どもが嫌いになった時ではありません。「子どもたちのために働きたいのに、システムがそれを許してくれない」と絶望した時です。
そして、「いい先生」は、往々にして有能です。彼らには「教員以外の場所でも活躍できる」という選択肢があるため、見切りをつけて去っていくのです。

「教員 嫌になった」「教員やってられない」心が折れるサイン
「教員 嫌になった」「教員やってられない」と感じながらも、責任感から働き続けていませんか? しかし、「教員の心が折れる」前には、必ず危険なサインが現れます。
以下のサインに複数当てはまる場合、あなたの心は「もう限界」だと悲鳴を上げています。
- 朝、涙が止まらない:出勤しようとすると、理由もなく涙が出てくる。
- 眠れない、または起きられない:仕事のプレッシャーで寝付けない。逆に、休日泥のように眠り続けてしまう。
- 笑えなくなった:大好きだった子どもたちの前でも、笑顔が引きつる。
- 日曜日の夜が怖い:「サザエさん症候群」が極端にひどく、日曜の夕方から動悸や吐気がする。
- 小さなミスが増える:普段ならあり得ないような、提出物の間違いや忘れ物が増える。
- すべてがどうでもよくなる:「教員 適当でいい」と本気で思い始める。
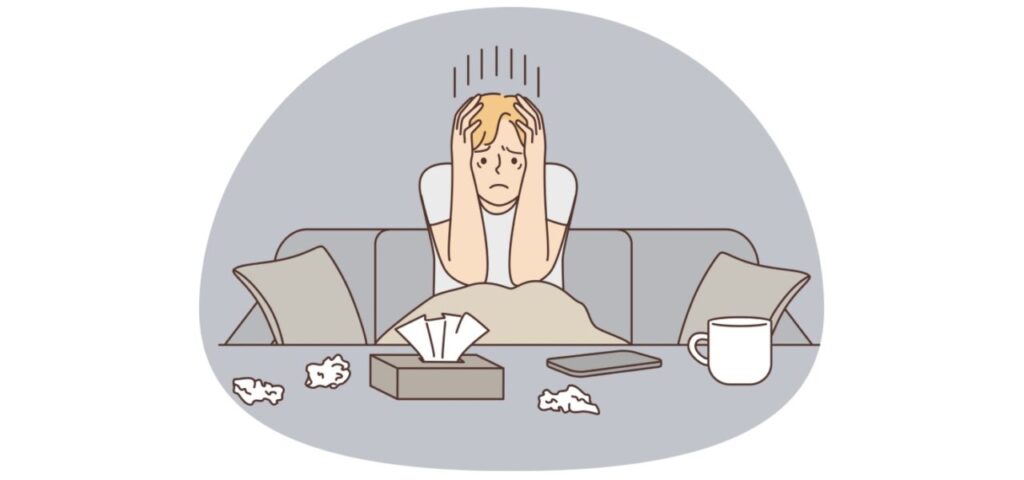
「教員 適当でいい」という危険な諦め
「教員 適当でいい」という考え方は、一見すると、このバカバカしいシステムの中で生き残るための「処世術」のように思えます。
「どうせ誰も見ていないんだから、書類なんて適当でいい」
「クレームも『すみません』と頭だけ下げておけばいい」
「授業も教科書通り、無難にこなせばいい」
確かに、このように「割り切る」ことで、一時的に心を守れるかもしれません。
しかし、もともと情熱を持って教職を志した人にとって、この「適当にやる」という行為は、自分自身の信念を裏切る行為に他なりません。
「適当でいい」と思い始めた時、それは心が麻痺し始めているサインです。児童生徒への情熱を失い、自分の仕事に誇りが持てなくなった時、それは「適応」ではなく「心の死」の始まりかもしれません。
「教員 もう限界」なら「教員はいつ辞めるのがベストですか?」
「教員 もう限界」だと感じた時、次に考えるのは「辞めるタイミング」です。「教員はいつ辞めるのがベストですか?」という問いには、いくつかの答えがあります。
ベストタイミング①:年度末(3月末)
最も「円満退職」しやすいタイミングです。
クラス担任や校務分掌(係の仕事)が切り替わるため、学校への迷惑を最小限にできます。
また、3月に退職すれば、冬のボーナス(12月)を受け取った上で、次のキャリアへの準備期間(春休み)を確保できます。
ただし、この時期に辞めるには、遅くとも10月〜12月頃には管理職(校長・教頭)に意向を伝えておく必要があります。年度末ギリギリに伝えると、後任の補充が間に合わず、強く引き止められる可能性が高くなります。
ベストタイミング②:夏休み前(7月)または夏休み中
年度途中ではありますが、比較的大きな区切りとなるのが夏休みです。
1学期の業務を終え、通知表を渡した後であれば、2学期からの後任(臨時的任用教員など)を探す時間ができます。
また、夏休み中に有給休暇を消化しながら、転職活動や心身の休息に充てることができます。
ベストタイミング③:今すぐ(心が壊れる前)
もし、あなたが前述の「心が折れるサイン」に当てはまり、毎朝涙が止まらなかったり、不眠が続いているのなら。
ベストなタイミングは「今すぐ」です。
「クラスの子どもたちが可哀想」「同僚に迷惑がかかる」…その責任感は尊いものです。しかし、あなたの心身の健康以上に大切なものはありません。
あなたが倒れてしまったら、結局は子どもたちにも同僚にも、もっと大きな迷惑がかかります。
すぐに辞めるのが難しい場合でも、まずは「休職」という選択肢を強く推奨します。心療内科を受診し、医師の診断書をもらえば、正式な手続きとして休むことができます。傷病手当金などを受け取りながら、今後のことをゆっくり考える時間を確保することが最優先です。
辞めたい、でもお金が…」その不安、放置していませんか?
「教員は辞めたい。もう限界だ。でも、辞めた後のお金のことが不安で一歩が踏み出せない…」
教員は安定していると言われますが、それは「働き続ければ」の話。退職金や年金も、昔ほど手厚くはありません。将来への漠然とした不安を抱えている20代、30代、40代の女性は非常に多いです。
- 「お金の上手な貯め方・殖やし方を知りたい」
- 「将来のお金に漠然とした不安を持っている」
- 「iDeCo、NISA、つみたてNISA、結局どれがお得なの?」
- 「投資をゼロから学び始めたいけど、難しそう…」
そんな「お金のモヤモヤ」を抱えているなら、一度プロの話を聞いてみませんか?
日本最大級の無料マネーセミナーサイト【アットセミナー】は、そんな女性の不安に寄り添うセミナーを全国各地で開催しています。
運営会社は、15周年を迎えた日本初の無料保険相談サービス「みんなの生命保険アドバイザー」を運営しているパワープランニング株式会社なので、信頼と実績も十分です。
「お金の話は難しい」と感じている初心者の方にこそ、ぜひ参加してほしい内容です。無理な金融商品の勧誘は一切なく、将来のマネープランの「考え方」をゼロから学べます。
さらに、セミナー参加&アンケート回答で、もれなく豪華ギフトが貰えるキャンペーンを常時開催中!
◆プレゼント例(時期によって異なります)
・こくうま霜降り黒毛和牛 A5等級
・スターバックスチケット(1400円)
・北海道産栽培米 ゆめぴりか (和紙袋) 2kg
・スイーツファクトリー 8種16個セット
スイーツ付きのセミナーも多く、リラックスした雰囲気で学べるのも嬉しいポイントです。
今の「バカバカしい」職場から抜け出すためにも、まずは将来の「お金の不安」をスッキリさせることから始めてみませんか?
▼参加特典付き!無料マネーセミナーの詳細はこちら▼
「教員 適当でいい」と割り切るか、新天地を目指すか
「教員 バカバカしい」と感じた時、あなたの前には大きく分けて2つの道があります。
1. 「割り切って」教員を続ける道
もし、あなたが「教員という仕事自体は嫌いではないが、雑務が多すぎる」と感じているなら、「適当にやる」のではなく「戦略的に手を抜く」という道があります。
- 完璧を目指さない:書類は60点でヨシとする。
- 断る勇気を持つ:明らかにキャパオーバーな仕事は「できません」と断る。
- 部活動は「顧問拒否」する:違法なサービス残業はしない、という強い意志を持つ。(※近年は、部活動の地域移行なども進んでおり、声を上げやすい環境になりつつあります)
- 有給休暇をすべて使う:休むのは権利です。「休んだら迷惑」という思考を捨てる。
これは「適当でいい」という諦めとは違います。自分の心身を守り、本当に大切な「授業」と「子どものケア」にエネルギーを集中させるための、積極的な自己防衛です。
2. 「辞める」ことを前提に動く道
もし、「この組織(学校)にいること自体がもう限界だ」と感じるなら、今すぐに転職活動を始めるべきです。
教員が持つスキルは、ビジネスの世界でも非常に高く評価されます。
- マネジメント能力:40人のクラスをまとめ、学級経営をした経験。
- プレゼンテーション能力:毎日、人前で授業(プレゼン)をしてきた経験。
- 事務処理能力:膨大な量の書類を捌いてきたスピードと正確性。
- 対人折衝能力:多様な子どもたち、保護者、同僚と連携してきた経験。
教育業界(塾、予備校、教材開発、EdTech企業)はもちろん、一般企業の人事、研修担当、営業、広報など、活躍の場は無限にあります。
🆘 ひとりで抱え込まないで
今、あなたが本当に「もう限界」で、誰にも相談できずにいるのなら、公的な窓口を頼ってください。
あなたの心を守ることが、何よりも優先です。
外部リンク: こころもメンテしよう ~教職員の皆さんへ~(厚生労働省)
厚生労働省が設置している、教職員向けのメンタルヘルス情報・相談窓口のポータルサイトです。各都道府県の相談窓口などがまとめられています。
結論:「教員 バカバカしい」は、あなたのせいじゃない
「教員 バカバカしい」
「教員 くだらない」
「教員 もう限界」
これらの言葉は、決してあなたの「甘え」や「適性のなさ」から来るものではありません。
それは、時代遅れで非効率なシステムに対する、当然の違和感です。
あなたは、子どもたちのために真面目に働こうとした結果、このバカバカしいシステムに心をすり減らされてしまった被害者とも言えます。
「いい先生ほど辞める」という現実がある一方で、「いい先生」が心を守りながら働き続けられる環境を作るのが、本来あるべき姿です。
どうか、自分を責めないでください。
そして、自分の人生を「学校」という狭い世界だけで完結させないでください。
休職する。
割り切って働く。
お金の勉強を始める。
転職活動をする。
どの選択肢を選んでも、それは「逃げ」ではなく「前進」です。
あなたの心が、これ以上折れてしまう前に。
どうか、あなた自身を一番大切にする選択をしてください。

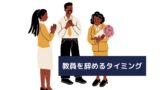



コメント