「教員を、辞めたい…」
毎日子どもたちのためにと身を粉にして働き、ふと一人になった瞬間に、そんな思いが胸をよぎることはありませんか?
特に、希望に燃えて教壇に立ったはずの初任の先生。キャリアを重ね、責任も増してきた40代の先生。そして、心身ともに「疲れた」と感じているすべての先生方へ。
その気持ちは、決して特別なものでも、甘えでもありません。あなたが一人で抱え込む必要はないのです。
この記事は、出口の見えないトンネルの中で、一人で悩み、苦しんでいるあなたのために書きました。
「辞める」という選択肢が現実味を帯びてきたとき、多くの疑問や不安が押し寄せてくるはずです。この記事を読めば、あなたのその不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための具体的な情報が手に入ります。
【この記事を読めば分かること】
- 教員の1年目までの離職率や、小学校の先生の離職率のリアルな数字
- 教師は年度途中でも退職できるのか、何ヶ月前に伝えればよいのかという具体的な手続き
- 多くの先生が辞めたいと思う理由と、あなたが一人ではないという事実
- 小学校教員の具体的な辞め方と、円満退職に向けた交渉のコツ
- 教員が特にしんどいと感じる時期とその乗り越え方のヒント
- 教師を辞めてよかったと感じる、新しい未来の可能性
- 今すぐ辞める以外の選択肢として、「特別支援学級」という道
この記事が、あなたの心を少しでも軽くし、自分らしい未来を描くための羅針盤となることを願っています。
関連記事もあわせて読んでいただける方はこちから👇
先生が辞めたいと思う理由は何ですか?
あなたが「辞めたい」と感じるのには、必ず理由があります。そして、その理由は決してあなた一人が抱える特殊なものではありません。
1. 終わりの見えない長時間労働と膨大な業務量
「定時に帰れる日は、年に何日あるだろう…」
授業準備、テストや宿題の丸付け、学級通信の作成、所見の記入、数々の調査物や報告書の作成。これらはほんの一部です。放課後は会議や研修、週末は部活動や行事の準備…。自分の時間や家族との時間を犠牲にしながら、毎日遅くまで学校に残るのが当たり前になっていませんか?
特に小学校の先生は、ほぼ全ての教科を一人で教え、学級経営の全責任を負います。心身をすり減らすような働き方が常態化し、「教員やめたい疲れた」と感じてしまうのは、あまりにも自然なことなのです。
2. 心を削る保護者対応
ほとんどの保護者は協力的ですが、中には理不尽な要求やクレームを突きつけてくる保護者も存在します。一度の対応ミスが大きな問題に発展することもあり、常に緊張感を強いられます。
「うちの子だけを見てほしい」「先生の指導力不足だ」
このような言葉に、あなたの教育への情熱や自尊心が傷つけられていませんか?誠心誠意向き合っても理解されないときの無力感は、計り知れません。
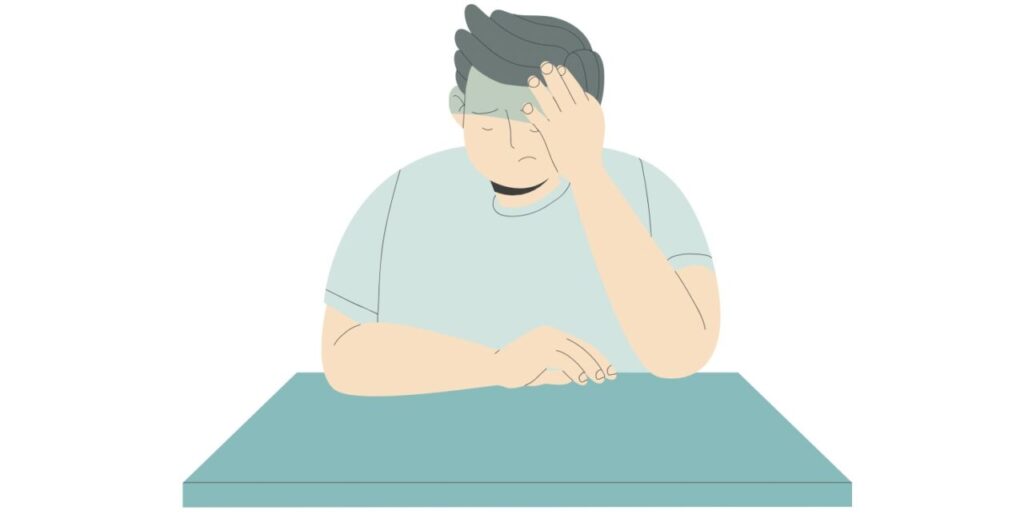
3. 複雑で閉鎖的な職場の人間関係
学校は、良くも悪くも閉鎖的な社会です。同僚や管理職との人間関係が、大きなストレスの原因になることも少なくありません。
学年団での意見の対立、管理職からの圧力、職員室での孤独感…。子どもたちのために連携すべき同僚との関係がうまくいかないと、精神的な負担は一気に増大します。相談できる相手がおらず、一人で抱え込んでしまう先生も多いのが現状です。
4. 理想と現実のギャップ
「子どもたちの成長を支えたい」
「未来を担う人材を育てたい」
そんな熱い思いを抱いて教員になったはずなのに、現実は事務作業とクレーム対応に追われる毎日。子ども一人ひとりとじっくり向き合う時間など、ほとんどない… G
この理想と現実のギャップに、心を痛めている先生は少なくありません。特に、経験の浅い初任の先生ほど、このギャップに苦しみ、自信を失いがちです。
5. 「教員やめたい40代」が直面する特有の悩み
40代になると、教員としてのキャリアも中堅からベテランの域に入ります。主任などの役職に就き、責任が増す一方で、体力的な衰えも感じ始める時期です。
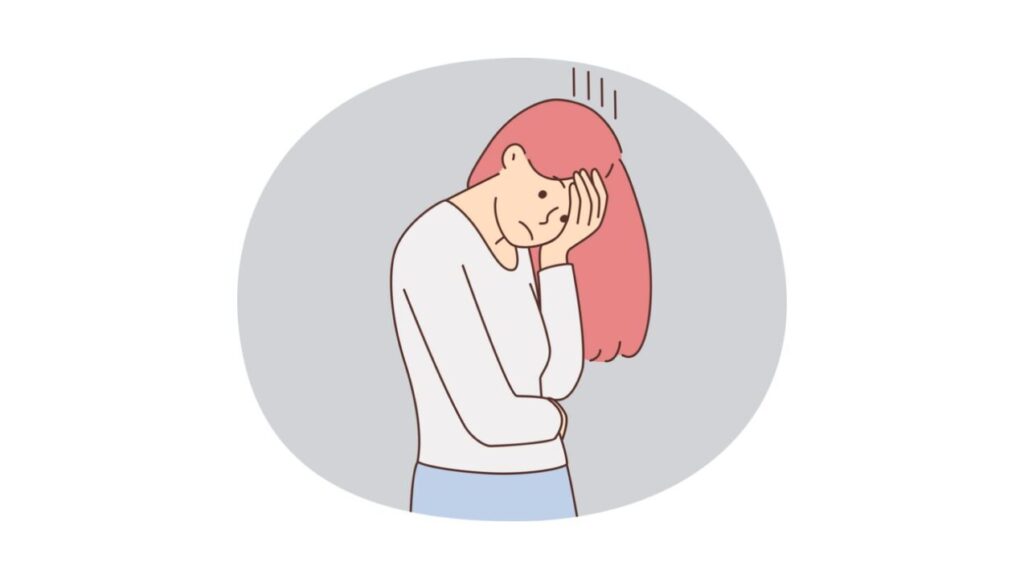
- 管理職と若手の板挟み: 中間管理職的な立場で、双方の意見調整に奔走し、疲弊する。
- 家庭との両立の難しさ: 子どもの進学や親の介護など、家庭での責任も重くなる年代。仕事との両立に限界を感じる。
- 将来への不安: 「このまま定年まで、この働き方を続けられるのだろうか…」という漠然とした不安。体力も気力もすり減り、セカンドキャリアを考える最後のチャンスかもしれないと感じる。
これらの理由が一つ、また一つと積み重なり、ある日突然、心の糸がぷつりと切れてしまうのです。あなたが「辞めたい」と思うのは、決してあなたの責任ではありません。
教員がしんどい時期はいつですか?
教員の仕事には、年間を通じて心身の負担が特に大きくなる「しんどい時期」があります。もしあなたが今、まさにその時期にいるのなら、少しだけ肩の力を抜いてください。多くの先生が同じように感じています。
- 4月~5月:期待と不安が入り混じる新学期
新しい学年、新しい子どもたち。期待に胸を膨らませる一方で、クラスがうまくまとまるか、保護者との関係は築けるかというプレッシャーが重くのしかかります。特に初任の先生にとっては、何もかもが初めてで、不安と緊張の連続。ゴールデンウィークが明ける頃に、最初の心身の不調のピークを迎えることが多い時期です。 - 6月~7月:行事と評価に追われる梅雨
運動会やプール指導、そして1学期の通知表作成。大きな行事が続く上に、子どもたち一人ひとりの評価という神経を使う作業が重なります。梅雨の気候も相まって、心身のバランスを崩しやすい時期です。夏休みを目前にして、気力だけで乗り切っている先生も少なくありません。 - 10月~12月:中だるみと新たな行事の波
夏休みが明け、学校生活も落ち着いてくる一方で、子どもたちの間にいじめやトラブルが起きやすくなる「中だるみの時期」でもあります。そこに、学習発表会や音楽会、持久走大会などの行事が重なり、息つく暇もありません。年末に向けて、心も体も「疲れた」と感じやすくなります。 - 2月~3月:寂しさと次年度へのプレッシャー
卒業や進級を前に、子どもたちの成長を感じて喜びを覚える反面、別れの寂しさも募ります。同時に、学年末の成績処理、膨大な量の事務作業、そして次年度の準備が猛烈な勢いで押し寄せます。一年間の疲れがピークに達し、「もう限界だ」と感じやすい、最後の踏ん張りどころです。
これらの時期を毎年乗り越えている先生方は、本当に素晴らしいです。しかし、その頑張りが、いつかあなたの心身を蝕んでしまう前に、自分の心の声に耳を傾けることが何よりも大切です。

教員の1年目までの離職率は?小学校の先生の離職率は?
「辞めたいなんて思うのは、自分だけではないか…」
そんな不安を抱えているかもしれません。しかし、データは「あなただけではない」という事実を示しています。
文部科学省の「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、令和3年度に採用された公立の小学校教員のうち、1年以内に離職した正規採用の初任者は409人にのぼります。 これは、新規採用者全体の約1.4%にあたります。
また、精神疾患を理由に離職する教員も後を絶ちません。令和4年度には、精神疾患による病気休職者は6,539人と過去最多を記録し、そのうち小学校教員は3,296人と半数以上を占めています。
これらの数字は、氷山の一角に過ぎません。休職や離職には至らずとも、多くの先生が心身の不調を抱えながら、ギリギリの状態で教壇に立ち続けているのが現実です。
「教員辞めたい 初任」という言葉で検索してしまうのは、決してあなた一人ではないのです。この厳しい現実を知ることは、自分を責める気持ちを和らげ、客観的に自分の状況を見つめ直す第一歩になります。
教師は年度途中でも退職できますか?
結論から言うと、法律上は年度途中でも退職は可能です。
地方公務員である公立学校の教員にも、労働者の権利として「退職の自由」が認められています。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると定められています。
しかし、現実的には「円満な」年度途中退職は非常に難しいと言わざるを得ません。
- 子どもたちへの影響: 担任が年度の途中で代わることは、子どもたちに大きな動揺を与えます。
- 後任者の確保: すぐに後任の先生が見つかる保証はなく、見つかるまでは他の先生がカバーすることになり、多大な迷惑をかけてしまいます。
- 引き継ぎの問題: 学級経営や校務分掌の引き継ぎが不十分になり、学校運営に支障をきたす可能性があります。
こうした理由から、管理職(校長や教頭)からは強く引き止められることがほとんどです。

ただし、心身の健康が著しく損なわれている場合(医師の診断書があるなど)や、家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は、年度途中での退職が認められやすくなります。
あなたの心と体が壊れてしまう前に、自分を守ることを最優先に考えてください。もし、どうしても今の環境から一刻も早く離れたいのであれば、年度途中での退職も選択肢の一つとして、法的には可能であると知っておきましょう。
教員を辞める時は、何ヶ月前に伝えればよいですか?
円満退職を目指すのであれば、退職の意向を伝えるタイミングは非常に重要です。
法律上は2週間前でも可能ですが、学校現場の慣習や、後任者の確保、引き継ぎにかかる時間を考えると、最低でも3ヶ月前、できれば半年前に伝えるのが望ましいでしょう。
多くの学校では、例年10月~12月頃に、次年度の校務分掌や人事異動に関する意向調査が行われます。 このタイミングで、管理職に退職の意向を伝えるのが最もスムーズです。
いきなり「辞めます」と退職届を突きつけるのではなく、まずは直属の上司である教頭先生に「ご相談があります」とアポイントを取り、面談の場で丁寧に伝えるのが一般的な流れです。
その際、強い引き止めにあう可能性が高いです。しかし、あなたの意思が固いのであれば、「退職の意思は変わりません」とはっきりと、しかし誠実に伝え続けることが大切です。
小学校教員の辞め方は?
実際に退職を決意した場合、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、円満退職に向けた具体的な流れをご紹介します。
ステップ1:意思を固め、家族に相談する
まず何よりも大切なのは、「本当に辞めるのか」「辞めてどうしたいのか」という自分の意思を固めることです。なぜ辞めたいのか、その原因は何かを紙に書き出してみましょう。そして、退職後の生活設計(収入、住居など)についても、ある程度考えておく必要があります。
そして、必ず家族に相談しましょう。あなたの人生の大きな決断です。一番の味方である家族の理解と協力を得ることが、精神的な支えになります。

ステップ2:管理職(教頭・校長)に退職の意向を伝える
意思が固まったら、前述の通り、教頭先生に相談の形で意向を伝えます。
- 時期: 年度末退職を目指すなら、10月~12月の意向調査の時期がベスト。
- 場所: 他の先生に聞かれない、校長室や相談室など、落ち着いて話せる場所を確保してもらいましょう。
- 伝え方: 感情的にならず、冷静に、しかし固い決意を持って伝えます。「お時間をいただきありがとうございます。本日は、来年度のことでご相談があり、お時間をいただきました。大変申し上げにくいのですが、一身上の都合により、今年度末で退職させていただきたく考えております」といった形で切り出します。
- 退職理由: 詳細に話す義務はありません。「一身上の都合」で十分ですが、もし聞かれた場合は、「家庭の事情」や「自身のキャリアを見つめ直したい」など、学校や同僚への不満ではない、前向きな理由を伝えられると角が立ちにくいでしょう。
ステップ3:退職願を提出する
校長との面談を経て退職が承認されたら、教育委員会指定の書式で「退職願」を提出します。提出時期や書式については、管理職の指示に従ってください。一度提出したら、基本的には撤回できないので、覚悟を持って提出しましょう。
ステップ4:丁寧な引き継ぎを行う
後任の先生や、同学年の先生方のために、丁寧な引き継ぎ資料を作成しましょう。
- 担当クラスの子どもたちの情報(個別の配慮が必要な子など)
- 学級経営の方針や年間計画
- 保護者対応で留意すべき点
- 校務分掌や委員会の仕事内容
- 各種データの保存場所 など
立つ鳥跡を濁さず。お世話になった学校や同僚、そして何より子どもたちのために、責任を持って最後まで務め上げることが、円満退職の鍵となります。
ステップ5:最後の挨拶と退職
最終出勤日には、職員や子どもたちへ感謝の気持ちを伝えます。私物を整理し、貸与品を返却して、教員人生に一区切りをつけましょう。
教師を辞めてよかったことは何ですか?
「辞めたい」という気持ちの裏には、「辞めた後、どうなるんだろう」という大きな不安があるはずです。しかし、勇気を出して一歩を踏み出した多くの元教員が、「辞めてよかった」と感じています。そこには、どんな未来が待っているのでしょうか。

- 心身の健康と時間の自由を取り戻せる
「土日に仕事のことを考えずに、心から休める日が来た」
「夜、ぐっすり眠れるようになった」
これが、多くの人が最初に実感することです。慢性的な睡眠不足やストレスから解放され、心身ともに健康を取り戻すことができます。自分のため、家族のために使える時間が圧倒的に増え、人間らしい生活を送れるようになります。 - ワークライフバランスが劇的に改善する
持ち帰り仕事や休日出勤がなくなります。平日の夜に友人と食事をしたり、趣味に没頭したり、週末に旅行に出かけたり…。これまで諦めていた「当たり前の幸せ」を手に入れることができます。 - 新たなキャリアの可能性が広がる
教員として培ったスキル(コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、計画実行能力など)は、他の業界でも高く評価されます。
・ 教育業界: 塾講師、家庭教師、教材開発、教育系NPO、私立学校の教員など。
・ 異業種: IT業界、人材業界、広報、事務職など。
自分の興味や得意を活かして、新しい世界に挑戦することができます。 - 「先生」という鎧を脱げる
常に「先生」として品行方正を求められるプレッシャーから解放されます。一人の人間として、フラットな人間関係を築ける環境は、想像以上に心地よいものです。 - 正当な評価と対価を得られる
頑張りが給与や評価に直結する企業に転職すれば、サービス残業が当たり前だった教員時代には得られなかった達成感や満足感を得られる可能性があります。
「教員やめたい疲れた」と感じていた日々から抜け出し、自分らしく輝ける場所が、学校の外には無限に広がっているのです。
【提案】辞める前の一つの選択肢:特別支援学級担任
「仕事は本当にしんどい。でも、子どもと関わること自体は嫌いじゃない…」
もしあなたがそう感じているなら、完全に教職を辞めてしまう前に、もう一つだけ考えてみてほしい選択肢があります。それは、「特別支援学級」の担任になることです。
現在の通常学級の環境が、あなたに合っていないだけかもしれません。
特別支援学級担任の魅力
- 一人ひとりとじっくり向き合える:
クラスの在籍人数が少ないため、30人以上の子どもを同時に見る通常学級とは異なり、一人ひとりの発達段階や特性に合わせて、きめ細やかな指導が可能です。子どもの小さな成長を日々実感できる、大きなやりがいがあります。 - 保護者と強固な信頼関係を築きやすい:
子どもの特性を深く理解し、家庭と連携して指導にあたるため、保護者と協力的なパートナーとしての関係を築きやすい傾向があります。理不尽なクレームよりも、感謝の言葉をいただく機会が増えるかもしれません。 - 専門性が身につく:
特別支援教育に関する専門的な知識やスキルが身につきます。研修の機会も多く、自分自身のキャリアアップにも繋がります。
もちろん、専門的な対応が求められる大変さや、個別の支援計画作成などの業務もあります。しかし、「大人数の一斉指導が苦手」「一人の子と深く関わりたい」というタイプの先生にとっては、通常学級よりも働きやすさを感じる可能性があります。
次年度の意向調査の際に、「特別支援学級を希望する」という選択肢を、心に留めておいてみてはいかがでしょうか。環境を変えることで、あなたの教師としての輝きが、再び見つかるかもしれません。
まとめ
ここまで、教員を辞めたいと悩むあなたへ、様々な情報や選択肢をお伝えしてきました。
「教員を辞めたい」
この気持ちは、決して逃げではありません。あなたの心と体が発している、限界のサインであり、自分らしい人生を取り戻すための、勇気ある一歩の始まりです。
初任で理想と現実のギャップに苦しんでいる先生も、40代で将来に不安を感じている先生も、日々の業務に「疲れた」と感じているすべての先生も、まずは自分自身をこれ以上責めないでください。あなたは、今日まで本当によく頑張ってきました。
退職は、あなたの人生の終わりではなく、新しい可能性の始まりです。この記事で紹介した退職までのステップや、辞めた後の未来、そして特別支援学級という選択肢が、あなたの視野を広げ、心を少しでも軽くする一助となれば幸いです。
あなたの人生の主役は、あなた自身です。どうか、あなたにとって一番幸せな道を選び取ってください。心から応援しています。





コメント