教室でよくある場面。新人の先生が対応しても落ち着かなかった子どもが、別の先生が関わった途端に落ち着きを取り戻す。
「やっぱりベテランの先生はすごい…?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
でも実は、
この別の先生が関わった途端に落ち着きを取り戻す。現象には子どもの心のしくみに関わる深い理由があります。今回は、その理由を分かりやすく解説します。
具体的な支援の方法やSSTの実践はこちら👇
先生が変わるだけで子どもが落ち着く現象
実際の現場でよく見かけるこんな光景。
A先生(新人)が子どもに指示しても暴れ続け、B先生(ベテラン)が代わりに関わるとすっと落ち着く——
この出来事だけを見ると、「A先生よりB先生の方が指導力がある」と判断しがちです。でも、本当にそうなのでしょうか?
対応する人が変わることの“力
子どもが落ち着いた原因は、B先生の対応がうまかったからかもしれません。
でも実はそれ以上に注目したいのが、
「人が変わった」こと自体が、子どもにとって大きな影響を与える
という点です。
単に“ベテランの技”ではなく、“新しい大人との関わり”そのものが子どもの気持ちに変化をもたらしていることがあります。
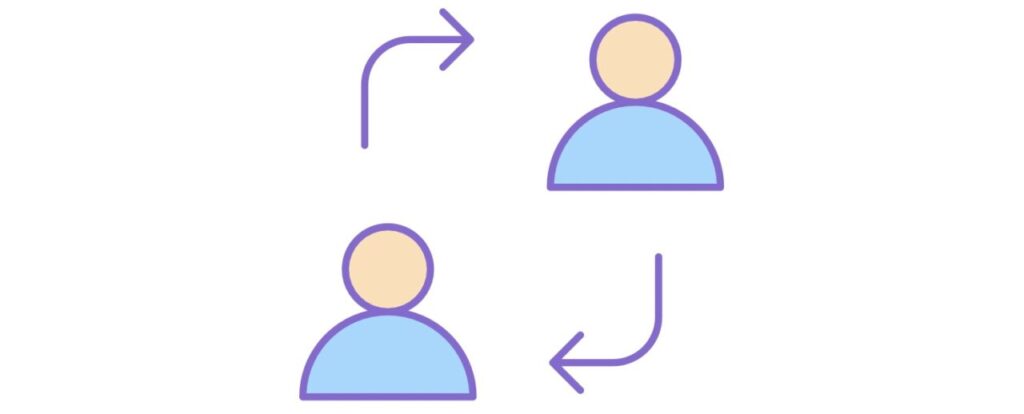
心理学から見た「人が変わると落ち着く」理由
このような子どもの行動には、心理的な裏づけがあります。代表的な理由を4つ紹介します。
1. 関係性のリセット効果
A先生との間に“言い争い”や“不信感”が生まれてしまった場合、子どもは感情を引きずります。
B先生という“新しい関係の人”が入ることで、子どもにとって気持ちを切り替えるチャンスが生まれるのです。
2. 転移と逆転移
子どもは過去の体験を現在の大人に投影することがあります。A先生に対して「この人は怖い」と感じていた子が、B先生には「この人は大丈夫かも」と感じ、行動が変わることがあります。
3. 感情の同調(ミラーニューロンの働き)
子どもは大人の感情にとても敏感です。焦っている先生の感情を受け取って不安定になることもあれば、落ち着いた先生の雰囲気に同調して安定することもあります。
4. 注意の切り替え(刺激の変化)
B先生が登場することで、子どもの注意がそちらに向き、気持ちの“リセット”が起こります。これは心理的に自然な現象です。
これは「A先生がダメ」な話じゃない
こうした現象があると、「やっぱり新人よりベテランだね…」という声が上がりがちです。
でもそれはあまりに単純な評価です。
「人が変わるだけで子どもが変わる」現象には、誰が良い・悪いという判断を超えた理由があるのです。
A先生が悪いわけではありません。むしろ、A先生が一生懸命関わった積み重ねがあったからこそ、B先生の登場が効果的だったとも言えます。
子どもが落ち着いた理由を「一緒に」考えよう
このような場面では、結果だけを見て終わるのではなく、その背景を振り返ることが大切です。
例えばこんなふうに振り返ってみましょう。
- A先生と子どもの関係にどんなズレがあったか
- B先生が登場したことで、子どもは何を感じ取ったのか
- 自分が次回どのような“切り替え役”になれるか
先生同士がこうした視点を共有することで、次に同じような場面が来たとき、より柔軟に対応できるようになります。
教育はチームで支えるもの
「一人の先生の力でどうにかしよう」という考え方は、実は子どもにとっても先生にとっても苦しいものです。
子どもの成長を支えるのは、チームでの連携とお互いのリスペクトです。
人が変わっただけで落ち着く現象も、見方を変えれば「チームの中で役割をうまく分担できた」という成功例なのかもしれません。
おわりに 〜大切なのは支え合う関係性〜
「先生が変わったら落ち着いた」
この現象の裏にあるのは、「人が変わることで子どもの気持ちが切り替わる」という心の自然な働きです。
それを知っていれば、新人の先生が必要以上に落ち込んだり、ベテランの先生が「自分だけができる」と思い込んだりすることも減っていきます。
大切なのは、先生同士が支え合い、子どもの気持ちに寄り添いながらチームで関わっていくこと。
それこそが、子どもにとって一番の安心につながるはずです。


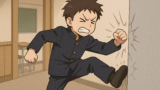



コメント