「運動会が楽しみ!」そう感じる子がいる一方で、胸の奥がキュッと苦しくなる子もいます。
特に、感覚過敏のある子どもたちにとっては、運動会の音やにぎやかな雰囲気が強いストレスとなり、「行きたくない」「無理」と感じるのは珍しいことではありません。
この記事では、支援学級の担任として日々子どもたちと関わる中で感じた「不安を抱える子の気持ちにどう寄り添えばよいか」、そして「どのような配慮や工夫ができるのか」について、私自身の実践も交えながらご紹介していきます。
感覚過敏とは?
「感覚過敏」とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚など、私たちが日常的に受け取っている感覚に対して、強く敏感に反応してしまう状態のことを指します。
たとえば、こんな子がいます。
- ピストルの音が耳を突き刺すように痛い
- 応援の声や音楽が頭の中で反響して混乱する
- 人混みやざわざわとした雰囲気に飲み込まれ、体が固まってしまう
こうした反応は、本人の努力や気持ちの問題ではありません。
脳の感じ方そのものが違うために起こる、自然な現象です。

運動会での「見えにくい困りごと」
運動会は、普段と違う環境・スケジュール・音・雰囲気に満ちています。
そのため、以下のような不安を感じる子がいます。
- 音がこわい(ピストル・応援・マイクの声)
- いつ何をするかわからず、不安になる
- 目の前がにぎやかすぎて、集中できない
- 緊張や混乱からパニックや涙が出てしまう
支援学級の子だけでなく、通常学級の中にもこうした特性を持つ子がいることを、まずは大人が知っておくことが大切です。
合理的配慮としてできること
合理的配慮とは、子ども一人ひとりの特性に合わせて、公平な参加ができるようにするための具体的な工夫や変更のことです。
1. ピストル音への配慮
- ピストルの代わりに、旗や太鼓・電子ホイッスルなどを使用
- 事前にピストル音を小さな音で聞いてみる「段階的慣れ」の練習
- ノイズキャンセリングヘッドホン・耳栓の使用(必要に応じて先生も一緒に)
2. 応援・ざわざわへの配慮
- 「静かに応援するゾーン」を設け、そこに本人が行けるようにする
- 応援練習のときは距離をとる・別室で練習
- 観覧エリアのすぐ後ろに逃げ場スペース(安心の場所)を用意
3. 役割の変更・選択肢の提示
- 本人の希望を聞きながら、競技の参加ではなく補助役に変更(旗を持つ・道具を運ぶなど)
- 「最後までやらなければならない」ではなく、「途中で抜けてもOK」「やってみて無理ならやめていい」という柔軟な選択肢を用意
指導・支援の視点で大切にしたいこと
1. 自分の感じ方を知ること(気づきの支援)
- 「なんで怖いのか?」「どんな音がつらいのか?」を言葉や絵で一緒に整理
- 感情カードや気持ちメーターを使って、「今、どう感じているか」に気づけるように支援
2. 一緒に「できる形」を考える(対話的な支援)
「これはできるけど、これはやめたい」「この時間だけなら大丈夫」など、本人と相談しながら参加の方法を決めることが大切です。
3. クラス全体の理解を育てる(共感的なクラスづくり)
- 朝の会や道徳の時間に、「音が苦手な人がいるんだよ」「みんなちがう感じ方があるんだよ」と話す
- 自分の感じ方とちがうことに出会ったときに、どう関わればよいかを考える機会をつくる
子どもたちの姿から学んだこと
私のクラスにも、感覚過敏が強くて、ピストルの音が苦手な子がいます。
「運動会なんて絶対ムリ」と話していたその子が、今年は「ゴールのテープを持つならできるかも」と言ってくれました。
当日は、耳栓をして、そっと先生と手をつないでゴールの位置につきました。
終わったあと、その子は「ちょっとこわかったけど、がんばれた」と話してくれました。
大切なのは、“できないこと”を見るのではなく、“できたこと”を一緒に喜ぶことなんだと、改めて気づかされました。
おわりに 〜 すべての子に安心とチャレンジを 〜
運動会は、全員が一律に頑張る場ではありません。
一人ひとりのペースで、自分なりにチャレンジできることを見つけていく場であってほしいと私は思います。
感覚過敏のある子どもたちにも、安心して参加できる方法があります。
それは、本人との対話、周囲の理解、そして私たち大人の「その子の感じ方をまるごと受け止める」姿勢から始まります。
運動会が、すべての子どもたちにとって「自分らしくいていい」と感じられる一日になりますように。
※この記事の内容は、支援学級担任としての私の実践と気づきをもとに構成しています。
同じような悩みを抱える先生方、保護者の方々に少しでもヒントになれば幸いです。


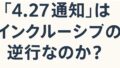
コメント