前回は、アドラー心理学の視点から、一見ネガティブな「劣等感」こそが、子どもたちが「こうなりたい!」と願う成長のエネルギーになる、というお話をしました。子どもたちの内にある「できない自分」と「やりたい自分」の間の葛藤が、彼らを前に進める力になることを学びましたね。
前回の記事はこちらになります。👇

さて、今回ご紹介するのは、19世紀ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェです。彼の哲学は、時に強烈で難解だと言われますが、その思想の根幹には、人間が自身の限界を乗り越え、より強く、より新しい自分へと生まれ変わるための力強いメッセージが込められています。
ニーチェの思想は、子どもたちが困難に立ち向かい、成長していく姿をどのように照らし出すのでしょうか? 特に、特別支援学級の子どもたちや不登校を経験している子どもたちが抱える「乗り越えたい壁」について考える上で、ニーチェの哲学は私たちに大切な視点を与えてくれます。
ニーチェの哲学「自己超克」と「超人」とは?
ニーチェは、当時のヨーロッパに根付いていた価値観や道徳を厳しく批判し、人間が自身の力で新しい価値を創造することの重要性を説きました。彼の哲学の中心にある概念の一つが「自己超克(Selbstüberwindung)」です。
自己超克とは、文字通り「自己を乗り越えること」。それは、過去の自分、弱い自分、慣れ親しんだ考え方、そして自分自身を縛るあらゆる限界や制限を乗り越えようとする、自分自身との戦いであり、絶え間ない努力のプロセスです。
そして、この自己超克を通して、自分自身の価値を創造し、新しい自分となる存在を、ニーチェは「超人(Übermensch)」と呼びました。超人とは、特定の誰かを指すのではなく、人間が自身の可能性を最大限に追求し、常に「生成」し続けるべき理想像、あるいはその「乗り越え続ける」プロセスそのものを象徴しています。
ニーチェは、安定や停滞を否定し、常に変化し、困難に挑戦し、自分自身を更新していくことこそが、人間が生きる上で最も力強く、創造的なあり方だと考えたのです。
子どもたちは、日々「自己超克」している小さなニーチェだ!
このニーチェの「自己超克」という考え方は、子どもたちの日常的な発達の姿と見事に重なります。子どもたちは、まさに日々、小さな「超人」として、自分自身の限界を乗り越えようと奮闘しているのです。
考えてみてください。
- 赤ちゃんが立とうとする時。何度も転んで「立てない自分」という限界に直面します。それでも立ち上がろうとする姿は、まさに「立てる自分になりたい」という「自己超克」への強い意志の表れです。
- 難しいパズルに挑戦する時。うまくいかずに悔しい思いをする「解けない自分」と向き合います。試行錯誤を繰り返し、集中力を維持しようとするのは、パズルを完成させたいという「自己超克」のエネルギーです。
- 友達との関係で悩む時。自分の気持ちがうまく伝わらなかったり、相手の気持ちが理解できなかったり。「コミュニケーションがうまくいかない自分」に直面します。それでも、相手に話しかけたり、自分の気持ちを伝えようとしたりするのは、より良い関係を築きたいという「自己超克」への挑戦です。
- 宿題を前にして「やりたくないな」と思う時。誘惑に負けそうな「弱い自分」と、「やらなければ」と思う「やるべき自分」の間で葛藤します。その葛藤を乗り越えて机に向かう時、子どもは小さな「自己超克」を成し遂げているのです。
これらは全て、子どもが自分自身の身体的、知的、感情的、社会的な限界や弱さと向き合い、それを乗り越えようと努力する「自己超克」のプロセスなのです。彼らは、ニーチェが理想とした「超人」のように、現状に留まらず、常に新しい自分自身を「生成」しようとしているのです。
困難に直面する子どもたちへ。ニーチェが照らす「乗り越える力」
特別支援学級の子どもたちや不登校を経験している子どもたちは、この「自己超克」のプロセスにおいて、他の子どもたちよりも高く、そして分厚い壁に直面していることが多いかもしれません。
学習面でのつまずき、特定の行動様式の困難さ、集団への適応の難しさ、そして「学校に行けない」という状況そのもの。これらは、彼らが自分の「やれない部分」「弱い部分」と真正面から向き合わざるを得ない、過酷な「自己超克」の戦いとも言えます。
彼らが示す「うまくいかない姿」や「つまずき」は、単なる失敗や問題なのでしょうか? ニーチェの視点から見れば、それは彼らが自分自身の限界を乗り越え、新しい自分になろうと必死にもがいている、「自己超克」という壮大な旅の途上にある、尊い戦いの証なのです。
支援者である私たちは、彼らの抱える困難を「取り除くべきもの」としてだけでなく、彼らが自分自身の内に秘めた「乗り越える力」を発揮するための「挑戦の機会」として捉え直すことができます。ニーチェのように、彼らの「乗り越えようとする意志」そのものを力強く肯定する視点を持つことが、私たちに希望を与え、子どもたちの可能性を信じる勇気を与えてくれるのです。
ニーチェの哲学から学ぶ、子どもたちの「乗り越える力」を育むヒント
ニーチェの思想は、子どもたちの「乗り越える力」を育む上で、私たちにどのようなヒントを与えてくれるでしょうか。
1. 挑戦と困難を「成長の機会」として捉える
安全な環境の中で、子どもが少し背伸びをすれば達成できそうな、適度な挑戦の機会を提供しましょう。そして、うまくいかなかったとしても、それを「失敗」として断罪するのではなく、「乗り越えるためのプロセス」「次への学び」として捉え直すメッセージを伝えます。困難に立ち向かう勇気を育てます。
2. 自分の「弱さ」や「苦手」と向き合うサポート
子どもが自分の苦手なこと、嫌な感情、うまくいかない部分など、ネガティブな自分の一側面と向き合えるように寄り添います。「そういう気持ちになることもあるよね」「ここはちょっと難しいね」と感情を受け止め、共感しつつ、それは逃げるものではなく、乗り越えるべき「自分自身の課題」であることを、無理強いではなく、子どもが自分自身で気づけるようにサポートします。
3. 「過去の自分」との比較で成長を承認する
他人と比べて「できる/できない」で評価するのではなく、「過去の自分と比べて、今の自分ができるようになったこと」に焦点を当てて承認しましょう。「前はこの計算難しかったけど、今は解けるようになったね!」「前はこれが怖かったけど、今日は挑戦できたね!」のように、具体的な変化を言葉にすることで、子どもは自身が「自己超克」していることを実感し、自己肯定感を高めます。
4. 自分だけの「超人」像を描くことを応援する
子ども自身が、たとえ漠然とでも「どんな自分になりたいか」という未来の自分(小さな「超人」像)を描けるようにサポートします。それは「〇〇ができるようになりたい」「こんな人になりたい」といった、子どもにとって身近で具体的な目標で構いません。その目標に向かって努力するプロセスそのものを応援し、「君は君自身の超人を目指せるんだよ」というメッセージを伝えます。
まとめ。困難を乗り越える子どもたちは、皆「超人」への道を歩んでいる
ニーチェの哲学は、人間の内なる限界や困難との戦いを力強く肯定し、そこから新しい自己が生まれることを示唆しています。子どもたちが日々経験する「やれない自分」との葛藤や、困難に立ち向かう姿は、まさにこの「自己超克」という壮大な旅の一部なのです。
特別支援学級や不登校の子どもたちが直面する壁は高く見えるかもしれません。しかし、彼らの内に秘められた「乗り越えようとする意志」は、ニーチェが理想とした「超人」への道を歩む力そのものです。
彼らの「つまずき」を単なる問題として片付けるのではなく、彼らが自分自身の「超人」(新しい自分)へと生成していくための、尊い戦いとして捉え直すこと。そして、その挑戦を信じ、見守り、共に歩む伴走者となること。
それが、子どもたちの内に眠る「乗り越える力」を最大限に引き出し、彼らが自分自身の力で未来を切り拓いていくための、最高のサポートとなるのではないでしょうか。困難を乗り越えようとする子どもたちは、皆、希望に満ちた小さな「超人」なのです。
このシリーズでは、様々な思想家たちの視点から、子どもたちの「内なる葛藤」と「成長」についてさらに探求していきます。
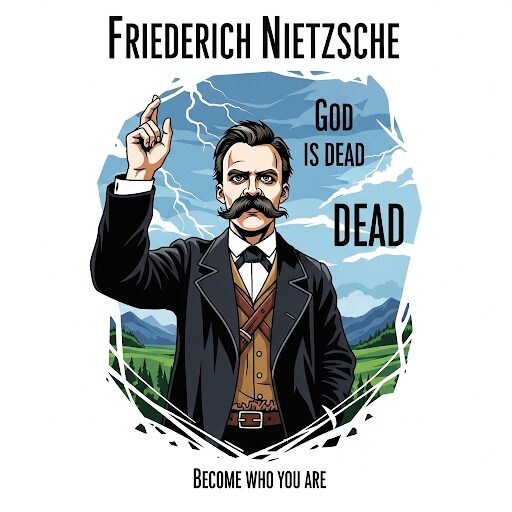


コメント