「人間知恵の輪」とは、複数人で手を取り合って絡まり、そこから協力して“解いていく”という遊び感覚の活動です。実はこの活動、子どもたちのコミュニケーション能力や問題解決能力を自然と育むため、特別支援学級における自立活動やSST(ソーシャルスキルトレーニング)にとても効果的な教材として活用できるんです。
この記事では、
- 人間知恵の輪の基本的なやり方と「正解」の考え方
- 2人から楽しめる!タオルを使った効果的なアレンジ方法
- 思わず「なるほど!」となる、解き方の具体的なコツ
- 特別支援学級での具体的な工夫・活用事例
を、私が実際に経験した内容を交えてご紹介します。日々の支援に役立つヒントがきっと見つかるはずです。
おすすめの自立活動はこちら💁
1. 基本の「人間知恵の輪」のやり方(3〜6人)
やり方の手順
- 3〜6人で円をつくって立ちます。
- 目を閉じて、右手で別の人と手をつなぎます。
- 左手も同じように、違う人と手をつなぎます(同じ人はNGです)。
- 目を開けて、手を離さずに絡まりを解いていきます。
詳しくはこちらの記事にまとめています👇
正解はあるの?
「絶対この形!」という唯一の正解はありません。元の円形に戻ったり、全員がスムーズにほどけたら“成功”とする場合が多いです。
大切なのは、「協力しながら問題を解決していく過程」そのもの。子どもたちが自ら考え、工夫し、助け合う経験こそが学びになります。
2. 2人でもできる!人間知恵の輪のやり方と正解【タオル使用】
「大人数じゃないとできないんじゃない?」そんな声に応えて、ここでは2人から楽しめる、タオルを使った人間知恵の輪をご紹介します。少人数でも、そして直接手をつなぐのが苦手な子でも安心して取り組めますよ。

用意するもの
- フェイスタオル(もしくは布やひも)1本
2人バージョンのやり方
- 2人が向かい合って立ちます。
- それぞれの右手でタオルの端を交差して持ちます。
- 左手も同じように、交差させてタオルの端を持ちます。
→ このときタオルがねじれて“8の字”のような形になります。 - そのまま手を離さずにタオルのねじれを解きます。
少し不自然な絵ですが、こんなイメージです👇
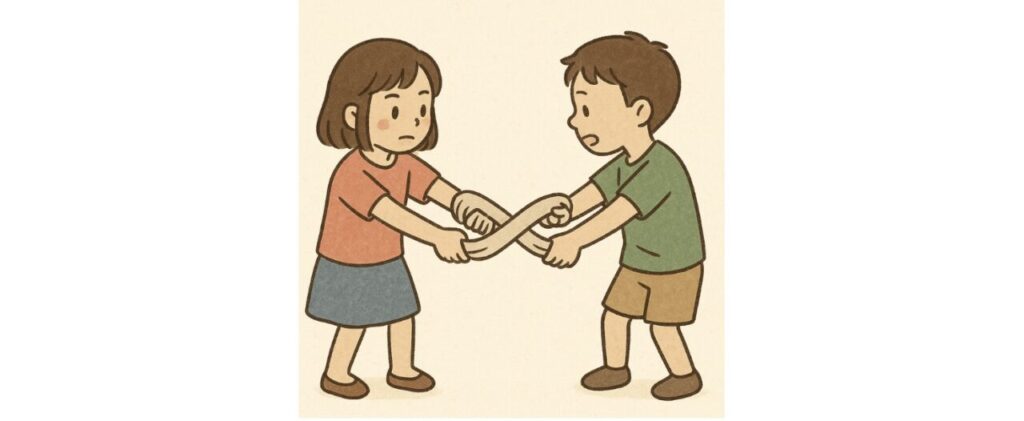
3. 解き方のコツ(正解へのアプローチ)
2人の人間知恵の輪に「こうすれば絶対正解!」という唯一のルートはありません。しかし、うまく解くためのヒントはいくつかあります。
解き方のヒント
- 一人がタオルをまたいで回転してみる。
- 肩や腕をくぐらせるように試してみる。
- 両者が交互に動き、タオルのねじれを慎重にほどいていく。
- 積極的に声をかけながら、「次は右かな?」「私がくぐる?」などと相談し、協力して試行錯誤する。
ここで最も大切なのは、「これが正解!」と子どもたちに押しつけないことです。「自分たちで工夫して解けた!」という成功体験こそが、子どもの主体性や自己肯定感を育むかけがえのない学びとなるからです。
4. 人間知恵の輪でタオルを使うメリットと支援級での工夫
タオルを使う3つの理由
- 直接手をつながなくて済む:触覚過敏がある子どもや、人との接触が苦手な子どもでも安心して参加できます。
- 感染症対策にも有効:直接触れる機会が減るため、衛生面での配慮にもつながります。
- 視覚的にも楽しい:色や柄のあるタオルを使えば、活動がより楽しく、視覚的な刺激にもなります。
特別支援学級での配慮例
| 課題 | 工夫例 |
|---|---|
| 直接手をつなぐのが苦手な子 | ハンカチやスカーフを間に挟むことで、直接的な接触を避けつつ活動に参加できるようにする。 |
| 動きのイメージがわきにくい子 | 教師や支援員が前に出て実演したり、イラストや図解で視覚的に手順を提示したりすることで、見通しを立てやすくします。 |
| 声が出しにくい、コミュニケーションが苦手な子 | 「くぐっていい?」「助けて!」など、よく使う言葉をまとめた「こう言ってみようカード」を準備し、指差しなどで気持ちを伝えられるように支援します。 |
| 見通しが持てず、不安になりやすい子 | 活動全体の流れを図や写真で分かりやすく提示し、事前に「こういう流れで進むよ」と伝えることで、安心して取り組める環境を整えます。 |
5. 自立活動・SSTとの関連
人間知恵の輪は、ゲーム感覚で取り組める一方で、実に多くのスキルを育てる要素を含んでいます。
自立活動との関係(6区分27項目より)
| 区分 | 育てられる力 |
|---|---|
| 人間関係の形成 | 協力・役割意識・相手を思いやる心、声をかけ合い、譲り合う姿勢を通して、他者との協調性を育む。 |
| 心理的な安定 | 安心感・達成感・自己表現の機会、成功体験を通じて大きな達成感と安心感を味わい、自信を育む。 |
| 身体の動き | 空間認知・バランス・柔軟な動き、自分と他人の位置関係を把握し、身体を柔軟に動かす力を養う。 |
| 自己理解と自己調整 | 感情のコントロール、困難な状況で自分の気持ちを調整し、冷静に問題解決に取り組む力を培う。 |
特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしました。
SSTの視点でのねらい
- 「伝える・聞く」練習(例:「くぐっていい?」「そこ、通れる?」など、具体的な言葉でのやり取り)
- 自分の気持ち(「わからない」「困った」など)をコントロールし、適切に表現する練習
- 助け合いや相手を待つなどの協調スキルを身につける
6. 実際の支援学級での成功例
私が担当したある自閉スペクトラム症の5年生の児童は、活動の導入で「わからない!」「どうせできない!」と不安が強くなり、表情が硬くなってしまいました。しかし、支援員さんがすかさず「じゃあ私が先に回って見本を見せるね」と、実際にタオルをまたぐ動きをゆっくりと見せると、その子の目に変化が。「え、そういうこと?じゃあ僕もやってみる!」と、一気に前向きな姿勢に変わったのです。
最終的には、自分の力でタオルのねじれをほどき、「やった!できた!」と大きな声で叫び、飛び跳ねて喜びを表現していました。この成功体験が、彼にとって大きな自信となり、その後の活動にも積極的に取り組めるきっかけとなりました。
7. 活動後の振り返りもセットで深まる学び
活動のあとに「ふりかえり」の時間を設けることで、子どもたちは自分の体験を言葉にする力や、感情を整理する力をさらに育むことができます。
ふりかえりの問いかけ例
- 今日の活動は楽しかった?難しかった?
- どんなときに「うまくいった!」と感じた?
- 相手のことを考えて動けたかな?何か気づいたことはあった?
- 次にこの活動をするなら、どうしたい?何か工夫したいことはある?
まとめ|人間知恵の輪は2人でもできる!正解より「協力と達成感」
「人間知恵の輪」は、大人数でなくても、たった2人でも、そしてタオルといった身近な道具を使って気軽に楽しむことができる活動です。
特別支援学級においては、直接手をつなぐのが苦手な子への配慮や、動きのイメージがつきにくい子への視覚的なサポート、声が出しにくい子へのコミュニケーション支援など、ほんの少しの工夫で、どの子も「できた!」という達成感を味わえる活動になります。
大切なのは、「完璧な正解の形」にこだわることではありません。子どもたち一人ひとりが、協力する過程で得られる気づきや、自分なりの“成功”を体験することです。ぜひ日々の自立活動やSSTに「人間知恵の輪」を取り入れて、子どもたちの成長をサポートする楽しい時間を作ってみてくださいね!





コメント