「勝ち負け」だけじゃない!家族みんなで笑えるゲーム時間
「せっかくボードゲームを買ったのに、兄弟げんかになっちゃった…」「パパやママが勝つと、子どもが泣き出しちゃう…」
ボードゲームって楽しいけれど、家庭で遊ぶ時には「勝ち負け」が原因でちょっぴり困ったことになりませんか?
そんなお悩みをお持ちの親御さんにぜひ知ってほしいのが、「協力型ボードゲーム」です!
協力型ボードゲームは、プレイヤー同士で競争するのではなく、家族みんなで一つのチームになり、ゲームという共通の敵に立ち向かうスタイルのゲーム。だから、ゲームの最後には「家族みんなで大成功!」か「惜しかったね、次は頑張ろう!」のどちらか。誰か一人だけが勝って、誰かだけが負けて悲しい思いをする、ということがありません。
今回は、そんな協力型ボードゲームの中から、実際に多くの子どもたちが楽しんでいる、特におすすめの5つをご紹介します。
この記事を読めば、
- なぜ協力型ボードゲームが家族のコミュニケーションに良いのか
- 子どもたちのどんな力が遊びながら伸びるのか
- 家庭ですぐに楽しめる具体的なゲームはどれか
が分かります。ぜひ、次の家族時間にぴったりのゲームを見つけてくださいね!

※アフィリエイト商品含みます。
家族で楽しむ!おすすめ協力型ボードゲーム5選
子どもたちの「できた!」や、家族みんなの笑顔がたくさん生まれる、協力型ボードゲームをご紹介します。
1. おばけキャッチジュニア(Geister Geister Schatzsuchmeister)
かわいいおばけと宝探し!家族みんなでドキドキ冒険に出かけよう。
- 対象年齢: 6歳以上
- ゲームってどんな感じ? おばけ屋敷を探検しながら、呪われた宝物を協力して運び出すゲームです。サイコロを振って進み、おばけに見つからないようにルートを考えます。屋敷には色々な部屋があり、ドアを開けるたびに新しい発見やちょっぴりピンチが待っています。
- ここがすごい!家庭でのメリット:
- 自然な声かけが増える: 「次は〇〇ちゃんが行ってみる?」「パパ、こっちのおばけが近づいてきたよ!」のように、ゲームの状況を教え合ったり、相談したりする会話が自然に生まれます。
- 「大丈夫だよ」の優しい気持ち: 誰かが間違えそうになっても、「あ、ちょっと待って!」と優しく教え合ったり、うまくいかなくても「ドンマイ、次があるよ!」と励まし合ったり。家族間の思いやりが育まれます。
- ハラハラドキドキを共有: おばけが近づいてくるスリルをみんなで味わうことで、ゲームへの一体感が生まれます。
- おすすめポイント: ルールが分かりやすく、小さな子でもすぐに参加できます。1回のプレイ時間も長すぎないので、ちょっとした空き時間にもピッタリ。親御さんも一緒になってワイワイ楽しめるゲームです。
2. ゾンビキッズ(Zombie Kidz Evolution)
遊ぶほどにパワーアップ!家族のチームワークでゾンビから学校を守り抜け!
- 対象年齢: 7歳以上
- ゲームってどんな感じ? 可愛いイラストのゾンビから学校を守るため、家族みんなで協力して学校の四隅にあるゲートを閉めるゲームです。このゲームの一番の特徴は、遊ぶたびにゲーム自体が進化する「レガシー(キャンペーン)要素」!特定の条件を満たすと、新しいルールやキャラクター、ミッションが追加され、どんどん面白くなっていきます。
- ここがすごい!家庭でのメリット:
- 「続きがやりたい!」が止まらない: ゲームが進化するたびに新しい発見があるので、子どもたちが「また明日もやりたい!」と夢中になります。家族で継続して一つのことに取り組む良い機会になります。
- 家族で戦略会議!: 難易度が上がると、「どうすればもっと上手くできるかな?」「次は〇〇から攻めよう!」のように、自然と家族みんなで話し合い、チームとしての戦略を考えるようになります。
- 成長を実感!: ゲームが進むにつれて、家族のチームワークが上がっていくのを実感できるはず。
- おすすめポイント: 同じゲームでも毎回新しい発見があるため、飽きずに長く楽しめます。家族で協力してミッションをクリアしていく達成感は格別!リビングに置きっぱなしにして、いつでも「続き」ができるようにしておくのもおすすめです。
3. にじいろのへび(Regenbogen-Schlange)
つなげてて!カラフルなへびをどこまで長くできるかな?
- 対象年齢: 4歳以上
- ゲームってどんな感じ? サイコロを振って出た色と同じ色のヘビのパーツを探し、ボード上ですでにつながっているヘビにつなげていくゲームです。家族みんなで協力して、途切れることなくできるだけ長いへびを完成させることを目指します。ルールは「サイコロを振る」「同じ色をつなげる」のたったこれだけ!
- ここがすごい!家庭でのメリット:
- 小さな子もすぐに楽しめる: 複雑なルールがないので、小さなお子さんのボードゲームデビューに最適。家族と一緒に「できた!」の成功体験を気軽に味わえます。
- 色の学びにも!: 遊びながら自然と色の名前を覚えたり、同じ色を探したりする練習になります。
- 「つながったね!」の共感: ヘビがどんどん長くなるのを見て、「わー!つながった!」「すごーい!」と、家族みんなで喜びや感動を共有できます。
- おすすめポイント: ルール説明が簡単で、準備もすぐにできるので、「ちょっとだけゲームしたいな」という時に気軽に遊べます。コマが大きくてカラフルなので、視覚的にも分かりやすく、子どもたちの興味を引きつけます。勝ち負けがないので、穏やかな雰囲気で楽しめます。
4.フォレストスクールアドベンチャーForest School Adventure
家族みんなが名探偵!ヒントを集めて犯人を見つけ出せ!
- 対象年齢: 5歳以上
- ゲームってどんな感じ? 森で誰かがパイを盗みました!家族みんなで協力して探偵になり、手がかりを集めたり、容疑者を調べたりしながら、犯人のきつねを見つけ出す推理ゲームです。サイコロを振ってボードを進み、手がかりを見つけたら特別なデコーダーで確認!「このきつねは犯人じゃないみたい!」と容疑者を絞り込んでいきます。
- ここがすごい!家庭でのメリット:
- 「これ、ヒントじゃない?」相談が弾む: 「この足跡は誰だろう?」「この場所は誰が行けるかな?」のように、自然と家族で推理について話し合い、情報共有するようになります。
- 考える力が身につく: 集めた手がかりから論理的に犯人を絞り込んでいくプロセスは、子どもたちの考える力(ロジカルシンキング)を養います。
- 家族で「なるほど!」を共有: みんなで考え、「わかった!犯人はきっと〇〇だ!」と答えにたどり着いた時の達成感は格別です。
- おすすめポイント: 子ども向けの推理ゲームですが、大人も一緒に考えながら楽しめる面白さがあります。可愛いコンポーネントと、デコーダーというユニークな仕掛けが、子どもたちの「やってみたい!」を引き出します。協力して謎を解くワクワク感を家族みんなで味わえます。
5. パンデミック:ジュニア(Pandemic: Rapid Response または ジュニア版)
世界の危機を救う医療チームに!本格的な協力ゲームの入口。
- 対象年齢: 8歳以上
- ゲームってどんな感じ? 世界中で病気が発生!家族みんなで医療チームとなり、それぞれが持つ特別な能力(役割)を活かして協力し、治療薬を届けたり、病気の蔓延を食い止めたりして世界を救うゲームです。大人向けの有名協力ゲーム「パンデミック」を子ども向けに分かりやすくアレンジしたバージョンです。
- ここがすごい!家庭でのメリット:
- 「私はこれ担当!」役割意識が育つ: 家族一人ひとりに違う役割があるため、自分の役割を理解し、チームの中で自分がどう貢献できるかを考えるようになります。
- 「パパ、そこに行って!」指示や相談: ゲームの状況を見ながら、「〇〇ちゃん、今行くといいよ!」「パパがこっち担当するから、ママはあっちお願い!」のように、自然と指示や相談が飛び交い、チームで動く感覚が身につきます。
- 時間との勝負で集中力アップ: (ラピッドレスポンス版)時間制限がある中で協力することで、緊迫感とともに家族の集中力が高まります。
- おすすめポイント: 「みんなで世界を救う」という壮大なテーマが、子どもたちの使命感や達成感をくすぐります。少し複雑になりますが、より本格的な協力ゲームの面白さを家族で体験できます。家族みんなで「ああでもない、こうでもない」と話し合いながらプレイするのが醍醐味です。
遊びをもっと豊かな学びに!家庭での小さな工夫
協力型ボードゲームは、それだけでも十分楽しいですが、遊びの前に「今日のゲーム、〇〇くんはコマを順番通りに動かすのを頑張ってみようか」「〇〇ちゃんは、パパに『ありがとう』を言うのを意識してみようね」のように、その日の小さな「めあて」を決めたり、
ゲームの後に「今日のゲームで楽しかったことは?」「めあてはできたかな?」「どうすればもっと上手くできたかな?」のように、簡単な「振り返り」の時間を持ったりすると、遊びがさらに子どもの成長に繋がる豊かな時間になります。

おわりに:ボードゲームで、もっと笑顔あふれる家族時間を!
協力型ボードゲームは、勝ち負けのプレッシャーなく、家族みんなで力を合わせる楽しさを存分に味わえる素晴らしいツールです。ゲームを通して交わされるたくさんの言葉や笑顔、そして協力できた時の達成感は、きっとご家族にとってかけがえのない宝物になるはずです。
今回ご紹介したゲームが、皆様のご家庭に笑顔と学びあふれる時間をもたらすきっかけとなれば幸いです。ぜひ、ピンときたゲームを一つ、試してみてはいかがでしょうか?
このブログ記事が、ご家族でボードゲームを楽しみたい親御さんたちの一助となれば幸いです。








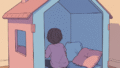
コメント