 支援の工夫
支援の工夫特別支援教員の手当、調整額削減はおかしい|処遇改善と専門性の軽視を考える
2025年6月、文部科学省の「教員の処遇改善」に関する方針が大きな波紋を呼んでいます。公立学校の教員に支給されている教職調整額を4%から10%に引き上げる一方で、特別支援教育に携わる教員に支給されている「給料の調整額」を段階的に半減させると...
 支援の工夫
支援の工夫 支援の工夫
支援の工夫 支援の工夫
支援の工夫 支援の工夫
支援の工夫 おうちでできる支援
おうちでできる支援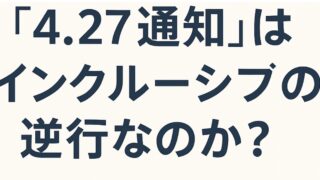 支援の工夫
支援の工夫 実践アイデア集
実践アイデア集 おうちでできる支援
おうちでできる支援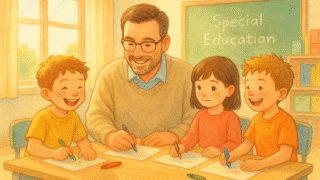 おうちでできる支援
おうちでできる支援 支援の工夫
支援の工夫