「学校に行けない。」
この一言の裏側には、たくさんの思いが隠れています。
不登校は、子どもにとっても、そして親にとっても、とても苦しく、つらい経験です。
「どうしてうちの子は学校に行けないんだろう」
「何が悪かったんだろう」
そんなふうに、自分を責めてしまうことばかりかもしれません。
でも、これまで多くの子どもたちと関わる中で、私は確かに感じてきました。
子どもたちには、前に進む力がある。
それは、ただ時間が解決するものではありません。
安心できる場所、自分を認めてもらえる場所に出会うことで、子どもたちは少しずつ変わり始める可能性をもっています。
今日は、私が情緒学級で出会った子どもたちの小さな変化の物語を通して、
“不登校”という悩みの中にいる方に、そっと希望を届けられたらとおもいます。
不登校には、さまざまな背景がある
いじめを受けた経験、先生との関係、体調不良、起立性調節障害、過敏性腸症候群……
不登校になる理由は、決して一つではありません。
そして、時には「無気力」という言葉でまとめられてしまうこともあります。
けれど、私は違うと感じています。
それらはすべて、「生きづらさ」というもっと深い部分の表れなのではないか、と。
生きづらさの中身は、子どもによってさまざまです。
- 周りに合わせられない苦しさ
- 完璧でいようとするプレッシャー
- 感覚に敏感すぎるつらさ
- 自分を表現できないもどかしさ
表面的な「行けない理由」だけを見ていては、子どもたちの本当の気持ちにたどり着けないこともあります。
そして、それを一番近くで感じ、悩み、苦しんでいるのは、おそらく親御さんだと思います。
小さな一歩──保健室から、情緒学級へ
ある男の子がいました。
彼は長い間、教室に入れず、保健室で静かに過ごしていました。
朝、学校の門をくぐるだけで、涙が止まらなくなってしまう日もありました。
お母さんも、そんなわが子の姿を見て、胸が張り裂ける思いだったと思います。
でも、情緒学級という「安心できる場所」と出会ったことで、少しずつ変化が訪れました。
最初はほんの数分、情緒学級の教室に顔を出してみるところから。
そして、机に座らずとも、ただその場にいることを認めてもらう時間。
毎日、ほんの小さな積み重ねを続けるうちに、彼は「今日も行ってみようかな」と自分で言うようになったのです。
このとき、周りの大人たちがしたことは、「無理をさせないこと」だけでした。
それでも、彼は確かに、自分の力で前に進んでいったのです。
音に敏感だった子どもが、安心できる場所を見つけた
別の女の子の話です。
彼女は、教室のざわざわした音、人の話し声、チャイムの音──
すべての音に敏感に反応してしまい、学校生活を続けることが難しくなりました。
「音が怖い」
「頭が痛くなる」
そんなふうに訴えて、教室にいることすらできなくなってしまったのです。
けれど、情緒学級では、人数も少なく、静かな環境の中で過ごせます。
少しずつ、彼女は落ち着いて活動に参加できるようになりました。
そして、「学校にいるのが楽しい」と、笑顔を見せてくれる日が増えていったのです。
子どもたちは、自分に合った環境に出会うことで、
こんなにも自然に、こんなにも力強く、歩き出すのだと改めて感じました。
「できなかった自分」を許せなかった子が、変わっていった
もう一人、印象に残っている子がいます。
彼は、誰よりもまじめで、誰よりも頑張り屋でした。
でも、だからこそ「できない自分」を許せず、
学校で過ごすことがどんどん苦しくなっていったのです。
「どうせ僕なんて……」
「みんなみたいにできない」
そうつぶやく姿に、胸が締めつけられました。
でも、情緒学級では、彼の小さな「できた!」を大切にしました。
漢字を一文字書けたこと。
人に挨拶できたこと。
今日、教室に来られたこと。
何でもないようなその一つひとつを、心から喜び合う時間。
そのうちに、彼はこう言うようになりました。
「ぼく、学校に来られてるよね」
それは、誰にとっても小さな一歩かもしれない。
でも、彼にとっては、世界を変えるような大きな一歩だったのかもしれないです。
生きづらさに、環境で応える
不登校というと、「心が弱い」「親のしつけが悪い」なんて、誤解されがちです。
でも、子どもたちが学校に行けない背景には、
たいてい、自分ではどうにもできない生きづらさがあります。
だからこそ、大人がすべきことは、
「どうしてできないの?」と問い詰めることではなく、
「どうしたらこの子が安心していられるか」を一緒に考えることだと、私は思っています。
それが、情緒学級だったり、
場合によってはフリースクールやホームスクールだったりするかもしれません。
どこにいるか、ではなく。
その子が”自分らしくいられるか”が、何より大切なのです。
いま悩んでいる親御さんへ
もし、いま、
「うちの子はこのままでいいんだろうか」
「もっとがんばらせなきゃいけないんじゃないか」
そんなふうに自分を責めている親御さんがいたら──。
どうか、こう伝えたいです。当事者でない私の言葉で申し訳ないですが、
あなたは、もう十分、がんばっています。
子どものために悩み、苦しみ、あきらめずに支えようとしてきた。
それだけで、あなたは、かけがえのない存在でしょう。
子どもたちは、自分を理解してくれる大人がそばにいるだけで、
もう一度、歩き出す力を取り戻すことができます。
その小さな一歩を、一緒に信じていきましょう。
おわりに
不登校だった子どもたちが、少しずつ前に進むことができたのは、
彼ら自身の力、
そして、それを信じ、待ち続けた大人たちの力です。
情緒学級という選択肢も、きっと、その一つです。
朝起きることさえ辛かった子が、1週間に1度、情緒学級に顔を出せるようになった」
「教室に入れなかった子が、窓から先生に手を振れるようになった」
みたいな、ちいさな行動の変化が起きてほしいです。
あなたとお子さんにとって安心できる場所が、きっと見つかりますように。
「まずは、どんな小さな一歩でもいいんです。」
生きづらさを抱えながらも、自分らしく生きるために。
子どもたちも、大人たちも、みんな、少しずつ、前に進んでいける。
そんな未来を、私は信じています。
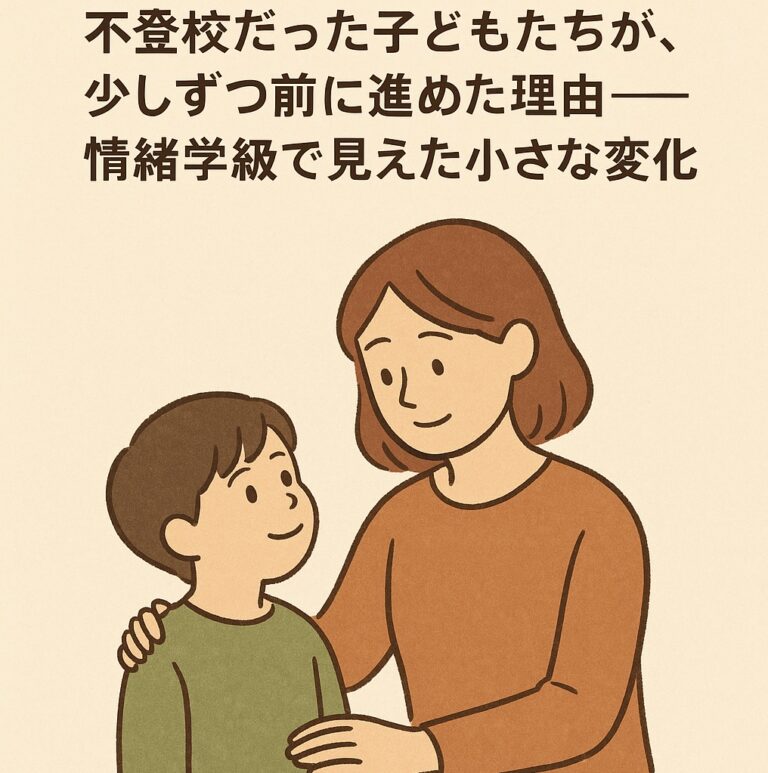


コメント